米国はもう覇権国ではないのか
米国はイラク戦争の失敗で世界の顰蹙をかった。米国はもはや、世界の指導者としての資格がないと感じる人が増えている。そういう感情に受けたのか、トッドの『帝国以後―アメリカ・システムの崩壊』は世界的なベストセラーとなった。はたして、トッドが言うように、米国の覇権は本当に崩壊したのだろうか。
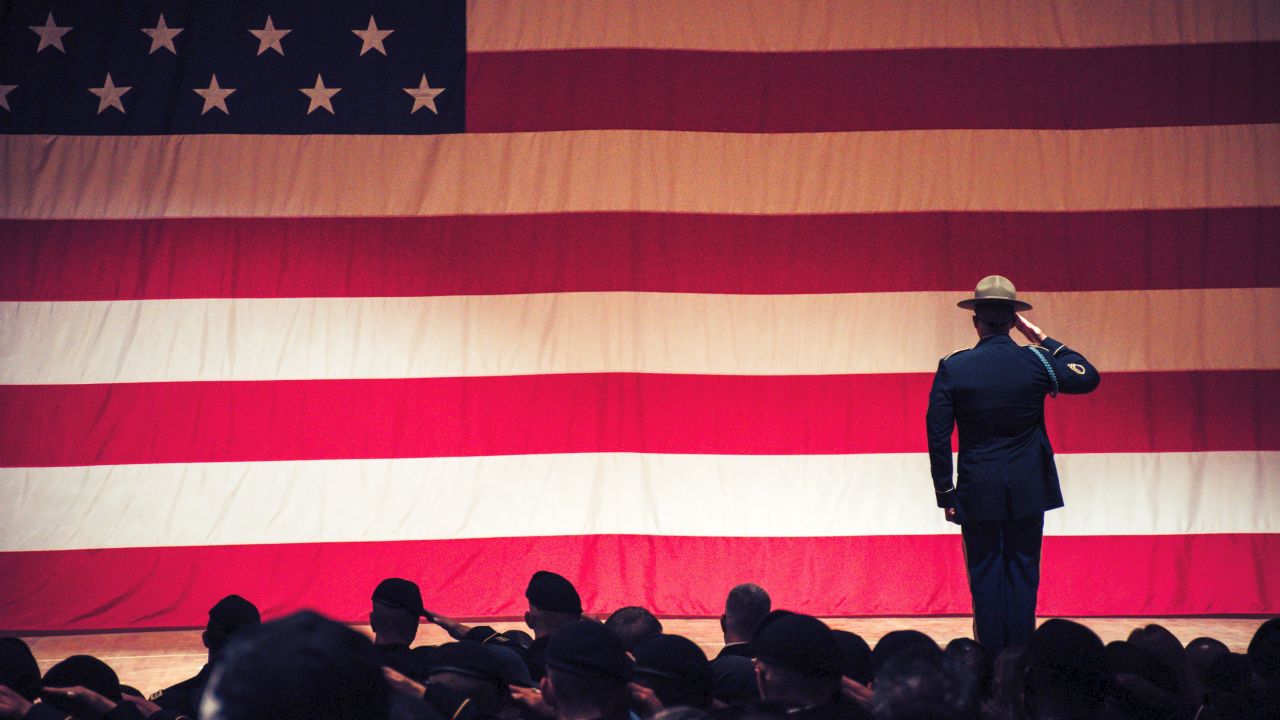
1. 米国の経常赤字問題
ソ連の崩壊により、米国は唯一の超大国となった。しかし、トッドは、米国の慢性的で大規模な貿易赤字を理由に、米国が、10年遅れでソ連と同じ運命をたどっていると主張する。
終戦直後の過剰生産の自律的な国であったアメリカ合衆国は、いまや一つのシステムの中核となったが、そのシステムの中でアメリカの果たす使命は生産ではなくて消費なのである。[1]
トッドが、米国内の工業部門の衰退を強調したために、サービス部門を軽視した、脱工業化時代を理解しない古い発想という批判を浴びることになるわけだが、実は、米国は、貿易収支だけでなく、経常収支も慢性的に赤字であり、サービス産業が貿易収支の赤字を補っているわけではない。
一般的な傾向として、日本、ドイツ、フランスでは、経常収支が黒字で、資本収支が赤字であるのに対して、米国と英国では、経常収支が赤字で、資本収支が黒字である[2]。このことは、日独仏が、英米への直接投資や証券投資や資本移転などにより、経常収支の赤字をファイナンスしているということである。経常収支が赤字の英米が、イラクで、戦争というサービス産業に力を入れていることは、偶然ではない。
1990年代の後半のようなバブルが起きると、米国政府が何もしなくても、あるいは、せいぜい政府要人が「強いドルを望む」と発言しているだけで、日欧から民間ベースで資金が流入してくる。しかし、バブルが崩壊すると、政府が世界から資金を集めるような公共事業でもしなければ、経常収支の赤字を支える資本の流入が途絶え、ドルの暴落を惹き起こすことになる。
1991年の湾岸戦争では、この方法はうまくいったが、現在の「テロとの戦い」では、独仏が協力していないたために、うまくいっていない。2001年のアフガニスタン侵攻以来、ヨーロッパから米国への純資本流入は大きく減少し、ドルはユーロに対して、下がり続けている。米国経済は、日本をはじめとするアジアが米国債を買い支えることで、何とかもっているというのが現状である。

2. 米国は世界の平和を望んでいない
フランシス・フクヤマは、主著『歴史の終わり』で、共産主義の崩壊により、民主主義と資本主義が最終的に勝利し、もうこれ以上社会制度が発展することがなくなるから、歴史は終わったと喝破した[4]。しかし、実際には、冷戦の終わりで始まったのは、歴史の終わりではなくて、米国の終わりではないのかというのがトッドの考えである。
教育的・人口学的・民主主義的安定化の進行によって、世界がアメリカなしで生きられることを発見しつつあるそのときに、アメリカは世界なしでは生きられないことに気付きつつある。[5]
社会が高学歴化すると、晩婚化と教育費の高騰で、子供の数が減る。少子化は世界的なトレンドである。高学歴化は、民主主義を可能にし、また、人口増加に伴う資源の奪い合いも減るので、世界は平和になると予想される。しかし、世界が民主主義化され、平和になって、一番困るのは、米国である。ちょうど、社会からトラブルがなくなると、トラブルを解消するのが仕事である弁護士が困るように、国際社会が平和で民主主義的になると、世界の平和と民主主義を守ることが仕事である世界の警察、米国が困るのである。
冷戦終結後、米国は、新たな敵を作らなければならなかった。オサマ・ビンラディンやサダム・フセインは、もともと米国が育てた人材である。こうした平和の敵であるテロリストや民主主義の敵である独裁者は、米国の軍産複合体にとっては、なくてはならない人材である。米国には、国営企業がないので、デフレ対策の公共事業と言えば、戦争ぐらいしかないのだが、戦争するには、海外から資金を集めるための大義名分が必要なのである。
3. イラク戦争は石油のための戦争か
米国が、イラク戦争を行ったのは、石油の安定供給のためだとよく言われる。しかし、湾岸地方の油田の確保それ自体は米国経済にとって死活問題ではない。米国の貿易赤字に占める石油の割合は、18%程度で、しかも、輸入する石油の大半は、新大陸からのものである。日本が、国内で消費する石油の9割弱を中東に頼っているのに対して、米国のペルシャ湾岸諸国への石油の依存率は2割弱にすぎない。
アメリカ合衆国は同盟国の石油供給の安全を保障すると称するが、実のところは、ヨーロッパと日本に必要なエネルギー資源を統制することによって、この両国に有意的圧力を加える可能性を保持できると考えているのである。[6]
私は、以前「ブッシュはなぜ戦争を始めたのか」で、ブッシュは石油そのものが欲しくて戦争をしているわけではないと書いたが、トッドもそういう意見のようだ。ブッシュは、中国、日本、ヨーロッパという、米国の経常赤字を作り出す国々の重要な輸入相手である中東を支配し、原油の販売で経常赤字を削減しようとしたわけだが、この目論見は外れた。積極財政により、デフレを克服することはできたが、財源を十分確保できなかったので、米国は、今後厳しい経済運営を迫られることになる。
4. 米国の覇権は瓦解したのか
ヨーロッパと日本は、米国が支配者として世界を飛び回るために必要な両翼であり、現在一方の翼を失って、きりきり舞いになっている状態であるが、しかし地面に墜落するまでには、まだまだ時間がかかるだろうというのが私の見通しである。だから、私は、米国が覇者としての地位を失ったとするトッドの見解には与しない。
米国のヘゲモニーが終焉を迎えたかどうかを論じる前に、そもそも覇権国の条件は何なのかを考えなければならない。トッドは、人口や工業生産高や天然資源が多い国を大国と考え、覇権国を最大の大国と考えているようだが、これらは覇権国であるための必要条件でもなければ、十分条件でもない。
トッドは、人口学者らしく、人口を重視するのだが、米国以前の覇権国、すなわち、スペイン、オランダ、英国は、人口大国だっただろうか。国内でも、支配者階級は、決して社会の多数派ではなく、むしろ少数派であることが普通である。元や清の場合、支配民族が、被支配民族の漢民族と比べて、無視できるほど少なかったが、その治世は長く続いた。
工業生産高は、人口と比べれば、重要なファクターではあるが、工業生産高がたんに量的に大きいだけでは、覇権国にはなれない。重要なことは、その時代の最も重要で先端的な産業で主導権を握っているかどうかなのだ。
大航海時代に最も重要であった産業は繊維産業だった。スペインは、毛織物工業のおかげで「太陽の没することのない帝国」を築いたが、プロテスタントの抑圧が原因で、オランダが独立し、国内の毛織物工業が衰退して、没落した。スペインに代わって、オランダが毛織物工業を武器に世界の貿易を支配したが、英国が、産業革命による綿織物の大量生産に成功して、世界の支配者となった。その英国も、重工業化の波に乗り遅れたために、二度の世界大戦で勝利したにもかかわらず、急速に没落した。そして、英国に代わって、世界の覇者となったのは、世界で最初にモータリゼーションに成功した米国である。
今でも米国は、情報工学や遺伝工学といった、最も重要で先端的な産業の基幹技術を握っている。コンピュターの頭脳ともいうべきCPUでは、米国が主導権を握り、他の国は、より重要でないDRAMを作るとか、OSをはじめとする基幹ソフトは、米国がデ・ファクト・スタンダードを握り、他の国は派生的で泡沫的なソフトを作るといったぐあいに、量では測ることのできない、質的な差異が米国とそれ以外の国にある。
最後に、天然資源であるが、これも覇権国になるための条件では全くない。毛織物、綿織物、鉄道、自動車、情報機器といった、各時代の花形産業の原料を提供した国ほど、覇権国から縁遠い国はない。トッドが次のように言って、ロシアを持ち上げることに首をかしげるのは、私だけではないだろう。
ロシアの石油生産、とりわけガスの生産は、エネルギーの面でロシアを世界的行為者に押し上げる底のものなのだ。それにその広大な国土は膨大な量のその他の天然資源を保証していることを忘れてはならない。[7]
なるほど、石油危機のとき、OPECが注目されたことはあった。しかし産油国は、当時、豊富な資金を手にしたが、世界を支配するだけの知的資源を持たなかった。世界を支配するには、富・知・力の三つにおいて、他の国に対して優位に立たなければならない。そして、その中で一番重要なのは知的支配であろう。先端的な産業の分野で、米国を凌駕する国が現れれば、その時米国は覇権国の座から降りることになるだろう。
5. 参照情報
- エマニュエル・トッド『帝国以後 ― アメリカ・システムの崩壊』藤原書店 (2003/4/30).
- フランシス・フクヤマ『歴史の終わり〈上〉歴史の「終点」に立つ最後の人間』三笠書房; 新装版 (2005/5/1).
- フランシス・フクヤマ『歴史の終わり〈下〉「歴史の終わり」後の「新しい歴史」の始まり』三笠書房; 新装版 (2005/5/1).
- ↑エマニュエル・トッド『帝国以後 ― アメリカ・システムの崩壊』藤原書店 (2003/4/30). p. 99.
- ↑International Monetary Fund. International Financial Statistics Yearbook. Volume 57, 2004.
- ↑内閣府. “アメリカ:経常収支赤字のファイナンス 民間資金流入は減少、外国の公的部門からの流入は増加.” 今週の指標 No.444. 2003年7月7日.
- ↑Francis Fukuyama. The End of History and the Last Man. Penguin (1993/1/28).
- ↑エマニュエル・トッド『帝国以後 ― アメリカ・システムの崩壊』藤原書店 (2003/4/30). p. 37.
- ↑エマニュエル・トッド『帝国以後 ― アメリカ・システムの崩壊』藤原書店 (2003/4/30). p. 196.
- ↑エマニュエル・トッド『帝国以後 ― アメリカ・システムの崩壊』藤原書店 (2003/4/30). p. 217.

















ディスカッション
コメント一覧
郵政事業の民営化は、郵貯マネーを米国に献金するための陰謀だといった主張をネットでよく見かけますが、米国債を買い支えることが目的ならば、民営化しないほうがやりやすいのではないでしょうか。
旧郵便貯金時代はその資金の一部は「財政投融資」として5年以上の長期運用分については国会の議決が必要だった。年金資金も財投に含まれる。つまり足枷があった。融資先が特殊法人等に偏り、不公平だったから改革したのではないか。
2004年のアメリカの強い要望で民営化は進められてきた。陰謀というよりはまだ金融が破綻していない時期にサブプライムローンを担保にした金融工学を駆使したといわれる複雑な証券を足枷なしに買ってもらおうとしていたのが当初の予定。
繰り返し主張したい。今回のゆうちょ銀行の融資解禁はモラトリアムが必要である。世界経済の回復をみながら融資解禁にすればよい。ゆうちょ銀行は直接米国債を購入しない。ゆうちょ銀行の資金が民間金融機関に融資され、複雑なしくみの又貸しの中で米国債購入につながるシステムを想定される。資金はアメリカの富裕層の中にあり、日本から調達しなくても十分なのである。
歴史的教訓としては浜口雄幸内閣の金解禁が何をもたらしたかを考えれば理解できる。今回はGOLDではなくてYEN。解禁は「嵐に向けて窓を開け放つ」ことを意味する。
日本は資金で貢献するのではなく、新しい産業を創出する技術やシステムで貢献すればよい。ゆうちょ銀行に関しては保護主義と非難されようととにかくモラトリアム。「ゆうちょ銀行は全国に分散し、それぞれの融資担当者が審査に不慣れなもので数年間は融資できません。」とアメリカに伝える。
日本が保護主義ではない証にグリーンニューディールに貢献する。グリーンニューディールが成功するかしないかは日本の技術にかかっている。食料や資源の切り札をきられるまえに資金以外の方法でアメリカに協力するしかない。
前回も述べたように食料高や資源高にともなうハイパーインフレが起きれば、貯金も預金も不良債権もそして財政的な負債もすべてリセットされてしまう。もちろん日本の国民はハイパーインフレを望んでいない。
アメリカの覇権は日本をはじめ、アジアの協力でもうしばらく維持される。
英国訪問中の温家宝(ウェン・ジアバオ)首相は米国債について「購入を続けるのかどうか、どの程度購入するのかは、中国の需要と資産価値を保持できるかにかかっている」と発言、購入見直しに含みをもたせた。
と
クリントンは、米国債のセールスレディーみたいな卑屈なことはしないでしょう。今回の訪問の主な議題は北朝鮮問題で、米国としては、北朝鮮という脅威に対して、日米同盟の重要さを、つまり日本が米国を買い支えることの重要性を日本に認識させたいということなのかもしれません。
この2つの論説は、米国財務省証券を日中どちらか(或いは両方)に消化して貰わなければ、米国の今後の政策が成り立たない、と主張するものだと受け取りましたが、米国債の消化は、FRBが行うことも可能ではないのでしょうか?
また、当のFRB議長がそれを示唆する発言を2009年1月28日にしてると思います。
これは、わが国が第二次大戦中に行った、日銀の国債引受と同じことだと思います。
つまりアメリカは、今後国債消化に伴なう制約を一切受けずに、世界運営が可能になることを示していると思います。(日本にも中国にも気兼ねはしない)
このような世界が出現した場合、永井さんは日本がどうすべきであると考えますか?
米国人は資産を持っていますが、貯蓄を持っていません。そして資産価格がデフレにより暴落しています。これが問題なのです。
あの金解禁が金の流出とデフレを惹き起こしたのは、旧平価で解禁したからであって、平価を市場価値にまで切り下げていたら、そうはならなかったでしょう。濱口内閣の失敗から学ぶべきことは、世界的なデフレ時に通貨を切り上げることはするべきではないということです。円高を放置している今の日本政府と日銀は、その教訓から学ぶべきでしょう。
ゆうちょ銀行の預金は預金者のものであって、ゆうちょ銀行や日本政府のものではありません。預金者は、少しでも金利が高くなることを求めています。国内よりも海外のほうが利回りが高いなら、預金者は海外への融資を望むでしょう。これまで日本のマネーが海外に流出していたのは、日本の生産性が低くて、利回りが低いからです。日本への投資と融資を増やしたいならば、保護主義を捨てて、日本の生産性を向上させることが重要です。
中央銀行が国債を引き受けると、通貨価値が下落し、インフレやキャピタルフライトを惹き起こすので、無制限にはできません。ただし、米国通貨は、2009年2月現在、円を除く他の通貨よりも高くなっており、米国国内でもデフレが進行しているので、ある程度実施する余地はあるかと思います。実は、こうしたインフレ政策を取る必要性が最も高い国は、円高とデフレに苦しんでいる日本ですが、日本銀行における国債の引き受けは、財政法第5条によって禁止されています。
今回、「特別の事由」として、ある程度行うか、財政法第5条を改正するか、あるいは政府与党の一部が検討しているように、政府紙幣を発行するか、何らかの手段で、ベースマネーを増やすべきでしょう。こういうインフレ政策は、通貨価値をさせ、キャピタルフライトを惹き起こすという副作用を伴うとはいえ、世界の主要国が、同時にこれを行えば、こうした副作用を最小限に抑え、世界的なデフレから脱却することができるでしょう。
昨日の産経新聞に、こういう記事がありました。みんな考えていることは同じですね。
オバマが、将来財政赤字を削減することを宣言したのも、国債乱発による通貨下落とマネー流出を防ぎたいという意図からでしょう。
さっそくのご返答、ありがとうございました。
さて、国債の中央銀行引き受けは、日米両国とも障害を乗り越え行うであろうと考えております。
というか、すでに通貨の発行を中央銀行が独占する時代は、終わったのではないかと感じています。(政府紙幣か、それに類するものを発行すべきでは?)
オバマは莫大な国債の発行と消化、及びドルの価値の維持を、同時に行わなくてはならず、この二律背反は不徹底にならざるを得なかった、ルーズベルトのニューディール政策を思い起こさせます。
思うように回復しない経済と、イラクとアフガンを抱えた米国、過剰なまでの期待を背に登場したオバマが、どのような行動をとるか心配です。
(デフレ下での戦争の誘惑に勝てるのか?)
このような場合、従来型の戦争による回復を求めず、政府紙幣の供給による回復は出来ないでしょうか?政府が国債を発行したら債務は積み上がりますが、政府紙幣ならそのような心配もないと思います。
政府紙幣の日本への効用は、わが国の膨大な供給を消化する市場が消滅し立ちすくむ今、ヘリコプターマネーや社会保障費に充当してはどうでしょう?
特に日本における通貨の供給は、流動性の罠がますます発揮されると容易に想像されますので、社会保障費や消費税を軽減したり事実上撤廃すれば、その分需要の喚起となり、外需依存の悪弊から逃れる一助になりはしないでしょうか?
(米国に変り中国などに市場を見いだしても外交は益々厳しく難しいでしょう)
(当方は、ことさらに中国を敵視する立場では御座いません)
以上の方法では、インフレの恐怖を理由に拒否され易いとも存じますが、デフレ退治に手をこまねいていては、最悪戦争しか手段がないのでは…と愚考しております。
永井さんでしたら、現下のデフレ(既に15年超)をどう退治されますか?
私は、以下のようなポリシーミックスで景気循環に対処するべきではないかと考えています。
1.デフレ期における政策=減税+インフレ税
減税によって生じる歳入不足額を通貨の増発により補い、インフレ圧力をかけます。インフレにするということは、通貨の保有者から、通貨の減価分をインフレ税として徴収しているのと同じことになります。だから、減税によって減る負担が、インフレ税によって相殺されます。したがって、納税者の負担は変わりませんが、通常の徴税とは異なり、人々にインフレ期待を持たせ、デフレスパイラルを食い止めます。
2.インフレ期における政策=増税+デフレ補助金
増税によって生じる歳入超過額を通貨の回収により減らし、デフレ圧力をかけます。デフレにするということは、通貨の保有者から、通貨の増価分をデフレ補助金として給付しているのと同じことになります。だから、増税によって増える負担が、デフレ補助金によって相殺されます。したがって、納税者の負担は変わりませんが、通常の徴税とは異なり、人々にデフレ期待を持たせ、インフレスパイラルを食い止めます。
通常は、通貨の代わりに国債を増発したり回収したりするのですが、通貨の方が国債よりも流動性が高いので、インフレ効果もデフレ効果も大きいと思います。また長期的に経済が成長し続けるためには、回収する通貨よりも増発する通貨の方が多くなければならないので、発行した分をすべて償還しなければならない国債は、経済の成長を阻害します。経済が成長し続けるには、通貨は少しずつ死ななければなりません。さらに、国債には利子が付いているので、インフレ時に急激に膨らむ点も問題です。そこで、与党は利子なしの国債を発行することを考えているようですが、相続税免除を前提にした利子なし国債や政府紙幣よりも通常の日銀券の方がよいかと思います。
私は景気循環に合わせて歳出や歳入を増減することには反対です。歳出も歳入も、したがって納税者に対する負担と便益を常に一定に保ち、インフレ税/デフレ補助金の使い分けにより、マーケットに対してネガティブ・フィードバックを働かせるべきだと思います。こうすれば、ある世代の負担を次の世代に押し付けることなく、また公的セクタの肥大化によって生産性を低下させることなく、恐慌を防ぐとともに、バブルの過熱を防ぐことができます。
>相続税免除を前提にした利子なし国債や政府紙幣よりも通常の日銀券の方がよいかと思います。
申し添えるのを忘れておりましたが、現在の政府紙幣発行論者は、2種類の紙幣の並行流通を想定しておりません。
例えば、政府が1兆円と記載した紙を日銀に引き受けさせ(財政法等に抵触しない方法もあるようです)、政府は同価で引き換えた日銀券にて政策を実行するものです。(無利子無期限の国債とはまったく違います、政府紙幣と日銀券の等価物々交換)
1.デフレ期における政策=減税+インフレ税
減税によって生じる歳入不足額を通貨の増発により補い、インフレ圧力をかけます。インフレにするということは、通貨の保有者から、通貨の減価分をインフレ税として徴収しているのと同じことになります。だから、減税によって減る負担が、インフレ税によって相殺されます。したがって、納税者の負担は変わりませんが、通常の徴税とは異なり、人々にインフレ期待を持たせ、デフレスパイラルを食い止めます。
日本政府は減税らしき減税をした試しがないので論評は難しいのですが、国民性向を思うと反応が目に見える気もします。
減税による政府財政の逼迫と、通貨の増発に伴う国債残高増を嫌気するのではないでしょうか?
つまり通貨の供給によるインフレ圧力を上回る、自己防衛(消費を減し貯蓄)に走るのではと危惧します。
バブル崩壊後のデフレスパイラルを止める為の政府日銀の施策は、おおむね通貨の供給増でしたが、増加したマネーは結局預金として滞留死蔵されています。
通貨供給の増加が意味ある政策の体をなさない証拠は、インフレらしきインフレが昨年の資源バブルインフレまで無かった事です。(資源バブルが続いたら物価のみ高騰する悪性インフレになる可能性が高かった)
外部環境に強要される避けがたいインフレでもなければ、現在の国民にインフレ期待を持たせる事こそが、至難でありましょう。
また仮にお説の通りであったとしても、国民が未来に不安しか持たず、政治や官僚やマスコミに不信のみ抱く現状では、どんな政策も効果を発揮せず無益かもしれません。(政府紙幣含む)
(政と官(公的セクタ)の透明化と生産性の向上は最も肝要で、まず医療と年金改革を喫緊の課題とし行政システムも集約簡素化へと改造し、政治家の定数削減も必要でしょう)
(政治と政治家の質は、国民の質と同義でありますので早急な向上は望めず、数を減して対応)
政府紙幣である意味と問題点
魅力ある財とサービスが政府紙幣の源泉で、資産たる紙幣は日銀券を償却できます。
今の世界で、日本が最も発行するに有利な地位を占めていると思われます。
が、私も含め政府紙幣論者の最大の弱点が、上記の政治家と国民のレベルです。
極論すれば、無制限に発行する事も可能な紙幣を私達は制御し得るのか?
政と官、程度の問題もクリア出来ないのにです。
クリア出来るなら政府紙幣など発行しなくて済むのでは?と問われれば答えに窮せざるを得ません。
時あたかも世界恐慌前夜とでも評しましょうか。
戦争に突入した昭和の日本を繰り返すか?
維新を成した江戸末期の日本になるのか?の境目なのかもしれません。
乱文長文にお付き合い頂き、有り難うございました。
日銀が政府に対して債権を持つということですか。これでは、発行した日銀券をすべて税として回収すると宣言しているのと同じことですから、インフレは起きません。
私が言っている通貨の増発は国債残高を増やしません。
日本銀行が行った量的金融緩和(長期国債買い切りオペ)は、銀行券発行残高を長期国債保有残高の上限としておりました。よく、日銀の量的金融緩和にはインフレ効果がなかったと批判をする人がいますが、日銀の量的金融緩和の目的が、財政ファイナンスではなくて、インフレなき資金供給であった以上、インフレが起きなかったことは当然でしょう。
円高とデフレが進行しているということは、実は人々が日本政府を信用しているということです。2009年2月現在円安が起きていますが、この原因の一つは、麻生内閣に対する信任の低下です。