神は完全であるがゆえに存在するのか
神は完全な無限者であり、その神がたんに観念的で現実に存在しないならば、完全な無限者とは言えないので、神は現実に存在する。このような神の存在の証明を存在論的証明と言い、アンセルムスやデカルトなどによって行われてきた。カントは、存在論的証明が、分析的判断と総合的判断を混同する間違いを犯していると指摘したが、存在論的証明の誤謬は、それとは異なるところに、すなわち、存在論的証明がその存在を証明する完全な無限者は、キリスト教徒が神と考える全知全能の至高な存在者とは全く逆の存在者であるというところにある。

1. アンセルムスによる存在論的証明
神の存在の存在論的証明を最初に明確な形で行ったのは、中世ヨーロッパの神学者、カンタベリーのアンセルムス(Born: 1033; Died: 1109)である。アンセルムスによると、神とは、それよりも偉大なものを考えることができない無限の存在者であり、無神論者は、そうした神は観念的なものに過ぎないと言うが、このことは、神という無限者が観念の中には存在するということを無神論者ですら認めているということである。
それゆえ、無神論の愚か者ですら、それよりも偉大なものを考えることができない何かが、少なくとも悟性の中にあることに納得している。なぜなら、その概念を聞くと、その人はそれを理解するし、何を理解しているかは別として、それは悟性の中に存在しているからだ。そして、それよりも偉大なものを考えることができないものは、間違いなく、悟性の中にのみ存在することはできない。というのも、もしもそれが悟性の中にのみ存在するのであれば、それよりももっと偉大なものが現実に存在すると考えることができる。それゆえ、もしもそれよりも偉大なものを考えることができないものが悟性の中にのみ存在するならば、他ならぬそれよりも偉大なものを考えることができないものが、それよりも偉大なものを考えることができるものになってしまう。しかし、これは明らかに不可能だ。それゆえ、それよりも偉大なものを考えることができないものが悟性と現実の両方に存在することには疑いがない。[1]
引用文に頻出する“maius”は、ラテン語で「偉大な」を意味する中性形容詞“magnum”の比較級である。R.M.ヘアーの表現[2]を用いるならば、この形容詞は、日本語の「偉大」と同様に、「大きい」という記述的意味(descriptive meaning)と「偉い」という評価的意味(evaluative meaning)の二つを持っているが、今、“maius”には、たんに「より大きい」という記述的意味しかなく、神をその意味で最も大きな、つまり最も包括的な存在者と定義しよう。その場合、神とは、悟性と現実の両方の世界を含めた世界全体ということになる。もしこのように定義された「神」が存在しないならば、存在するものは何もないということになるが、これは経験的事実に反する。だから、最も包括的な存在者として定義された「神」は存在する。
しかし、存在論的証明によってその存在が証明される「神」は、記述的な意味で大きいだけの存在者であり、「偉い」という評価的意味を持たない。もしも神が、たんに最も大きな存在者であるだけでなく、最も偉い存在者であるならば、その神は、全知全能であるとか、至高の存在者であるとかいったことが言えるかもしれないが、一般的に言って、大きいから良いとは限らないから、そうした価値判断はできない。このように、存在論的証明の問題点は、証明の仕方にあるというよりも、記述的意味と評価的意味を混同することで、本来の神とは異なる存在者の現実存在を証明してしまっているところにある。
2. デカルトによる存在論的証明
近代における存在論的証明の継承者としては、ルネ・デカルトが有名である。デカルトは、最も確実な存在を「考える自我」に求め、ここから出発するという点でアンセルムスと異なる。デカルトによれば、自我がその観念を持つところの神は自我の内部に留まるものではない。
なぜなら、私自身が実体なのだから、実体の観念が私の内にあるのは確かであるものの、私は有限であり、私という実体の観念は、本当に無限なある実体から出てこない以上、無限な実体の観念であるはずがないからである。[3]
だから、神という実体は自我である実体を超えた存在というわけだが、デカルトは、無限な実体である神と有限な実体である自我との間には因果関係があり、前者には後者以上の実在性があるとも主張している。
ところで、動力因全体のうちに少なくともその結果の内にあると同じだけのものがなければならないということは、自然の光により明白である。なぜなら、結果は、原因からでなければ、いったいどこから自分の実在性を得ることができるのか。また原因は、自分で実在性を有するのでなければ、どうしてそれを結果に与えることができるのか。そして、ここから、いかなるものも無からは生じないということのみならず、また、より完全なもの、つまり、自己の内により多くの実在性を含むものは、より完全でないもの、つまりより少ない実在性を含むものからは生じえないということが帰結する。[4]
もしもこれが正しいならば、その実在が確実な有限な存在者である自我よりも、それを生み出す無限な存在者である神は、さらに大きな実在性を持つということになる。しかし、このような議論は本当に成り立つだろうか。
原因は結果に対して時間的に先行しており、過去に遡るほど、それに関する情報の不確定性が増大するので、その点では、むしろ原因のほうが結果よりも実在性が少なくなる。原因と結果の関係ではなくて、根拠と帰結の関係でなら、前者の方が後者よりも確実と言えるだろうが、その場合、『省察』の理論展開から言って、自我の現実存在が根拠で神の現実存在はそこから証明されるところの帰結ということになる。もしも神の現実存在が根拠で、自我の現実存在が帰結なら、なぜ『省察』は、神の存在証明をした後に自我の存在証明をしなかったのだろうか。
因果関係から、神を第一原因としてその存在を証明する方法は、宇宙論的証明と呼ばれる。デカルトは宇宙論的証明と存在論的証明を混ぜ合わせて神の存在を証明しようとしたが、もしも神の存在が、デカルトがそう考えるように、数学的真理と同様に証明できるというのであれば、そこに因果関係など持ち込むべきではない。
宇宙論的証明は別のページで論じることにして、ここでは、デカルトの存在論的証明に焦点を絞ろう。デカルトによれば、神は完全な存在者なので、その本質(essentia)には、その現実存在(existentia)が含まれている。
このことは、もとより、一見したところ全く分明とは言いがたく、むしろ一種の詭弁の観を呈するかもしれない。なぜなら、私は他のすべてのものにおいて現実存在を本質から区別することに慣れているので、神の現実存在もまた神の本質から切り離すことができ、かくして、神は現実存在しないものと考えることができると信じかねないからである。しかし、もう少し注意して考察すると、神の現実存在を神の本質から分離することができないのは、三角形の三つの角の大きさが二直角に等しいということを三角形の本質から分離することができない、あるいは谷の観念を山の観念から分離することができないのと同じことであることが明白となる。だから、現実存在を欠いている神(つまり、ある完全性を欠いている最高に完全な存在者)を思惟することは、谷を欠いている山を思惟するのと同じく矛盾である。[5]
本質に現実存在が含まれているからと言って、それが現実存在しているといえるだろうか。「現実存在」という概念は、現実存在を意味するから、その本質には現実存在が含まれていると言うことができる。しかし、「現実存在」は理念的概念だから、そ理念的対象が現実存在することはない。「現実存在する物」なら現実存在しうるが、私が現実存在すると思っているある物が本当に現実存在しているのかどうかは、その概念の意味だけでは決まらない。要するに、「現実存在する物」という概念は、現実存在する物を可能的な対象として意味しているだけで、「その物が現実存在する」ことの証拠にはならない。同様に、「現実存在する神」という概念は、現実存在する神を可能的な対象として意味しているだけで、「その神が現実存在する」ことの証拠にはならない。
もとより、デカルトによる神の定義は、「現実存在する物」ではなくて、「完全な存在者(ens summe perfectum)」である。「完全」という概念では、評価的意味を持たない記述的意味と評価的意味を持つ記述的意味は別なのだが、デカルトは両者を「完全」という同じ名称のもとに混同している。評価的意味を持たない記述的意味に限定しても、一義的ではないし、なぜ完全なら現実存在するのかに関しても次の二つの解釈が成り立つ。
- 完全であるということは、限界を持たない、つまり無限に大きいということを意味する。この場合、デカルトの存在論的証明は、アンセルムスの存在論的証明と同じになる。
- 完全であるということは、あらゆる述語を洩れなく持つということを意味する。この場合、存在論的証明は、以下のようになる。神は、完全であるがゆえに、すべての述語を持つ。したがって「現実存在する」という述語も持つ。ゆえに神は現実存在する。
第二の解釈は、第一の解釈に勝るとも劣らず問題的である。もしも神が完全な存在で、すべての述語を持つのであれば、「虚構」あるいは「不完全」という述語まで持つことになる。述語の多くは対立関係にあるので、神は矛盾を孕んだ存在になってしまう。もし対立する述語のうちどちらか一方しか持たないのであれば、神は完全な存在者、あるいは無限の存在者ではなくなってしまう。
これと同じ問題は、第一の解釈における存在論的証明にも当てはまる。もしも神が実在の世界のみならず思惟の世界をも含む全体者であるならば、思惟の世界における対立する思想が神という一者の元に統一されることになる。量子力学によれば、宇宙は無数の世界の重ね合わせであり、それらも神という一者の元に統一されることになる。その場合、神はどちらの世界でも矛盾を孕んだ存在ということになる。
要するに、どちらの解釈においても、評価的意味を持たない完全な存在者は、評価的意味を持つ完全な存在者、すなわち、全知全能の至高な存在者と結び付かない。そもそも知性や意志は、複数の可能性のうち一つを選び取ることで可能になるのだから、あらゆる可能性、あらゆる述語を統合した全体者は、情報エントロピーが最大であり、いかなる判断もできない。だから、評価的意味を持たない完全な存在者は、何もわからない、何もできない、最低の価値しか持たない無秩序であり、全知全能の至高な存在者とは全く逆の存在者なのである。
3. カントによる存在論的証明の批判

存在論的証明に対する批判としては、カントが『純粋理性批判』で行ったものが有名である。カントによれば、「神は存在する」という判断は、判断一般がそうであるように、分析的判断か総合的判断かのどちらかで、もしも前者ならば、その存在は思惟の中に留まり、もしも後者ならば、その真偽は矛盾律にのみ依拠するわけではないので、「神は存在しない」という述語を否定した判断が神という主語の概念に矛盾するという存在論的証明の主張は成り立たない[7]。
存在論的証明の結論は、少なくともデカルトのものに関して言えば、分析的判断ではない。まず、デカルトが最も確実と考えた「我思う、ゆえに我あり」という判断は分析的判断ではない。考える自我が存在しない世界は理論的には可能でも、考える自我の存在が事実である以上、考える自我が「自我が存在しない」と考えることは不可能である。デカルトの存在論的証明が、デカルト本人の経験に基づく総合的判断に基づいているのだから、その結論は、総合的判断ということになる。
デカルトは、思惟の外部に思惟の対象である世界が現実存在すると考えたが、たとえこの判断が間違っていたとしても、世界が現実存在していることは必然である。なぜならば、思惟が虚構であるのは、思惟の外部に現実の世界が存在するからであって、思惟の外部にいかなる現実の世界も存在しないのであるならば、意識内部の世界はもはや虚構ではなくなってしまう。要するに、すべてが虚構ならば、すべては現実存在でもある。このように、自我を含めた世界の全体が現実存在を少なくとも部分的には含むのだから、神を世界の全体と定義するならば、神の存在は虚構ではないということになる。
カントは、存在論的証明の不合理さを強調するために、貨幣を例に取り、可能的概念と現実的対象との異同を説明している。カントによれば、「ある(Sein)」はレアールな述語ではなく、これを主語に加えても、主語概念は何も変化しない。
しかし、私の財産状態においては、100ターラーというたんなる概念(すなわち100ターレルの可能性)を持つ場合よりも、現実の100ターラーを持つ場合の方がより多くを持つことになる。対象は現実においてはたんに私の概念の内に分析的に含まれているだけではなく、私の(財産状態を規定する)概念に総合的に付け加わるものであるからである。もとより、私の概念の外に存在するからといって、この想像上の100ターラーはそれ自体少しも増えることはないが。[8]
カントは、存在論的証明に対する批判を次のように締めくくっている。
最高存在体の現存在を概念から証明する有名な存在論的(デカルト的)証明においては、あらゆる苦労と努力が失われた。人がたんなる理念によって知見を豊かにすることができないのは、商人が自分の状態を良くしようとして現金在高にいくつかゼロを付け足しても財産を豊かにすることができないのと同じことである。[9]
カントによる100ターラーの議論は有名だが、可能的概念と現実的対象の違いを説明するのに貨幣を用いるのは適切ではない。カントは、ターラー銀貨[10]をターラーの現実的対象と考えていたのだろうが、ターラーの本質は、そういう金属の塊にではなくて、将来100ターラーの価値のある商品と交換するという約束にある。律儀な人が100ターラー分の贈り物をすると約束したならば、それを保証する現実的対象がなくても、私は、100ターラーの貨幣を所有している場合と財産状態が同じになる。逆に100ターラーの硬貨を現実的対象として所有しても、それを発行する政府が消滅すれば、その硬貨は、硬貨ではなくて、たんなる金属の塊になる。したがって、現実的対象よりも可能的概念の方が貨幣の本来のあり方なのである。
もちろん、私が100ターラーの所有をたんに願望しただけでは、その可能的概念である100ターラーは、私の財産とみなすことはできない。私が実際に100ターラーの貨幣を所有しているかどうかは、100ターラーが現実的対象なのか可能的概念にすぎないのかによってではなくて、それが間主観的に承認されているか否かによって決まる。神が存在するかどうかも、同様に、神が現実的対象なのか可能的概念にすぎないのかによってではなくて、それが間主観的に承認されているか否かによって決まる。
現実存在(existence)は、ヨーロッパ言語では《外に-立つ ex-sistere》という意味のラテン語に由来する。アンセルムスもデカルトもカントも、神の現実存在を、意識の外に立つことと理解していたが、神が神として機能する上で重要なこと、たんなる可能的概念以上であるために必要なことは、むしろ個人的意識の外に、つまり社会的意識に立つことであって、意識の外にまで立つ必要はない。
このことは、宗教が意識の内部で完結するということを意味しない。信者は、神を可視化するために偶像を作ってそれを拝むことがある。とはいえ、偶像は神を象徴してはいるだけで、神そのものではない。同様に、貨幣は、金属片や紙片や電気信号によって表されるが、それらは貨幣を象徴してはいるだけで、貨幣そのものではない。神や貨幣の本質は、現実的対象にはないのである。神も貨幣も、誰も信じなくなった段階で存在しなくなり、神や貨幣の現実的対象は、たんなる物になってしまう。
貨幣と神には、交換の不均等を是正するという共通点を持っている。貨幣が信認されているかぎり、ある人の生産が消費よりも多いあるいは少ないことで生み出される不均衡は、貨幣という媒体により、資産あるいは負債という形で埋め合わされる。神による裁きが信じられているかぎり、生前の善行や悪行は、死後の裁きで埋め合わされる。
本来、生前の善行や悪行に対する褒賞や刑罰は、地上の権力者によって生前に行われるべきなのだろうが、地上の権力者は全知全能ではないので、善人が不幸になったり、悪人が幸福になったりする。そこで、道徳的秩序を維持するには、すべての行為を監視する知力と信賞必罰を実行する能力を兼ね備え、この世のみならずあの世をも支配する、あらゆる地上の権力者を越えた権力者の存在が必要になってくる。これが、神、すなわち、全知全能で至高な無限者の存在が社会的に求められる所以である。
神が無限の存在者だからといって、神が世界の全体というわけではない。それは、貨幣が、いかなる商品とも交換可能であるという普遍性を持つからといって、貨幣が商品全体と同一であるのではないのと同じである。原始的な経済の段階では、貨幣は商品価値を持つ商品貨幣であったが、時代とともに自らの商品性を抹殺してきた。今日、貨幣は、商品価値を完全に失うことで、普遍的な媒介者となっている。原始的な宗教の段階では、神は現実的対象であったが、時代とともに自らの具象性を抹殺してきた。ユダヤ教以降の父権宗教では、神は、現実的対象であることを否定し、具象性を完全に失うことで、普遍的な媒介者となっている。
カントは、神の存在を理論的に証明することを断念し、道徳を遵守する者が幸福となるようにという道徳的観点から神の存在を要請した[11]。もしもカントが神をそのようなものとして考えているのであるならば、カントは、存在論的証明の間違いを、分析判断を総合判断にすりかえたことにではなくて、神とは異なる無限者の存在証明を神の存在証明にすりかえたことに求めるべきだったのだ。
4. 参照情報
- ↑“Convincitur ergo etiam insipiens esse vel in intellectu aliquid quo nihil maius cogitari potest, quia hoc, cum audit, intelligit, et quidquid intelligitur, in intellectu est. Et certe id quo maius cogitari nequit, non potest esse in solo intellectu. Si enim vel in solo intellectu est, potest cogitari esse et in re; quod maius est. Si ergo id quo maius cogitari non potest, est in solo intellectu: id ipsum quo maius cogitari non potest, est quo maius cogitari potest. Sed certe hoc esse non potest. Existit ergo procul dubio aliquid quo maius cogitari non valet, et in intellectu et in re." Anselm of Canterbury. “Quod vere sit Deus" in Anselmus Cantuariensis Proslogion. Hackett Publishing Co. (February 17, 2012). 2.
- ↑R. M. Hare. The Language of Morals. Oxford University Press, U.S.A.; Reprint (1991/5/9). p. 111-126.
- ↑“Nam quamvis substantiae quidem idea in me sit ex hoc ipso quòd sim substantia, non tamen idcirco esset idea substantiae infinitae, cùm sim finitus, nisi ab aliquâ substantiâ, quae revera esset infinita, procederet." René Descartes. Meditationes de prima philosophia. University of Notre Dame Press; 1st edition (January 30, 1990). Meditatio III, 23.
- ↑“Jam verò lumine naturali manifestum est tantumdem ad minimum esse debere in causâ efficiente & totali, quantum in ejusdem causae effectu. Nam, quaeso, undenam posset assumere realitatem suam effectus, nisi a causâ? Et quomodo illam ei causa dare posset, nisi etiam haberet? Hinc autem sequitur, nec posse aliquid a nihilo fieri, nec etiam id quod magis perfectum est, hoc est quod plus realitatis in se continet, ab eo quod minus. Atque hoc non modo perspicue verum est de iis effectibus, quorum realitas est actualis sive formalis, sed etiam de ideis, in quibus consideratur tantùm realitas objectiva." René Descartes. Meditationes de prima philosophia. University of Notre Dame Press; 1st edition (January 30, 1990). Meditatio III, 14.
- ↑“Quanquam sane hoc primâ fronte non est omnino perspicuum, sed quandam sophismatis speciem refert. Cùm enim assuetus sim in omnibus aliis rebus existentiam ab essentiâ distinguere, facile mihi persuadeo illam etiam ab essentiâ Dei sejungi posse, atque ita Deum ut non existentem cogitari. Sed tamen diligentius attendenti fit manifestum, non magis posse existentiam ab essentiâ Dei separari, quàm ab essentiâ trianguli magnitudinem trium ejus angulorum acqualium duobus rectis, sive ab ideâ montis ideam vallis: adeo ut non magis repugnet cogitare Deum (hoc est ens summe perfectum) cui desit existentia (hoc est cui desit aliqua perfectio), quàm cogitare montem cui desit vallis." René Descartes. Meditationes de prima philosophia. University of Notre Dame Press; 1st edition (January 30, 1990). Meditatio V, 8.
- ↑AndreasToerl. “Statue of Immanuel Kant in Kaliningrad State University area, Kaliningrad, Russia. Replica by Harald Haacke of the original by Christian Daniel Rauch lost in 1945..” Licensed under CC-BY-SA.
- ↑Immanuel Kant. Kritik der reinen Vernunft. 2. Aufl. 1787. p. 400. Reprinted: Felix Meiner Verlag (July 1, 1998).
- ↑“Aber in meinem Vermögenszustande ist mehr bei hundert wirklichen Talern, als bei dem bloßen Begriffe derselben, (d. i. ihrer Möglichkeit). Denn der Gegenstand ist bei der Wirklichkeit nicht bloß in meinem Begriffe analytisch enthalten, sondern kommt zu meinem Begriffe (der eine Bestimmung meines Zustandes ist) synthetisch hinzu, ohne daß durch dieses Sein außerhalb meinem Begriffe diese gedachten hundert Taler selbst im mindesten vermehrt werden." Immanuel Kant. Kritik der reinen Vernunft. 2. Aufl. 1787. p. 401. Reprinted: Felix Meiner Verlag (July 1, 1998).
- ↑“Es ist also an dem so berühmten ontologischen (cartesianischen) Beweise vom Daseyn eines höchsten Wesens aus Begriffen alle Mühe und Arbeit verloren, und ein Mensch möchte wol eben so wenig aus blossen Ideen an Einsichten reicher werden, als ein Kaufmann an Vermögen, wenn er, um seinen Zustand zu verbessern, seinem Cassenbestande einige Nullen anhängen wollte." Immanuel Kant. Kritik der reinen Vernunft. 2. Aufl. 1787. p. 403. Reprinted: Felix Meiner Verlag (July 1, 1998).
- ↑ターラー銀貨は、当時ヨーロッパ使われていた銀貨の名称で、ドルの語源にもなっている。
- ↑Immanuel Kant. Kritik der praktischen Vernunft. 1787. p. 124. Reprinted: Felix Meiner Verlag; 1 edition (September 1, 2003).





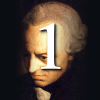


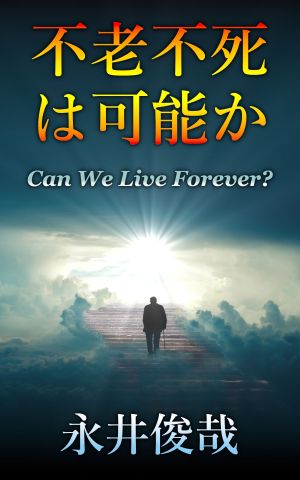

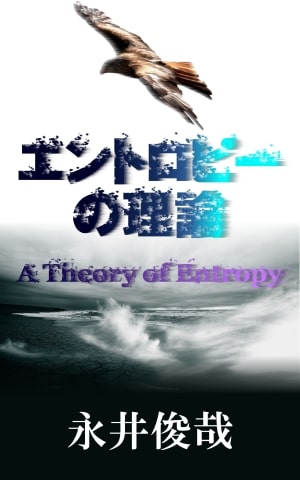

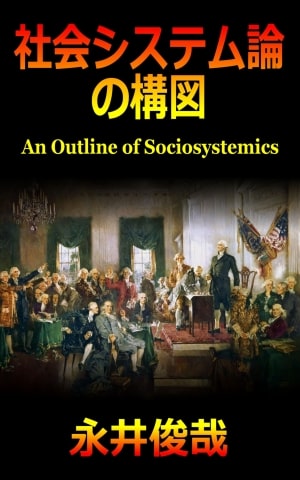

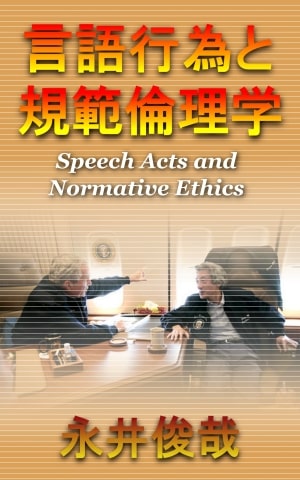
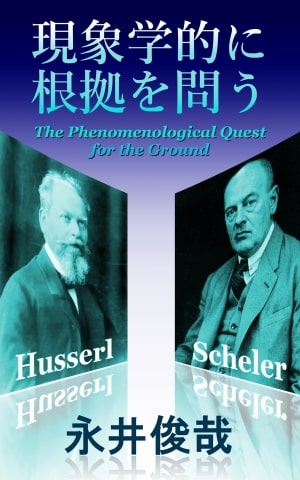
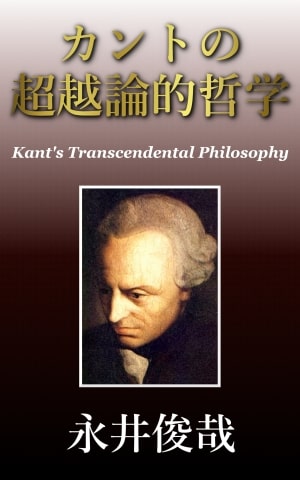
ディスカッション
コメント一覧
要は存在しないってことね
存在するとするなら、どういう意味で存在するのかが問題です。
考えてみると宗教は「障碍」と言う概念を無視している点があると思います。
障碍者が僧侶や神職や神父・牧師になりにくい(在家の僧侶になることも難しい)点。
説法・講話や祝詞をあげる事や聖書の解説に手話をあまり用いない点。
仏教やキリスト教の木造や銅像、宗教絵画に描かれる神仏の姿などに不格好なものがない点。
建物の構造で考えたら古い建物での神社や寺院や教会がバリアフリーが徹底されていない点。
これらの事情により宗教は完全であれ、神仏は完全なる存在であるという方針なのか?
追記
「人間は完全な存在であれ、できないことがない状態」こそが人間として最高である。だから神も完全である、と考えるのは当然ではないかと思います。
「不完全な神」だったら誰も崇拝しないと思うのです。
「架空の存在」だからこそ完全な存在(つまり欠点がない)と言う発想です。
ここで話題となっているのは、一神教の神です。古代の日本やギリシャのような不完全な神は対象外です。特に日本の怨霊信仰では、信仰対象となる神は、政争に敗れ、無念の死を遂げているので、その意味では不完全な神といってよいでしょう。