なぜティックトックが台頭したのか
ショート動画プラットフォームのティックトックが、ショート動画の先駆者ではないのにもかかわらず、ソーシャル・メディアにおけるゲーム・チェンジャーとして注目されている理由は何でしょうか。ティックトックが成功した理由を「農村から都市を包囲する」毛沢東以来の中国の戦術で説明しましょう。

ティックトックのショート動画はなぜ人気なのか
中国企業のバイトダンス(字節跳動)が運営する動画共有サービス、ティックトック(TikTok)が人気を集めています。ティックトックは、2022年に世界で最もダウンロードされたモバイル・アプリとなり[1]、2024年現在、月間アクティブユーザー数は15億人を超えています[2]。あまりの人気に危機感を抱いた米国は、バイトダンスが事業を売却しないなら米国内で運営禁止にする法律を2024年4月に成立させました。

テキストから動画へ、デスクトップからモバイルへというのが現代のコンテンツ・マーケットのトレンドなのですから、スマホ向けに最適化されたショート動画に特化したティックトックが流行するのは当然と思うかもしれません。しかし、そうした説明では、ティックトックの躍進は説明できません。なぜなら、そもそもティックトックは、ショート動画のパイオニアではないからです。
ショート動画を最初に流行らせたのは、2013年1月にローンチしたツイッター(Twitter=現X)傘下のヴァイン(Vine)です。スマホのカメラで6秒以内のショート動画を撮影し、それをユーザー間で共有し、ループ再生できるこのアプリは、瞬く間に人気となりました。しかし、その成功を見たスナップチャット(Snapchat)やインスタグラム(Instagram)といった他のソーシャル・メディアがヴァインのサービスを模倣し、競争が激しくなる中、2017年にヴァインはサービス終了となりました。
バイトダンスが中国国内向けにショート動画アプリを提供したのは2016年で、海外向けにティックトックを提供したのはその翌年です。ショート動画事業への参入という点では、実は後発組なのです。小さな会社が大手のサービスを模倣しても、通常は成功しません。それにもかかわらず、バイトダンスが現在のショート動画ブームにおいて台風の目となったのは、ユーザーに動画をレコメンドするアルゴリズムにパラダイム・シフトをもたらしたからです。
それまでのソーシャル・メディアのフィードは、基本的にフォロー選択の結果に基づいていました。ユーザーがフォローしたアカウントのコンテンツをフィードに表示するというのは合理的に思えます。しかし、アルゴリズムがフォロー関係を重視すると、新規参入が困難になるという弊害があります。フォロワーがいない新規参入のクリエイターは、《フォロワーがいないから表示されない》⇔《表示されないからフォロワーが増えない》という悪循環に陥り、成果を出せないまま挫折してしまいます。他方で消費者にとっては、新しい出会いがないので、既に知っている著名人のアカウントだけをフォローすることになりがちです。
ティックトックは、フォロワー重視のアルゴリズムから関心重視のアルゴリズムへとパラダイムを変えました。ティックトックでは、フォロワーの数は重要ではありません。人工知能が、動画の内容を解析し、フォローしているかどうかとは関係なく、関心を持ちそうなユーザーに表示します。そして、視聴時間が長いなど、エンゲージメントが良好なら、優良な動画と判断して、さらに多くのユーザーに表示する仕組みになっています。無名のクリエイターにとっては、視聴者に発見されるチャンスがあり、視聴者にとっては、未知のクリエイターと出会うチャンスがあります。
2012年に張一鳴(チャン・イーミン)が創業したバイトダンスは、ショート動画事業に進出する前、「今日頭条」(日本語訳:本日のトップニュース)というニュース配信アプリを運営していました。中国にも、もちろん、それ以前からニュース配信アプリはありましたが、伝統的なマスメディアが一般向けにリリースするニュースをプロの編集者がキュレートして読者に一斉配信するという手法を用いていました。これに対して、バイトダンスは、人工知能を使って、読者が興味を持ちそうなニュースを個別に選別して配信し、収入源である広告までパーソナライズしました。また、伝統的なマスメディアだけでなく、誰でもニュース記事を投稿できるようにしました。無名のライターでも、良い記事を書けば、多くの読者に読んでもらえ、収入が得られるようになったということです。バイトダンスは、このスキームをショート動画に適用しました。こうして生まれたのが、ティックトックだったのです。
新規参入が容易なプラットフォームの新規参入
ソーシャル・メディアのようなネットワーク型のサービスにおいては、ネットワーク外部性があります。ネットワーク外部性とは、交換主体の数が増えるにしたがって増加する交換ネットワークの価値の外部性です。交換ネットワークの価値が高まると、より多くの交換主体がそのネットワークに参加するというポジティブ・フィードバックが働くので、ネットワーク間の参加者獲得競争は、勝者総取り(Winner-Takes-All)となる傾向があります。

そのような事例として、上の図に示した電話以外に、ウィンドウズによってロックインされたコンピューターのオペレーティング・システムが挙げられます。ネットワーク上で情報を交換するコンピューターのプラットフォームは、交換相手と同じである方が有利なので、「みんなが使っているからみんなが使う」という状態になるのです。ソーシャル・メディアも同じです。世界最大のソーシャル・メディアであるフェイスブック(Facebook)が、古臭いと言われつつも、今なお世界ではユーザー数を増やし続けるのは、まさに「みんなが使っているからみんなが使う」というポジティブ・フィードバックのおかげなのです。
動画共有サイトで勝者となったのは、ユーチューブ(YouTube)です。ポジティブ・フィードバックによってユーチューブの優位性が維持されただけでなく、勝ち組ユーチューバーも、プラットフォーム内で働くポジティブ・フィードバックによって優位性が維持されました。ユーチューブのフィードは、フォロー関係を重視していたので、フォロワーが多ければ、多く表示され、多く表示されればフォロワーが増えやすくなり、「みんなが見ているからみんなが見る」という結果になったからです。ベストセラーの本を「みんなが読むからみんなが読む」ようになるのと同じような現象です。
その結果、ユーチューブではごく一部のチャンネルにアクセスが集中しました。2018年の研究[4]によると、トップ3%のチャンネルがトラフィックの90%を占めています。また2019年の調査[5]によると、アップロードされた88.4%の動画の再生回数が1000回未満であるのに対して、全体の0.77%にすぎない10万回以上再生された動画が、全再生回数の82.83%を占めています。パレートの法則として、売上げの8割は2割の従業員に依存するといった例がよく挙げられますが、ユーチューブでは、それ以上の集中が起きていたということです。この極端な集中は、ポジティブ・フィードバックのせいと考えてよいでしょう。
2017年から2018年にかけて、ユーチューブは、有害な動画に広告を出したくないという広告主の要望に応える形で、収益化条件を厳しくしました。チャンネル登録者数千人以上や直近一年での総再生時間四千時間以上などが参加条件となったのですが、《フォロワーがいないから表示されない》⇔《表示されないからフォロワーが増えない》という悪循環に陥っている新規参入者は、マネタイズのハードルを高く感じるようになりました。
新規参入が困難になり始めたのは、ユーチューブだけではありません。ユーチューブを運営するグーグル(Google)は、九割以上の市場シェアを持つ検索エンジンのアルゴリズムをアップデートして、ウェブでの新規参入に非常に高いハードルを設定するようになりました。2017年4月のアウル・アップデート(Owl Update)以降、YMYL(Your money or Your life)分野を中心に、E-A-T(Expertise-Authoritativeness-Trustworthiness=専門性-権威性-信頼性)を重視するようになったのです。その結果、検索結果の上位を有名企業や公的組織のサイトが占めるようになり、個人ブログは下位に沈むようになりました。
それ以前のグーグルは、もっと民主的でした。無名の個人が作ったサイトであっても、内容が良ければ、検索上位に表示していました。クリエイターたちも、コンテンツは王様(Content is King)という格言を信じて、高品質なコンテンツ作りに励みました。ところが、偽情報対策のためにE-A-Tを重視して以降、コンテンツではなくて、ドメインの権威が王様となり、個人ブログへのアクセスが激減するようになりました。その結果、個人のクリエイターたちは、ウェブからソーシャル・メディアに活動の場を移しました。しかし、そのソーシャル・メディアでも寡占化が進み、新規参入者の活躍が厳しくなってきました。
バイトダンスがティックトックを提供し始めたのは、ちょうどその頃です。2017年11月に、バイトダンスは、米国でリップ・シンク(口パク)動画共有サービスにより人気を博したミュージカリー(Musical.ly)を買収し、翌年ティックトックと統合して、その人気を引き継ぎました。ミュージカリーの創業者で、現在、バイトダンスの製品・戦略担当副社長を務める朱駿(Alex Zhu)は、既存のソーシャル・メディアからミュージカリーへのクリエイターの移動をヨーロッパからアメリカへの移民に譬えています[6]。
当時のヨーロッパでは階級が固定されていて、下流階級が上流階級に昇格することは困難でした。そこで、多くのヨーロッパの下流階級が、成功のチャンスを求めてアメリカ大陸に渡りました。貴族が存在しない新大陸では、平民でも、才能と努力次第で、大金持ちや権力者になれます。そんなアメリカン・ドリームを体現しようとして米国で作ったソーシャル・メディアが、現在米国で禁止されそうになっているのは、皮肉なことです。
ティックトックが、噂通り、新規参入者に十分なチャンスを与えているのかどうかを確かめるべく、私もこっそり(つまり、既存フォロワーに告知することなく)アカウントを作って、何本か動画をアップロードしてみました。すると、フォロワーがゼロであったにもかかわらず、一本を除いて、すべて1日で3桁以上の再生となりました。特にこの動画は、40万回以上(2024年7月28日現在)再生されました。フォロワー重視であった昔のユーチューブやインスタグラムでは、これほど再生されることはなかったでしょう。後発プラットフォームであるにもかかわらず、先発プラットフォームからクリエイターを引き抜けたのは、新規参入のハードルの低さのおかげということです。
もとより、それだけでは、なぜティックトックが台頭したのかという問いへの答えとしては不十分です。そもそもなぜ若者向けのリップ・シンク動画から始めたのか、なぜティックトックはショート動画からスタートしたのに、段階的に尺の制限を延ばし、今では長編動画を奨励するようになったのかといった問いに答えるには、毛沢東以来の中国の戦術について説明する必要があります。
辺境革命としてのショート動画革命
2024年6月20日に告示された東京都知事選挙で、三選を目指す小池知事は、選挙活動を八丈島から始めました。それは、マスメディアの記者から学歴疑惑を追及されるのを避けるためではありません。まだそうした疑惑が浮上していなかった8年前の初当選時においても、小池百合子は、告示翌日に八丈島から演説を開始しています。選挙戦を過疎地(川上)から開始し、徐々に人口の多い地域に移動し、最終日に最も人口が多い場所(河口)で演説を行う選挙戦術は、川上戦術と呼ばれます。最初に過疎地に行けば、現地の人々からありがたがれます。その評判を、より浮動票の多い都市部へと川の水のごとく広げていって、勝利をつかむという方法です。
川上戦術は、田中角栄が提唱し、小沢一郎(小池のかつてのボス)が継承したと言われていますが、これとよく似た戦術を毛沢東が実践していました。それは、農村から都市を包囲する(农村包围城市[7])革命戦術です。上海を本拠としていた中国共産党は、ヨーロッパの共産党と同様、都市から革命を起こそうとしていましたが、国民党の強力な軍隊に討伐され、失敗しました。これに対して、毛沢東は、国民党の支配が弱かった農村という攻めやすいところから攻め始めました[8]。地主や富農の土地を没収して貧農に分配すれば、貧農が味方になります。農村に次々に革命拠点を作り、数で優位に立ち、最終的には都市にいる敵を包囲殲滅するという戦術を用いることで、毛沢東は中国全土を掌握しました。

毛沢東の革命戦術は、もう少し一般化するなら、辺境革命論で説明可能です。勝者は中心を支配し、自分の既得権益を守ろうとして、保守的になります。中心からイノベーションが起きないのは、起こす必要性が勝者にないからです。他方で、辺境は、その重要性の低さから、イノベーションを起こしやすいので、中央の勝者に挑むチャレンジャーは、まず辺境で小さな成功をおさめ、そこに拠点を作り、勢力を拡大し、最終的に中心に陣取る勝者を包囲殲滅します。政治的な革命だけでなく、経営における破壊的イノベーションや科学におけるパラダイム・シフトは、辺境から始まって、中心に波及する形で完遂されます。
毛沢東は、大躍進政策の失敗により失脚しましたが、文化大革命で復権する時にも、辺境革命的な戦術を使いました。政治や経済ではなく、文化という権力にとって辺境的なジャンルで、若者という辺境の年齢層を扇動して、造反有理を主張したのです。この戦術の適用は、国内にとどまりません。中華人民共和国は、ソ連との関係が悪化すると、辺境革命的な戦術を国際政治に適用し、国際社会の辺境というべきアフリカを支援するようになりました。第二の毛沢東を目指す習近平総書記が、一帯一路構想のもと、米国から見て辺境に位置する旧大陸の発展途上国と連帯して、米国の覇権に挑戦するのも、伝統的な外交方針に基づいてのことなのです。
毛沢東の戦術は、中国のビジネスマンにも受け継がれています。バイトダンスの張一鳴にせよ、ミュージカリーの朱駿にせよ、軽薄短小の辺境から攻略を開始し、そこに拠点を作ってから、本命の重厚長大の中心に進撃するという辺境革命的な手法を用いています。バイトダンスの最初の成功したサービス、今日頭条は、ニュース記事という誰でも簡単に書けるコンテンツを配信しました。ミュージカリーは、歌わずにリップ・シンクするだけのダンス動画という誰でもスマホで作れるコンテンツを配信しました。辺境的な生産者が作った軽薄短小のコンテンツでも、辺境的な消費者には受け入れられます。毛沢東が辺境で富農と貧農の格差を解消して貧農から支持されたように、ティックトックは、辺境メディアでプロと素人の格差を解消して、素人から支持されました。
2021年発表のアップエイプの報告[11]によると、米国におけるティックトック・ユーザーで最も多いのは10~19歳(25%)、次いで20~29歳(22.4%)、30~39歳(21.7%)、40~49歳(20.3%)、50歳以上(11%)と年齢が高くなるにつれて減っていきます。また、2021年発表のピュー研究所の調査結果[12]によると、米国でティックトックを使っている成人の51%が5万ドル未満で、大卒は19%しかいません。つまり、このころのティックトック・ユーザーには、低年齢、低学歴、低所得を特徴とする辺境的なユーザーが多かったということです。辺境的な消費者は、購買力が低いので、既存の大手ソーシャル・メディアから軽視されがちです。そこに新規参入者が《商機=勝機》を見出したのです。
ティックトックは、辺境からサービスを始めましたが、辺境に留まろうとはしませんでした。東京都知事選挙の活動を八丈島から始めるのは良いとしても、そこにとどまる限り、選挙には勝てません。それと同じです。ヴァインが、ショート動画の先駆者であったのにもかかわらず、失敗に終わったのは、6秒以内という当初のルールに固執して、辺境にとどまり、辺境から中心へと事業を拡大しなかったからです。低年齢、低学歴、低所得の辺境的な消費者だけを顧客にすると、収益が伸びないので、そのままでは、中心を支配する覇者に負けてしまいます。実際、ヴァインは、収益性の低さから、サービス停止となりました。
ティックトックは、ヴァインの轍を踏みませんでした。ユーザー数の増加とともに、当初15秒であった制限時間は、1分、3分、10分というように段階的に引き上げられ、2024年5月には、60分となりました。また、ティックトックの動画は、2023年2月に、スマート・フォンだけでなく、スマート・テレビでも視聴できるようになり、短尺縦長動画だけでなく、長尺横長動画もフィードでお薦めされるようになりました。2024年4月に発表されたクリエイター向け収益化プログラム(Creator Rewards Program)では、1分以上の長尺動画が収益対象として奨励されています[13]。動画の尺だけでなく、内容も、ダンスだけでなく、あらゆるジャンルを網羅するようになりました。大手が軽視していた辺境から出発したティックトックは、ついに動画共有サービスの覇者、ユーチューブの中心領域にまで進出したのです。これは、まさに「農村から都市を包囲する」毛沢東の方法通りの事業展開です。
もとより、その勢いで、中心の覇者を包囲殲滅とまではいきそうにありません。ティックトックは、中国企業であるがゆえに、各国から警戒されているからです。ティックトックのレコメンド・エンジンが優れているのは、非常に多くの個人情報を収集しているからと推測され、この点で危険視されるのです。インドなどいくつかの国で禁止されたのに続いて、米国でも禁止されそうになっています。

米国の同盟国である日本でも、将来禁止になるかもしれません。しかし、仮にそうなったとしても、ティックトックから他のプラットフォームに波及したアルゴリズムのパラダイム・シフトが後退することはないでしょう。
例えば、インスタグラムは、2020年8月にティックトックに類似したリール動画投稿サービスを始めただけでなく、2024年4月には、アルゴリズムもティックトック式に変更しました[14]。それまで、インスタグラムは、投稿をまず一部のフォロワーに表示し、反応が良ければ、すべてのフォロワーに表示し、さらに反応が良ければフォロワー以外にも表示するという方法を用いていました。このアルゴリズムは、最初から多くのフォロワーを持つ有名人には有利ですが、そうではない一般人にとっては不利です。しかし、アルゴリズムをティックトック式にしたおかげで、新規参入が容易になりました。私も、インスタグラムにアカウントを作って、試しに何本か投稿したところ、フォロワーがゼロであるにもかかわらず、再生回数は三桁となりました。
グーグルの検索エンジンのアルゴリズムにも変化が見られます。2022年に、グーグルは、ヘルプフル・コンテンツ・アップデートを実施しました[15]。E-A-T にもう一つの E(経験)が加わって、E-E-A-T となり、個人的な経験も重視されるようになったのです[16]。その結果、「フォーラムのスレッドへのコメント、あまり知られていないブログの記事、特定のトピックに関する独自の専門知識を持つ記事など」の「隠れた宝石」が検索結果に表示されるようになりました[17]。冬の時代を迎えていた個人ブログもようやく日の目を見ることになりそうです。
朱駿は、既存のソーシャル・メディアを階級が固定されたヨーロッパに譬えていましたが、そのヨーロッパでも、市民革命以降、貴族が没落し、民主化が進みました。米国ほどではないにせよ、ヨーロッパでも、一般人に出世の道が開かれるようになりました。ビッグ・テックのプラットフォームによる市場の寡占化が進む中、プラットフォーム内部でも勝ち組と負け組の固定化が進んでいただけに、ティックトックのような新規参入が容易なプラットフォームの新規参入は、コンテンツ市場の活性化に貢献したと評価できます。これまでも、情報革命は、権力の脱中心化と流動化をもたらしてきたし、今後もそうあるべきでしょう。
参照情報
- マシュー・ブレナン, 露久保由美子『なぜ、TikTokは世界一になれたのか?』かんき出版 (2022/7/21).
- 黄 未来『TikTok 最強のSNSは中国から生まれる』ダイヤモンド社; 第1版 (2019/10/30).
- 興梠 一郎『毛沢東 革命と独裁の原点』中央公論新社 (2023/12/7).
- ↑Statista. “Most downloaded apps worldwide 2022.” Published by Laura Ceci, May 22, 2024.
- ↑Statista. “Biggest social media platforms by users 2024.” Published by Stacy Jo Dixon, Jul 10, 2024.
- ↑Woody993. “Diagram showing the network effect in a few simple phone networks." 31 May 2011. Licensed under CC-0.
- ↑Bärtl, Mathias. “YouTube Channels, Uploads and Views: A Statistical Analysis of the Past 10 Years.” Convergence 24, no. 1 (February 1, 2018): 16–32.
- ↑Pex. “State of YouTube 2019.” AUG 4, 2020.
- ↑“Musical.ly’s Alex Zhu on Igniting Viral Growth and Building a User Community 2016.” 10:45 – 13:21. YouTube.
- ↑中国军网. “毛泽东关于农村包围城市、武装夺取政权思想的提出.” 中国共产党历史网. 责任编辑:吴昊.
- ↑“「農村から都市を包囲する」道を開く.” 人民中国インターネット版. 2011年5月.
- ↑U.S. Army. “Communist Offensives April – October 1949." Licensed under CC-0.
- ↑Orihara1. “Mao Zedong’s Proclamation of The People’s Republic of China during a Speech on October 1, 1949." Licensed under CC-0.
- ↑App Ape. “Distribution of TikTok users in the United States as of March 2021, by age group". Retrieved from statista.
- ↑Pew Research Center. “Demographics of Social Media Users and Adoption in the United States.” 2021, April 7.
- ↑“Be at least one minute long." ― TikTok Help Center. “What are the video requirements under the Creator Rewards Program?” in Creator Rewards Program.
- ↑Instagram. “Helping Creators Find New Audiences.” Instagram for Creators. April 30, 2024.
- ↑Google for Developers. “What creators should know about Google’s August 2022 helpful content update.” Google Search Central Blog. Thursday, August 18, 2022.
- ↑Google for Developers. “Our latest update to the quality rater guidelines: E-A-T gets an extra E for Experience.” Google Search Central Blog. Thursday, December 15, 2022.
- ↑Google SearchLiaison. “Helpful information can often live in unexpected or hard-to-find places: a comment in a forum thread, a post on a little-known blog, or an article with unique expertise on a topic. Our helpful content ranking system will soon show more of these “hidden gems” on Search, particularly when we think they’ll improve the results.” X.com May 10, 2023.










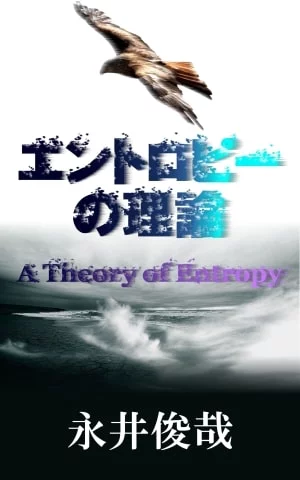

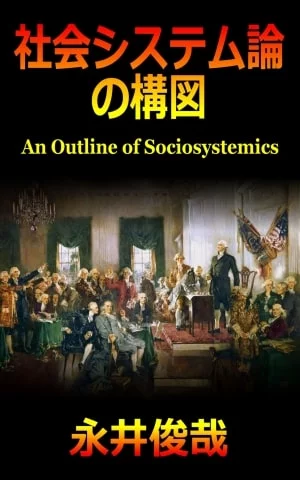

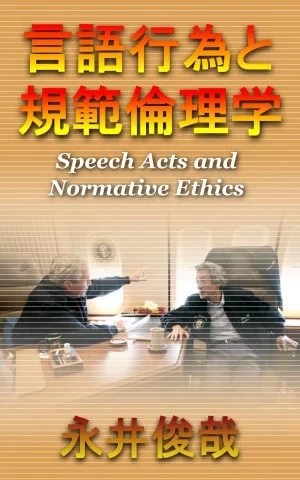
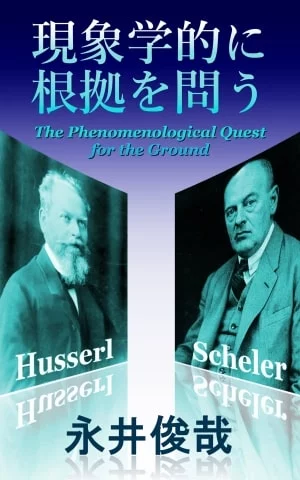

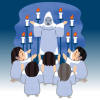




ディスカッション
コメント一覧
投稿ありがとうございます。TikTokを閲覧してみましたが、印象的だったのはコンテンツブロッカーをOFFにしても不快な広告やコンテンツは表示されませんでした。YouTubeのほうは広告ブロッカー(=コンテンツブロッカー)の使用をしないように画面に警告を出すようになっています。巷には、広告はサービスの対価だからブロックしないでほしいという意見があるようで、危うくうなづきそうになりました。がしかし例えば、CMはテレビ放映の対価だからCM中に席を立たないでほしいという主張にうなづけないことと同様に、その主張にもうなづけません。
ショート動画が中心だと、広告で稼げないので、ショッピングで収益を得ようとしているようです。YouTube もショッピング・アフィリエイト・プログラムを実験的に開始しました。広告に過度に依存しないビジネス・モデルを構築することが、各プラットフォームの課題になっています。
農地改革によって辺境が保守化し、中央で保守合同が起こったと考えれば日本でも辺境革命が起こっていたのでしょうか。
むしろ、農村から辺境革命が起きないようにGHQが先手を打ったと考えた方が適切です。私は、日本的経営を「本物の社会主義革命あるいは共産主義革命を阻止するための妥協策」と特徴付けましたが、同じことは農地改革についても言えます。
中央の思考を想像してみると、辺境革命阻止のための懐柔策には2通りあります。ひとつは現金支給、もうひとつは農地や不動産などを与える場合です。直接懐柔か間接懐柔かということです。景気の谷間のときは現金支給で懐柔できるでしょう。デフレがひどくなったら、お金を生み出せない資産や市場をまるごと政府が所有して現金を流します(=公有化・公営化)。一方インフレ下では現金を与えるよりも、お金を稼げそうな資産や市場を明け渡す間接懐柔のほうが効き目がありそうです。つまりデフレ下では直接懐柔による中央集権化が進み、インフレ下では間接懐柔による脱中心化が進みます。
中心が革命を阻止するための代表的な手法は、分割統治です。辺境の中で体制よりの半辺境にある程度の特権を与えると、半辺境は与えられた既得権益を守るために、革命に反対するようになります。