太平洋戦争における保守と革新
戦後の日本人は、保守と革新が右派と左派の関係にあり、保守勢力が好戦的であるのに対して、革新勢力は平和主義者であると考えがちである。しかし、戦前の日本を満州事変以降の自滅的な侵略戦争に駆り立てたのは、保守勢力ではなくて、一見すると右翼的であるが、実は左翼的な革新勢力であった。保守と革新という観点から、近現代の日本の歴史を振り返ってみたい。

1. 保守の戦争と革新の戦争
大日本帝国の歴史は、侵略戦争と領土拡大の歴史であったと一括りにされる傾向があるが、大日本帝国時代の日本の戦争は、第一次世界大戦以前と満州事変以後では、その性格が大きく異なる。すなわち、第一次世界大戦までは、日本は、勝つ見込みのある戦争しかしなかったし、実際ほとんどの戦争で勝ち続けていた。また、戦争は、当時の国際法に則って行われ、戦争による領土の獲得も、すべて国際的に承認されていた。しかし、満州事変から太平洋戦争に到る一連の戦争は、勝つ見込みのほとんどない無謀な戦争であったし、満州国建国以降の支配圏の拡張は、国際的に非難されるものであった。要するに、リスクの大きさと国際的な承認という点で雲泥の差があったのである。
このような違いはなぜ生まれたのだろうか。私は、第一次世界大戦までの日本の戦争が保守派による戦争であったのに対して、満州事変から太平洋戦争に到る一連の戦争は、革新派によって惹き起こされた戦争であったがゆえに、その性格が大きく異なるのではないかと考えている。保守派とは、社会の上層部を占める特権階級で、自分の利権を確実に増やす、勝つ見込みのある戦争ならするが、利権をすべて失うことになる、勝つ見込みのない冒険的戦争に対しては慎重になる。これに対して、特権から疎外された社会の下層部は、失う恐れのある利権をほとんど持たないがゆえに、自分たちの待遇改善のためなら、ハイリスクな戦争をも辞さない。それどころか、彼らの中には、戦争に負けた方が革命を起こしやすいという理由で戦争を支持する共産主義者たちまでいる。
明治維新以後、特権階級となった保守派とは、維新政府樹立に功績があった薩長土肥、なかんずく、薩摩藩と長州藩の出身者たちである。彼らは、維新政府樹立後、藩閥を形成し、維新政府と敵対した佐幕派、とりわけ、戊辰戦争で最後まで維新政府と戦った東北諸藩の出身者たちを長らく冷遇し続けた。日本の軍部も第一次世界大戦の頃までは、薩長の軍閥によって支配されていた。なかでも、戊辰戦争、西南戦争、日清戦争、日露戦争で軍功をあげた長州出身の軍人、山縣有朋は、軍閥の象徴的存在で、1921年に失脚するまで、日本の陸軍、否、日本の国家権力の頂点に君臨した。
山縣は、議会を無視した超然主義の方針を採り、そのため、山縣の軍国主義は、民主主義を無視したファシズム期の軍国主義と安易に同一視されがちである。たしかに、山縣は、日露戦争後、ロシア帝国との協調により、中国から英米を排除するという、日ソ中立条約を結んで、日中戦争を行ったファシズム期の日本の軍国主義者と似たような外交戦略を試みたこともあったが、1917年にロシア革命が起きてロシアが共産主義の支配下に入ると、山縣は自分の外交戦略の失敗を認め、1918年以降、親英米派の原敬を、盛岡藩出身で、立憲政友会総裁であるにもかかわらず、首相にして、英米との協調に努めた[2]。このあたりが、勝つ見込みがなくなっても、際限もなく戦争を続行したファシズム期の軍国主義と異なるところである。
2. 内ゲバ型革新と外ゲバ型革新
山縣が権力を掌握していた間、日本は、無謀な戦争や国際的に非難される戦争はしなかった。また、日本の軍部がクーデターを起こしたり、内閣の意向を無視して暴走したりしたことはなかった。このことは、山縣がリーダーとして優れていたということを意味していない。仮に山縣がもっと早い時期に失脚ないし死去したとしても、保守派は、第一次世界大戦終結の頃までは保守的な政治と外交を続けることに成功しただろう。ところが、第一次世界大戦終結以降、日本経済は、明治維新以来例を見ないほど長期的で深刻なデフレを経験するようになり、これが革新勢力の台頭を許すこととなった。山縣は失脚後すぐに死去し、元老は西園寺公望一人だけとなった。彼は、英米との協調を主張し、革新勢力の台頭を抑えようとしたが、結局それには失敗した。
藩閥政治に対する非特権階級の不満は、維新政府発足当時からあった。ただし、経済が順調に成長していた明治時代においては、その不満はあまり先鋭化することはなく、藩閥外勢力は、言論を通じて自由民権運動を進め、穏健な手段で藩閥政治の弊害を是正しようとした。ところが、世界恐慌(日本では昭和恐慌)でデフレが深刻になると、下層民たちはもっと過激な方法で、つまりゲバルト(Gewalt 暴力)を用いて階級社会を打破しようとするようになった。これからみるように、格差を解消するために、ゲバルトは、国家の内向きと外向きに向かった。それぞれを内ゲバ型革新と外ゲバ型革新と名付けることにしよう。
まず、内ゲバ型革新であるが、これは、ゲバルトを国内の特権階級に振り向け、階級なき平等な社会を国内だけでも作ろうとする左翼的な革新運動で、その代表的な理論的指導者は北一輝であった。北一輝は右翼思想家と一般に認知されているが、彼の主著『日本改造法案大綱』を読めばわかるとおり、彼が言っている「改造」とは、社会主義(共産主義)革命以外の何物でもない。1931年の三月事件、十月事件、1932年の血盟団事件、五・一五事件、陸軍士官学校事件、1933年の神兵隊事件、1936年の二・二六事件といった昭和恐慌の時代に起きた軍部のクーデターは、実はたんなるクーデターではなくて、君側の奸(藩閥)を取り除き、天皇親政による階級なき平等な社会を作ることを目指す社会主義(共産主義)革命であった。
内ゲバ型革新の最後にして最大のものは二・二六事件である。二・二六事件というと、陸軍内部における皇道派と統制派という二つのセクトによるたんなる権力争いと見られがちであるが、もともと「皇道派というのは藩閥に反旗を翻した荒本、真崎等を中心として[3]」集まった青年将校たちのグループであるのだから、やはり藩閥政治打破のための革命と位置付けることができる。
二・二六事件を率先して鎮圧したのは、当時戒厳司令部参謀だった石原莞爾であった。しかし、石原は、決して国内の革新に反対していたわけではなかった。石原は、東北の出身ということもあって、藩閥政治には批判的だった。山口重次は、庄内藩士だった父からの影響として、次のようなエピソードを紹介している。
父の啓介は、よく言い聞かせていた。
「東北には、ずいぶん、すぐれた人物がいたが、薩長政府にそむいたために、賊という汚名をかぶせられてしまった。維新後、薩長政府は、四民平等というて、士農工商の差別をとりのぞいた。それで農民でも、町人でも、足軽でも、どんな身分のひくい者でも、立派な地位につくことが出来たとはいえ、この恩恵に浴するのは、自分たちの藩だけで、一旦敵となった東北人のことなどは念頭におかなかった。だが、これからは、それでは通らぬ。お前の時代になったら、名ばかりの四民平等でなく、真の四民平等が実現されて、理非曲直の明白な道義の世界をつくりあげなくては、本当でない」
感受性の強い彼がうけた、この父の一言は、彼の一生をとおして貫いたという。[4]
石原は、しかしながら、国内だけで平等を実現するというスケールの小さな内ゲバ型革新を目指したのではなかった。石原は、ゲバルトを外部へと振り向け、最終戦争(日米決戦)に勝つことにより、白人が有色人種を支配する階級社会を地球規模で是正し、それにより、同時に国内の革新も実行しようとしていた。石原は、関東軍作戦参謀だった1931年に、東北(盛岡藩)出身の関東軍高級参謀、板垣征四郎とともに、満洲事変を惹き起こしたが、後に彼が述べたように、これは、昭和維新という国内外の革新を行うための手段だった。
当時私共の当面の敵は支那軍閥であつた、然し此敵と戦ひ、之を撃破し乍ら、私共は絶えず次の国際的な相手を顧慮し、此欧米覇道勢力の完全な覆滅の為の物心両面の備を保持して居らねばならなかつた、世界最終戦を予想しての八紘一宇の為の次の階梯への準備である。
更に日本国内の維新改革も重大な問題であつた。満洲事変は当時の日本国内の政治、経済思想の行詰りと之が維新の要求とにも大きな関聯を有して居たのである。昭和維新の先駆としての満洲事変の性格である。[5]
石原は第二次世界大戦参戦前夜の心境を次のように語っている。
第二次欧州大戦で新しい時代が来たように考える人が多いのですが、私は第一次欧州大戦によって展開された自由主義から統制主義への革新、即ち昭和維新の急進展と見るのであります。
昭和維新は日本だけの問題ではありません。本当に東亜の諸民族の力を総合的に発揮して、西洋文明の代表者と決勝戦を交える準備を完了するのであります。明治維新の眼目が王政復古にあったが如く、廃藩置県にあった如く、昭和維新の政治的眼目は東亜連盟の結成にある。満州事変によってその原則は発見され、今日ようやく国家の方針となろうとしています。
[…]
第一次欧州大戦以来、大国難を突破した国が逐次、自由主義から統制主義への社会的革命を実行した。日本も満州事変を契機として、この革新即ち昭和維新期に入ったのであるが、多くの知識人は依然として内心では自由主義にあこがれ、また口に自由主義を非難する人々も多くは自由主義的に行動していた。しかるに支那事変の進展中に、高度国防国家建設は、たちまち国民の常識となってしまった。冷静に顧みれば、平和時には全く思い及ばぬ驚異的変化が、何の不思議もなく行なわれてしまったのである。[6]
ここからもわかるように、石原は、昭和維新を明治維新とのアナロジーで理解している。但し、石原が考えていた昭和維新は、たんなる国内の革新ではなくて、国内外に及ぶ革新であるという点において、さらに、維新の指導者が、維新成就後、特権を要求せずに、平等な社会を目指すという点において明治維新とは異なる。
東亜連盟は東亜新秩序の初歩である。しかも指導国家と自称せず、まず全く平等の立場において連盟を結成せんとするわれらの主張は世人から、ややもすれば軟弱と非難される。しかり、確かにいわゆる強硬ではない。しかし八紘一宇の大理想必成を信ずるわれらは絶対の大安心に立って、現実は自然の順序よき発展によるべきことを忘れず、最も着実な実行を期するものである。下手に出れば相手はつけあがるなどと恐れる人々は、八紘一宇を口にする資格がない。[7]
もしも、昭和維新の指導者(日本)が、最終戦争で特権を持つようになれば、その特権から疎外された国々は、格差を解消しようとして再び維新を企てるようになり、かくして最終戦争が、最終の戦争ではなくなってしまう。石原は、満州国を日本の傀儡国家ではなくて、日本と対等の独立国家にしようとしたが、これは、革新が新たな格差を生み出してはいけないという考えに基づいていた。
満州事変で突破口を開いた外ゲバ型革新は、その後、アジアを白人支配から開放するという大義名分の下、日中戦争から太平洋戦争へと戦争の規模を拡大しつつ、続けられた。石原の指摘の通り、一連の戦争により、日本は自由主義経済から統制主義経済、すなわち、当時「革新官僚」と呼ばれていた人たちによる計画経済へと移行し、国内の革新も遂行された。そして、戦時経済への突入により、日本経済はデフレから脱却することができたが、その代償はあまりにも大きかった。
石原は、各民族を平等に扱う東亜新秩序を夢見たが、それでは、何のために日本人が血を流しているのかわからなくなる。日本国内の世論の支持を得られなかったという点で、石原の戦略は非現実的であったと言わざるを得ない。石原が始めた外ゲバ型革新は、その後もっとエゴイスティックに日本の国益を追求する侵略戦争へと変質していき、石原が最終戦争で日本が同盟するべきだと考えていた中華民国と日本が戦うことになった。石原は日中戦争を進める東条英機と対立して、左遷された。最終的に太平洋戦争を始めたのは東条英機であるが、彼もまた東北(盛岡藩)出身の家系に位置していた。
3. 直接的革新と間接的革新
保守勢力が日本を支配していた時、日本は、当時の世界の覇権国家であった英米と協調しつつ、手堅く戦争に勝利してきた。しかし、山縣失脚後、革新勢力が台頭し、日本は、覇権国家の英米と戦争をするという、当時の日本の国力を考えると無謀としか言いようのない賭けに出た。日本がこのような自殺行為に打って出た理由は何か。石原は、日本が最終戦争に勝てると考えていたが、外ゲバ型革新を推進した人たちは、必ずしもそういう愛国者たちばかりではなかった。尾崎秀実のように、日本が敗北した方が、日本で共産主義革命を起こしやすいという理由で、日本の戦争拡大を謀った人もいた。尾崎は、近衛文麿のブレーンで、日中戦争が起きた時、近衛が「爾後國民政府ヲ對手トセズ」という声明を出して、日中戦争の泥沼化させた背景には、尾崎の画策があった。
石原と尾崎を区別しようとするならば、内ゲバ型革新と外ゲバ型革新という区別だけでは不十分である。非特権階級が特権階級をゲバルトを用いて直接倒そうとする直接的革新と特権階級同士を戦わせ、非特権階級が漁夫の利を得る形で権力を握ることができるようにしようとする間接的革新という新しい区別が必要である。日中戦争は、こうした間接的革新を実行しようとする共産主義者たちの策略に日本と蒋介石が嵌められたことによって起こった。日本と蒋介石の中華民国が力を消耗すればするほど、毛沢東率いる中国共産党にとっては有利になったのである。
1964年に、当時社会党の副委員長であった佐々木更三と会見した時、毛沢東は、侵略戦争を謝罪する佐々木に対して、次のように言ったと伝えられている。
日本軍国主義は中国に大きな利益をもたらしました。おかげで、中国人民は権力を奪取しました。日本の皇軍なしには、わたくしたちが権力を奪取することは不可能だったのです。[8]
尾崎は、後にゾルゲ事件で逮捕され、ソ連のスパイであることが発覚した。この事件にショックを受けた近衛は、終戦間際に、以下のような見解を昭和天皇に上奏した。
職業軍人の大部分は、中以下の家庭出身者にして、其多くは共産的主張を受け入れ易き境遇にあり、只彼等は軍隊教育に於て、国体観念丈は徹底的に叩き込まれ居るを以て、共産分子は国体と共産主義の両立論を以て彼等を引きずらんとしつつあるものに御座候。
抑も満洲事変、支那事変を起し、之を拡大して遂に大東亜戦争にまで導き来れるは、是等軍部一味の意識的計画なりし事今や明瞭なリと存候。満洲事変当時、彼等が事変の目的は国内革新にありと公言せるは、有名なる事実に御座候。支那事変当時も、「事変は永引くがよろし、事変解決せば国内革新はできなくなる」と公言せしは、此の一味の中心人物に御座候。是等軍部内一味の者の革新論の狙ひは、必ずしも共産革命に非ずとするも、これを取巻く一部官僚及び民間有志(之を右翼と云ふも可、左翼と云ふも可なり。所謂右翼は国体の衣を着けたる共産主義なり)は、意識的に共産革命に迄引きずらんとする意図を包蔵し居り、無知単純なる軍人、之に躍らされたりと見て大過なしと存候。[9]
共産分子に躍らされた革新シンパは、「無知単純なる軍人」だけではなかった。近衛本人もそうだった。
4. 米国版革新としてのニューディール
共産主義者は日本だけでなくて、米国にもいた。フランクリン・ルーズベルト大統領の側近に多くのソ連のスパイがいたが、これは、ルーズベルト大統領本人が共産主義シンパであったためである。財務次官補のハリー・デクスター・ホワイトの強硬な試案がハル・ノートとして採用され、日米開戦を決定的にしたり、国務省高官のアルジャー・ヒスの活躍により、ソ連に有利なヤルタ協定が結ばれたりして、ソ連が目指す世界の共産主義化に有利な事態が展開した。
私は、米国の参戦は、ルーズベルトにとってニューディール政策の継続であったという解釈を提示した。その時には、ニューディール政策という言葉を、たんに、財政支出の拡大によるリフレ政策という意味で使っていたのだが、ここで、ニューディールとは何だったのかということを、その語源にさかのぼって、改めて考えてみたい。ニューディール(New Deal)という英語は、本来、トランプゲームでカードを配り直して新たにゲームを始めることをいう。トランプゲームは勝ち組と負け組みという格差を生み出す。これに対して、ニューディールは、カードを回収して、格差を解消し、もう一度新たなルールの下でゲームをすることを意味する。だから、私は、「ニューディール」という言葉は、当時の日本での流行した「革新」に相当すると思う。ちなみに、漢字の「革」は、『説文』(三下)にあるように、「獸皮なり。其の毛を治去して、之れを革更するなり」、すなわち、毛を剃ってゼロから新たに始めるという意味の漢字であり、革新は、格差という、長く伸びてしまった毛を根こそぎ除去するという意味で、ニューディールなのである。
ルーズベルトは、社会主義的な政策により、資本家と労働者の格差を是正し、所得の再配分を行おうとした。しかし、国内の革新は、議会における保守派の反対で思うように進まなかった。そこでルーズベルトは、日本を挑発して、真珠湾を攻撃させ、この「裏口」を通って、第二次世界大戦に参戦した。これは、石原莞爾が外ゲバ型革新によって国内外を革新しようとしたのと同じである。ルーズベルトは第二次世界大戦終結前に死去したが、ニューディールを世界全体に広げようとする彼の野望は、第二次世界大戦後の共産主義勢力拡大により、かなりの程度実現した。すなわち、イギリスやフランスといったかつての植民地大国や日本やドイツといった新興工業国家の手から多くのカードが取り上げられ、共産主義者へと新たに配り直された。そして戦時経済を通して、米国経済は、自由主義経済から軍産複合体が支配する混合経済へと変貌していったのである。
5. 格差を固定する保守とリセットを目指す革新
一般的に言って、戦争や競争が起きると、勝ち組と負け組みが決まり、格差が生まれる。勝ち組は、自分たちが手にした既得権益を永続的に維持しようとして、勝ち組ゆえに持っている権力を使って、格差を固定しようとする。合法的に上昇する道を閉ざされた負け組みが、固定された格差を解体しようと思ったら、直接的にか間接的にか、内的にか外的にかは別として、ゲバルトを用いるしかない。
長州藩と薩摩藩は、明治維新における勝ち組だったが、江戸時代においては、負け組みだった。関が原の合戦と大坂の陣は、江戸維新とでも言うべき日本国内における直接的内ゲバ型革新であり、戦国時代の勝ち組だった豊臣家は、これにより没落し、豊臣秀吉に臣従していた徳川家康が、新たな勝ち組となった。徳川家康は、豊臣秀吉の朝鮮出兵に積極的に賛同したが、これは、秀吉が海外遠征で力を消耗することを期待した上でのことであり、家康からすれば、間接的外ゲバ型革新ということになる。江戸時代になってから、関が原の合戦で西軍に所属していた、あるいは豊臣家とつながりが深かった大名は外様大名として冷遇された。毛利氏と島津氏は、西軍であったから、外様大名として、長州藩と薩摩藩に封じられていた。
パクス・トクガワーナは、200年以上続いたが、幕末になると、江戸幕府の支配体制は揺らぎ始めた。江戸幕府の反体制派は、当初、攘夷という外ゲバ型革新を試みたが、幕府にその意思がないことから、内ゲバ型革新に転じた。それは明治維新として成功した。その後、十分な特権に与ることができなかった多くの士族は、征韓論を唱えて、外ゲバ型革新を試みたが、維新政府にその意思がないことから、内ゲバ型革新に転じた。だが、そうした不平士族の反乱は、西南戦争を最後に、完全に鎮圧された。かくして、薩摩藩と長州藩の出身者が特権的な地位を占める藩閥政治が始まった。この格差社会を打破するために、非特権階級がどのような革新を企てたかに関しては、これまで述べてきたとおりである。
日本を共産主義化しようとする革新勢力の試みは失敗し、戦後の日本は、米国の占領政策により、自由主義的要素を残す混合経済となった。とりわけ、米ソの対立が表面化してから、米国はレッド・パージを行うなど、革新勢力の弾圧を始めた。この動きは、当時「逆コース」と呼ばれたが、こうした名称は、太平洋戦争が革新勢力ではなくて、保守勢力によって推進されたという誤解に基づいている。戦後の日本の政治は、親米の保守勢力と反米の革新勢力という米ソの対立を反映した対立軸のもと、資本家階級と労働者階級の対立と和解を主な争点としてきた。しかし、現在の日本の社会では、これとはまた異なる格差の問題が出てきた。
それは、正規労働者と非正規労働者という格差である。この格差は、必ずしも労働者の能力によって決まるわけではなくて、学校を卒業した時の景気の良し悪しという偶然時に大きく依存している。たまたま卒業時に、景気が良ければ、新卒で正社員となり、その人の一生の生活はほぼ保障される。しかしたまたま景気が悪くて、正社員になれなければ、そのまま非正規労働者として一生を終えることになる。両者の生涯賃金や社会保障には大きな格差がある。ちょうど関が原の合戦で生じた格差が江戸時代を通して維持され、明治維新で生じた格差が明治時代を通して維持されたように、学校卒業時での競争で決まった勝ち組と負け組みの格差が一生を通じて固定され、維持されるのである。
正規労働者の地位を獲得した勝ち組は、自ら自分たちの特権を放棄しようとはしない。この結果、負け組みである非正規労働者のフラストレーションは、大きくなる一方である。非正規労働者たちは、社会的弱者ではあるが、《親米反中の保守派》対《反米親中の革新派》という伝統的な政治的対立軸の中で、必ずしも後者を支持しているわけではない。伝統的な革新政党は、労働組合に加入している正社員の権利の保護にばかり力を入れてきた。また、彼らは概して親中的であるが、非正規労働者たちは、中国のような新興工業国のおかげで、自分たちの待遇が悪くなったといった意識を持つ傾向があり、反中的になりやすい。おそらく彼らの不満の受け皿となるのは、《親米反中の保守派》でもなく、《反米親中の革新派》でもなく、《反米反中の革新派》であろう。
「プロレタリア型右翼」で提示した分類を使うならば、《親米反中の保守派》は保守主義者、《反米親中の革新派》は左翼、《反米反中の革新派》は右翼ということになる。もしも、今後、正規労働者と非正規労働者との格差が固定的に維持され、後者が増え続けるならば、将来、彼らは、極右政党を支持して、国内における格差と日米間の格差を同時に解消しようとするかも知れない。しかし、日本は、太平洋戦争と同じ間違いを繰り返すべきではないだろう。正規労働者と非正規労働者との格差の問題を根本的に解決するには、「どうすれば労働者の待遇は良くなるのか 」で既に主張したように、正規社員の雇用に対する過剰な保護を撤廃し、固定的な格差社会から流動的な格差社会への移行を目指すべきである。
6. 参照情報
- ↑Naval History and Heritage Command. “USA C-5904 Pearl Harbor Attack, 7 December 1941.” Accessed on 8 Sep 2019.
- ↑川田 稔. 『原敬と山縣有朋―国家構想をめぐる外交と内政』中央公論社 (1998/10). p. 153.
- ↑義井 博 (編集)『目撃者が語る昭和史(4)2.26事件』新人物往来社 (1989/05). p. 278.
- ↑山口重次. 『石原莞爾―悲劇の将軍』世界社 (1952). p. 13.
- ↑石原莞爾. 「満州建国前夜の心境」1941. in 『現代史資料 続・満州事変』みすず書房 (1965). p. 631.
- ↑石原莞爾. 「最終戦争論」1940. in 『最終戦争論・戦争史大観』中央公論社 (1993/7/1).
- ↑石原莞爾. 「最終戦争論」1940. in 『最終戦争論・戦争史大観』中央公論社 (1993/7/1).
- ↑『大衆政治家佐々木更三の歩み』総評資料頒布会 (1980/01). p. 476.
- ↑「近衛上奏文」1945年2月14日.








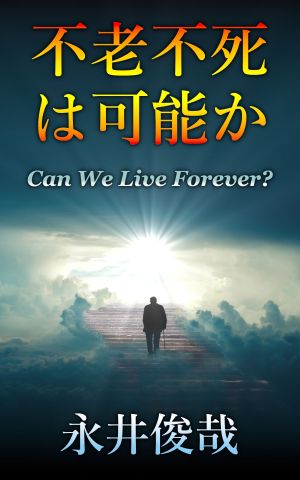

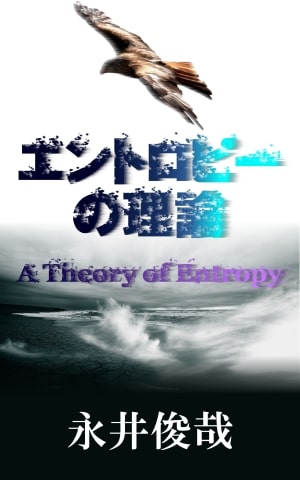

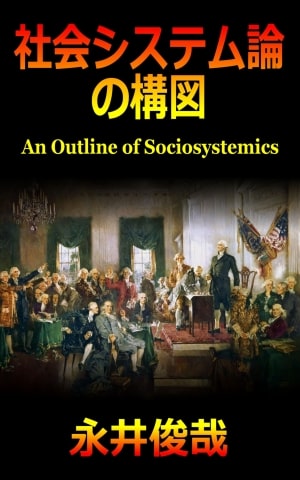

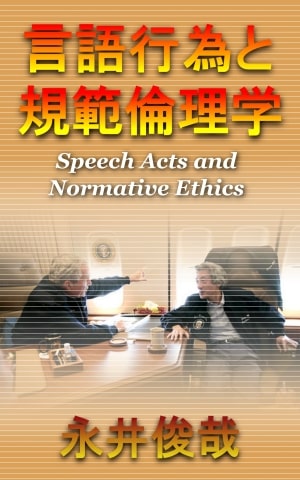
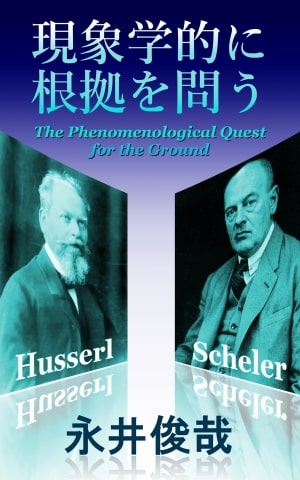
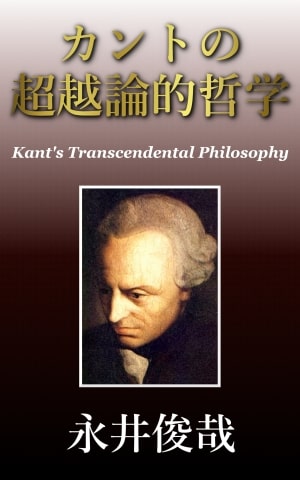

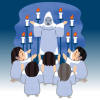



ディスカッション
コメント一覧
はじめまして。内容が面白く時折読んでおりますものです。
かつて歴史書を読んでいる段階では、無謀な15年戦争に至る経緯が分からなかったですが、今のような時代背景からしますと、よく理解できるようになってきました。
内容から、2点ほどご認識をおうかがいしたいと思いました。
1)陸軍と革新官僚に関する認識は、その通りと思います。
日米開戦は特に海軍が当初反対し、山本五十六は場合によっては中央に大臣で戻って、開戦を食い止める意思があったとされています。(当人の実戦指揮能力を鑑みますと、中央で軍政に携わっていたほうが結果は良かったと感じます。)
その際、「海外に戦争するなら、国内でテロやクーデターがあってもやむなし」という認識
でしたが(当時の言葉で言いますと、ジリ貧ドカ貧論)、為政者としては外でのゲバルト以前に、国内で求心力を高めるため、あえて外にそらすのではないでしょうか?
(ここは革新と保守の利害が一致すると思われますが)
2)特に軍部では「組織の論理」にも考察を向けることが大事と感じます。
軍部は実力機関ですが同時に官僚機関で、予算とポストを持ってくることを是とするところでもあります。
日米開戦の際に、陸軍から「陸軍の予算の半分を海軍に回せば勝てるのか?」と聞かれ、返答に窮した経緯がありますが、それでもNoと押し通すと予算が減る・ポストが減る・組織が持たない、という判断のほうが強かったのではないでしょうか?
海軍でも、青年将校たちが五・一五事件を起こしたりしていますから、事情は、陸軍とそう変わりません。海軍の米内光政や山本五十六は、日米決戦に否定的でしたが、彼らが日米開戦を回避できなかったのは、たんに陸軍が回避に反対していたからではなくて、国民の幅広い層に戦争を渇望する傾向があったからでしょう。
>>正規社員の雇用に対する過剰な保護
鳩山政権で企業の倒産が続いて、正規労働者の人口が非正規労働者の人口+失業者の人口以下になれば、後者を保護する(正確には前者を保護しない)政党が支持されるでしょうから、過剰な保護は撤廃する方向に向かうでしょうね。
市場原理に逆らう(様に見受けられる)民主党が、市場原理に貢献するとは。
民主党が、製造業派遣や日雇い派遣を禁止すれば、非正規労働者が減って、その代わり失業者が増えるでしょう。しかし、民主党は、労働組合の支援を受けているので、正社員の保護を緩和することはないでしょう。出生率や農業自給率の低下をバラマキで解決しようとする政党ですから、きっと失業率の低下に対しても、バラマキ的な彌縫策で問題を解決しようとするのではないかと予想されます。
>>バラマキ的な彌縫策で問題を解決しようとする
となると、バラマキの有効度合で決まりますか。
バラマキでは根本的な問題解決にはならないというのが私の考えであり、だからこそ彌縫策(失敗を一時しのぎにとりつくろう策)と表現したのです。
戦争から現代の経済や政権に着地するとは予想外で面白かったです。
米中への親反は前振りもなく出てきたので、あまり関係ないように感じましたが。
永井さんは次世代の政権はどこになるとお考えでしょうか。
執筆は衆院選前なので、結果的に現在民主政権になったことも本件の理論どおりということでしょうか。
このまま景気がよくならず経済的弱者が増えると、この理論でいけば次はより左翼的な共産党や社民党なのでしょうか。
確かにリーマンショック後に共産党に入党した人が増えたというニュースはありましたが、どこまで悪くなっても日本が社会主義や共産主義な国になるとは思えません。
また、共産党や社民党が政権をとった場合、健全な格差社会の正反対に向かうことになると思います。
社会主義や共産主義が国を豊かにするとは到底思えません。かといって、現状(永井さんの分類では保守派ということでしょうか)を継続したところで貧困層が増えても、大人しい日本人は右翼的にもならないと思います。
リバタリアンな政党はないように思いますし、どう転んでも日本は衰退するしかないのでしょうか。
今の鳩山内閣は、私の分類では、保守ではなくて、革新に属します。社民党が左寄りで、国民新党が右寄り(所謂、国家社会主義に近い)という違いはあるものの、現在の連立与党は、保守の自民に対して、革新という点で、一致しています。
日本には、リバタリアン政党はありませんが、2010年3月現在、それに最も近いのが、みんなの党でしょう。この政党は、小さな政府という理念を明確に掲げている唯一の政党です。もっとも、みんなの党は、一般にそう思われているような市場原理主義の政党ではなくて、かなり左翼的な側面も持った政党でもあります。彼らの選挙公約には、例えば、「社会的弱者に配慮した所得再分配を強化する」ために、以下のような政策が掲げられています。
1.低所得者層への「給付つき税額控除方式」の導入、「生活保護の母子加算」の復活、「障害者の一割負担」の廃止等「社会的弱者」への施策を強化。
2.その財源として、人定控除の見直しや高額所得者への課税強化(所得税、相続税等)を検討。
3.生活保護制度の不備・不公平、年金制度との不整合等の問題を段階的に解消し、最終的には、基礎年金や生活保護を統合した「ミニマムインカム」を導入
自民党にも「小さな政府と大きな社会保障を目指すべき」[河野太郎公式サイト | 自由な政党]という意見がありますが、その立場に近いという感じがします。
ヨーロッパでは、移民政策が原因で、極右政党が躍進していますが、日本では、移民政策を行わなくても極右政党が躍進するでしょう。
今年、楽天やユニクロが英語を社内公用語化し、パナソニックは外国人の採用を大幅に増やす代わりに、日本人の採用を減らしています。
もし、外国人の採用が増加し、日本人の採用が減少する傾向が続くのであれば、日本人の失業者や非正規雇用者が増え続け、彼らは極右政党を支持するでしょう。そして、排斥運動が大幅に激化するでしょう。
なお、外国人だけではなく、老人も排斥の対象になります。なぜなら、極右政党支持するのは、ほとんどが若者で、社会福祉が世代間格差の原因になっているからです。
そういえば、『マンガ嫌韓流』を書いて、「在日コリアンは弱者」という常識に挑戦した山野車輪が、最近では、『「若者奴隷」時代 “若肉老食(パラサイトシルバー)”社会の到来』を書いて、「老人は弱者」という常識に挑戦していますね。山野車輪は、1971年生まれの団塊ジュニア世代なのだそうですが、この世代は、最も競争率が激しかったバブルの時に大学受験をし、もっとも就職が厳しかったバブル崩壊後に就職活動をしなければならなかった受難の世代で、それだけに、政府とマスコミが保護しようとする自称弱者に対する怒りが大きいのでしょう。
“山野車輪は、1971年生まれの団塊ジュニア世代なのだそうですが、この世代は、最も競争率が激しかったバブルの時に大学受験をし、もっとも就職が厳しかったバブル崩壊後に就職活動をしなければならなかった受難の世代、それだけに、政府とマスコミが保護しようとする自称弱者に対する怒りが大きいのでしょう。”
そのことからふと思い浮かんだのですが、ネット上では、ゆとり世代を軽蔑する傾向が強いですよね。この世代は学力やモラルの低下が問題になった「失敗作」と言われていますが、最も重要な理由は、ネットユーザ(厳密に言うと2ちゃんねらー)の多くが団塊ジュニア世代だからではないでしょうか。
ゆとり世代は、最も競争率が低い時代に大学受験をしました。団塊ジュニア世代から見れば、これはかなりうらやましいことです。
また、ゆとり世代はバブルジュニア世代でもあります。そして、ネットいじめの被害者の多くが、この世代です。団塊ジュニア世代は、バブル世代がよほど憎いのでしょう。ゆとり世代はバブル世代の「愛の結晶」なのですから。
“『マンガ嫌韓流』を書いて、「在日コリアンは弱者」という常識に挑戦した山野車輪が、最近では、『「若者奴隷」時代 “若肉老食(パラサイトシルバー)”社会の到来』を書いて、「老人は弱者」という常識に挑戦していますね。”
そのうち、山野車輪は、「女性は弱者」という常識に挑戦するのではないでしょうか。元々ネットでは、フェミニストのことをフェミナチと呼んで軽蔑するほど、反フェミニズムの傾向が強いです。
日本広告主協会Web広告研究会が発表した「消費者メディア調査」によると、2005年9月現在で、990万人いる2ちゃんねる利用者に30歳代が占める割合は、他の年齢層よりも大きく、30.7%なのだそうです。1971-1974年生まれの団塊ジュニアは、2005年では、31-34歳ですが、この世代がすっぽり入る30-34歳が2ちゃんねる利用者に占める割合は、14.3%であり、同年齢層がCGM(Consumer Generated Media)全体の利用者に占める割合、11.8%よりも高くなっています[ITmedia:ブログ訪問者は1年で2倍の2000万超に 2chは990万人]。
ここから判断して、団塊ジュニアは、2ちゃんねるの熱心な利用者であると言ってよいでしょう。ただし、2ちゃんねる利用者のもう一つのボリュームゾーンに、2005年現在で、35-44歳の新人類世代(あなたが謂う所のバブル世代)が含まれていたことも見逃せません。この世代は、団塊の世代とは異なる価値観を持つがゆえに、このように呼ばれるようになったわけで、古い価値観に支配されたマスコミを「マスゴミ」とか言って批判している2ちゃんねらーには、新人類が多いのではないでしょうか。
2ちゃんねる利用者は、しばしばネット右翼と呼ばれますが、日本に990万人も右翼がいるはずはなく、大部分は、右翼とは言えない保守主義者だろうと思います。2ちゃんねる利用者のコアを形成する新人類世代は、バブルで景気が良かった時期に大学卒業を迎え、バブル崩壊後も、定年雇用制に守られて、正社員としての地位を維持していることの多い世代ですから、自分たちの既得権益を守ろうとする保守主義者が多いのではないかと考えられます。
フェミニスト批判は、小林よしのりなどがすでにやっているので、いまさらという感があります。山野車輪は、小林よしのりが取り上げなかったが、団塊ジュニアが不満を持っていそうなニッチな問題を取り上げて、漫画にしているという感じですから。
大東亜戦争の際、二度の原子爆弾の
投下をされております。
一発は広島、一発は長崎。
(長州過激派テロリストが)
パクストクガワーナ
を誹謗した報いです。
(広島は長州テロリストの先祖代々の
主の本拠地、長崎は長州過激派
テロリストの支援者
トーマス・グラバーの拠点である)
興味深く読ませていただきました。
満州から何故南下したのかわからなかったのですが、腑に落ちる説明でした。
ありがとうございます。
昭和天皇は非戦だったというが、永井さんの説明で腑に落ちたね。
本人は贅沢な暮らしをして食べるのも生きるのも困らなかったたんだから。
そりゃ自らを不利に回すような冒険的な政策は取れないよね。
226事件の対処も保守の態度そのもの。
東条とか伏見宮とかは陸軍・海軍内部の論理で生きてるから彼らにはわからなかっただろうけど、国民の大部分は戦争を望んでいた。
戦前のエリートやインテリすら共産主義に染まるぐらい戦前社会の格差と流動性のなさが酷かった。
昭和天皇は石原莞爾や田中角栄が嫌いだったらしいから、そういう革新性というものを好まなかったのだろう。
昭和天皇には恨みも嫌悪もないが、今の日本でもテロが多くなっているのは、社会がだんだん閉塞的になってきて暴力で打開しようとする(実際今の政界見ると打開できているようだ)風潮が広まってきているんだろうね。
万世一系の血統を守る立場にある天皇系が保守なのは当然です。近衛文麿が、若いころ、革新思想に染まったのは若い時の苦労のせいですが、近衞家の血統を引くだけあって、最後は保守に戻りました。