『エントロピーの理論』を出版しました
私の著作『エントロピーの理論』の解説動画、書誌情報、販売場所、概要、読者との質疑応答などを掲載します。本書に関してコメントがありましたら、このページの下にあるコメント・フォームに投稿してください。誤字脱字の指摘から内容に関する学問的質問に至るまで幅広く受け入れます。

1. 解説動画
2. 販売場所
販売価格は小売店によって異なることもあります。リンク先で確認してください。
- アマゾン日本 :: エントロピーの理論
- アマゾン米国 :: Entropy no Riron (Japanese Edition)
- グーグル・プレイ・ブックス :: エントロピーの理論
- 楽天市場ブックス :: エントロピーの理論
- スマッシュワーズ :: エントロピーの理論
3. 表紙画像

4. 書誌情報
- Title :: エントロピーの理論
- Furigana :: エントロピーノリロン
- Romaji :: Entropy no Riron
- Author :: 永井俊哉
- Furigana :: ナガイトシヤ
- Romaji :: Toshiya Nagai
- Author bio :: 著作家。インターネットを主な舞台に、新たな知の統合を目指す在野の研究者。専門はシステム論。1965年8月、京都生まれ。1988年3月、大阪大学文学部哲学科卒業。1990年3月、東京大学大学院倫理学専攻修士課程修了。1994年3月、一橋大学大学院社会学専攻博士後期課程単位修得満期退学。1997年9月、初めてウェブサイトを開設。電子書籍以外に、紙の本として『縦横無尽の知的冒険』(2003年7月, プレスプラン)、『ファリック・マザー幻想』(2008年12月, リーダーズノート)を出版。
- Language :: ja
- Page :: 626ページ
- Release Date :: 2019-06-09
- Identifier (Publisher)
- ISBN :: 9780463501139 (Smashwords, Inc.)
- ASIN:: B07SSP3P2G (Nagai, Toshiya)
- GGKEY :: URRFGWYLJ4W (Nagai, Toshiya)
- 楽天商品番号 :: 1230003269626 (Nagai, Toshiya)
- BISAC :: Book Industry Standards and Communications
- Science / System Theory
- Social Science / Sociology / General
- Philosophy / Social
- 社会科学 > 社会学 > 一般
- 哲学 > 社会哲学
- Tags :: キーワード
- Japanese :: 哲学、歴史学、エントロピー、システム論、文明論、戦争論、コミュニケーション、複雑性、オートポイエーシス、スケープゴート、社会哲学
- English :: philosophy, history, entropy, system theory, civilization, communication, complexity, autopoiesis, scapegoat, war
5. 短い概要
エントロピーはたんなる物理学の概念ではない。エントロピーの理論は、生命システム、意識システム、社会システムといったあらゆるシステムを貫く理論とすることが可能である。本書は、オートポイエーシス、超越論的自己関係性、コミュニケーション・メディア、ファルス、スケープゴート、貨幣のシステム論的分析を行いつつ、さらにエントロピー史観から人類史を概観する。
6. 長い概要
エントロピーはたんなる物理学の概念ではない。熱力学第二法則を非熱力学的分野に拡張することで、エントロピーの理論は、生命システム、意識システム、社会システムといったあらゆるシステムを貫く理論とすることが可能である。本書は、拡張されたエントロピーの概念で物理学の領域を超えた事象を説明しようとする哲学的な試みである。
どのような開いたシステムも、自らの低エントロピーな構造を維持するためには、環境のエントロピーを増大させなければならない。生命システムは、自己準拠的に自己自身を創作し、数を増やすことで全滅するリスクを低下させている。この点で、他の非生命システムとは異なる。生命のうち、自己保存のための選択が、不確定な情報エントロピーの縮減に基づくシステムは意識を持つ。
意識を持つシステムは、相互に相手の不確定性に依存する社会的エントロピーに晒される。この社会的エントロピーを縮減してくれる媒介的第三者が、コミュニケーション・メディア(文化システムにおける記号、経済システムにおける貨幣、司法システムにおける刑罰、政治システムにおける票)である。
コミュニケーション・メディアの起源は、系統発生的にはスケープゴートであり、個体発生的にはファルスである。境界上の両義的存在者の抹殺はシステムのエントロピーを縮減することに貢献する。その貢献ゆえに、いったん排除されたスケープゴートは媒介的第三者として機能する。また去勢以降、母子を結びつけるファルスも、その非存在ゆえに媒介的第三者として機能する。
本書は、最後に、エントロピーの経済学を概説した後、人類史のマイルストーンを振り返る。人類は、太陽活動が低迷し、物質的エントロピーが増大し、情報エントロピーが減少する時に、つまり革命を起こす必要があり、かつ起こす能力がある時に革命を起こす。このエントロピー史観の法則に基づいて、人類誕生から現代資本主義の成立にいたる歴史のシステム論的説明を試みる。
7. 関連著作
熱力学的な、つまりオーソドックスな一般向けのエントロピーの解説に関しては、
竹内薫. 熱とはなんだろう―温度・エントロピー・ブラックホール?
マーティン・ゴールドスタイン. 冷蔵庫と宇宙―エントロピーから見た科学の地平
ピーター・アトキンス. エントロピーと秩序―熱力学第二法則への招待
などがある。本書では取り上げることができなかったが、エントロピーと環境問題に関しては、
エントロピー学会. 循環型社会を創る―技術・経済・政策の展望
を参照されたい。エントロピーと情報の関係については、
堀淳一. エントロピーとは何か―でたらめの効用
が詳しい。ただ、エントロピーの大きさをそのまま情報量と考え、でたらめの効用を説くのは、受け容れられない。
杉本大一郎. エントロピー入門―地球・情報・社会への適用
が、指摘するように、でたらめさをたくさん否定すれば否定するほど情報量が大きくなると考えるべきである。この本は、物理学者が書いた本だが、経済学への適用も試みており、少し古いけれども、お薦めの入門書である。







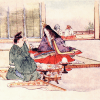









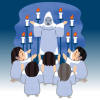




ディスカッション
コメント一覧
御指摘ありがとうございます。「宇宙や物質の究極を語っている」と受け取られることは想定外でした。こうした誤解が生じないように、「森羅万象を説明しようとする哲学的な試み」を「物理学の領域を超えた事象を説明しようとする哲学的な試み」に変更することにします。
「ソクラテスの命日について」
永井さま
はじめまして.永井さま著作の巻末のインデックスには,ソクラテスが亡くなった日として,紀元前399年4月27日,アリストテレスの場合は,前322年3月7日と書かれております.こちらの情報の典拠を教えていただくことは可能でしょうか?当方は,厳密な一次史料を知りたいわけではなく,典拠となる書籍を紹介いただけると助かるのです.
当方でも随分調べてみたのですが,見つけることが出来ませんでした.よろしくお願いいたします.
『エントロピーの理論』にはそのような「巻末のインデックス」はありません。多分他の著作の人名索引についての指摘でしょう。
日本では、4月27日にソクラテスが毒杯を仰いで死んだことになっていて、この日が「哲学の日」と呼ばれています。妻のクサンティッペが悪妻として有名であったことから「悪妻の日」とも呼ばれているようです。しかし、4月27日にソクラテスが刑死したとする根拠ははっきりしません。Socrates on Trial (Thomas C., Smith, Nicholas D.) の脚注(p.13-14)によると、裁判が始まったのは、4~5月で、刑死したのは5~6月という推測もあるようです。
アリストテレスの死亡日時は、海外の文献でよく目にします。例えば、Alexander The Man: King Alexander (Chandler, Joyce) の Part 9 冒頭(p.39)にそう書いてあります。しかし、これもしっかりした根拠があるかどうか不明です。
生没日の正確さまで気を配らなかったのですが、どちらも根拠不明であるようなので、次回改訂時に月日の情報を削除することにします。
永井さま
書名を誤ってしまい申しわけございません.
内容承知いたしました.
熱力学第二法則を社会に適用する試みは、ジョージェスク=レーゲン以来、様々な人によってなされていますが、私にとって満足できるものではないがゆえに、私独自の理論を本書で提示している次第です。ジョージェスク=レーゲン批判は、私のサイトの「ジョージェスク=レーゲンのリサイクル論」で行っているので、興味があれば、参照してください。
「学術」という言葉は、「学問と芸術」という意味なので、幅広い知の領域をカバーしており、哲学も学術に含まれます。おそらく「学術書ではない」というのは「専門書ではない」という意味なのでしょう。私は、哲学を、専門知とは異なる全体知と認識しており、アカデミックな専門書とは異なるアプローチを意図的に選択しています。したがって、専門書ではないことは当然で、内容紹介でも「哲学的な試み」と明記していますので、購入する前によくご確認をお願いします。