熱力学第二法則からエントロピーの法則へ
熱力学には二つの基本法則がある。熱力学第一法則は「エネルギーは保存される」、第二法則は「孤立したシステムにおけるエントロピーは減少しない」というものである。熱力学第二法則を、熱力学の範囲を超えて拡張してみよう。
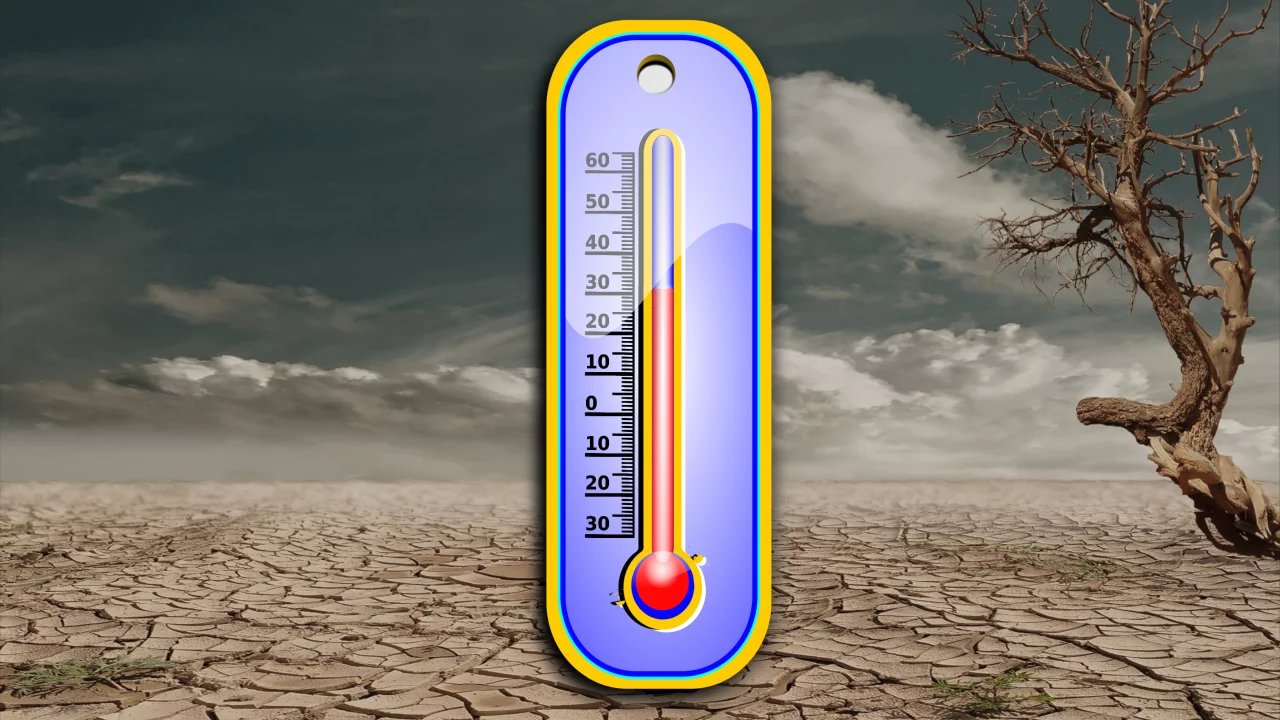
1. エントロピーの法則とは何か
エントロピーについては、「システムとは何か」で説明したが、熱力学第二法則は、実は誰もが知っている自然現象を物理学的に説明しただけのものである。熱湯に氷を浮かべるとぬるま湯になるが、ぬるま湯を放置していても、氷が「自己組織化」され、周りが熱湯になるということは起こりえない。熱は高きから低きへと一方的に流れるのである。

エントロピーの法則を、熱の移動がない一般の不可逆過程にまで適応した法則をエントロピー非減少の法則、略してエントロピーの法則と呼ぶことにしよう。水の入ったコップがテーブルから落ちてこなごなに割れることはあるが、こなごなに割れたガラス破片が、周りに散らばった水を集めながら、テーブルの上にジャンプしてもと通りに戻ることは期待できない。エントロピー(無秩序)一般は、増えることはあっても減ることはないというわけである。
2. エントロピー補償の法則
ただこの第二法則には、「孤立したシステムにおいては」という条件がある。孤立したシステムとは、環境とエネルギーや物質や情報のやりとりがまったくないシステムのことである。魔法瓶も、擬似的な孤立したシステムとみなすことができるが、完全な孤立したシステムは、宇宙全体しかない。エネルギー交換のある閉鎖系や物質交換まである開放系では、第二法則は成り立たない。逆にいえば、非孤立したシステムでエントロピーが減少する時、それは常に環境におけるより多くのエントロピーの増大によって可能となっているのである。
例えば、水と油をかき混ぜて放置しておくと、油と水が分離して、秩序が自己組織化するかのように見える。しかし断熱された孤立したシステムで水と油をかき混ぜると、運動エネルギーが熱となって周囲に排出されないため、系内部が高温のままとなり、水と油は混ざったままになる。また冷蔵庫は、冷媒を蒸発する時の気化熱で庫内の温度を下げ、エントロピーを小さくすることができるが、そのためには気化熱と同量の凝縮熱を庫外に排出しなければならず、また電気を使うため、最終的に大量の熱を庫外で発生させなければならない。
エントロピーの法則によれば、ビッグバン以降宇宙は秩序から無秩序へと向かい、最後は熱的死を遂げるはずである。しかし地球上では、こうした宇宙全体の流れに逆行して生命が進化し、そして人類の文明は時間とともに進歩を遂げているように見える。これは生物が開放系で、太陽や地球といった低エントロピー資源の散逸(エントロピーの増大)を通して自らのエントロピーを減少させているからである。人間を含めた生物、そして人類が築き上げた文明は、環境におけるエントロピーの増大によって可能となるシステムである。人間は、他の動物と同様に、食物摂取を通じて獲得した低エントロピー資源を呼吸によって消費しているが、人間の場合、化石燃料をはじめとする食物以外の低エントロピー資源までも燃焼によって消費している。
3. 非熱力学的なエントロピー
しかし人間が、環境の熱エントロピーを増大させながら創り出している低エントロピーは、決して身体や建築物といった物質レベルでの資源だけではない。我々が創り出す意味の世界も、無意味という無秩序を否定しているという点で、低エントロピーなのである。ただ、物質システムがエントロピーを捨てる環境が、システムの物理的な外部に存在しているのに対して、情報システムがエントロピーを捨てる環境は、可能的多世界として仮想的にしか存在しない点が異なるだけである。
我々は本能によってのみ支配されていないという意味で自由な存在であり、自由であるということは、不確定な環境に晒されつつ、さまざまな選択肢の中から自己の行為を選択する、つまり情報のエントロピーを減少させる能力があるということである。「右」という概念があるから「左」という概念があるというように、言語は示差的であり、我々が言語を通じて世界を認識する時、差異化された多様な記号を選ぶという意味で、認識するという行為はエントロピーの縮減であり、無秩序からの秩序の形成である。
4. ネゲントロピーの三つのレベル
整理すると、ネゲントロピーには次の三つの場合があることになる。
- 環境における物質レベルのエントロピーの増大が、物質レベルの低エントロピーを創り出す(物理学的なエントロピーの法則)
- 環境における物質レベルのエントロピーの増大が、情報レベルの低エントロピーを創り出す(呼吸による新陳代謝が脳における思考を、電気がコンピュータにおける情報処理を可能にする)
- 環境における情報レベルのエントロピーの増大が、情報レベルの低エントロピーを創り出す(他の可能性の否定によってはじめて意味が可能になる)
3番目は、難しいので、具体的な例を出そう。「ファシズムは正しいか正しくないかのどちらかである」という言明には何の情報価値もない。「ファシズムは正しい」といえば、それは、「ファシズムは正しくない」という他の可能性を排除しているから意味がある。つまり「ファシズム」という一つの主語に対して、「正しい」あるいは「正しくない」という述語の候補があり、そのうちのどれを述語として選ぶかという不確定性(エントロピー)を縮減してはじめてその命題は意味をもつのである。
命題が有意味であるからといって、それが正しいとはいえない。ある選択が正しいかどうかは、社会システムというメタレベルの選択によって決まる。ある政治家が、ファシズムの正しさを訴えて立候補したとする。当選者のいすが一つしかないとするならば、有権者は複数の候補の中から一人を選ぶことになる。ファシズムの正しさを訴えた政治家が落選するならば、「ファシズムは正しい」という選択は選択されなかったことになる。社会システムにおいては、選択主体が相互に選択し合うことによって秩序が創り出される。
5. エントロピーの法則の重層構造
以上結論をまとめよう。
- 物質システムは、環境におけるエントロピーの増大によって、ネゲントロピーとして存続できる。
- 情報システムは、述語の可能性の増大によって、無意味の排除による有意味性を獲得する。
- 社会システムは、さまざまな可能的行為の選択肢の増大に伴って、逸脱者の排除による秩序形成ができる。
社会的なエントロピーが増えるということは、行為の他の可能性が増えるということであり、この自由の増加が低エントロピーの生成、すなわち生活水準の向上を可能にする。










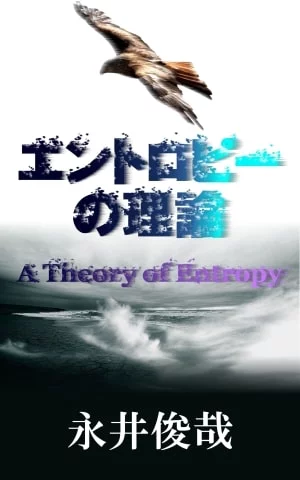

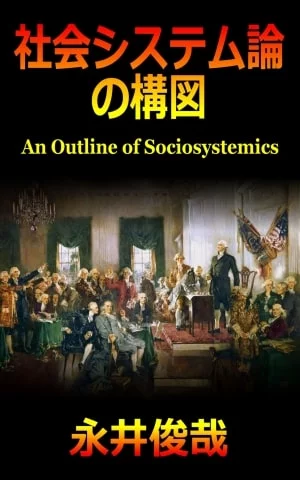

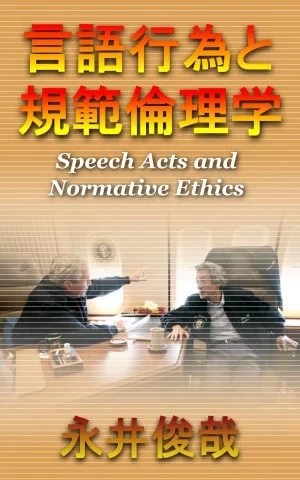
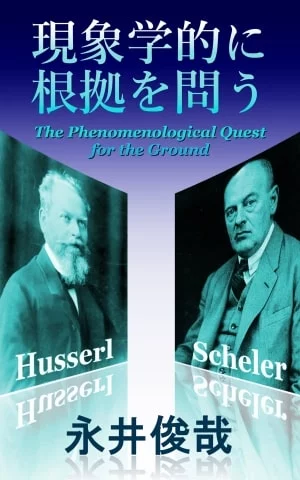

ディスカッション
コメント一覧
情報科学、社会科学でいうエントロピーと、物理学でいうエントロピーを一緒に議論することには少し問題があると思います。
物理学のエントロピーの定義には、熱力学的なものと統計力学的なものがありますが、どちらも熱平衡に達した系、つまり素性のよくわかっている系に適用されるものです。熱湯に氷を入れた瞬間など、複雑な過程の途中でエントロピーを計測することなどできません。ただ、熱湯に入れる前の氷の持つエントロピーと、熱湯の持つエントロピーの和が、混ざってできたぬるま湯のエントロピーよりも低いということならいえます。
社会のような、常に複雑な状態にある系にエントロピー増大の法則を適用することは、定量的はおろか定性的な分析にも役立つとは思えません。また、情報科学で言うエントロピーは(詳しくないのですが)S/N比のような、乱雑さのことを言うのではないですか?物理でいう保存量から導かれるエントロピーとは、質の違うものであるという気がします。
そもそも物理でのエントロピーの定義は「なんだかよくわからないけど常に増える量」であって、人間の定義する「秩序」とは違うものです。エントロピーと秩序がどこまで一致するか、わかっているわけではないのです。
私の個人的な感覚としては、エントロピーは「秩序の無さ」よりむしろ「汚さ」に近いものであるという気がします。汚れをふき取ると、ふき取った方が必ず汚れます。汚くなった布巾は、洗って汚れを下水に流します。汚れがなくなることはありませんし、汚れが自然に拡散することはあっても、仕事をせずに汚れを集めることはできません。力仕事をすると必ず汚れます。
しかしこの認識も、人間の感覚をベースに置いている限り、エントロピーそのものを把握しているとはいえません。ブラックホールの事象の地平面の面積がエントロピーに対応している、と言われても、人間にはあまり感覚がつかめません。エントロピーって、そういうもんじゃないですか?
私は物理専攻なので、ちょっと物理的な意味に偏った書き方をしてしまいましたが、もともとエントロピーの考え方は哲学的・形而上学的なものではなくて、経験則を定量化するものに過ぎないというところを強調したくて、以上のように書いた次第であります。
たしかにエントロピーはエントロピーであって、他の概念に置き換えることは難しいのですが、最も汎用性がある概念は、不確定性だと私は考えています。
散らかっている部屋は無秩序であり、私たちは「汚い」と感じますが、そういう部屋では、どこに何があるのかわからないので、不確定性が大きいといえます。
反対に、整理整頓された部屋には秩序があり、私たちはそれを「きれい」と感じます。その部屋では、どこに何があるのかわかりやすいので、不確定性が小さいともいえます。
もちろん、散らかった部屋でも、住み慣れれば、どこに何があるのかわかるようになりますが、それは認知という仕事がなされてエントロピーが小さくなったからで、はじめからエントロピーが小さいわけではありません。
社会科学にエントロピー概念を定量的に応用することができるかどうかは、やってみなければわかりませんが、経済学のような比較的定量化しやすいところからはじめようかなと思っています。
「つまり「ファシズム」という一つの主語に対して、「正しい」あるいは「正しくない」という述語の候補があり、そのうちのどれを述語として選ぶかという不確定性(エントロピー)を縮減してはじめてその命題は意味をもつのである。
」
ここで不確定性の「縮減」とされているものは、不確実性の「解消」に近い意味と考えてもよろしいでしょうか。私自身、「不確実性の縮減」について、その主体となるシステムの設定のあり方自体が不確実なものと考えています。不確実性の縮減でイメージしているものは、数ある差異の中から、ある特定の差異(ここでは、ファシズムが「正しい/正しくない」)が選択される・に絞り込まれることです。ファシズムについて正しい/正しくないかという選択にまで絞られることを不確実性の「縮減」というふうに捉え、この二者択一からの更なる選択は、「不確実性の解消」というふうに捉えるのが妥当なのではと思いますが。
場合の数が2から1に減るのですから、二者択一の選択肢から一つ選ぶことは不確定性の縮減になります。不確定性の表し方は、複雑性とエントロピーと二通りあって、場合の数が複雑性であるのに対して、エントロピーはその対数です。どちらを用いても、不確定性の縮減は、数字が小さくなることによって表現されます。
リンク先にて、特に低エントロピーと思われる建築物などを紹介したり、
「低エントロピー」と「モダンなデザイン」の関係について考えています。
ここで「低エントロピー感」という言葉が産声をあげました。
社会システムが低エントロピーを生成するためには、逸脱者の排除による秩序形成という管理指向な方法と、短期的には社会的なエントロピーが増えるものの自由を増加させ、自由の増加が低エントロピーの生成すなわち生活水準の向上を可能にするという自由指向な方法の、2つのアプローチがあると理解してよいでしょうか。
またそうだとすると、ある社会システムが逸脱者の排除と自由の増加の併存、いわば「秩序ある自由」を生成するためには何が必要となるのでしょうか。
御教授いただければ幸いです。
市場原理です。市場原理が機能している社会では、複数のシステムが存在し、それぞれのシステムが、システムとして存在するために、自分のエントロピーを縮減しつつも、その縮減の仕方がそれぞれで異なるために、個々のエントロピーの縮減が社会全体のエントロピーを増大させます。こうした社会では、ご指摘の二つのアプローチが共存しており、消費者による選択が、増大した社会全体のエントロピーを縮減し、社会システム全体の生存能力を高めます。
理解が深まりました。ありがとうございました。
私は経営の実務家として、企業というシステムの生存確率の増大を考えています。
お忙しい中恐縮ですが、もう一つ教えてください。
国家などのマクロな社会システムが低エントロピーを生成するためには、下位システムの多様性とその自由選択、つまり市場原理が必要であることは理解したつもりです。
一方、そのような下位システムを持たないミクロな社会システム、例えば企業の一部門などでの低エントロピー生成は、どのように考えればよいでしょうか。
市場における多様な経営と多様な商品を可能にするためには、市場におけるプレーヤーである個々の企業は、むしろ逆に多様性(エントロピー)を削減しなければなりません。経営者は、独自の経営理念に基づき、独自の商品を生産しなければならないということです。所謂「選択と集中」が、経営におけるエントロピーの縮減に相当すると考えてください。すべての経営者が、独自の経営方針を持つことなく、あらゆるものに手を出し始めると、市場全体では、逆に多様な経営と多様な商品が失われてしまいます。
かつて、ソニーは、カンパニー制を導入して、企業内部に擬似企業(カンパニー)を作って、カンパニー間に市場原理が働くようにしようとしましたが、この試みは、失敗しました。社会主義経済よりも市場経済の方がうまくいくから、後者の原理を企業経営にも取り入れようという、アナロジーに基づいた経営改革だったわけですが、ソニー内部に同業異種の生産者と消費者がいるわけではないから、ソニーの内部では市場原理は機能しません。大企業病を治したいというのであれば、完全に分社化するべきであり、責任の所在をあいまいにする中途半端な分権化の導入は、集権化のデメリットと分権化のデメリットの両方を抱え込むことになるので、するべきではありません。
ありがとうございました。
企業が、低エントロピーを生成し生存確率を増大するためには、変化適応よりも環境適応を優先した方がよい、という意味に解釈しました。
以下は質問ではなく、私なりの理解を整理したコメントです。もし誤謬などありましたらご指摘いただければ幸喜です。
多くの企業が、企業内に分権化、多様化、多角化を指向する施策を導入しています。またそうした方向性の実現のため、わざわざ企業買収などを通じて社内の多様化を図ることさえあります。
企業が、そうした多様化ないし変化適応指向の行動を採用する動機には、環境変化による損失への恐れと、市場原理の適用対象に関する誤解のほかに、分散投資によるリスクヘッジ効果の期待もあると思われます。
金融工学によれば、投資家の立場では、資本を出来る限り価格変動の相関の薄い投資対象に分散して投資すること、すなわち投資の多様化が、長期的にはリスクあたりの期待リターンを最大化します。そこには投資家の思想や理念が入る余地はないか、非常に少ないはずです。
これとは逆に、経営者の立場では、資本をできるだけ特定の領域や方法に集中させて企業と製品の独自性を高めることが、リスクあたりの期待リターンを最大化する、という表現も可能であろうかと考えました。そしてその集中のあり方には、経営者の思想や理念、すなわち経営者の個性が反映されるし、反映されるべきだと理解しています。
投資家と経営者で、採用すべき方向性が真逆であるのは、消費者と同様に投資家も、市場原理における選択者の役割を担っているからだと思います。
以下に整理を試みます。
個人も企業も、低エントロピーを生成し生存確率をあげるためには、自由選択者から選択される対象となれるように、自己ないし自己が提供する価値を高める必要がある。
価値とは低エントロピー資源そのものであり、独自性すなわち希少性と、有用性の積である。したがって、有用性があっても独自性が低ければ価値も低くなる。よって個人も企業も、有用性と同時に独自性を高めるべきである。たとえば有用性が高いが独自性が低い企業は、競合企業との価格競争にさらされるなどの結果、長期的に利益を獲得することが困難となる。
複数の独自性が企業内に発生した場合には、中途半端に分権化せず、完全に分離した方がよい。
一方、環境変化などによって、独自的な特徴の有用性が大きく減衰する事態があり得る。その場合は、独自性のある資本が今後も有効な場へ移動するか、速やかに資本蓄積の方向を転換を行うべきである。マクロ的にみれば、新しい環境に適応できないサブシステムが淘汰されることで、社会全体の資源再配分が実現される。