地平の中間性構造
地平は、私たちの視界を部分的に遮ると同時に、部分的に与える。ここから、地平は、認識を制限する制約であると同時に認識を可能にする条件という両義性を帯びた哲学的概念として使われる。私たちは、神のような全知全能の存在ではないが、完全な無知無能の存在でもなく、その中間に位置する。本稿ではこれを地平の中間性構造と名付け、地平の中間性構造が私たちの存在の本質を規定していることを確認したい。[1]

1. 認識における地平の中間性構造
ヨーロッパ言語の「地平」は ギリシャ語の「遮る(ὁρίζειν ホリツェイン)」から派生し、そこから天文学などでは、天空を遮る海や平原の線が、したがってまた海や平原を遮る天空の線が地平線(水平線)と呼ばれるようになった。このように、地平概念は語源的にも認識の限界を表す言葉である。しかし我々は全く何も認識できないわけではない。我々は全知全能の神と意識を持たない物との間にある中間的存在者であり、この中間性の公式を我々は様々な射映から表現することができる。
まず認識の側面から話を始めよう。認識の出発点は問いである。我々は問いを立て、その問いに答えることによって認識を深めていく。ソクラテスやプラトン以来、それが愛知としての哲学的探究のあり方の原型であった。そしてプラトンが語っているように[2]、問いに関しては、 次のような中間性の公式が当て填まる。
公式1.問いの地平. もし全てについて知っているならば、問いを立てることは不必要であり、またもし何も知らないならば、問いを立てることは不可能である。既知の事柄に未知の事柄があるときのみ、我々は問いを立てることができる。
我々は、方程式の未知数を求めるときのように、既知を手掛りに未知を既知化し、そしてこの既知によって新たに地平化される未知に対して問いを立てる。ちょうど地平性に辿り着こうとするときのように、学問的探究にはきりがない。ネガティヴに言えば、それが人間の有限性ということになるが、ポジティヴに言えば、人間の好奇心は常に満たされる余地があるということでもある。認識の基本単位は判断(命題)であり、判断の主語-述語関係の地平は有意味性である。
公式2.判断の地平. 主語と述語が全く同じであるならば、その命題はトートロジーであり、無意味である。主語と述語が全くカテゴリーを異にするならば、その命題も無意味である。カテゴリー・ミステイクを犯さない総合命題のみが真や偽でありうる。
恒真式「四角は四角である」やその述語のたんなる否定である恒偽式(矛盾式)「四角は四角ではない」は、論理学的には世界について何も語らないという意味で無意味である。他方「四角は素数である」はカテゴリー・ミステイクを犯していて無意味である。ヘーゲルによれば、「ライオンは机ではない」とか「精神は像ではない」などの命題は「無限判断」で、「これらの命題は 正しいことは正しいが、しかし“ライオンはライオンである”“精神は精神である”などという同一的命題と全く同じように無意味である[3]」。
有意味と無意味はいかなる規則に基づいて区別されるのか考えてみよう。フッサールは、「アブラカダブラ」、「緑はであるまたは」などの統語論的に無意味な命題と「丸い四角は素数である」のような、統語論的規則には反していないのだが、意味論的に無意味な命題を区別して、前者のような意味付与不可能な無意味を防止するのは文法学であって、これに対して後者の「丸い四角」のような意味付与可能ではあるが、意味充実不可能な反意味は、文法学によってではなく論理学によって防止されると言う[4] 。
だがはたして論理学が反意味を防止するのだろうか。「四角ではない四角」は確かに論理的に矛盾であるが、「丸い四角」の方はそうとは言えない。四角は丸くないが、丸くないからそれが四角であるとは言えない。「正十面体」も無意味ではないのであるが、意味充実することは不可能なので反意味ということになろうが、しかしその判定は論理法則によるとは言えない。有意味と無意味の区別はあくまでも意味論的規則によってなされる。
では、真/偽と有意味/無意味はどう区別すればよいのか。さしあたり次のように考えよう。「四角は丸い」という命題は偽ではあっても無意味ではなく、したがってその述語を否定した「四角は丸くない」は真である。ところが「丸い四角は素数である」の場合、その述語を否定した命題「丸い四角は素数でない」も前者に負けず劣らず不可解である。
「四角は丸い」では述語「丸い」は主語と「図形」なる地平を共有することができるが、「丸い四角は素数である」は述語「素数」が求める「正の整数」という地平を、いやそれどころか「数」という地平すらも共有することができないのだから無意味なのである。他方「『丸い四角は素数である』は無意味である」は、無意味性という有意味性の地平によって地平化される地平を共有しているがゆえに有意味である。
私は、『カントの超越論的哲学』で、カントの二律背反を p∧q と p∧¬q との対立と定式化したが、qまたは¬qが現象を地平とする述語であるのに、それをそれとは類を異にする物自体を主語のpにすることは、ライル謂う所の「カテゴリーの取り違え category mistake」なのである。ここから明らかなことは、地平とは対立の地平であるということである。
公式3.対立の地平. 全く同じものは対立しないが、全く違うものは対立しない。共通の類をもちながら反対の種差を含む二つの概念が対立する。
例えば「赤い」と「黒い」は対立するが、「赤い」と「柔らかい」とか「赤い」と「騒々しい」は対立しない。両者は全く種/類が異なるからである。もちろん異なると言っても、その相違は相対的であって絶対的ではない。
ヴィトゲンシュタイン曰く「赤いと黒いは、赤いと柔らかいほどには異なっていないといえるだろうか。もちろんこんなことは無意義である[5]」 。彼のこの主張は、同じ『哲学的考察』の45節の主張「黒い色がより明るくなることは可能だが、より騒々しくなることは不可能である。すなわち、それは明-暗-空間内にあるものの、騒-静-空間内にあるわけではない」と矛盾しているように思えるのだが、「赤い」も「柔らかい」も「騒々しい」も五感の対象となるような物理的性質という点では共通の地平内にある。赤いか赤くないかが問題となっているとき、柔らかいか騒々しいかは意識の地平外である。柔らかさや騒々しさが問題となるとき、赤いか否かの問題は地平の内部で消滅する。このように地平を広げていくことはできるが、外部の存在しない、全てを包括する地平に辿り着くことはできない。それはちょうど全てを包括する類概念が存在しないのと同様である。
概念の対立が完全な同一性と完全な差異性の中間で生じることと問いは無知と全知の中間で生じることは密接な関係がある。対立地平、すなわち選択肢について既知であって、どの選択肢かが未知であるとき、問いが生じる。このことを具体的な例で確かめてみよう。
一般に問いには(1)「この花は白色ですか?」のように「はい/いいえ」で答えられる場合と(2)「この花は何色ですか?」のようにそうでない場合とがある。(1)では「この花は白色ですか、白色ではないのですか?」という選択の問いに変形できるところから明らかなように、「花」なる地平において「白色」と「非白色」が対立している。もし主語の対立地平が既知でないならば、それが白であるか否かを問うことすらできない(例えば素数が主語の地平である時を考えてみよ)。一方(2)では対立は表だっていないが、そこでは複数の色の述語の候補の中から一つを選ぶことが要求されており、一つが選ばれるや否やそれ以外の述語と対立関係に入ることになる。
2. 社会における地平の中間性構造
判断における問いの不確定性が、問う人の存在の有限性と不確定性を反照する。同様に判断における同一の主語に対する二つの対立した述定が、二つの判断者の対立を反照する。そこで公式3のコロラリーとして、次の中間性の公式が成り立つ。
公式4.闘争の地平. 利害が一致している二つの主体は闘争をする必要がない。利害関係がない二つの主体が闘争することはありえない。利害関係があってかつ利害関係が対立する二つの主体のみが闘争をする。
公式3では有意味性が、公式4では利害関係が地平である。両方併せて「関連性 relevance」と呼ぶことができる。同一でも無関係でもない差異の関係性が意識の世界を構成している。間主観的世界は、「関係のネットワーク」といった単一次元的な網の目状のものではなく、そのつど関心によって規定された、多元的に地平的な構造を持っている。だから《人間的諸関係の総体》は一望の下に見渡せないのであって、おのれの地平を自覚していなときにのみ全関係を概観しているかのように思い込めるのである。
この相対主義は不可知論をもたらさない。地球をメタファーに用いて喩えると、私は、地球の表面を概観しようとする時、ある地平の内部で、パースペクティブ的なゆがみをもってそのごく一部しか見ることができないが、原理的には地表面のいかなる部分をも概観できるという意味ではすべての地表面は不可知ではない。
闘争はネガティヴな互酬性として交換のようなポジティヴな互酬性の対局にある。だが、どちらも差異を含んだ同一性の地平で生起する間主体的関係であるから、交換に関しても次の中間性の公式が当てはまる。
公式5.交換の地平. 全く同じ商品は交換する必要はないが、価値が異なる商品は交換することは不可能である。価値が同じ二つの異質の商品のみが交換されうる。
“価値”を妥当性の意味にとるならば、経済的な商品交換のみならず、すべての交換(コミュニケーション)、例えば言語的な意思疎通について、公式5が成り立つ。
公式6.他者認識の地平. もし全く意見が同じであるならば、他者とコミュニケーションをする必要はない。全く意見が違うならコミュニケーションをすることは不可能である。共通の土台があるときにのみ、他者とのコミュニケーションが可能かつ有意味になる。
他者認識の地平は、精神的動機の理解に対する問いによって対自化される身体性である。身体は他者を隠すことによってあらわにする。もし身体がなければ私は他者を認識することができない。だがもし他者が身体を媒介にせずして私に現れてくるならば、それはもはや他者ではなくて私になってしまう。この正反対であるにもかかわらず、それゆえに表裏一体の無限定性の否定が他者の身体性という限定性なのである。
他者という未規定的な潜在性の地平は顕在的に現出する身体の知覚によってのみ間接呈示されるというフッサールのテーゼは、一般に評判が悪いのだが、フッサールは次のように理由付ける。「もしも他者の固有本質的なものが直接的に接近できるなら、その固有本質的なものはたんに私の固有本質の契機となり、かくして他者自身と私自身は同じに成ってしまうであろう[6]」 。我々はフッサールの他者論に“所詮は超越論的エゴ・コギトに固執する近代哲学者の間モナド論”なるレッテルを張 って終わりにするわけにはいかないのである。他者認識における身体による被媒介性は、社会認識にとって障害なのではなくて、むしろそれの本質的な構成契機である。
他者の存在証明は次節に回すが、予告的に結論を述べておくと、フッサールも認識していたように、他者は自我と等根源的に先与的であることは、認識の地平性から帰結する。認識が地平的であることはその[として]の述定に関して未規定的であり、認識作用が「私は今とは他のように行いうる。Ich kann anders als ich tue.[7]」 というように《不確定的=有限的》であるということである。私の認識が「他のようにも」の可能性をはらんでいるかぎり、たとえこの地球上に私以外の意識主体がいなくなったとしても、《身体的な=有限な》他者は、私に(現在化されないにしても)現前化されうるのである。
地平は《私の述定の有意味性=述定の「他のようにもありうる」不確定的可能性》の制約であるがゆえに、《私の「他のようにもありうる」述定の存在つまり他者の存在の可能性=私と他者のコミュニケーションの有意味性》の制約である。同時代的コミュニケーションについて成り立つことは、過去との対話についても成り立つ。
公式7.解釈の地平. もしテキストが分かり切ったものであるならば解釈は不必要であり、またもしそれが我々にとって全く疎遠なものであるならば解釈は不可能である。興味はあるが、自明でないテキストに対してのみ解釈が行われる。
これはガーダマーの解釈学のテーゼである。古典的テキストを解釈する時、過去の地平と現在の地平との間に時代の隔たりがある。「全ての有限な現在はその制限を持っている。我々は状況[有限な現在性]の概念を、状況が見ることの可能性を制限する立場を示すというまさにこのことによって規定する。それゆえ状況の概念には本質的に地平概念が属している[8]」 。時代の隔たりという制限はしかし解釈にとってあらずもがなの障害ではなく、むしろ解釈にとって積極的な可能性を与えるものであるし、だからこそそこに「著者以上に良く著者を理解する」ことを標榜する解釈学の理念が成り立つのである。
古典を理解することは、古典を現在の地平に引きずりこむことではないし、また現在の地平を飛び越えて-それは不可能なことである-歴史的地平に埋没することではない。「むしろ理解することは、常にそのような[現在の地平と歴史的地平という]それ自体で存在すると思念された地平を融合する出来事である[9]」 。「理解することにおいて現実的な地平の融合[Horizontverschmelzung]が生起するが、その融合は歴史的地平を企投すると同時に止揚する[10]」 。
歴史認識に関して言えることは、他者認識に関しても言える。一般に他者認識とは、自己を他者の立場へ移し置くことであるとされているが、「そのような自己を移し置くことは、ある個別性を他の個別性へと感情移入することでもなければ、他者を自己の尺度へと服従させることでもなく、自己の特殊性のみならず、他者の特殊性をも克服するより高次の普遍性へと上昇することを常に意味する[11]」 。
だがこの「より高次の普遍性へと上昇すること」は、決して人間の認識と存在の有限性としての地平性を捨象して無地平性へと《超越する》ことなのではなく、地平的存在者がその地平性を自覚することを通しておのれの地平的被制約性から《超越論的に》自由になることに他ならない。もしも超越論的哲学とは自己関係的自己反省の学というほどのことを意味するならば、我々の「地平の哲学」は超越的哲学ではなくて超越論的哲学であるということになるであろう。
ガーダマーは『真理と方法』の第二版の序言で、自分の解釈学的な《遊戯 Spiel》論とヴィトゲンシュタインの《言語ゲーム Sprachspiel》の理論との親近性を認めているが、実際 両者はたんに言語を重視したという以上の共通性を持っている。ガーダマーは、カントの美学に対して「遊戯者に対する遊戯の優位 Primat des Spieles gegenüber dem Bewußtsein des Spielenden[12]」 を説き、「すべての遊戯すること(Spielen)は遊戯されること(ein Gespieltwerden)である[13]」 と言うが、これは後の「言語を手引きとした解釈学の存在論的転回」の伏線となっている。そして遊戯(Spiel)は、ドイツ語においては「賭け」という確率論的な意味を持っていることにも注目したい。ガーダマーによれば、「そもそも究極的な意味で、一人だけで遊ぶということはない[14]」 。例えば一人でボールと遊ぶ子供にとって、ボールの動きが自分の意思のままにならない。つまり他なるものであって不確定的であるがゆえに、ボール遊びは Spiel でありうる。不確定なものと遊ぶことは、私の存在 の不確定性でもある。そしてこの Spiel 論から私的言語批判を導くことができる。ヴィトゲンシュタインの Sprachspiel においても、私は主体的・能動的に規則を作るのではなく、ただ盲目的に規則に従うだけなのだから(もちろん私はまさに「従っている」のだから、spielen する存在であるにしても)、私は言語によって spielen される存在でもあるということになる。
ハーバマスは、ガーダマーが伝統とその権威を復活させ、先入見と解釈学的循環のうちに居直ったことを「超越論的」遂行論の立場から啓蒙主義的に「批判」するのだが、我々の「地平の哲学」からすれば、地平超越的なハーバマスよりもむしろガーダマーのほうがヴィトゲンシュタインの言語ゲーム論を正しく継承しているのではないのかと言いたくなる。ヴィトゲンシュタイン以降、英米では過去や異文化の理解に対してクーンなりクワインなりがパラダイムの共約不可能性/翻訳の非決定性を主張するが、このように「地平の融合」の不確定性を自覚することが却って自己の現在の地平を地平として正しく認識していることになるはずである。
3. 時間における地平の中間性構造
他のようでもありうる不確定性は、時間的には他のようにも成り得る変化可能性である。変化しないことも変化可能性の一つであって、変化可能性がなければ、無変化も概念的にありえない。カントがすでに認識していた変化のパラドックス [15] も、次のような地平的中間性の公式で表現される。
公式8.変化の地平. ある時点におけるAの後にBが継起するとき、AとBが全く同じであるならば、それは変化とは言えないが、何の連続性もないならば、それは転変(Wechsel)であって、変化(Veränderung)ではない。基体が持続していながら、属性が変わった場合にのみ、変化と言える。
現在の地平と過去の地平の《連続的不連続性=不連続的連続性》があるからこそ、地平の融合による思想的継承が可能になるのであったが、この《連続的不連続性=不連続的連続性》は変化一般の基本的要件である。
時間的認識の不確定性は、認識者の時間的不確定性に依拠し、歴史的認識の有限性は、認識者の歴史的有限性によって限定される。したがって、認識論的地平は存在論的地平である。
公式9.時間的有限性の地平. もし人間が無限の時間を生きることができるのなら、人間は死について考える必要はない。もし人間が無ならば、死について考えることすらできない。時間的に有限であるからこそ、人間は自らの死と人生について真剣になりうる。
フランクルは次のように説明している。
もし我々の人生が時間的に有限ではなくて無限であるならば、我々の人生はどのようなものとなるであろうか。もしも我々が不死ならば、いかなる行為も永遠に延期することは正当となるであろう。どんな物事も今するかどうかは重要ではなく、全ての行為は、明日やってもあさってやっても、1年後にやっても10年後にやっても同じである。だが、我々の将来の絶対的終わりとしての、我々の諸可能性の絶対的限界としての死に直面する時、我々は、どんな機会 - その“有限な”合計が全人生を構成する - をも無為に逃すことなく、自分の人生を最大限活用しなければならなくなる。[16]
問いは人間の認識と存在の地平性を対自化させると公式1で述べた。問いを立てて答えても、それはさらなる未知の地平をあらわにするだけである。もし人生が永遠であるならば、学的探究は永久に続けることができる。しかし人生が有限であるから我々の知も有限に留まる。そこで問いの地平は時間であることになる。これはハイデガーの地平論に通じる。
ハイデガーは、あらゆる問いの中でも最も根本的な問いである存在への問いを、存在を問いうる問いの存在(現存在)に問い尋ね、存在の意味が時間性であることを剔抉する。したがって「存在了解内容の地平としての時間を、存在を了解しつつある現存在の存在としての時間性から根源的に説明する必要がある[17]」 。
ハイデガーの言う時間性は、今の連続としての水平化された通俗的(自然科学的)時間性ではなく、「既在しつつある現成化する到来[18]」 なる様態を持つ先駆的決意性としての時間性である。
世界の可能性の実存論的・時間的条件は、時間性が脱自的統一として地平といったようなものを持っていることのうちに潜んでいる。諸脱自態[Ekstasen 到来・既在・現在]は単純に何かへの脱出 であるのではない。むしろ脱自態には、脱出の《行き先 Wohin》が属しているのである。脱自態のこの行き先を我々は地平的図式と名付ける。[19]
到来なる脱自態の地平的図式は「自己自身が存在しうる」ための目的であり、既在性の図式は被投性であり、現在の図式はかく被投されながら目的へと企投しつつおのれに先んじて世界に内存在することである。
地平は、生きようとする(同時に死によって限界付けられる)我々の存在の構造を規定する図式でもある。だから死の可能性がなくなったとき、生きようとする意志が、そして全ての実践的目的が消滅し、現存在の存在了解は無意味となるであろう。死はネガティヴな現存在の限界であると同時に、ポジティヴな有意味性の条件でもある。
人間は時間的に有限であると同時に空間的にも有限である。そこで空間的存在に関しても次の中間性の公式が成り立つ。
公式10.空間的有限性の地平. もし私が空間的・身体的に無限な存在者であるならば、私は空間的環境を持たないがゆえに私について考えることはない。もし私が無ならば、私は私について、いや全てに関して考えることすらできない。空間的に有限な存在者であるからこそ、私は自己回帰的自己反省を行える。
空間的な私の有限性は、私のパースペクティブ的特殊性をもたらし、同時に私とは違った身体的存在を空間的に可能ならしめる。だから公式10は自己認識のみならず他者認識の地平でもある。
4. 参照情報
- 永井俊哉.『システム論序説』Kindle Edition (2015/05/07).
- プラトン『饗宴』中澤務 (翻訳). 光文社 (2013/9/20).
- ハンス=ゲオルク ガダマー『真理と方法 I』法政大学出版局; 新装版 (2012/11/20).
- ハンス=ゲオルク ガダマー『真理と方法 II』法政大学出版局; 新装版 (2015/6/24).
- Gadamer, Hans-Georg. Wahrheit und Methode: Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik. Gesammelte Werke Bd. 1. Mohr Siebeck, 2010.
- ↑本稿の初出は、永井俊哉 “「地平の哲学」序説“『一橋論叢』(通巻616号 52-68頁 日本評論社 1992年2月1日)である。その後、『システム論序説』の第一章第一節になったが、それを再びブログ用の記事にしたのがこのページである。
- ↑Πλάτων. Συμπόσιον. プラトン『饗宴』中澤務 (翻訳). 光文社 (2013/9/20).
- ↑Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse. Hamburg: F. Meiner, 1959 (Originally published 1817). §. 173.
- ↑Husserl, Edmund. Logische Untersuchungen. Meiner Verlag, 2009 (Originally published 1900,1901). p.326. この無意味な命題は「現在のフランス王は禿げである」のように確定記述を含むわけではないが、“記述の理論”に従って、「丸くかつ四角でかつ素数であるようなxが存在する」というようにパラフレーズすれば、たんなる偽の命題となる。記号論理学は真と偽の二値しか持たないのだから当然である。
- ↑
Wittgenstein, Ludwig. Philosophische Bemerkungen. ed. Rush Rhees. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag Gmbh, 1964. §.39. - ↑Husserl, Edmund. Cartesianische Meditationen und Pariser Vorträge. 1931. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 1. Martinus Nijhoff. ed. Stephan Strasser. 1963. p. 139.
- ↑Husserl, Edmund. Cartesianische Meditationen und Pariser Vorträge. 1931. Husserliana, Edmund Husserl Gesammelte Werke, Bd. 1. Martinus Nijhoff. ed. Stephan Strasser. p. 82.
- ↑Gadamer, Hans-Georg. Wahrheit und Methode: Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik. Gesammelte Werke Bd. 1. Mohr Siebeck, 2010. p. 307.
- ↑Gadamer, Hans-Georg. Wahrheit und Methode: Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik. Gesammelte Werke Bd. 1. Mohr Siebeck, 2010. p. 311.
- ↑Gadamer, Hans-Georg. Wahrheit und Methode: Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik. Gesammelte Werke Bd. 1. Mohr Siebeck, 2010. p. 312.
- ↑Gadamer, Hans-Georg. Wahrheit und Methode: Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik. Gesammelte Werke Bd. 1. Mohr Siebeck, 2010. p. 310.
- ↑Gadamer, Hans-Georg. Wahrheit und Methode: Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik. Gesammelte Werke Bd. 1. Mohr Siebeck, 2010. p. 110.
- ↑Gadamer, Hans-Georg. Wahrheit und Methode: Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik. Gesammelte Werke Bd. 1. Mohr Siebeck, 2010. p. 112.
- ↑Gadamer, Hans-Georg. Wahrheit und Methode: Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik. Gesammelte Werke Bd. 1. Mohr Siebeck, 2010. p. 111.
- ↑Kant, Immanuel. Kritik der reinen Vernunft. Felix Meiner Verlag (July 1, 1998).
A.187=B.230-1. - ↑Frankl, Victor. The Doctor and the Soul. p.73.
- ↑Heidegger, Martin. Sein und Zeit. 1927. Max Niemeyer Verlag. p. 17.
- ↑Heidegger, Martin. Sein und Zeit. 1927. Max Niemeyer Verlag. p. 326.
- ↑Heidegger, Martin. Sein und Zeit. 1927. Max Niemeyer Verlag. p. 365.




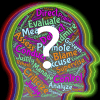



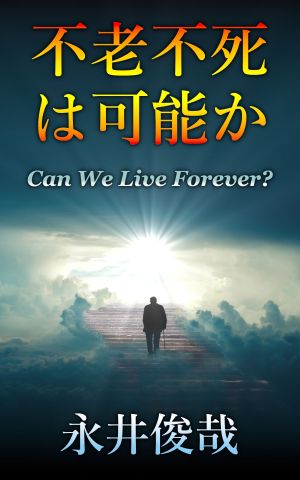

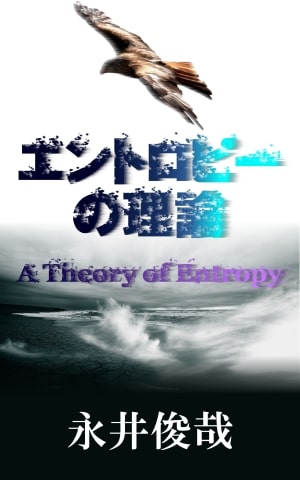

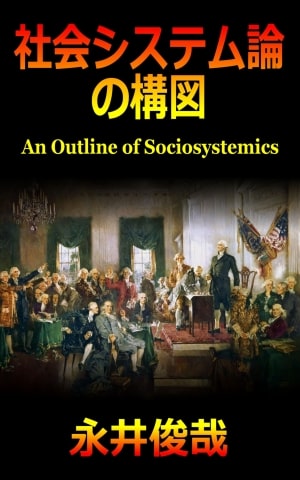

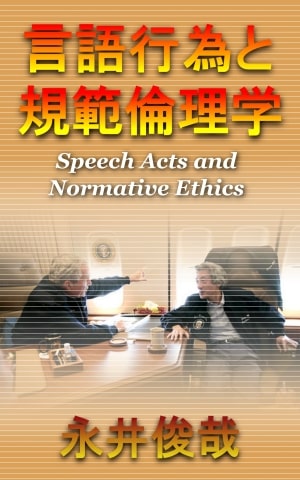
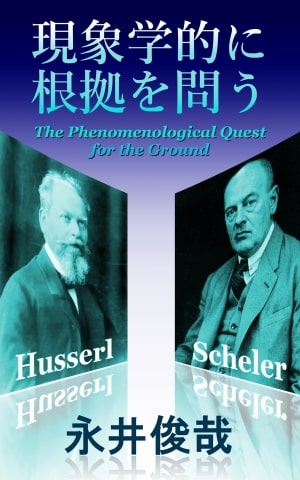
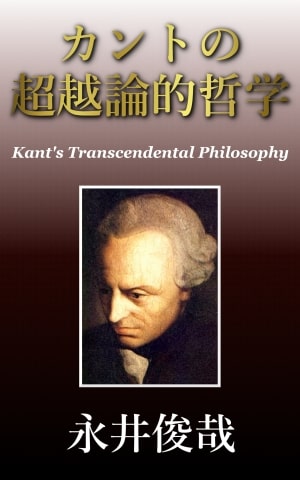
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません