卑弥呼の鏡
卑弥呼は、238年(または239年)に魏に朝献し、「親魏倭王」の称号とともに金印紫綬や銅鏡などをもらったと伝えられる。なぜ卑弥呼は、当時朝鮮半島に日本を脅かす勢力があったわけでもないし、また魏は、それ以前に倭が朝貢した漢とは違って、中国大陸全体を統治する大王朝でもないのに、魏に朝貢したのか。『魏志倭人伝』には、鏡が卑弥呼および倭人の「好物」であると記されているが、なぜ卑弥呼と倭人は、鏡を望んだのか。卑弥呼がもらった鏡は、本当に三角縁神獣鏡なのか。[1]

1. 卑弥呼はなぜ魏鏡を必要としたのか
1.1. 気候変動と邪馬台国の危機
卑弥呼は、もともと自らのシャーマン的な能力で邪馬台(やまと)国連合体を治めていたのであって、外国の権威など不要だった。卑弥呼(日巫女)は、それこそ太陽のような輝きでもって邪馬台国連合体を50年以上も治めたが、彼女が晩年に魏にお墨付きを求めるようになったことは、その輝きに陰りが見えてきたことを意味する。
花粉分析や縄文杉の年輪幅の調査から、西暦240年頃から古墳時代にいたるまで、日本の気候が寒冷化したことが知られている[3]。いわゆる古墳寒冷期である。気候が寒冷化すれば、作物は実らなくなり、食糧不足から社会不安が広まる。これは自然現象である。しかし当時の人は、卑弥呼がかつての若さを失って、霊力がなくなったので、太陽の力が衰えたと考えた。そして、これが、卑弥呼が魏に鏡を求めた時代的背景である。
1.2. 鏡像段階的解釈
日本人は「鏡(kyang)」を「かがみ」と訓じる。多くの学者は、その語源を「影見(かげみ)」に求めているが、吉野裕子は、蛇の古語が「カカ」であること、名前に「カガミ」を含む植物が、すべて蛇そっくりの蔓植物であることを手掛かりに、「カガミ」を「カカ」+「ミ」、つまり「蛇」+「身」と解釈する[4]。
しかし、「カガミ」の「ミ」は甲類で、「身」の「ミ」は乙類だから、この解釈は無理である。『類従名義抄』には、「カヾミル」という訓もある[5]ことから、「蛇」+「見る」と解釈できる。ちなみに、「見る」の「ミ」は、甲類である。「カヾミル」は、転訛して「カンガミル」(鑑みる)になった。
古代に日本では、K音とH音の区別がないので、「カカ」と「ハハ」は同じ言葉である。このことは、日本にも、世界の他の地域でと同様に、蛇を地母神の化身と見る女性崇拝の宗教があったことを示している。蛇は、川のように大地の上を蛇行するがゆえに、水の神としても見られていた。原始の日本人は、銅鏡ではなくて、水面を鏡として使っていたはずだ。その時、我々の祖先は、蛇のように身を「カガメ」て、「カガミ」に「カカ」を「ミ」たことだろう。
私たちが、鏡を通してはじめて、自分の全身を見ることができるように、そして、鏡像段階の幼児が、母親を通してはじめて、自己の存在を確認することができるように、縄文時代の人々は、地母神としての蛇を通してはじめて、自らの共同体をまとめることができた。ここでは詳述しないが、縄文人が蛇をトーテムとして崇拝していた証拠はたくさんある。
弥生時代になると、崇拝の対象は、蛇から太陽に変わる。男根期に幼児の関心が母親から父親に向かうように、古代人の関心も、母神から父神へと移っていく。鏡のメタファーを使うならば、鏡の中の理想自我と自己同一できるのは、鏡のおかげだけではなく、光のおかげでもあることに子供は気が付く。そして、その光の源が、父なる太陽という自我理想なのである。
卑弥呼の時代は、まさにそうした時代だった。卑弥呼は、太陽神と人々とを媒介する巫女であって、少なくとも生前は太陽神そのものではなかった。邪馬台国の民と卑弥呼と太陽神は、子供と母と父の関係にあったと考えてよい。
1.3. 第二の太陽としての魏の権威
158年に皆既日食が発生した時、倭の人々は、自己同一するべき理想自我を失い、内乱状態となった。卑弥呼は、日の巫女としてこの混乱を収めた。人々は、卑弥呼という鏡を通して、太陽神との自己同一、すなわち、太陽神のもとでの再統合を果たした。
やがて、自分の老衰と同時に太陽の衰退が始まり、太陽神のもとでの秩序の維持が難しくなると、卑弥呼は、<邪馬台国の民-卑弥呼-太陽神>という<子-母-父>の関係を、邪馬台国の<民-魏の銅鏡-魏の皇帝>の関係で補強しようとしたわけだ。
2. 三角縁神獣鏡は卑弥呼の鏡か
魏が卑弥呼に銅鏡を下賜したことが史実だとしたら、その銅鏡は、国内に残っているはずだ。邪馬台国が畿内にあったとする畿内説支持者は、畿内を中心に4世紀の古墳から大量に出土している三角縁神獣鏡(さんかくえんしんじゅうきょう)こそ卑弥呼の鏡だと主張している。三角縁神獣鏡は、背面が半肉彫りの神人および獣形の文様を持ち、縁の断面が三角形をしているのでこう呼ばれる。

『魏志倭人伝』によると、魏の皇帝は、景初二年(景初三年の間違いとする説あり)に、卑弥呼が遣わした難升米に「銅鏡百牧」を下賜した。邪馬台国が畿内にあったと想定する人々は、三角縁神獣鏡が卑弥呼の鏡だと主張しているが、邪馬台国が九州にあったとする人々は、三角縁神獣鏡は国産鏡で、魏の皇帝から賜った鏡は、北九州から多く出土する漢鏡のはずだと主張している。
三角縁神獣鏡は、本当に卑弥呼が魏からもらった鏡なのだろうか。以下の理由で、私は違うと思う。
2.1. 中国からは全く出土していない
三角縁神獣鏡は、日本国内では600枚以上見つかっているが、中国では全く出土しない。また、三角縁神獣鏡の径は22cmもあり、後漢・三国時代の鏡よりもはるかに大きい。だから、王仲殊(おうちゅうしゅ)や徐苹芳(じょへいほう)といった中国の考古学者たちは、三角縁神獣鏡は魏が作った鏡ではないと主張している。
三角縁神獣鏡とは別に、画文帯神獣鏡という、三角縁神獣鏡とよく似た神獣鏡があり、これも中国よりも日本で多く出土する。また、中国とは言っても、画文帯神獣鏡が出土するのは、魏の領土でではなくて、敵国である呉の領土や呉と内通して滅ぼされた公孫淵の領土である朝鮮の楽浪郡からである。この理由は、後で説明することにしよう。
2.2. 枚数が合わない
現在、三角縁神獣鏡の数は600枚以上にのぼっているが、これは、銅鏡百枚を贈ったとする『魏志倭人伝』の記述と矛盾する。但し、卑弥呼が生きていた時代の魏の年号が入った三角縁神獣鏡はわずかしかないので、畿内説支持者のなかには、年号の入ったものだけが本物だと考え、この難点を説明しようとする人もいる。
2.3. 記年が間違っている鏡がある
ところが記年銘鏡にも怪しげなものがある。「景初四年」という実在しない記年が入った鏡が、京都府福知山市の古墳から出土している。景初は三年で終わりで、翌年は正始元年でなければならない。
これに対して、畿内説支持者は、三角縁神獣鏡は、魏で作られたものではなく、魏の皇帝が職人を遣わして、倭人の好みに合わせて倭で独自の鏡を作らせたとする特鋳品説を唱え、倭に来ていた職人は、元号が変わったことに気が付かずに、「景初四年」という記年を入れてしまったのだろうと推測する。なるほど、この特鋳品説ならば、三角縁神獣鏡が、中国では全く出土しない理由をも説明することができる。
魏の皇帝が職人を遣わすというのは、ありそうにない話だが、百歩譲って三角縁神獣鏡が特鋳品であると認めても、さらに次のような問題がある。
2.4. 三角縁神獣鏡は呉の様式で作られている
中国の考古学者・王仲殊氏は、鏡の様式から「三角縁神獣鏡は、日本に渡った呉の鏡職人が日本で製作したもの」と判断している。そもそも作った年月を鏡に記す習慣も、魏ではなく呉のものである。
問題は、三国時代の呉が魏の敵国であったことである。魏の皇帝が呉様式の鏡を倭に下賜することは、現代の譬えで言えば、中国の北京政府が、李登輝台湾総統の肖像が刻まれた日中友好記念硬貨を日本に贈るようなもので、おおよそありえない国辱的行為である。奴隷と引き換えに鏡を贈ることは、例えば、自動車を輸出して石油を輸入する現在の実利的な貿易とは異なって、象徴的儀礼的な政治的行為である。だから魏の皇帝の名のもとに敵国様式の鏡を贈ったり、まして敵国の職人を派遣するなどということは考えられないのである。
畿内説支持者の中には、画文帯神獣鏡が朝鮮半島から中国北部にかけても見られることから、三角縁神獣鏡が魏鏡だと主張する人もいる[7]。しかし、画文帯(がもんたい)神獣鏡は、朝鮮半島よりも、かつて呉が存在した長江流域でたくさん見つかっているから、やはり呉の鏡といわなければならない。少なくとも、魏の本土では全く見つからないのである。
卑弥呼の朝貢直前に、魏は、朝鮮半島北部の楽浪郡を占領していた公孫淵が呉と結び、独立して、漢の後継を目指したので、公孫淵を滅ぼしているが、公孫淵が呉と同盟を結ぶ際、呉の鏡が同盟の証として贈られたと考えることができる。もしも卑弥呼が画文帯神獣鏡を持っていたら、呉と内通しているのではないかと魏の使者に疑われたことであろう。だから、三角縁神獣鏡や画文帯神獣鏡といった呉様式の鏡は、卑弥呼の鏡ではない。
2.5. 銘文に疑わしい点がある
魏王朝特鋳説は鏡の銘文からも否定される。詩や銘は韻文であり、韻を踏むのが原則であるが、三角縁神獣鏡には、魏ではすでに韻を踏まなくなった字を韻字として用いたり、韻文をつくるつもりすらない拙劣な銘文が見られる。森博達は次のように言っている。
そもそも魏の時代は、曹操父子を中心として詩壇が形成され、「建安詩」「正始詩」の時代として文学史上高く評価されている。詩は銘と同じく韻文であり、音韻の知識も深まっていた。卑弥呼を親魏倭王に任命した景初三年は、まさにこのような詩文隆盛の時代である。
そのとき明帝(曹操の孫)は卑弥呼に銅鏡百枚などを賜わり、次のように詔した。「これらすべてを汝の国内の者たちに示し、わが国家が汝をいとおしく思っていることを知らしめよ。 それゆえに鄭重に汝に良き物を賜与するのである」
この荘重な詔書とともに、「景初三年」銘の三角縁神獣鏡が下賜されたと、魏鏡論者は主張する。魏の詩人がこの三角縁神獣鏡の銘文を見れぱ、押韻の意識すら持たない拙劣さをあざ笑うだろう。「朕はアホなり」と言うに等しい銘文である。親魏倭王のみならず、皇帝自身の権威にも傷がつく。こんな銘文をもつ鏡を特鋳して賜わるはずがない。三角縁神獣鏡魏朝特鋳説は幻想だ。[8]
これに対する考古学からの説得力ある反論はまだ出ていないそうである。
2.6. 三角縁神獣鏡は四世紀の古墳から出土する
卑弥呼は三世紀中頃に死亡したにもかかわらず、鏡はすべて四世紀の古墳から発掘される。畿内説支持者は、虚偽の年代が鏡に入れられるはずがないというが、銘文の字体から、虚偽が明らかな鏡もある。安萬宮山古墳から出土した「青龍三年」(235年)鏡の「龍」の字の旁(つくり)は「大」となっている。この字体は四~五世紀の中国北朝時代に使用された異体字で、後漢・魏晋朝時代にはなかった字体である。つまりこの鏡は四~五世紀の作品であるということである。
私は、邪馬台国は北九州に存在し、畿内に東遷したと考えている。邪馬台国東遷説の立場からは、三角縁神獣鏡は、九州にあった邪馬台国が4世紀初頭に畿内を征服し、現地の豪族と主従関係を結んだとき、連れてきた呉の職人に量産させ、卑弥呼以来の由緒ある中国鏡と偽って彼らに下賜したと考えることができる。
1998年1月に、奈良県天理市の大和(おおやまと)古墳群にある古墳時代前期前半(四世紀初めごろ)の前方後円墳・黒塚古墳の竪穴式石室から、三角縁神獣鏡三十二面を含む大量の副葬品が、埋納当時のままの状態で出土した。黒塚古墳から出土した三角縁神獣鏡の兄弟鏡の分布地を見ると、畿内、瀬戸内海、九州、東海といった大和政権の友好国の領域と重なる。他方で、記紀で敵国として描かれている出雲や諏訪からは一枚も出土していない。
鏡を作ったのが、なぜ呉の職人なのかについても説明しよう。三角縁神獣鏡には、「絶地亡出」「至海東」といった銘文を持つものがある。呉が滅び西晋王朝が中国を再び統一したのは280年である。呉が280年に滅亡して、呉の鏡職人は新たな活動の場を求めて、鏡の需要が大きい日本に来たと考えられる。呉の鏡職人の渡来と九州勢力の東征は時期的に非常に近い。三国時代が終わると、中国では鏡の生産が急速に衰えて行った理由もこれで説明できる。
3. 邪馬台国に関する最近の報道
ここ数年、邪馬台国畿内説に有利な報道がなされているが、私が見るところ、決定力に欠けている。以下、マスコミで大きく取り上げられた「畿内説有利情報」を検討してみよう。
3.1. ホケノ山古墳の築造年代測定
私は、「三角縁神獣鏡は四世紀の古墳から出土する」と書いたが、畿内説支持者たちは、畿内の古墳の年代を引き下げることで、奈良県纏向遺跡にある箸墓を卑弥呼の墓に、三角縁神獣鏡を卑弥呼の鏡にしようと懸命に努力している。
2000年3月27日に大和古墳群学術調査委員会が発表した、ホケノ山古墳第4次研査の結果の報道にもそのような努力の跡が見られる。マスコミは、箸墓と同じく奈良県纏向遺跡にあるホケノ山古墳が造られたのは3世紀前半と報道した。畿内説支持者の中には、これは卑弥呼の父の墓で、これと同じ前方後円墳の箸墓は、卑弥呼の墓かもしれないと言った人もいた。
3世紀中ごろの築造で、国内最古の前方後円墳とされる奈良県桜井市のホケノ山古墳から出土した木棺の破片を放射性炭素(C14)年代測定法で分析した結果、築造年代が3世紀前半にさかのぼることが分かった。7日発表した大和古墳群学術調査委員会(委員長、樋口隆康・同県立橿原考古学研究所長)は「前期古墳の築造年代を、全体的に引き上げて考える必要がある」と評価。卑弥呼の墓との説がありながら、3世紀後半から末期の築造とされてきた最古の大型前方後円墳・箸墓古墳の築造年代が、卑弥呼の没年とされる247年ごろに近づく可能性も強まり、邪馬台国大和説の補強材料になりそうだ。
出土したのはコウヤマキ製のくりぬき式木棺(長さ5m、幅1m)。加工を容易にし、腐るのを防ぐため、棺の表面は焼かれ、黒く炭化していた。調査委が木棺北側の炭化部分から1センチ角のサンプル5点を採取し、米国フロリダ州の専門機関に分析を依頼した。
測定の結果、サンプルの年代は「西暦120年を中心に、75~215年」「120年を中心に、80~155年」などと判明。調査委は、欧米と日本の自然環境の違いなどからデータを補正し、木棺を加工した際に木材表面が削られていることなどを考慮、伐採年を2世紀末~3世紀前半と推定した。中国で2世紀末~3世紀初めに作られた画文帯神獣鏡が副葬されていたことなどから、築造年代を3世紀前半と判断した。[9]
どのように調査委員会がデータを補正したのかわからないが、放射性炭素年代測定法は、精度の低い方法で、同一資料を、より精度が高いと言われる年輪年代法で測った場合と比べて、200年古く出る傾向にある[10]。だから、ホケノ山古墳の築造年代は、西暦120年に200年を足すと320年となるから、4世紀前半と考えられ、邪馬台国東遷説と矛盾しなくなる。
ホケノ山古墳を邪馬台国の古墳とすることには、別の問題もある。『魏志倭人伝』は、倭人の墓に関して「棺あって槨なし」と記しているが、ホケノ山古墳では、木槨のなかに木棺がある[11]。
3.2. 勝山古墳から出土した木材の年輪年代測定
放射性炭素年代測定法では信用性が低いからなのか、奈良県立橿原考古学研究所と奈良国立文化財研究所は、翌年には、より精度の高いと考えられる年輪年代測定によって、畿内の古墳は3世紀初頭(遅くとも西暦210年)に造られたというレポートを発表した。測定対象となったのは、纒向古墳群に所属する勝山古墳である。
奈良県桜井市東田(ひがいだ)の勝山古墳から出土したヒノキ材を年輪年代測定で調べた結果、同古墳か三世紀初めに築かれた、わが国最古の古墳であることがわかったと、県立橿原考古学研究所が三十日、発表した。古墳出現が半世紀近くさかのぼって中国の史書「魏志倭人伝」に登場する女王・卑弥呼の時代と重なることから、弥生時代と考えられてきた邪馬台国の時代(二世紀末~三世紀後半)がすでに古填時代だったことを示すなど、古代の年代観を変える画期的な成果となった。邪馬台国は初期ヤマト政権だった可能性が高まり、畿内説に弾みをつけそうだ。[12]
ところが、このヒノキ材が出土したのは、墓の中からではなくて、周濠埋土中からだった。両者を結びつける必然性は何もない。だから、ヒノキ材の推定伐採年代を勝山古墳の築造時期とみなすことはできない。
橿原考古学研究所は、次のように、両者を関係付けようとする。
これらの木材および木製品には、建築部材と考えられるものが多数存在し、また、朱が塗られたものや付着したものも多く認められる。出土した鋤柄は小形のもので実用品とは考えにくい。これらは、いずれも意図的に破壊された後、墳丘側から一括投棄された可能性が高い。以上の点から、これらの遺物は、墳丘上で執行された何らかの祭祀で使用された後、一括廃棄されたものと考えられる。[13]
しかし、こうした祭祀葬礼の慣行は、後世にない。そもそも、彼岸と此岸を分かつ境界である周濠をゴミで汚すなどということは、宗教学的にありそうにない話である。
ところで、奈良国立文化財研究所がやっている年輪年代測定は、本当に正確なのだろうか。奈良国立文化財研究所は、2002年2月21日に、法隆寺の五重塔の心柱の伐採は594年であると発表した。法隆寺五重塔は、670年の火災の後、遅くとも711年までに再建されたということがわかっている。そうすると、100年ほど前に伐採された木材が建築資材として使わたという奇妙なことになる。
実は、1987年の発表では、ヒノキには建築材料として不適で、切り捨てられた部分が53±17年分あると推定して、心柱の伐採は644年、早くても627年とされていた。それが2002年には、3年へと大幅に短縮されて、594年になってしまった。このように、年輪年代測定では、丸太から何年分が切り捨てられたかの推測に関してあいまいなところが残る。
ともあれ、もしも、100年前に伐採された木が法隆寺の心柱の資材として使われたのであれば、100年前に伐採された木でできたゴミが勝山古墳の周濠に捨てられたとしても、別に不思議ではない。
3.3. 三角縁神獣鏡の成分測定
2004年には、卑弥呼の墓ではなくて、卑弥呼の鏡に関して、畿内説に有利な報道がなされた。
青銅鏡のコレクションを持つ京都市の泉屋博古館(せんおくはくこかん)(樋口隆康館長)と、スプリング8を運営する兵庫県三日月町の高輝度光科学研究センターが共同で分析に取り組んだ。15日午後、京都市で開かれた文化財科学会大会で発表した。
強力なX線を鏡に当てて、不純物としてごく微量に含まれている銀とアンチモンの反応の強さを調べた。この方法で、同館所蔵の中国の戦国時代(紀元前3世紀)から三国西晋時代(3世紀)にかけての鏡69枚と、古墳時代前・中期(3~4世紀)の三角縁神獣鏡ではない日本製の鏡18枚を分析したところ、中国製の各時代の鏡と日本製の鏡はそれぞれ異なるまとまりをつくった。
その上で、同館にある三角縁神獣鏡8枚を同方法で分析した結果、6枚からは三国西晋時代の年号が入った中国製鏡と近い測定値が得られ、残る2枚は日本製のまとまりに入った。[14]
これに対して、安本美典は、比較対照となった中国製鏡が本当に中国製かどうか疑わしいと言っている。
泉屋博古館所蔵の鏡はほとんどが出土地不明であり、考古学的な資料価値は低いものである。ふつうの人は「中国製」と書かれれば中国産と信じてしまうが、これらの鏡は模様などから館長の樋口隆康氏が中国製と判断しているだけで、中国で作られたものかどうか疑わしい。
調査対象になった三国西晋時代の神獣鏡というのが、画文帯神獣鏡だとすると、画文帯神獣鏡は日本での出土数の方が中国からの出土数の倍近くあり、その一部は日本で作られた可能性がある。[15]
仮に材料が中国のものであったとしても、それが中国人の手によって、中国で作られたという証拠にはならない。
廣川守は、レポートの末尾で次のように付け加えている。
上記検討は測定件数が非常に少ないため、今後、三角縁神獣鏡および古墳時代製鏡の測定試料数を増やす必要があります。また、三国・西晋時期の中国鏡についても、今回は神獣鏡のみに留まっており、神獣鏡以外の形式の魏・西晋鏡の測定も不可欠です。[16]
材料の由来と製造地を確かめるには、中国から出土した魏の鏡と「景初四年」の記年が入った三角縁神獣鏡と正常な三角縁神獣鏡の三種類の鏡の成分を比較しなければならない。
3.4. 金銀錯嵌珠龍文鉄鏡と曹操墓出土鉄鏡
曹操高陵を発掘した中国河南省文物考古研究院の潘偉斌(ハン・イヒン)が来日し、大分県日田市日高町にあったダンワラ古墳から出土した金銀錯嵌珠龍文鉄鏡(きんぎんさくがんしゅりゅうもんてっきょう)を確認した上で、これが卑弥呼の鏡である可能性が高いという見解を示した。金銀錯嵌珠龍文鉄鏡は曹操墓出土鉄鏡と大きさや品質の点で劣らず、潘は、「金錯や銀錯が施される鏡は王宮関係に限られる。この鏡は国宝級の貴重なものであり、公式なルートで日本に伝わったと考えられる」と述べた[17]。
金銀錯嵌珠龍文鉄鏡は、1933年にダンワラ古墳を線路の盛土を採集するために破壊していた時に渡辺音吉によって発見された。ダンワラ古墳は、古墳時代後期に特徴的な横穴式石室を持つ古墳であるが、金銀錯嵌珠龍文鉄鏡は、横穴式石室よりも下にある、より古い古墳の竪穴式石室の中から見つかった。鏡は、1962年に、京都大学教授の梅原末治によって考古学的価値が見いだされ、64年に重要文化財に指定された。鏡自体は、後漢から魏の時代にかけて作られたと考えられるが、梅原は、同じ竪穴式石室から出土した辻金物の細工から、この石室は五~六世紀に作られたと推測した。もっとも、九州北部では横穴式石室が四世紀後半から作られ始め、五世紀に普及した。竪穴式石室は横穴式石室よりも古いから、六世紀ということはないだろう。
239年に魏の皇帝が卑弥呼に銅鏡百枚を下賜したと魏志倭人伝は伝えている。邪馬台国畿内派は、銅鏡百枚は、その後各地の豪族に下賜されたという説明をしている。しかし、金銀錯嵌珠龍文鉄鏡は、凡庸な百枚の銅鏡、ましてや国産と疑われる希少価値のない三角縁神獣鏡とは格が違うから、畿内にあった邪馬台国が大分県日田市あたりにいた凡庸な地方豪族に下賜したとは考えにくい。潘が言うように、「王宮関係に限られる」「国宝級の貴重なもの」なのだから、卑弥呼や台与(卑弥呼と同族とされる)の一族に受け継がれ、五世紀にその末裔と共に葬られた可能性が高い。
安本美典は、邪馬台国の中心は旧甘木市(現在は朝倉市の一部)にあったと推測している。ダンワラ古墳があった大分県日田市日高町は、旧甘木市の近くに位置する。なぜ旧甘木市から出土しなかったのかと訝しむ人もいるかもしれないが、墓は通常都の中心には作られない。例えば、平安京遷都後の天皇陵は、洛西や洛南など、江戸時代では東山区泉涌寺の月輪陵など、都からやや離れた場所に造営されている。五世紀になっても経済活動が活発に行われていた旧甘木市の平野部から少し離れたところに墓を造営したことは自然なことである。鏡は運搬可能な物なので、決定的な証拠にはならないが、潘の見解は邪馬台国甘木説にとっては有利であるということは言える。
4. 参照情報
4.1. 関連著作
- 中村啓信『新版 古事記 現代語訳付き (角川ソフィア文庫)』KADOKAWA (2014/2/15).
- 松尾光『現代語訳 魏志倭人伝』KADOKAWA (2014/6/30).
- 渡邉義浩『魏志倭人伝の謎を解く 三国志から見る邪馬台国』中央公論新社 (2012/5/25).
- 孫栄健『邪馬台国の全解決 中国「正史」がすべてを解いていた 』言視舎 (2018/2/15).
- 安本美典『日本の建国―神武天皇の東征伝承・五つの謎』勉誠出版 (2020/6/15).
- 安本美典『邪馬台国は福岡県朝倉市にあった!!―「畿内説」における「失敗の本質」』勉誠出版 (2019/9/6).
4.2. 注釈一覧
- ↑本稿の初出は、1999年11月13日発行のメルマガ記事、「卑弥呼はなぜ魏の鏡を必要としたのか 」である。その後大幅に加筆を行った。1999年11月13日当時のメルマガ原文に関しては、リンク先を参照されたい。
- ↑Tokyo National Museum. “Mirror with Triangular Rim and Design of Buddhist Characters and Animals, Kofun period, 4th century, from Shinyama Tumulus, Koryo-cho, Nara.” Licensed under CC-0.
- ↑阪口豊. 「日本の先史・歴史時代の気候」『自然』39(5), 1984-05. 中央公論社. p18-36.
- ↑吉野裕子.『蛇―日本の蛇信仰』法政大学出版局 (1979/02).
- ↑白川静.『字通』平凡社; 普及版 (2014/3/20).
- ↑Wikiwikiyarou. “Bronze Mirror in Ancient Japan." Licensed under CC-BY-SA.
- ↑福永伸哉.「三角縁神獣鏡の系譜と性格」『考古学研究』38(1). p. 35-58, 1991-06. 考古学研究会.
- ↑『毎日新聞』2000/09/12.
- ↑『毎日新聞』2000/04/12.
- ↑邪馬台国の会.「C14年代測定法の信頼性」accessed on 19 Oct 2003.
- ↑邪馬台国の会.「ホケノ山古墳の年代について」accessed on 11 Sep 2003.
- ↑『読売新聞』2001/05/31.
- ↑橿原考古学研究所.「勝山古墳出土木材年輪年代測定結果について」accessed on 2016/03/26.
- ↑『朝日新聞』2004/05/15.
- ↑邪馬台国の会.「三角縁神獣鏡神獣鏡に関する最近の報道について」accessed on 11 Oct 2004.
- ↑廣川守.「SPring-8を利用した古代青銅鏡の放射光蛍光X線分析」accessed on 2006/01/05.
- ↑“卑弥呼の鏡「可能性高い」大分・日田で出土の鉄鏡 中国・曹操陵の発掘責任者が見解.” 『佐賀新聞』2020/1/3 10:29.










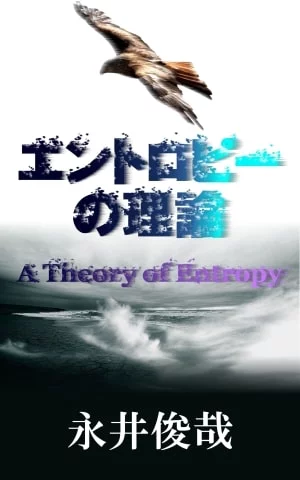

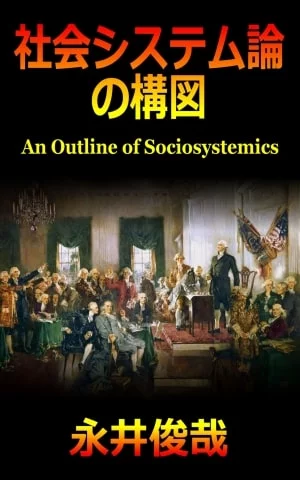

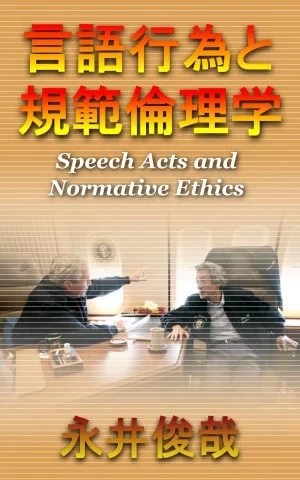
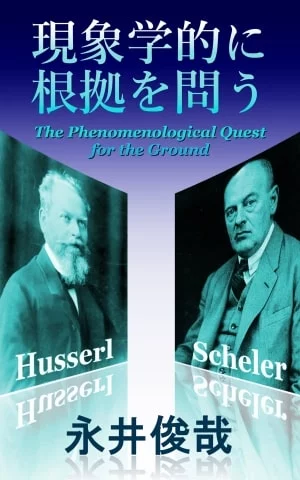

ディスカッション
コメント一覧
(<1>で触れられている)、「鏡(かがみ)」の語源論について、コメントさせて戴きます。
引用ミスでしょうか? 吉野裕子著『蛇』を引用なさって永井様は、<吉野は(・・・)「カガミ」を「カカ」+「ミ」、つまり「蛇」+「身」と解釈する>、と書いておられますが、この本は法政大学出版局からのものと、講談社学術文庫刊のものがありますが、手持ちの文庫本を見るとは、<第三章 六、『捜神記』における大蛇と目と鏡 > の項目の中で、吉野さんは、
<「カガミ」を私は「蛇目(カカメ)」の転訛として捉える。この、『捜神記』において蛇の目が大鏡に譬えられていることは、この推測の有力な裏付けと思われる>(142頁) と書いております。
つまり、「カカメ(蛇目)」が「カガミ」に訛った、というのが吉野説だと思います。
一方、永井説は、直截に「鏡=かか(蛇)み(見)」説ですね。実に素晴らしい新見解だと感服した次第です。既に発表した私の説では「川」の語源は(中国の「蛇行」という表現の影響もあって)「かか(蛇)這(は)ふ」の縮約形で「かは→かわ」となったと見るわけですが(拙著『原始日本語はこうして出来た』参照)、この大空説を更に一歩進めて、永井様は、「(川の)水面(みなも)を鏡として使っていたはずだ」と推察なさり、この「川鏡・水鏡」に<「カカ(蛇)」を「ミ(見)」たことだろう>とされます。実に鋭い指摘だと思います。
ただ、欲を言えば、吉野説と合体させて、更に踏み込んで、「川を蛇に見立てる以上、川である蛇がこちらを見ている」ということでの「かか(蛇)み(見)」という解釈も成り立つと思います。永井様が「いやいや、そこまでは言わない」と仰るのでしたなら、大空説としてそう主張したいところですが、如何でしょう?(笑) それとも永井説は「蛇がこちらを見ている」という意味も含んでの「蛇見」説でしょうか?
上記の拙著の中で、私は「かがみ」の語源を「光(か)々身(み)」とし、それが「光(か)々見」に転訛したと記しましたが、最近はこれを改め、「かか(光々・蛇)見」と解することにします。
ほつま文字では「か」に「光」の意味がありますが、拙著では、中国語の「光(コウ)」の音が日本語に取り込まれて「か(光)」と決めたのだろうと推察しましたが、今回これを改めて、「蛇と光」両概念の交わる接点としての「稲光」を重く見て、古代日本人は日本書紀にある通り「雷光」を火神=雷神である「軻遇突智(かぐづち)」と呼び習わしていたこと、そしてこの「かぐづち」の語源は拙著で指摘した通り「かか(蛇)づ(突)ち(力)」の訛ったものであると容易に推察できるので、結論として
「かか(蛇)」という言葉は、仲介としての「かかづち(→後の軻遇突智)」という呼び名を介して、「かか」に光の意味が付与され、その約音としての「か」にも「光」の意味が付与されたのではないか、と推察します。
「か=光」については、拙著で例証を挙げている通り、「かがやく・かね(金)・かすむ・かなた・かそけし・かすむ・あかり・ひかり・かみ(上←光を見るのは上だから)」などが挙げられましょう。
(追伸)永井様の論文「天照大神とは誰か」の「2.卑弥呼の語源は何か」で拙著を紹介して下さりましたこと、衷心よりお礼申し上げます。
「カガミ」=「蛇」+「身」は、『蛇-日本の蛇信仰』(講談社学術文庫)の78-85頁に出てくるはずなのですが、後で調べてみます。
私が鏡に映った自己を見るということは、鏡の中の自己が私を見るということでもあるわけですから、「カカを見る」ということは「カカが見る」ということでもあります。だから、「カガミ」という言葉には、鏡像的反転を含意するだけの二義性があるということです。
「かか(蛇)づ(突)ち(力)」の「ち」についてですが、梅原さんが次のように言っています。
———————————————————————
火の神は、アイヌでも沖縄でもわずかの異聞を除けば、女神であった。では、日本の火の神カグツチの性は、女性か男性か-、私はカグツチは男神であると考える。その理由はカグツチの「チ」にある。
大蛇のことをオロチ、竜のような怪物のことをミヅチ(蛟)、またサチ(幸)、チチ(乳)、チ(血)など、霊なる力を「チ」という。男性セックスにもこの「チ」が付く。アイヌ語では、例えば、虹のことを「ラオチ」(raoci)、穴のことを「トンチ」(tonci)、という。虹も不思議な自然現象であるし、穴は神秘な場所である。カグツチの「チ」は男性セックスのチに通ずると私は思うのである。
———————————————————————
[梅原 猛:梅原猛著作集〈7〉日本冒険(上), p.60]
https://www.amazon.co.jp/dp/4096771074/?tag=n08-22
カグツチは、古事記では、火之夜藝速男神(ひのやぎはやをのかみ)と呼ばれ、男神扱いなのですが、他方で、陰部から闇山津見神(くらやまつみのかみ)を産むという記述からすれば、女神とも判断できます。
このように、古事記の叙述には混乱があるのですが、私は、「チ」は、本来、男性の力ではなくて女性の力だと思っています。梅原さんが指摘するように、火(アペ)の神を意味するアペフチ(apehuci)は、「フチ」が「お婆さん」という意味なので、女性だからです。
虹や穴も蛇や竜と関係があることから、アイヌでも、「チ」は、蛇神の霊力だったと考えられます。ところで、大空さんは、血の「チ」も、オロチやミヅチの「チ」と同様に、霊力を表す「チ」だと解釈しますか。
1.吉野著『蛇』(学術文庫刊)の84頁に有りました! <「カガミ」とは「蛇身」の意ではなかろうか>と。 しかしこれは、吉野さんが「かか=蛇」説を主張する例証として、古事記に登場する「羅摩(かがみ)」及び日本書紀に登場する「白?(かがみ)」という植物について、これらの植物が「蛇の身体の相似」であるから「かがみぐさ」と呼ばれるのだろうと推測しているクダリでした。つまり植物で「カガミ」という言葉が付く場合、その語源は「かが(蛇)み(身)」に由来するのではないか、という推察が吉野説ですね。
2.永井様が「鏡(かがみ)」の語源を「かか(蛇)み(見)」と解して、「蛇を見る/蛇が見る」という反転関係をも含むもの、と仰られたので、その永井説に私も賛同します。思うに、「鏡(かがみ)」の語源はこの永井説で決まりだと思います。あとは、「いつこれが通説になるか」、という期間の問題に過ぎないでしょう。
3.梅原さんは「カグツチを男神と考えその理由をカグツチのチに求める」、一方、永井様は「この<チ>を本来、女性の力を表す言葉だと解して、カグツチを女神と考える」 ということですが、私は、もっと直截単純に「見たまま」の説です。
拙著『原始日本語はこうして出来た』160~161頁で書いていますが、以下要約すると、
「稲光の閃光は見たまま<男根の一突きの相似>であり、加えて乾坤(陰陽)思想で言えば、電光に突かれた大地は<坤=陰>つまり男女で言えば女である。また、落雷に突かれた地点は<ほ(火)と(処)>となり、この<ほと>は女陰の名称でもある。更に、巨木に落雷して巨木が二つに裂ければ、その裂口は女陰の相似形ともなる。また、<いなづま>は古くは<稲夫>と表記されていたこと。また、男神の稲光と大地の女神の<ちぎり>により稲穂が実る、という考えがあること---以上の理由により---稲光は男神のはずである」 (但し、巨木に落雷の事例は今回新たに追加しました)
という主張です。
永井様は 「古事記では、火之夜藝速男神(ひのやぎはやをのかみ)と呼ばれ、男神扱いなのですが、他方で、陰部から闇山津見神(くらやまつみのかみ)を産むという記述からすれば、女神とも・・」 と書いておられますが、ここでの「陰部から」とは「ほと(火処)」からの意味と解し、闇山津見神とは、火で焼けて闇(・)のように真っ黒になった黒炭の山(・)が積(・)まれている「残骸」の出現を神格化したものと解することができるので、火が燃える活動の結果として「焦げた黒山を生み出すことになる」火神に対して、「だから女神だ」と言う必要はないと考えます。
ですから、火の種類にもよると思いますが、「火柱や稲光については、見たまま男根の相似形」なので、男神と解して宜しいかと思います。
4.「チ」について
拙著『原始日本語はこうして出来た』249頁で書いていますが、以下要約すると、
「古代は<つ(付)>一語で名詞や動詞であったと推測され、活用も語尾変化無しにいきなり、<ち>となったと推察可能である。つまり<付く>の名詞形として<付けたもの、付く物>を<ち>と呼んだと推察できる。その例証として、釣り針の古語は<鉤(ち)>だが、これは釣り針が釣り糸の先端に<付けた物>ゆえこう呼ばれたか、ここに魚が食い<付く物>だからこう呼ばれたものだろうと推察できるし、こう解すると、するすると他の言葉の謎も解けて来る。
<ち(霊)>は、古代のシャーマニズムの影響からして、霊力は生き物に<憑(つ)くもの、憑いたもの>と考えていたに違いないので、霊を<ち>と呼んだのだろう。
また、<さち(幸)>とは、古代、とらえた獲物を意味したが、その語源は<さ(箭)>と呼ばれる小型の槍で獲物を刺して<さ(箭)に付けた物>だから、と容易に理解できる。なお、これに幸の字を当てるのも、小槍に獲物を刺し付けた状態で、 <ゑ(餌)し⇒ゑ(吉)し⇒これ幸い> という連想は、誰でも容易に浮かぶので自然。」
また、拙著158頁に書いていますが、
古代、「つ(築)く」の名詞への活用は「あ段止め」で「つか(塚)」とする規則が有ったこと。この規則で行くと、「か(離)る」の名詞形は「から(離脱物)」と推察できる(大空説)。
こう考えると、「ちから(力)」とは「ち(霊)から(離脱物)」と解析でき、「たから(宝)」は「た(田)から(離脱物)」と解析でき(何故なら、古代、米こそ宝だから)、「はらから(同胞)」は「はら(腹)から(離脱物)」と解析でき、「ちから(税)」は「うぢ(氏)から(離脱物)」と解析できる、と主張しています。
また、拙著18頁に書いていますが、
お尋ねの「ち(血)」についても、「つ(付)」の名詞形と解しています。理由は、血は「付くもの」であり、何かに「付いてしまうもの」だからです。従って、「ち」は語源からすると、本来、男性・女性とは全く関係ない、ニュートラルな概念であったと推察します。
なお、『字訓』では「ち(血)」の古形は「つ」だとあります。まさに「付(つ)」の意味でしょう。
更に、大祓の祝詞にある「ちぎ(千木)たかしりて」については拙著176頁で解説している通り、「ちぎ」は「契り木」の縮約形と解析して始めて意味が通るものであり、この「ち」は「交叉させる」という意味で「付けた木」だから「ちぎ」と呼ばれます。これも「ち」が「つ(付)」の活用形である有力な論拠になります。
5.「チチ」について
なぜ、「ちぶさ(乳房)」と言うのか?
私は上記の推察を貫徹して吉だと思います。即ち、「ちぶさ」の「ち」は「付いたもの」という意味で、「(胸に)付いた房(ふさ)」の意味だと解析して自然な解釈だと思います。よって、この派生で、「乳汁」も「ち」と呼ばれるようになったものと解します。また、乳房を「ちち」と反復するのは「乳房が二つ」即ち「付いているものが二つ」という意味での反復とも解し得ます。
では、なぜ「ちち(父)」と言うのか?
私はこれも上記の推察の延長線上で無理なく解釈できると思います。即ち、「付(つ)」の名詞形である「ち」の派生語としての「霊(ち)」、ここから「ちはふ(霊這ふ)」という古語が生まれました。「護ふ」という漢字を当てます。意味は <神霊の力によって護り助けること> と『字訓』にあります。私流に言えば、「守護を行き渡らせる意味」でしょう。
そして、まさに、この「ちはふ」の派生語こそが「父(ちち)」だと私は解析します。
というのも、「ちち(父)」は古く「ち」一語であり、元々は「年長者・尊貴の人・族長」を意味する言葉・・と字訓にあります。であるならば、まさしく、「年長者・尊貴の人・族長」などこそ、小さき者たちを「ちは(護)ふ」者であるがゆえに「ち(父)」と呼ばれた、と容易に推測できるからです。
血の解説ありがとうございました。アイヌ語では、血はケムと言うのですが、大和言葉との関係がはっきりしないので、聞いてみました。
ところで、『原始日本語はこうして出来た』366頁では、《付+居=ち》説を使わずに、千(ち)を散るの派生語として説明していますが、散るの「チ」は、分離であって、付着とは逆です。チには甲乙の違いもないわけですが、分離のチと付着のチをどう関連付けますか。
もう一つ、『原始日本語はこうして出来た』176頁では、契(ちぎ)る=交わる》という説明があるのですが、これは、《ちぎる=ち+切る》だから、《交差=付着してから離れる》と解釈するということですか。
「ち」が(大空説のように)付着概念としての「つ(付)」の活用形だとするならば、分離拡散を意味する「散る」という概念に、どうして「ち」が使われているのか? これは矛盾ではないか? というご質問ですね。
「ち(散)る」の語源で自然に思い浮かぶのは、「散る物の代表は木の葉」ということです。これは古代人も同じだったでしょう。つまり、「枝々から落下した葉が地表に落ちた様子」こそが「ちる」概念の原形であり中核でしょう。従って、「つち(土)」の約音としての「ち(土・地)」 プラス「ゐ(居)る」で 「ち(土・地)+(居)る = ち(散)る」と造語されたであろう事が素直に連想されます(大空説)。
但し、括弧書きで「地」と入れましたが、「地(チ)」は中国音なので、この影響を受けたかどうかは、ここでは保留にして、脇に置いておくべきだと思います。
擬音・擬声語から原始の日本語が創案・形成されていたと想定すると、その成立年代は極めて太古と考えられるので、(幼児的)擬音語から初期的に派生した基本単語も極めて古い成立年代と考えられます。そのため、それらの太古日本語の単語音韻が中国語の形成に影響を与えて、中国語の基本単語に取り込まれて「日中同音」になったというケースも、「無きにしも非ず(可能性はゼロではない)」として、一応考慮に入れておくべきだと思っております。
とまれ、「日中同音」の事は脇に置いて、ここではあくまで、「散る」という概念は、その現象の代表物である木の葉に着目して、「つち(土)」の「ち」と、そこに「ゐる」の合成語としての「ち(散)る」だと解します(大空説)。
「散る」の名詞への活用形が「ちり(塵)」であり(通説)、塵(ちり)は無数で数えられないので、数えられないほどの数量を表す単語として、「ちり」から「ち(千・無数)」が派生したと考えるのは自然な連想でしょう。
では、付着の「ち」を 拡散の「ち(散)る」へと用法拡大させた仲介者(張本人)としての「つち(土)」の語源は何でしょうか?
『字訓』には、<「ち」は「霊」の意。「つ」はあるいは「處(と)」の母音交替形であろう> とあります。更には <「つち」は土一般をさすのではなく、その地中にひそむ霊的なものをよぶ名であった。すなわち地霊をいう語であったと思われる> とあります。
白川博士が断言しておられるように、「つち」の「ち」は「霊」の意味でOKでしょう。しかし、「つ」については「處(と)」の母音交替形と解するのは無理があると思います。
私は、「つ(積)ち(霊)」 と解します。(大空説)
何故なら、古代の土葬は盛土をするので、塚(つか)を作り、土を積むからです。また、陵墓の「陵」も盛り上がりを示す語です。
次のご質問--「契(ちぎ)る」についても、付着の「ち」と、切断の「き(切)る」 両者、全く相反する単語が並んでいるので、両者の関連は? ということですが・・・
まず、「ちぎ(契)る」と「ちか(誓・盟)う」は類義語ですから、この「ち」は同じ「ち」だと考えます。
『字訓』の「ちぎる」には「契」の字義として <人身に契刻して約することをいうもの> とあります。また「血」の字義としては <・・盟なども、その形義からしてみな血に従う字である> とあります。このように、(武士たちの血判状ではないですが)古代では日中共通して、「血を以て約する行為」が原初的に存在したと推察されます。
『字訓』には、吉田金彦説として「ちかう⇒ち(霊)か(交)ふ」説が挙げられていますが、 私は、「ち(血)+かしる・かしふ ⇒(略して)ちかふ」 となったと見ます(大空説)。
一番最初の頃は、「ちかしる」とか「ちかしふ」と言っていたが長いので三音に略された可能性もあります。或いは、造語の天才が一気に略した形で創案したか・・・。いずれにせよ、「血」及び、「宣誓祈祷すること」を表す「かしる・かしふ」、これら2概念の合成語と見るのが大空説です。
『字訓』では「かし(呪)る」とは、<神に祈って人を呪うこと> とありますが、この名詞形である「かしり」には「神咒」という漢字を当てることでもわかる通り、原義は「神の言葉を口走ること」であったろうと解します。私は拙著『原始日本語はこうして出来た』 435頁で
<「かし(呪・神咒)る」の語源は「かみ(神)+し(占)る」の縮約形である。つまり、神が或る者を占拠して神憑りして、その状態で口走ることが「かしる」の原義である。よって、本当の神憑りの場合の「かしり」は「神の言葉(神咒)」となる。>
と書きました。
また、それに続けて、神咒を宣べて祈ることも「かしり・す」と言うようになり、派生用法として、「かしる」で「祈る」意味にもなった(であろう)、と解説しました。
以上から、「ちか(盟・誓)ふ」の語源は「ち(血)+か(神咒)ふ」で、「血を以て、神明にかけて盟誓する言葉を宣べ交わすのが原義であろう」 と推察します(大空説)。
そして、「ちぎる」の語源は、「ち(血)+き(着)る」と見ます(大空説)。
『字訓』の「き(着)る」の項には、<着と著(・・・)もとは同じ字である> として、著の「者」の部分の字義について これは呪符を土で埋め隠した形であり <呪能をかくし儲えておく意である。すなわち、呪能を付著することをいう> とあり、<着も呪能をそこに定着する意味のある字>とあります。
日本古代のシャーマニズムからしても、「(命や霊力の象徴・代用としての)血を以て、その呪能を(付着・定着させて)着るという思想」があったものと容易に推察できるので、この習俗から、「ちぎる」という単語が創案されたと考えるのは自然なことだと思います。
以上から、「ちぎる」の「きる」は切断を意味する「切る」ではなく、付着定着を意味する「着る」であり、「ち」と「きる」共に、類義を連ねての合成語と見ることになります。
なるほど、「ち」を霊と考えるとわかりやすいですね。ところで、「散る」という言葉は、「戦いで散る」というように、しばしば死ぬことを意味します。実際、花や葉は散ると死にます。そして、生命が死ぬと、魂はあの世へと連れて行かれます。だから、《散る=ち+ゐる》は《霊を率る》と解釈できるかもしれません。
「ちぎる」は「血着る」ですか。ブードゥー教とかでは、実際にそういうセレモニーがありますね。羊や鶏などの犠牲獣を「千切る」ことで「血着り」、神と「契り」を結ぶ。そういえば、セックスのことを「契り」と言うこともありますが、あれも一種の「血着り」ですね。プリミティブな宗教でのユニオ・ミスティカは、エロティシィズムと紙一重だから、男女の契りと神との契りも同じようなものと考えることができます。
カ(良い行い)とガ(悪い行い)をみるから、カガミ。
とてもシンプル。
あたし本で見たコトあるー。銅鏡は、卑弥呼が使いを中国へ送って、銅鏡100枚を親魏倭王からもらったという話。
卑弥呼の墓発掘プロジェクトを計画しております。
興味があればのぞいてみて下さい。
http://www.max.hi-ho.ne.jp/m-kat/keizibann/Project-H.html
三角縁神獣鏡についてのご意見はもっともだと同意できます。三角派の研究者の方々も最近は少しずつ拠り所の軌道修正をしておりますが、福永先生は言い出したてまえ研究の自己否定に結びつくので固執されているようにも見えますが更に論争が白熱することを願っております。さて、論争にはずみがつきそうです。中古にもプレミアムがつき、なかなか入手困難な書籍の一つだったのですが、このたびミネルヴァ書房より待望の復刻が、「古田武彦・古代史コレクション」と銘打ってスタートしたようです。「初期三部作」と呼ばれている、『「邪馬台国」はなかった』『失われた九州王朝』『盗まれた神話』の三冊がまず復刻されました。次いで『邪馬壹国の論理』『ここに古代王朝ありき』『倭人伝を徹底して読む』の復刻予定とのこと。 特に初期三部作は古田史学のデビュー作と言うだけでなく、その学問の方法を徹底して重視した論証スタイルに古代史学界が受けたインパクトもかなりの強烈なものでした。論争をもっと盛り上げましょう。