フェミニズムとは何か
人々は、フェミニズムをジェンダー・フリーな平等主義と誤解することで、フェミニズムが持っている欺瞞的性格を覆い隠してきた。フェミニズムと平等主義を区別しながら、なぜフェミニズムが女性を解放しないのかを明らかにしよう。

1. フェミニズムは平等主義ではない
アメリカでは、1973年に徴兵制が廃止されて志願兵制になってから、多くの女性兵士が誕生したが、女性が戦闘行為にまで参加することがよいかどうかをめぐってフェミニストたちの間で意見が分かれた。男女の完全な平等を実現するためには、女性兵士も、男性兵士と同様に銃を手に前線で戦うべきだと賛成する女性もいれば、戦争は男性原理に基づくもので、女性自ら戦争に荷担することは、フェミニズムの敗北だと言って反対する女性もいた。
こうした論争は、フェミニズムと呼ばれている思想に、狭義のフェミニズムと平等主義という対立する二つの立場があることを示している。平等主義は、「もし男性が戦場で戦うことが許されるのなら、女性にも同じことが許されるべきである」とする形式的な理念であって、戦争を許容するかどうかという実質的な価値判断に関してはニュートラルである。
しばしばフェミニズムとは、男女差別を撤廃し、ジェンダーフリーな社会を作ろうとする平等主義のことだと思われているが、フェミニズムは直訳すると「女性主義」であり、名前自体が<男女平等=ジェンダーフリー>でない。たんなる男女の平等を目指す立場は、フェミニズムではなくて、エガリタリアニズム(egalitarianism 平等主義)と呼ばれるべきである。
2. ラディカル・フェミニズムの誕生
1960年代後半から1970年代前半までの女性解放運動は、女性が男性と同じになることを目指していた。しかし70年代後半から80年代にかけて、女性解放運動家たちは、そうした要求は、女性的価値に対する男性的価値の優位を前提にしており、ヨーロッパ系言語に見られる《男=人間》の観念に追従するものだと考えるようになった。こうして、「男らしさ」と「女らしさ」の差異を解消するのではなくて、両者の異質性を強調し、両価値の平等を、さらには後者の優位を説くラディカル・フェミニズムが登場する。女性解放運動の目的が、女性の権利から女性のアイデンティティの確立へと変質していったのである。
その典型が、70年代に盛んになった環境保護運動と連動したエコフェミニズムである。エコフェミニストは、近代資本主義社会による資源の搾取と自然破壊を男性の女性に対するレイプに喩え、母性原理による地球の保護を訴える。彼女たちは、母性対父性の二元論を優しさ対勇ましさ、自然対文明、協調対競争、平和対戦争、感情対理性などの二元論へと重ね、男たちが「男らしい」と賞賛する力の論理を批判する。
「男らしさ」に対する「女らしさ」の優位を説くエコフェミニストは、男尊女卑のセクシスト(sexist 性差別主義者)のたんなる裏返しではない。伝統的な男尊女卑のセクシストは、女性が男らしくなることに嫌悪感を示すが、エコフェミニストは、男性が女性的になることに好感を示す。セクシズムがたんなるエゴイズムであるのに対して、フェミニズムには思想がある。
ラディカル・フェミニズムのもう一つの潮流として、マルクス主義的フェミニズムがある。マルクス主義的フェミニストは、男性/女性の関係をブルジョワ/プロレタリアンや先進国/発展途上国といった搾取/被搾取の関係で捉えているため、男性であってもプロレタリアンや第三世界の人々に連帯意識を感じている。
セクシストとフェミニストの違いを説明するためには、セックスとジェンダーが異なることを説明しなければならない。セックスが生物学的な性であるのに対して、ジェンダーは社会的・文化的な性である。生物学的な性が男性でも、ジェンダーは女性でありうる。フェミニストは、ジェンダー・コンシャスではあるが、必ずしもセックス・コンシャスではないと言うことができる。
しかしそうは言っても、ジェンダーはセックスと無関係というわけにはいかない。マーガレット・サッチャーのような、競争原理を肯定する女性が増えてくれば、もはやジェンダーのレヴェルでも、弱者切り捨てや競争原理が男の論理だとは言えなくなる。
3. フェミニズムの落とし穴
ジェンダー・コンシャス・フェミニズムの最大の問題は、女性を女らしさに閉じ込め、選択の自由を奪うところにある。私たちは、生まれる前に、自分の意志で男性になるか女性になるかを決めたわけではない。また性転換技術が不十分な現時点では、生後にも性を選択する自由がない。生物学的な性とジェンダーレヴェルでの性自認が異なるトランスジェンダーにとって、性差極大主義者(maximizer)であるフェミニストあるいはマスキュリニストは、迷惑な存在である。性同一性障害者が、乳房やペニスを切り落とそうとするのは、がん患者ががん細胞を切り落とそうとする場合とは異なって、社会や文化がジェンダー・コンシャスであるからである。
フェミニズムと同じ弊害をオリエンタリズムが抱えている。近年欧米の哲学者たちは、従来の西洋=ロゴス中心主義を反省し、東洋思想に関心を持ち始めている。しかし東洋思想に関心のない日本の哲学者である私は、こうした傾向を嬉しくは思わない。カントを研究している日本の哲学史研究者がドイツに行って、カントをテーマにした講演をしようとしたが、誰も聞いてくれないので、予定を変更して禅をテーマにしたところ、ドイツ人は珍しがって聞きに来てくれたという話がある。女性の社会学者も、フェミニストと自称した方が、マスコミで取り上げてもらえる確率が高くなる。しかし「日本人」も「女性」も、本人が自由意志に基づいて選んだ属性ではない。種の個性が、個人の個性と異なる時、種の個性が賞賛されても、本人は疎外感を感じるだけである。
話をエコフェミニズムに戻そう。先進国の豊かな生活にあこがれているアフリカの人にとって、アフリカの豊かな自然を賛美するヨーロッパの「進歩的知識人」の言説は偽善に満ちたものに聞こえる。「アフリカの自然がそんなに良いのなら、なぜあなたたちは、アフリカに定住せずに、逆にアフリカ人労働者のヨーロッパへの移住を拒否するのか」とそのアフリカ人は問い返すだろう。エコフェミニズムは、古き良き《女らしさ》や《処女的な自然》を賛美することによって、当事者に抑圧感を持たせることなく、女性原理を保存しようとする巧妙な手口なのである。
4. フェミニズムは女性を解放しない
かつて人種差別にフラストレーションを感じた黒人たちは、自分たちを心の温かい太陽の人、白人を心の冷たい氷の人と呼んで、価値観を逆転させようとした。こうした試みは、人種差別という最も是正しなければいけないところを是正せず、白人と黒人のどちらが上かというどうでもよいところだけを逆転させるきわめて皮相な抵抗運動である。
同様に、ラディカル・フェミニズムも少しもラディカルではない。ラディカルであるためには、「男らしさと女らしさのどちらが優れているか」という問題意識そのものを止揚しなければいけない。
90年代以降、女性の社会進出に反比例するように、フェミニズムは衰退していった。このことは、21世紀が「女性の時代」などではなくて「個人の時代」であることを示している。






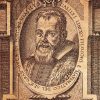











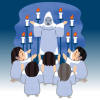



ディスカッション
コメント一覧
フェミニズムとは何か?についてですが、私は女性原理というものに大変疑問を持っています。いちおう男性が”女性らしさ”を女性に押し付けてきたということになっていると思っていたのですが、エコフェミニズムはそれを武器にしていたのですね。しかし、それが本当に生得的かどうかは別として事実わたしは「男性」「女性」で分かれた社会にいるので個性の時代といってもそこと切り離された個性なんてあり得ないと思います。もちろん考えることは大事ですが。
白人と黒人どちらが上かというのは本当にくだらないと思いますが、あの時代にあってはそう言うことが意味を持っていたのではないでしょうか。(つまりそう言うことで周りをというより自己をかえるため)事実いまここにある差別に対抗するために。なぜ差別があるのかということよりもっと直接的に、切羽詰まった問題だったのでは、と思います。21世紀が女性の時代だろうとなかろうといままで言論をかたちづくってきたのは男性のがわだったのでそれがかわってきたらいいなあと思いました。個人の時代万歳です(でも厳密な個人なんてないとも思うなあ)。
かつて黒人の女性が、黒い皮膚に劣等感を感じて、白くお化粧をしていた時代がありました。これと比べたら、黒人女性が”Black is beautiful.”という新しい価値観に目覚め、白人には真似のできない、黒さを生かしたお化粧をするようになることの方が、ずっと健全です。でも「黒人」にしても「女性」にしても、この属性を持った人は他にいくらでもいるわけですから、所詮個人の個性にはなりません。個人が集団の個性と自己同一すると、他の集団との対比において個性を持ちえても、結局集団内部で埋没してしまうことになります。工業社会の時代ではそうした集団主義でよかったのですが、個人がボーダレスなサイバースペースを漂流できる情報社会の時代では、自己をオンリーワンにしなければならなくなります。
その際、生得的な属性をベースに、自分の個性を磨き上げる人もいるでしょう。それで満足できる人は、幸運です。しかし中には、生得的な属性にどうしても自己同一できない人もいます。例えば私は、「なぜ日本に生まれたのだろう」と思うほど、日本社会の慣行に違和感を感じています。もちろんそれなら、外国に移住するという手段がありますが、性の場合には、こうした選択の自由がほとんどありません。私が問題にしたかったのはそこだったのです。
なお「厳密な個人なんてない」というご指摘は、その通りだと思います。個性が他者との反照関係において規定される以上、「個人の時代」が、「独我論的孤立主義の時代」を意味しないことは、当然です。私が、「個人の時代」でもって念頭においているのは、情報革命がもたらした《ピラミッド型社会からネットワーク型社会へ》という社会構造の変化のことです。
私は現在某大学院でジェンダー論を専攻している者です。毎回興味深く読ませていただいていたのですが、今回の「フェミニズム」の記述に関して、あまりにも永井様の誤解が多く見受けられるので、その旨お伝えいたしたく、メールさせていただきました。
日本では戦前の与謝野晶子、平塚らいてう、山川菊栄などの論争を経て、戦後にウーマンリブと呼ばれる女性の権利獲得運動が起こっているのですが、そのような、女性に男性並の権利を認めろという運動、法的平等を訴える運動は、一般に「リベラル・フェミニズム」と呼ばれます。そして、平等の根拠として持ち出されるのが、一方で「性差の無」、他方で「女性原理」の強調であったわけです。性差極大派、極小派の対立それ自体は、ラディカル・フェミニズムという名称とは関係ありません。
ラディカル・フェミニズムとは、法的平等だけでは決して男女平等は達成され得ない、という立場を指します。性差別一元論とも言われますが、男/女という性別の作られ方そのものの中に差別性を見て取る立場です。初期のラディカル・フェミニズムはそれを生物学的性差のなかに見たため、生殖技術による性差の解消を主張するような極端な極小派も現れましたが、genderを社会的な性差と見る立場の登場によって視点は社会による性別の編成に移っていきました。そして、どちらかといえばミニマリズムよりの考え方から、「性差はあるのかないのか」という問いそのものの中に差別性を見いだしていったのがラディカル・フェミニズムなのです。
従って、マキシマリズムの立場はどのような意味であってもラディカル・フェミニズムではありません。従ってエコロジカルフェミニズムもマルクス主義フェミニズムも、ラディカル・フェミニズムではありません。エコフェミは女性原理を強調する古きリベラル・フェミニズムの残滓でしょうし、マルフェミは性差別を階級差別の下位に置く点と性別の成り立ちそのものに焦点を当てない点でラディカル・フェミニズムではありません。
察するに永井様は現在のフェミニズム・ジェンダー論の水準をほとんど御存知ないままに文章を書いていらっしゃるようですが、全てのフェミニズムを極小派から極大派への以降の歴史として描き、あるいは極大派と極小派に二分し、両者を批判するというやり方は、藁人形たたき以外の何でありましょうか。永井様が書いていらっしゃるような「男らしさと女らしさのどちらが優れているか」という問題意識そのものを止揚する、という作業、飽き飽きするような二元論に反駁する作業を、もう随分長くし続けてきたのがラディカル・フェミニズムなのです。それは、エコフェミが消え、マルフェミが消えた現在、ジェンダー論を代表する立場となっているとさえ言えます。性別と身体、sexとgender、sexualityなどについても実に緻密な研究が為されています。
《90年代以降、女性の社会進出に反比例するように、フェミニズムは衰退していった。このことは、21世紀が「女性の時代」などではなくて「個人の時代」であることを示している》のような口当たりのよい言葉の中にこそ、性差別を隠蔽してしまう何かがあるのです。現在多くの男達は、女性も働くべきだというし、家事は分担すべきだというでしょう。それでもなお、統計をとってみれば共働き夫婦でさえ女性が男性の十数倍もの時間、家事育児に拘束されているのはなぜなのか、お考えになってみてください。働かなければ個人として自立してないと言われ、働けば家庭をほったらかしてなんて女だと言われる。そんなジレンマの不合理について考えてみてください。性別というものについて、フェミニズム以上に深く考えてきたラディカルな立場は存在しません。ちなみに私は男なのすけれど(^^;)
TKさんのご批判は、言葉遣いに関する批判と本質的な批判に分けることができると思います。
まず言葉遣いについて。現代のフェミニストたちがかつての「女性に男性並の権利を認めろという運動、法的平等を訴える運動」のことを「リベラル・フェミニズム」と呼んでいることぐらいはもちろん知っていますが、ジェンダーフリーな平等主義をジェンダー・コンシャスな「フェミニズム」という言葉で名指すことは不適切だと私は考えています。そして私は、「一方で「性差の無」、他方で「女性原理」の強調」を「平等の根拠として持ち出」すことが、本質的に矛盾していることを示したかったからこそ、平等主義とエコフェミニズムを「リベラル・フェミニズム」のような同じカテゴリーでくくりたくなかったのです。
私が察するところ、TKさんは「ラディカル・フェミニズム」とは「女性を根本的に解放してくれる思想」だと考えておられるようですね。もし「ラディカル・フェミニズム」という言葉に、そうした思い入れがあるとするならば、それをマルフェミやエコフェミに矮小化することに抵抗感を感じることは、理解できます。しかし言葉の定義には本来真とか偽とかはないわけで、言葉遣いについて論争するのは止めましょう。
TKさんの本質的批判、TKさんが本当に言いたかったことは、「たんなる平等主義では、女性は解放されない」ということでしょう。「女性を解放する」と言ってもいろいろな意味があるでしょうが、ここではTKさんが関心をもっておられる家事労働と女性の社会進出の問題を取り扱ってみたいと思います。
TKさんは、たぶん次のような推論をしているのだと思います。
大前提男女平等は常に望ましい小前提形式的平等主義は真の男女平等をもたらさなかった結論形式的平等主義は女性を解放しない
この推論は、大前提に問題があります。雇用における男女平等は、超歴史的理想ではありません。「男は外で働き、女は家で家事と育児に従事する」という性役割分担は、近代工業社会では有効でした。
もちろん専業主婦自体も歴史的産物です。産業が労働集約的であった前近代的社会では、職住接近ゆえに、人口の多数を占める農民や商人の妻は、家事や育児をするだけでなく、夫の仕事を手伝うことができました。しかし近代化=資本主義化による産業の資本集約化に伴い、職住遠隔が進み、妻には家事と育児の仕事だけが残されました。
1970年代に入ると、産業の資本集約化は限界に達し、先進国は、情報社会に向けての産業の知識集約化を迫られます。そして、情報革命は少子化をもたらします。家事労働も、家電製品の登場で大幅に減量されます。つまり時代の進展とともに女性の仕事は減りつづけたと言うことができます。一般に女性は男性と比べて肉体的な力が劣りますが、頭脳労働においては平等であり、産業の知識集約化は、職場における男女平等を大きく促進することになります。
70年代に女性解放運動が盛んになりましたが、これは70年代に始まった情報革命の結果です。フェミニストの中には、「私たちがフェミニズムの運動をした結果、女性の地位が向上した」と考えている人が多いですが、フェミニズム思想は、男女雇用機会均等法のような法律と同様に、女性が社会進出できるようになったことの結果であって、原因ではありません。原因は、情報革命という経済構造の変動です。
但し、工業革命に長い時間がかかったように、情報革命にも長い時間がかかることでしょう。女性の社会進出が進むにもかかわらず、実質的な男女平等が進まないのは、工業社会から情報社会への移行がまだ不十分だからです。
現在会社にデスクを持たないモバイル社員やSOHOが増えていますが、労働者の総自営業化、組織のネットワーク化に伴い、新たな職住接近が可能になりつつあります。フェミニストや反フェミニストたちは、「女性の社会進出=女性が家の外に出ること」を自明の前提としつつ、ゼロ歳児を24時間営業の保育所に預けることは是か非かという論争をやっていますが、工業社会的な雇用形態を前提に議論したら、女性側に不利になってしまいます。男女ともに自宅で働けるような情報社会的なワークスタイルの確立が、仕事と子育ての両立に必要です。
電車で女性専用車両がありますが、新聞の投書に「男性専用車両も作っては?」という意見があります。社会的にはまだ「女性が不利」と言えます。反対に女性だけが受けられる恩恵という物も一部(例・映画のレディース割引)で存在します。
ただし、時代劇を見るとわかるのですが、身分に関係なく女性が男性をひっぱたいたり、たたいたりする場面がほとんどありません(例外・長屋の夫婦喧嘩)。21世紀の日本は男女平等とはまだ程遠い社会なのでしょうか?でも、今の流行語で「草食系男子」、「肉食系女子」がありますし、「平成の20年で女性がかなり時代を担える様(例・2000年以降の女性知事の誕生)になっている」という意見もありますが。実際の所はどうなんでしょうか?先生のご意見をお願いします。
女性専用車両には、男性の身体障害者も入ることができるそうです。つまり、女性専用車両は、痴漢防止のための性別隔離室というよりも、弱者を保護するための特権車両としての性格が強いということです。これは、一種のアファーマティブアクションですが、アファーマティブアクションは差別利権問題を生み出すので望ましくありません。痴漢防止のための性別隔離室ということであれば、女性専用車両だけでなく、男性専用車両も作るべきでしょう。
まず、フェミニズムも含めて、女性優位の社会体制を奪取するための工作活動の教典に他ならない。
そして、セクシスト性に関しては、全くの考察エラーがある。女性の男性化は、強化されるので忌避されるが、男性の女性化は弱体化に他ならず、女性のアルファーメスがその他の奴隷階級の女たちを支配するように、弱体化した男も支配できるという目的に合致するので、アルファーオスと同様の反応をする必要がないからである。
男性専用車両の必然性とは、痴漢えん罪工作の餌食にならないための身を守るための切実な要望にほかならない。要するに嗜虐的、金銭的要求をもつ一部の女およびそれを利用する勢力から社会的レイプを防止するための方策であるからだ。アルファーオスでもなければ、女性に疑われるだけで堪え難い苦痛であるからだ。(アルファータイプは相手の感情を配慮しない。オスもメスも)
教育とは宣伝、洗脳と同義ですから、教科書的論考は、欺瞞性の高い工作活動のロンダリングの結晶であり、懐疑の精神なくして、取捨選択、真意を読み取ることはできないのでしょう。
フェミニズムが弱者の地位向上でない証拠は、父子家庭の援助措置を彼女たちはいいださないからです。田島陽子的、偽装大声人間により鬱憤をはらすという効果しかなく、田島陽子的、強姦体質(実は、彼女たちが否定しているアルファーオスへの対抗措置として批判してきた手法を彼女たちは利権獲得のテクノロジーとしてアルファーメスが取り入れているというパラドクスがここにある。)が、結局、異性差別の手口として、行使されているのです。
強姦被害者の女性の一部に、強姦体質を取り込み精神的強姦体質(一部で肉体的事例もある)を発揮しているのである。その一部の表現が、児童虐待に発露している。
洋式トイレで座って排尿させるという行為は、ソフト虐待の事例であるが、掃除が楽との建前で、少年の弱体化を意図していることはアルファーメスの思惑通りである。(奴隷階級の女性にまで、明確な意図があるわけではないし、本来の意図を知れば、それを積極的にも望まない人々もいる。)
もちろん、オスあるいは男性性の能力と意識を保持するために立って排尿することが必要だからである。野生動物でなるべく高い位置に排尿によるマーキングを行うのは、オスとしての矜持と機能を維持するための手段だからである。(去勢と同じ効果をアルファーメスは意図している。)
結局、フェミニストもアンチフェミニストもアルファーメスとアルファーオスとの主導権争いであり、善良な女性も男性もこういう勢力に両側から食い物にされたり、盾代わりされている。
ようするに、男か女かが問題ではなく、「横暴(=アルファー)」か否かが問題なのであろう。
もちろん「強姦性」も「横暴」と同義である。物理的だろうと、社会的にも精神的にもである。
そして他者を利用しての工作力は、女性や良い意味で女性化(強化)した官僚の十八番である。
ここにも、本来の問題に寄生する、マトリョーシカ人形やマルコビッチの穴構造が存在するのであろう。
永井先生は男性向けの萌えアニメを「性的」だと敵視している日本のフェミニストについてどう思われていますか。そういった人達は「ツイッターレディース」「まなざし村」「お気持ち自警団」と揶揄されます。
私は、そういった日本のフェミニストは男社会の存続を願う保守主義者だと思います。男社会と言えば男尊女卑を連想する通り、女性は男社会の被害者だと考えられがちです。しかし、男社会では女性は男性に庇護されます。日本のフェミニストはそういった恩恵を守ろうとしているように見えます。
例えば、日本における男女間の経済格差は世界で最も最悪だと言われています。しかし、日本社会では、女性は結婚すると、夫の給料を「家計の管理」という大義名分で自由に使うことができます。これは、日本における男女の経済格差を語る上で必ず無視される不都合な事実です。
実際、夫はお小遣いとして少量の金額しか使えない一方で、高級ブランド品を身に着けて楽しむ妻がたくさんいます。また、夫が趣味を持つことを許さず、夫のコレクションを処分する妻もいます。それだけ、夫の給料は自分のものだと考える妻が多いのでしょう。
こういった、夫が自分の給料を家庭(=自分の妻)へ上納する構造は、夫から妻への愛で成り立っているのが世間の常識です。夫がキャバクラへ行ったり、ポルノ雑誌を読んだりすることを許さないのは自分の既得権益を守るためだと言えます。
では、アニメオタクと一般的な日本人男性はどこが違うのでしょう。世間のイメージでは、アニメオタクは女性と結婚しようとしないし、お金を自分のためにしか使おうとしません。それが、女性を尊重しない最低男に映るのでしょう。
フェミニストに言わせてみれば、役所が萌えキャラを使って地域おこしを行うことや、NHKの番組にVTuberのキズナアイが出演することは、世間が女性を尊重しない最低男を許すようになることと同じことなのでしょう。アニメオタクが増えると、女性が玉の輿に乗ることが困難になります。だから、アニメオタクの排斥はフェミニストにとって最も重要な課題と言えるでしょう。
そもそも、日本のフェミニズムはどういったものでしょう。永井先生は、日本と欧米における男性の女性観の違いについて、次のように述べました。
フェミニストはこういった女性観が女性の抑圧につながると考えているのでしょう。ペット扱いから脱却して男性から自立するのが欧米のフェミニズムで、良妻賢母から脱却して自分のことを一途に守ってくれる強い男を求めるのが日本のフェミニズムと言えます。
そういった日本のフェミニズムは、上野千鶴子やアンドレア・ドウォーキンが掲げるマルクス主義的フェミニズムと親和性が高いです。マルクス主義的フェミニズムでは、男性は強者、女性は弱者と捉えています。フェミニストは、男女間の結果の平等を実現するために、加害者が被害者に慰謝料を払うように、男性は女性に補償しなければならないと啓蒙します。
先述した通り、日本のフェミニストは萌えキャラやポルノを女性の抑圧につながると敵視しています。男性のポルノ消費が許されるようになると、男社会にあった結婚すれば男性に庇護してもらえるという既得権益を失うリスクが高まるだけではなく、マルクス主義的フェミニズムが嫌う女性間の自由競争が起こることを懸念しているのでしょう。
自由競争に晒されていない産業は国や市町村の税金で保護されます。フェミニストは、そういう構造と同様に、自由競争に晒されている男性たちが、自由競争に晒させていない女性を保護することを訴えているのでしょう。結局、ラディカルフェミニストやマルクス主義的フェミニズムの訴えは、男性が女性を保護する男社会に帰結してしまいます。
ひょっとしたら、フェミニストは女性がお姫様扱い、もっと的確に言えば、男性に自分の欲求を一方的に満たしてくれることを、「女性の開放」と考えているかもしれません。つまり、女性が自立しなければならない状態を「女性の抑圧」と呼ぶのでしょう。
それにしても、フェミニストが「女性の解放」を謳っておきながら、結果的に女性が自立できない弱者で居続けようとしているのは皮肉な話です。
例えば、モデルの藤田ニコルがハロウィンの痴漢の被害者になりたくないのなら自衛するように啓蒙したところ、フェミニストと見られる女性たちから非難を受けました。
また、日本のフェミニストは緊急避妊薬の市販化に反対しています。避妊薬賛成派は避妊は女性の権利だと主張しますが、反対は男性が意識を変えよと主張します。
そして、日本のフェミニストは女性が護身術を身に着けることにも否定的です。女性のための護身術を広めているNPO法人・日本対性暴力研究所(日対研)はフェミニストから誹謗中傷を受けて民事訴訟を起こしました。(最終的に、日対研は解散しました。)女性が護身術を身に着けて男性を返り討ちにすることができるようになれば、男性は暴行目的で女性に近づかなくなるはずです。なのに、女性が護身術を身に着けることに対して否定的なのは不思議な話です。
日本のフェミニストは、女性が自衛手段を持つことで「女性は弱者」という常識が崩れて、男性が女性を庇護してくれなくなることを懸念しているのでしょう。フェミニストにとって、女性が弱者でいることは特権の源泉なのです。
フェミニズムはよく男性嫌悪(ミサンドリー)と結び付けられますが、実態は男性依存なのでしょう。他人が自分の思い通りに動かないと癇癪を起こして攻撃することは、ありふれた光景です。日本のフェミニストがTwitterで日本人男性を中傷することは、無能な上司が部下に罵声を浴びせることとよく似ています。
「日本のフェミニストは男社会の存続を願っている」と言えば、本人は顔を真っ赤にして激怒するでしょう。けれども、日本のフェミニストは、女性の社会進出を女性に特権を与えることで実現しようとします。特権階級は特権を持たない人が支えるので、こういう解決方法は男性が女性を庇護する男社会の構造と変わりません。
もしも女性の自立を促し、ほんとの意味で男女平等を目指すなら、配偶者控除/配偶者特別控除、扶養控除、第3号被保険者といった専業主婦を優遇する制度を廃止するべきですが、歴代政権は、表向き女性の自立や男女平等を口にしながら、こうした優遇制度を廃止しませんでした。専業主婦の反対が強いからです。石原里紗が『くたばれ!専業主婦』を出版した時も、専業主婦からのバッシングに遭いました。よく言われるように「女の敵は女」です。「専業主婦は2億円損をする」という試算があるようですが、人手不足の今、専業主婦という眠れる人材を発掘しないのは、国家的な損失でもあります。政府も、移民を増やす前に、専業主婦の保護政策の廃止から着手するべきでしょう。
歴代政権に女性がどれほど登用されていたか、も是非論じていただきたいです。
8.おかず氏のコメントにおける「日本のフェミニスト」像が、私の知人とはまったく異なっていましたので、恐らく同じ固有名詞でも、論者の肉体、自認によって、主観をどこに置くかが大きく異なり、結果として、指し示す対象も異なり、同じ名詞でも違うものについて論じているのだろうな、と感じました。フェミニズム、ジェンダーの話では、個人個人の人生の経歴を、言葉遣いや重ね方から少し推察でき、興味深く思いますね。
男女とも、「女の敵は女」という言い回しは昔からよく使っていましたが、近年になって、「男の敵は男」という言い回しがようやく現れたのも、おもしろいなと思いますね。それでは。
女性の国会議員が少ない中、女性であるという理由で能力を無視して女性を大臣に登用すると、「女は無能」という偏見に確証を与えることになるので、女性に対する評価がかえって下がってしまいます。女性活躍を推進したいのであるなら、大臣という目立つショーウィンドウに飾りのような女を置くことよりも、社会全体での女性の地位向上に努めるべきです。そしてそのための抜本的な解決策は、日本型終身雇用の廃止です。
もっと一般的な表現に「近親憎悪」や「同属嫌悪」というものがあります。同じ地平にいる者どうしほど対立が際立ちやすくなるということです。
女性は優秀だ!とか、女は素晴らしい!というようなラディカル・フェミニズムは、青年運動だと理解した。大学入学後にそれに目覚める傾向があることからそう考えた。ただし、ほとんどの女性はラディカル・フェミニズムには傾倒しない。青年心理とフェミニズムの関係について知りたい。
「大学入学後にそれに目覚める傾向がある」という情報の出所はどこですか。
フェミニズムが学生運動に影響を受けていたことと、高卒社会人でラディカル・フェミニズムに傾倒したという言論人を私が知らないことから、そう思い込んでいる。
象牙の塔にいる人ほど浮世離れしたイデオロギーに感化されやすくなるという傾向はあります。
親元を離れることとフェミニズムに限らずラディカルな思想に感化されることに繋がりがあるような気がしている。
同性婚の法制化も、フェミニストの謀略なのだろうか。