権威主義の被害者は誰か
人は権威に弱い。お上意識の強い日本人は特にそうである。自分で判断せずに、権威に依存することにはどのような問題があるのか。そして権威主義に陥ることで被害を受けるのは誰か。

1. ブランドは必要である
「権威主義」というレッテルは、通常非難の意味を込めて使われる。このことは、多くの人が、「評価は外面ではなくて、中身に対してなされなければならない」と信じていることを意味する。
しかし常にわかりやすい外面ではなくて、わかりにくい中身で判断するということは所詮不可能である。例えば、テレビを選んで買うとき、機能面でどちらが良いのかわからない時、たぶんみなさんは、聞いたこともない会社が作ったテレビよりもブランド企業のテレビを買うであろう。テレビに詳しい専門家ならともかく、そうでない一般の消費者にとって、ブランドに依存するということは、粗悪品をつかまされないための健全な防衛策なのである。
もちろん、雪印乳業のようなブランド会社が、黄色ブドウ球菌入りの乳飲料を平気で売りつけるということはある。だが私たちは、いちいち飲む前に牛乳の品質を調べることはできない。たとえそういう手段があるとしても、必要な時間や費用を考えると、何でも自分で中身を確かめて評価することは、合理的ではない。ブランドの役割を否定することは、信用で成り立っている社会を否定することになる。
しかし雪印があれだけの事件を起こしたにもかかわらず、「ブランド会社は腐っても鯛だ。無名会社の製品よりも、雪印の製品の方が信用できる」と言って割高な雪印の乳飲料を買い続ける人がいるとするならば、その人のブランド信仰は、ちょっと異常と言わなければならない。
2. ブランド信仰が本末転倒になる時
権威主義を特徴付けているのは、ブランド信仰に見られる価値と評価基準の転倒である。その転倒を理解するために、権威主義的言説の論理構造を分析してみよう。今、「東京大学の卒業生」という基準の述語記号をD、「優秀」という価値の述語記号をEで表すことにする。すると、通常のブランド利用から倒錯的な権威主義への移行には、次の三段階があることになる。
Step1. (∃x)(Dx∧Ex)
「あの人は東京大学の卒業生で、優秀である」
Step2. (∀x)(Dx⇒Ex)
「東京大学の卒業生は、すべて優秀である」
Step3. (∀x)(Dx⇔Ex)
「東京大学の卒業生である時、かつその時のみ、その人は優秀である」
ベン図で説明するなら、以下のようになる。

- 第一段階:東京大学というブランドへの信用は、通常は「東京大学の卒業生であるならば、優秀である確率が高い」という程度のもので、この段階では、「東京大学の卒業生だが優秀でない人がいる」と「東京大学の卒業生ではないが、優秀な人がいる」という二つの可能性が残されている。
- 第二段階:もしたまたま周りに「東京大学の卒業生で優秀でない人」が見当たらないなら、ブランドへの信用はさらに高まり、「東京大学の卒業生は、すべて優秀である」という信仰心が芽生えてくる。
- 第三段階:ブランド信仰がさらに熱狂的になると、「東京大学の卒業生はすべて優秀であり、かつ東京大学の卒業生でなければ、優秀とは言えない」と信じるようになる。学歴というブランドは、人材が優秀かどうかを見分ける一つの手段にしかすぎなかったはずなのだが、ここにいたって、価値と基準の主従関係が逆転してしまう。これは、G.E.Mooreが謂う所の「自然主義的誤謬」である。
一般に中身がわからない人ほど外観にこだわる。常に中身で判断しないということは、中身のない人間のすることである。能力もしくは時間がない素人がブランドに依存するのはやむをえないとしても、能力があり、しかも評価することが仕事である専門家が権威主義者であるとするならば、大いに問題がある。
3. 権威主義の被害者は権威主義者自身である
「価値あってこそブランドだ」ではなくて「ブランドあってこそ価値がある」を信じる権威主義が本末転倒であることは明らかであるが、では、「権威主義はけしからん」と憤らなければいけないのは一体誰であろうか。通常それは、権威主義によって排除された人たちだと考えられている。
例えば、企業に就職しようと面接に行ったところ、自分の出身(所属)大学が低偏差値であることだけを理由に門前払いにされたなら、その人は「学歴だけで判断しないでよ」と不満に思うに違いない。しかしその人は、権威主義の被害者とは言えない。もっとまともな人選をしている企業に就職すればよいだけである。権威主義の被害者は、優秀な人材を選ぶことができない企業それ自体である。
そもそも、評価とは、他人を喜ばせるための利他的行為ではなく、生き残るための利己的行為である。権威に目がくらんで、誤った選択をする時、最終的に損をするのは、権威主義者本人である。
権威主義者とは、喩えて言うなれば、豪華なお皿に盛られたまずい料理を食べる不幸な人であって、しかも自分が不幸であることに気付かず、世界一うまい料理を食べていると錯覚しているかわいそうな人である。私たちが権威主義者に対して抱く感情は、怒りではなくて、哀れみでなければならない。










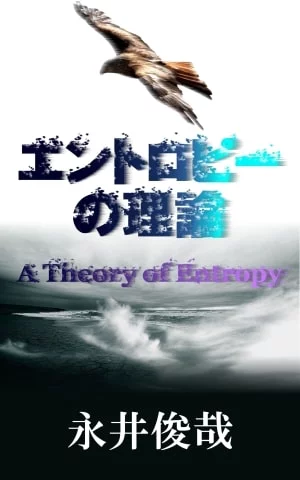

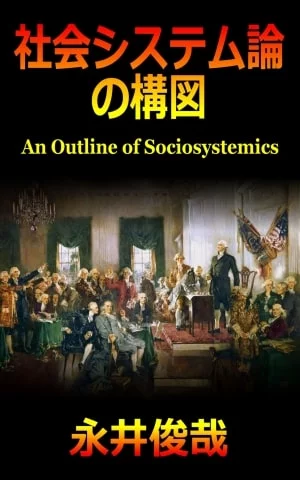

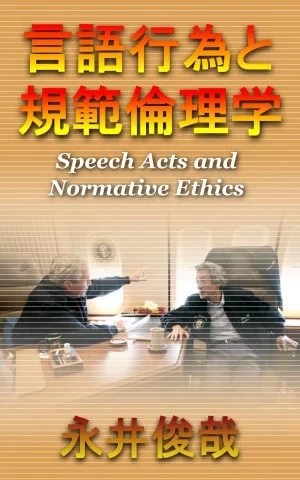
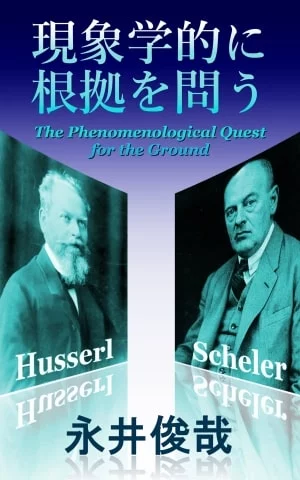

ディスカッション
コメント一覧
東大と言っても世界の大学ランキングでは100番以下の大学だし、アメリカの学者も東大の学者って翻訳しているだけだ、と言っていますよ。もういいかげん東大は止めようよ。
昔ある企業の人事担当者が「我々は東大の教育を信用していないが、東大の入試は信用している」と言っていました。東京大学が、他の日本の大学と同様に、教育機関/研究機関として三流であることには、私も同意しますが、しかしそんなことは昔からみんなが認めていることです。「東京大学」というブランドの本質は、あくまでも東京大学の入学試験による選抜の機能にあるわけで、東京大学にいる教育官僚たちの研究水準とは無関係です。一流大学の教授たちは、入学試験のブランド価値の上にあぐらをかいで、教育も研究もなおざりにして、学内行政や学閥抗争にうつつをぬかしています。学生は、大学に教育機能がないので、専門技能を磨くために、専門学校に通ったりしています。こうしたダブルスクールの弊害を取り除くために、私は、公教育の廃止を提案しています。
同感です。総ての学問の基本は独学です。これが大原則。ここではそういったことよりも問題の入学試験にテーマを限ります。文中の人事担当者のこのよう発想があるなんて考えもしませんでした。恐らく当人が東大の出身者で、しかもまさか東大が「学問の殿堂」・トップランナーとはとても恥ずかしくて言えたものじゃない、しかし自分は東大を出たつまり東大に入ったという実績は守らなければならないといったところでこういう発言があるのではないかと私は考えました。学歴は今の日本では財産の一部ですからね。
東大出つまり東大に入ったから優秀だというのではなく、東大に入った人を優秀だと称していることでしょう。日本の官僚(つまり東大法学部)は世界一優秀だと日本人は考えていますがこれは「決まったことを決まった通りにやる」能力が優れているということでつまり「猿真似世界一」だといういみですね。
東北大学の半導体の西沢先生がTVで”昔の2流3流の学生が今一流と言われている大学に入ってくる…”という意味の発言をしておられました。今の日本の学校教育は、入学試験はもちろん、いわば普通教育なのです。頭がよいといっても普通のレベルで頭が良いということですよね。「落ちこぼれ」という言葉がありますが逆に「浮き上がり」というのもあります。標準よりもさらに優秀な人達もやはり学校の中ではそれこそ「落ちこぼれ」ているようにみえます。私はアメリカでしばらく勉強していたことがありますが、ある教授(人工知能)が「天才とは学校へ行かないものだ」といって笑っていましたっけ。文化を造るのが天才、それを追っかけるのが秀才といったところか?
それともう一つ:よくTVやなんかで東大にはいった女子学生が「普通に勉強していただけ」といいますがこれは案外当たっていると思います。(私自身が東大受験生であった経験も踏まえて・因みに私の父は東大法祖父が京大です)東大の入学試験の問題はむしろオーソドックスで早稲田とか所謂私大の方が問題はヤヤコシイ。しかも受験科目が少なく競争的にはもっとキビシイ。こつこつと勉強するくせと集中力(もっともこれはなにをするにしてもですが)があれば実はいけますよ。こう考えると東大・東大って騒ぐことも実はないのです。
「天才とは学校へ行かないものだ」という指摘には共感できます。学校で他の人から教わらなければ勉強できない人よりも、自力で勉強できる人の方が本来有能だと思うのですが、学力社会から区別された学歴社会では、学校に行かない人の方が無能扱いになってしまいます。
もっとも私は、独学を推奨しているわけではありません。天才といえども、その天才を引き出してくれる場を必要としているはずです(educateは語源的には、引き伸ばすという意味です)。問題は、公教育がそうした場を提供できないところにあります。SNさんは、なぜか東京大学だけを目の敵にしているようですが、東京大学だけをスケープゴートにするならば、日本における教育問題は矮小化されることになるでしょう。「東大・東大って騒ぐことも実はないのです」というせりふを私はSNさんに向かって言いたいです。
私は、東京大学を含めた国公立大学はもちろんのこと、私立大学も、それが公教育の枠組みに組み込まれている限り、教育機関としては、機能不全に陥ったままだと思います。入試問題にしても、早稲田大学の入試問題が、東京大学の入試問題よりも優れているかどうかは疑問です。昔早稲田大学の日本史の入試問題で、日本に初めてもたらされた種子島の鉄砲の重さ(!)を問う問題が出題されたそうです。難問といえば、難問ですが、そうした知識があるからといって、学問的に優れた学生であるといえるのかどうか。
今回、例として挙げた新卒採用における学歴偏重も、別に東京大学の卒業生だけがやっていることではありません。むしろ低学歴の社長ほど、学歴コンプレックスがあって、ブランド校の卒業生を取りたがる傾向があるそうです。学歴だけで採用/非採用を決めることは、アメリカで教育を受けた人には驚きかもしれませんが、少なくとも私が大学生だった頃はそれが普通でした。私自身は、就職活動をしたことがないのですが、無名大学の4年生だった人の話によると、関西の大企業の面接試験を受けに、新しくスーツを買って行ったところ、履歴書を一瞥した受付の女性から、「ウチはおたくの学生さんは採りません」と言われ、文字通り門前払いになったそうです。このことは、多くの企業が大学における入学試験の選抜機能だけを重視し、その後の4年間を評価の対象外にしていたことを意味しています。
教育機関であるはずの学校が公的な選抜機関となることのもう一つの弊害は、たとえその学校が、教育機関として機能不全に陥っていても、それが補助金と規制によって守られ、存続しつづけることです。国公立大学と私立大学は、金融に譬えれば、郵便貯金と民間金融機関のようなもので、どちらも保護産業であることには変わりがありません。日本の金融機関は、民間企業とは名ばかりで、大蔵省の護送船団方式のもとで甘えの経営を行ってきました。同様に日本の私立大学も、文部省の護送船団方式のもとで甘えの経営をやってきました。しかし日本の大学も少子化と不況で、今後淘汰されていくことになるでしょう。
私は、今の日本には金融ビッグバンとともに、教育ビッグバンが必要だと思います。その際、学校における教育機能と学位認定や資格試験という公的な評価機能を分離し、前者を完全に民間に任せ、教育に市場原理が働くようにするべきでしょう。こうすれば、一方で新しい時代に適応できない大学は淘汰され、他方で学力を判断する純粋なブランドが確立されるようになると思います。
権威主義と権力にこだわる人はどう違うのでしょうか。
権威主義とは、実体のない権力の崇拝であり、実体のある権力崇拝とは異なります。
好きこそ物の上手なれと言いますね。
私は小中高と学年が上がるごとに自分の好きな方向に進むための試験をやるべきだと思います。
例えばパン屋なるにしても段階ごとに専門教育を選択して行く教育プログラムが必要です。また同じ目標を持ったものを寄せ集めることで自然と競争意識が沸きます
そういった教育を取ることで自分の仕事に誇りを持った大人が育成され、社会に出回る商品も質が高い物になります。各分野にエリートが存在することによって職業差別もなくなるのではないでしょうか?
何より、学生時代から目標意識を持つことは凄く良いことです。伸びしろが違います。
将来の目標もなしに普通科の学校を選択していく学生が大多数だと思います。それが18歳まで将来何をやろうと言う意識もなく普通科の高校に通い突然大学から専門分野の勉強をしだせば当然微妙な大学生が量産されますよ。仕方ないことだと思います。
そして、大学の勉強は単位を取る程度にしか考えなくなる。
「その分野が好きだ。学びたい。」と義務教育と高等教育の中で段階を踏んで準備させるのが本当の意味での教育ではないでしょうか?
1,2日社会化見学をすれば十分だと国のお偉いさんは思っているようですが・・・
日本は明治時代から一心不乱に先進国になってきましたから充実している(特に普通の学校教育)部分は賞賛に値すると思いますが、空洞の部分もかなり見当たるのではないかと思います。
様々な職業につく機械ができる。
様々な分野をもっと一般的な教育にしていくことが大事。
ゆくゆくは食糧自給率や雇用問題もそれで解決できると思います。
しかも品物の質がよくて、労働者一人一人が誇りを持って働いている社会。
これが実現できるなら日本の国家予算80兆の内何パーセントか割く価値は十分にあるのかと。
私も日本人の一人ではありますが、権威主義は大嫌いです!(20代後半の男より)
欧米の民主主義・フラットな実力主義社会を重視しています!
人は権威に弱い。お上意識の強い日本人は特にそうである。
→私は日本人であるけど権威というのは大嫌いです!平等意識・フラット意識を非常に強く持っています!
自分で判断せずに、権威に依存すること
→それどころかむしろ権威に強制されたり押し付けられている被害者です!
そして権威主義に陥ることで被害を受けるのは誰か。
→それはヒエラルキーにおける下っ端の人です!
記事の権威主義は、本当の権威主義とは言えないけどね。
実際の権威主義は、権威を傷つける者を無慈悲に切り捨てていくから、有能でない者は居ない。
何時からだろうか。
まやかしの権威主義こそが権威主義だと言われるようになったのは。