生命はいかにして進化するのか
ダーウィンの進化論は、偶然生じた生物の変異に自然選択(性選択等も含めるものとする)が働き、環境に適応しているものだけが生き残って子孫を増やすことで、進化が起きるとする説であるが、このダーウィンの進化論は、今日に至るまで進化論のパラダイムである。新しい進化の学説を唱える者は、そろってこのダーウィンの進化論を批判し、「ダーウィニズムはもう古い」と宣言するが、このことは、ダーウィニズムがまだ古くない証拠である。もし本当にダーウィニズムが古くなっているのならば、新しい進化の学説を唱える者は、そもそもダーウィニズム批判などしないはずだからだ。

1. ダーウィンに対する通俗的批判
もちろん、だからといって、ダーウィンの進化論が無謬であるというわけではない。では、ダーウィンの進化論は、どの点で正しく、どの点で間違っているのだろうか。ダーウィニズムに対する批判をいくつかに類型化して、その是非を検討しながら、生命はいかに進化するのかを考えていこう。
[批判1] 進化する単位は個体ではなくて種である。
今西錦司などは、こうダーウィンの進化論を批判するのだが、これはダーウィン批判としては的外れである。なぜならば、ダーウィンは、同じ種の個体と個体の間だけでなく、同じ属の種と種の間にも“struggle for existence”が起きると述べているからである。
同じ類の種は、習性と体質という点で、常にというわけではないが、たいていは大きな類似性を持ち、構造という点では常にそうであるので、お互い競争するようになると、闘争は、異なる類の種の間よりも、同じ類の種の間でより激しくなる。[1]
現代の進化論は、進化の単位を遺伝子としているので、もはや進化の単位が個体か種かといった議論はしない。ただ、後で述べるように、遺伝子の変化が個体の変化をもたらすとは限らず、また個体の変化が種の変化をもたらすとは限らないので、種の進化しか扱わない今西進化論は、進化現象の表面しか見ていないと言うことができる。
今西錦司とその支持者によるもう一つのダーウイニズム批判は、次のようなものである。
[批判2] 生物界には共生や棲み分けがあり、必ずしも優勝劣敗あるいは弱肉強食の競争が行われているわけではない。
このダーウィニズム批判は、和を以って貴しと為す日本人の心の琴線に触れるところがあるからなのか、日本では大いにもてはやされている[2]。だが、自然選択や適者生存を弱肉強食あるいは優勝劣敗の競争と理解することは、ダーウィンに対する誤解である。こうした誤解が生じるのは、従来、我が国では、“struggle for existence”あるいは“struggle for life”が「生存競争」と誤訳されてきたことと無関係ではない。
ダーウィンは、乾燥化に抗して生き延びようとする植物をも“struggle for life”の一つの例として使っている。
私はこの「生存闘争」という言葉を、他者への依存、個体が生き延びるだけでなく(こっちの方が重要ではあるが)、子孫が繁栄することをも含む広くて比喩的な意味で使っていると前置きしなければならない。二匹のイヌ科の動物は、飢饉の時、食料を得て生き延びなければならないお互いどうしで闘うと本来の意味で言ってよいかもしれない。しかし、砂漠の縁にある植物は、本来は湿気を求めていると言われるべきだが、旱魃に対して生存闘争をしているとも言われる。[3]
それゆえ、個体間の争いしか含意しない「生存競争」という訳語は狭すぎるのであって、環境適応への様々な奮闘を含意する「生存闘争」あるいは「生存努力」という訳語を採用するべきである。ダーウィンが“struggle for existence”あるいは“struggle for life”という言葉で表現しようとしたのは、すべての生物は、存在しようと奮闘する(struggle to exist)、あるいは生きようと奮闘する(struggle to live)という自明な事実だった。
共生や棲み分けは、生存競争ではないが、生存努力の一種である。共生している生物は、和の精神からそうしているのではなく、たまたま相互に寄生し合っているだけであり、そして寄生は、エゴイスティックな生存努力の一つである。また、棲み分けによる種分化も、ニッチな環境への適応という生存努力の結果である。だから、モーリッツ・ワグナーの地理的隔離説や今西錦司の棲み分け説は、その限りでは、ダーウィニズムと対立する進化論ではない。
「弱肉強食」あるいは「優勝劣敗」といった表現は、自然選択で生き残るのは、優秀で強い個体だけだという考えを前提しているが、これも、ダーウィニズムに対する誤解である。ダーウィンは、ラマルクを批判して、次のように言っている。
自然選択または適者生存は、必ずしも進歩的発展を含まない[4]
実際、知的で力が強い種が、環境に適応できずに絶滅することもあるし、「下等」で力が弱い種が、環境に適応して生き残るということもある。「もし自然が絶えず適者を選び続けているとするならば、なぜいまだに原始的な生物が、ほとんど何の変化もなく存在し続けているのか」といった疑問を持つ人は、進化と進歩を混同している。
こうした適者生存説に対しては、次のような批判がよくなされる。
[批判3]「環境に最も適応したものが生存する」という命題は、間違っているか無意味な同語反復であるかのどちらかである。
自然選択で生き残った種が、本当に環境に最も適応しているのかどうかを疑問視する人がいる。確かに、環境適応という観点からすれば、どの生物にも改善の余地はあり、完璧ではない。ダーウィンが、ハーバート・スペンサーから借用した“適者生存 the Survival of the Fittest”という言葉は、最上級の形容詞を用いているが、生き残っている種は、決して「考えうる中で最も適した種」ではないのだから、これは、たんに「絶滅したライバルと比べて、総合的に最も適した種」と解釈しなければならない。一般に生物は保守的で、生存し続けることができる限り、変化しようとしない。「環境に最も適応したものが生存する」という命題は、「生存できるものが最も環境に適応している」という命題として理解しなければならない。
このように主語と述語を逆にすることができるのならば、この命題は、無意味なトートロジーではないかと疑われても仕方がない。だが、環境に適応していれば、必ず生存するというわけではない。局所的・短期的には、環境に適応した個体がたまたま死滅したり、環境に適応していない個体がたまたま生存することはある。だから、「環境に適応したものが生存する」という命題は、トートロジーではない。ただ、十分に長い期間にわたって、十分な数の個体を観察するならば、環境に適応したものが生存する確率は、非常に高くなる。このように、適者生存説は、統計学的な蓋然性を語っていると解釈すればよい。
この批判とは逆に、次のような批判もある。
[批判4] 環境に見事に適応した生物が持つ精巧な器官は、偶然から生まれることはできない。
ダーウィン自身、眼を例にとって、次のように言っている。
様々な距離に焦点を合わせ、様々な量の光を受容し、光の球面収差や色収差を補正する比類なき機能を備えた眼が自然選択によって形成されことができたと想定することは、正直言って、きわめてばかげているように見える[5]
だが、ダーウィンによれば、明暗を感知するだけの原始的な光の受容体から、段階的に自然選択が働いて進化したと考えれば、高度な機能を持った眼が誕生することも不可能ではない。リチャード・ドーキンスの比喩を使うならば、サルがキーボードをランダムにたたいて、シェークスピアの名文を一度で打ち出すことはほとんど不可能だが、間違った箇所だけを修正していく段階的な方法でならば、比較的短い時間の内に可能である。ここから、ドーキンスは、その都度生じる変異に対して、少しでも理想に近いものが育種される段階的・累積的進化を説く[6]。
この段階的進化論には次のような批判がよくなされる。
[批判5] 進化が段階的であるならば、中途半端な途中の段階の生物は、環境に適応できずに淘汰されてしまうので、進化は不可能になる。
鳥を例に取ると、今日、ある種の恐竜が鳥に進化したとする説が有力であるが、もしも恐竜が、羽を生やし、重量を減らし、羽ばたくだけの筋肉をつけるといった諸段階を経て徐々に鳥へと進化するとするならば、途中の、陸上生活にも空中生活にも十分に適応していない段階の生物は、その適応の不十分さから、淘汰されるのではないのかというわけである。このような心配は無用である。恐竜に生えた羽毛は、当初体温を保持するのに役立ち、後に、飛ぶために使われるようになった。だから、飛べない恐竜にとっても、羽毛は環境適応に役立ったと考えることができる。
このように、一つの器官が複数の機能を重複して持つことが、段階的進化を可能にするわけだが、一つの機能を複数の器官が担うという重複も、段階的進化にとって重要である。ダーウィンが挙げている例を使うと、肺魚類は、呼吸をするのに鰓と肺の二つの器官を使い、肺に呼吸器官と浮き袋の二つの機能を与えている。ダーウィンは、浮き袋が肺に進化したと考えていたが、実際にはその逆である。このような事実誤認はあったものの、重複が連続的進化を可能にするという洞察は、今日でも有効である。
進化の連続性仮説に対する反論と誤解されることがあるのが、次の断続平衡説である。
[批判6] 進化は等速度的で漸進的なプロセスではなく、長い停滞期と短い変革期から成り立っている。
この断続平衡説が否定しているのは、進化の等速性・漸進性であって、連続性ではない。ダーウィンが連続性を強調したのは、神の奇跡によって生物が非連続的に創られたとする創造説を否定するためであり、断続平衡説を提唱したナイルズ・エルドリッジやスティーヴン・ジェイ・グールドも、決して創造説を復活させようとしたわけではない。
ただ、ダーウィンは、連続性を強調するあまり、等速性・漸進性まで主張してしまった。だから、彼は、カンブリア爆発のような、短期間での急激な進化を否定しようとした。しかし、今日の古生物学によれば、古い種の絶滅と新しい種の出現の頻度は、ダーウィンが想定した以上に偏っている。古生代の終わりから今日に至るまでに限って言えば、気候寒冷化によって既存種の大量絶滅と新種の適応放散が一定の周期で起きている反面、それによって区切られた期間内では、種の変化が少ないことが確認されている。
ダーウィンは、自然選択によって、絶えず少しずつ種が進化すると考えていた。だが、実際には、自然選択が排除するのは、通常、標準から外れた個体ばかりである。ほとんどの場合、自然選択は種の変化を促進しているのではなくて、逆に抑制している。ダーウィンは、変わることができるから変わるというラマルク流の能力史観に染まっていたようだが、生物は保守的だから、進化を説明する時には必要史観の方が有効である。種は変わる必要があるから変わるのである。もっと具体的に言うならば、大量絶滅等によって空白が生まれる、生き残った種が、その空白を埋めるべく新しい環境に適応しなければならなくなってはじめて進化するのである。
断続平衡説を受け入れると、次のダーウィニズム最大の難問が、より深刻になる。
[批判7] 環境の変化へに適応する進化は、たんなる偶然からは不可能である。
ダーウィニズムが当初から直面した問題は、議論の出発点である、遺伝可能な差異がいかにして生じるかという問題だった。ダーウィンは、ラマルク流の用不用説で、差異が生じると考えていたようだが、1885年のワイズマンの実験で獲得形質の遺伝が否定され、ダーウィニズムは危機に直面した。その後、1901年にド・フリースが遺伝子の突然変異を発見し、突然変異で生じた遺伝可能で有利な形質が自然によって選択され、生き延びることで進化が起きると主張するネオ・ダーウィニズムが支持を集める。現在、進化論のパラダイムとなっている総合説の中核は、正確に言えば、ダーウィニズムではなくて、このネオ・ダーウィニズムである。
2. ネオ・ダーウィニズムの根本問題
ネオ・ダーウィニズムにとっての頭痛の種は、自然突然変異が起きる確率がきわめて小さいということである。高等生物の遺伝子(機能しているDNA)では、一つの塩基対の突然変異率は、一年当たり10億分の1で、これでは、仮に自然選択が働かず、誤差が蓄積するとしても、100万年後の遺伝子の変化率は、たったの0.1%である。しかも、突然変異の圧倒的多数は、生物にとって有害な変異で、有利に働く突然変異の確率はきわめて小さく、小数点以下ゼロが600万個続くという試算すらある。さらにその突然変異は、いつ起きても良いわけではなく、変わる必要がある時に都合よく起きなければならないのだが、そのようなことは、奇跡でも起きない限り不可能である。
もっとも、DNA全体の変異は、実際にはもっと頻繁に起きている。木村資生によると、哺乳類での突然変異によるゲノムあたりのヌクレオチド置換は、少なくとも2年に1回起きるぐらい速度が高い。これは、表現形質に変化をもたらす突然変異とは別に、そうではない突然変異があって、後者の突然変異置換速度が前者のそれよりも高いからである。
DNAには、形質として発現する遺伝子とは別に、そうではない擬似遺伝子が存在する。擬似遺伝子を含むジャンクDNAがDNAに占める割合は高く、例えば人間のゲノムの場合、95%はジャンクDNAだと考えられている。擬似遺伝子がいくら変異しても、表現形質に変化がないので、自然選択によって淘汰されない。形質として発現する遺伝子でも、同義的置換、すなわち合成するたんぱく質に変化をもたらさない変異の方がそうでない変異よりも進化においてずっと高い速度で起こっている。
では、木村資生は、表現形質の進化をどのように説明するのか。彼の中立説によれば、表現形質として現れる有害な突然変異遺伝子は、有害ゆえに淘汰されるものの、微弱に有害な突然変異遺伝子は、自然選択に中立であり、遺伝子プールにおいて偶然的に浮動する。そして、環境の変化によって、表現形質の最適地の位置が変わり、弱有害突然変異遺伝子が有利となると、種はその平均を変えることにより、急速にその変化の跡を追うとのことである[7]。
3. ウィルス進化論
はたしてこれで進化が説明できるだろうか。環境の変化により、ある弱有害突然変異遺伝子が有利となり、ある有利な突然変異遺伝子が不要、すなわち弱有害になっても、その弱有害な突然変異遺伝子が遺伝子プールにおいて偶然的に浮動し続けるならば、表現形質にはほとんど何の変化も起きないことになるのではないだろうか。
もっとドラスティックな進化を説明する理論として、日本で有名なのが、ウィルス説(ウィルス進化論)である[8]。従来の総合説では、進化の主体はDNAとされ、遺伝情報はDNA→RNA→アミノ酸合成というように一方向にしか転写・翻訳されないものと思われていた。しかし1970年にRNAからDNAを逆転写するレトロウィルスの働きが発見されたことで、この「セントラル・ドグマ」は崩壊し、DNAのコピーミス以外の方法で、遺伝情報が変異することがわかった。中原英臣と佐川峻がウィルス説を提唱したのは、その翌年である。斜体文
中原英臣と佐川峻は、種がウィルス性の伝染病にかかることで進化すると主張するのだが、このようにウィルスが直接進化につながる変異を惹き起こすと考えると、ネオ・ダーウィニズムと同じ問題に直面することになる。ウィルス性病原体は、感染した生物に有害な結果をもたらすのが普通である。環境が変化し、生物が変わる必要に迫られた時に、たまたま都合よくウィルス性の伝染病に感染し、そしてそのウィルスが、たまたま環境に適合する形質を生み出すように遺伝子を変えるということは、確率が低すぎて非現実的である。
ウィルス説は、中原英臣と佐川峻が一般向けに啓蒙書をたくさん書いたことで有名になったが、アカデミズムの保守本流からは無視されている異端の説でもある。その意味で、ウィルス説は、学界においては、それ自体ウィルス的存在である。私としては、ウィルス説に感染して、彼らの受け売りをする代わりに、ウィルス説を中立説的に組み換えて、自然選択説(ダーウィニズム)に組み込むことにしたい。
4. ウィルス中立説
レトロウィルスは、宿主細胞に入り込んで、逆転写酵素によりDNAを合成してそれを利用して増殖する。HIV(ヒト免疫不全ウィルス)のように、宿主を殺してしまうと自分も道連れで死んでしまうが、擬似遺伝子に子孫を残すならば、表現形質に影響を与えないので、負の選択圧を受けることなく、うまく寄生し続けることができる。そしてその末裔ではないかと考えられているのが、トランスポゾンである。
トランスポゾンの起源がレトロウィルスであるかどうは別として、トランスポゾン、特にレトロトランスポゾンは、レトロウィルスとよく似た働きをする。レトロウィルスやレトロトランスポゾンによる逆転写で擬似遺伝子が組み替えられ、現役の遺伝子に取って代わる多様な設計図の予備軍が蓄積される。そして、環境の変化により、種が変わらなければならなくなった時、蓄積された様々な組み合わせの擬似遺伝子がランダムに発現し、多種多様な個体が現れ、そのうち最も環境に適した個体が、新しい環境のもとで適応放散すると考えればよい。
擬似遺伝子としてアクティブでなくなったDNAが、どのようなメカニズムで再びアクティブになるのかは不明だが、事実としては確認されている。例えば、馬の祖先の足には五本の指があったが、現在の馬には、三番目の指一本しか残っていない。しかし、他の指を作るDNAが消滅したわけではない。たんに現役を引退し、擬似遺伝子としてお蔵入りになっただけで、まれにカムバックすることがあり、その結果、指の数が多い馬が生まれる。多指の馬の三分の二は、第三指をたんに重複しただけであるが、残りは、第二指か第四指が蹄を具えた完全な指になって発達してきたものである。だから、擬似遺伝子は永遠に日の目を見ないというわけではない。
私がこの仮説を採用したいと考えるのは、この進化のモデルが、社会システムの進化を説明するモデルとしても有効だからである。生体内でたんぱく質を合成する権力を掌握した保守的な遺伝子とその権力から疎外された擬似遺伝子と生体の内外で権力奪取を狙うウィルスが、社会システム内の権力を掌握した保守的中心とその権力から疎外された周縁とシステムの内外で権力奪取を狙う革命の先駆者に相当することを確認して、進化論の復習をしよう。
断続平衡説が説くように、人類社会の歴史も、長い安定期と短い革命期の繰り返しである。政治の世界であれ、経済の世界であれ、学問の世界であれ、安定期の社会システムには、トップのたんなる世代交代など、中心における「同義的置換」と周縁における影響力のない実験的変革、つまり「表現形質として発現しない変異」しか見られず、結果としてシステムはほとんど変化しない。環境の変化に対して、システムが自己を維持できなくなると、中心は中心としての地位を失い、周縁から革命が起き、革命の勝者が次の中心となる。
生物の進化を社会の進化のアナロジーで理解するのはけしからんと思う読者もいるかもしれない。だが、ここで、ダーウィンの自然選択説も、その理論的原型が社会科学にあることに留意しなければならない。ダーウィンの『種の起源』の画期的意義は、進化という事実を指摘したことにあるのではなく、進化を自然選択によって説明したところにある。そして、そのアイデアの源泉を探ると、トマス・マルサスとアダム・スミスという二人の経済学者にまで遡ることができる。
ダーウィンは、マルサスを『種の起源』で何度か引用しているので、明らかに彼から影響を受けている。マルサスによれば、生活資料は算術級数的にしか増えないのに対して、人口は幾何級数的に増えるので、余剰人口と貧困が生じる。そうなれば、当然余剰となった人々は、希少な資源をめぐって闘争し、そしてその闘争に勝利した適者だけが生存できるといことになる。
アダム・スミスは『種の起源』で直接言及されていないが、1838年の数ヶ月間という決定的な時期にダーウィンがスミスの考えを勉強していたことから、ダーウィンはスミスからかなりの影響を受けたと判断できる。個人が私利私欲を追及しているうちに、見えざる手に導かれて、公共の利益を実現するという古典派経済学のアイデアが、生物は合目的的・主体的に進化すると考えるラマルキズムとは違って、各個体が生存努力をしているうちに、自然選択という見えざる手に導かれて、新しい種という秩序が予期せずして実現すると考えるダーウィニズムの誕生をもたらした。
後に、ダーウィニズムは社会現象へと再適用され、ソーシャル・ダーウィニズムが生まれるが、生物学と社会科学のこのような平行現象は、社会システムと生命システムは、情報をコード化するメディアが言語か遺伝子かという違いはあるものの、多くの類似性を持ち、したがって、生命進化と社会進化は、同じモデルで説明できるということを示唆している。
一般的に言って、システムは、増大した複雑性を縮減することで進化する。システムの周縁で様々な設計図の予備軍が蓄積され、他のようでもありうる可能性が増えることは、複雑性の増大であり、環境に適合しない設計図の候補が自然選択によって淘汰されることは、複雑性の縮減である。そして、この増大した複雑性の縮減で進化が可能になるという考えは、ダーウィニズムと基本的に一致する。
5. 参照情報
- ↑“As the species of the same genus usually have, though by no means invariably, much similarity in habits and constitution, and always in structure, the struggle will generally be more severe between them, if they come into competition with each other, than between the species of distinct genera.” Charles Darwin. On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life 6th edition, Chapter 3, Struggle for Existence. チャールズ・ダーウィン.『種の起源』第3章.
- ↑今西進化論は、個に対する種の優位、同じ種の内部での争いのタブー視、運命としての進化などの主張内容からわかるように、進化論にかこつけて「日本人の心」を表明したものに過ぎない。今西進化論に関しては、今西錦司『主体性の進化論』を参照されたい。
- ↑“I should premise that I use this term [struggle for existence] in a large and metaphorical sense, including dependence of one being on another, and including (which is more important) not only the life of the individual, but success in leaving progeny. Two canine animals, in a time of dearth, may be truly said to struggle with each other which shall get food and live. But a plant on the edge of a desert is said to struggle for life against the drought, though more properly it should be said to be dependent on the moisture.” Charles Darwin. On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life 6th edition, Chapter 3, Struggle for Existence. チャールズ・ダーウィン.『種の起源』第3章.
- ↑“natural selection, or the survival of the fittest, does not necessarily include progressive development” Charles Darwin. On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life 6th edition, Chapter 4 Natural Selection. チャールズ・ダーウィン.『種の起源』第4章.
- ↑“To suppose that the eye with all its inimitable contrivances for adjusting the focus to different distances, for admitting different amounts of light, and for the correction of spherical and chromatic aberration, could have been formed by natural selection, seems, I freely confess, absurd in the highest degree.” Charles Darwin. On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life 6th edition, Chapter 6 Difficulties on Theory. チャールズ・ダーウィン.『種の起源』第6章.
- ↑Richard Dawkins. The Blind Watchmaker. Why the Evidence of Evolution Reveals a Universe Without Design W W Norton & Co Inc; Subsequent版 (1996/8/29).
- ↑木村資生.『分子進化の中立説』紀伊國屋書店 (1986/10).
- ↑中原英臣,佐川峻.『ウイルス進化論―ダーウィン進化論を超えて』早川書房 (1996/7/31).








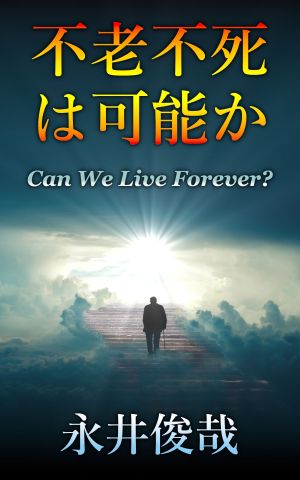

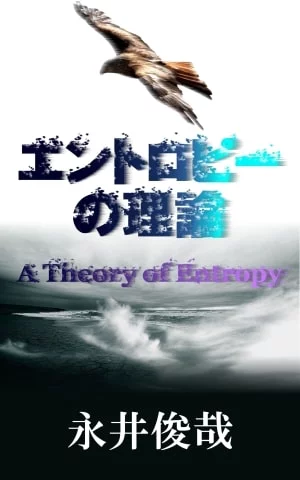

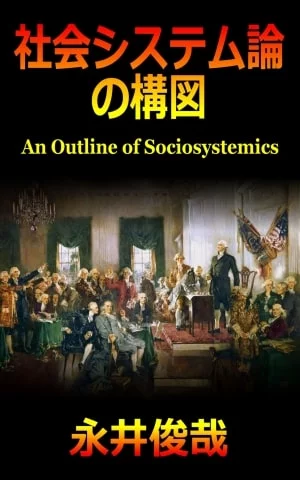

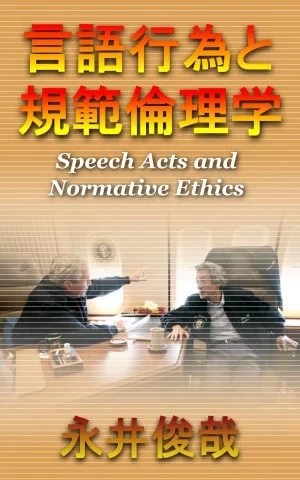
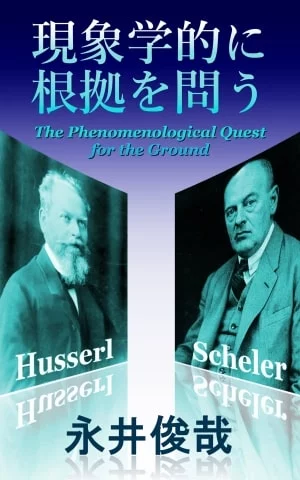

ディスカッション
コメント一覧
西洋中世でも農村部人口推移はゆるやかだったですね。マルサスは、どんな統計を根拠に「人口は幾何級数的に増える」と言ったのでしょうか?
マルサスは、統計に基づいて実証的にではなく、簡単な計算から理論的に「人口は幾何級数的に増える」という結論を出しました。第1世代が男と女2人で、各カップルが4人ずつ子供を産むと仮定すると、第n世代の人数は2のn乗になり、その合計は、等比級数(geometric progression 幾何級数)となります。当時は、現在のように合計特殊出生率が低くなかったので、こうした推論が成り立ったわけです。
わたしの母(84)は12人出産して、4人が生き残っていま す。(自殺ひとりふくむ) いったいどういうつもりで生んだんだか、、怒りを感じます。 わたし(54)は3人育てましたが、23年間外出もままなり ませんでした。どういう教育を受けたんだか、、バカらしさを 感じます。マルサスなんて教わりませんでした。われわれ余っっちゃってる世代の行き着く先の高齢者問題を論 じてくださることを期待しております。
批判1として、「進化する単位は個体ではなくて種である」が掲げられています。ダーウインに対する批判として的外れというのはそうだと思いますが、進化現象の表面だけを見ているというのは、どうなんだろうと思いました。今西仮説は、進化のフィードバックが、種のレベルで起きるということ、つまり選択する環境としての群生のようなものを考えているのではないですか?異常に繁殖した種が集団自殺をする現象がありますよね。これは、種としての環境悪化(生存スペースの減少)に対して不適応な種を淘汰することだと考えられませんか?こう考えると、種としての性質は、環境の変化、個体を取り巻く生存スペースの変化を通じて、選択的な進化に寄与することになります。永井さんの必要史観の立場とも整合するように思います。むしろ近くないですか?いかがでしょう。
その前に書いてある「現代の進化論は、進化の単位を遺伝子としているので、もはや進化の単位が個体か種かといった議論はしない」という文に注目してください。個体であれ、種であれ、どちらにしても、それらは遺伝子の表現形質であって、遺伝情報そのものではありません。今西進化論を含めて、従来の生物学は、生物を物として扱ってきましたが、現在の分子生物学や遺伝学は、生物を情報として扱っています。その意味で、今西進化論は古いパラダイムであり、遺伝子レベルにまで議論を深めないという意味で、「表面的」なのです。なお、本能的に行われる集団自殺現象も、遺伝子戦略の一つと理解されています。
ちょっと、別の方面から質問します。
この木村説の要約の中で、「弱有害突然変異遺伝子」という概念が分かりません。つまり、自然選択に中立であるならば、微弱とはいえ有害とは言えないはずです。もし言えるとすれば、自然選択とは独立に有害と判断することが出来る場合です。どういう場合を想定しているのでしょうか?統計的にメジャーではなくマイナーであるといった意味なのでしょうか。しかし、それなら自然選択に対して中立ではありませんよね。
例えば、人間は、LGGLOがアクティブではないので、他の霊長類と異なって、自分でビタミンCを合成することができません。だから、この点では、人間は他の霊長類よりも環境への適応力がないということになります。しかし、実際には、ビタミンCを含む食物がたくさんあるので、この欠陥は、人類の存続を脅かすことはありません。だから、LGGLO擬似遺伝子は、弱有害ながら、人類の遺伝子プールの中に定着することができました。
ウイルス説と木村説を折衷させて、永井さんは
とこの論文をまとめておられます。この潜伏している擬似遺伝子という考え方がとても面白いと思いました。特に、自然選択に対して、ほぼ中立といった点は刺激的です。このような擬似遺伝子の有り様が、永井さんのいう物から情報へのパラダイムチェンジと関係していると思うのです、実はよく分かりません。もう少し、説明していただけませんか?
自然選択に対して中立な進化があるというのは、木村資生の主張です。物から情報へのパラダイム転換とは、生命の本質が、表現形質ではなくて、遺伝子にあるとする近年の生物学の傾向のことを言っているのであって、擬似遺伝子の話とは関係がありません。
「生命の本質が、表現形質ではなくて、遺伝子にあるとする。」この傾向が物から情報へのパラダイム転換であるということですね。その傾向の中で、擬似遺伝子は、進化との関係で、唱えられている木村の仮説であるという位置づけだと了解しました。少し、分かってきました。ありがとうございます。 社会理論への展開を考えるとき、例えば情報と権力の関係を解明するのに、こうした生物モデルがレトリック以上の有効性を持ちうるのでしょうか?生物モデルの射程は、既存の社会理論のモデルと比べてどういった利点があるものなのでしょう?どういう現象に対してこのモデルは、その有効性を発揮するものなのでしょう。