ニューディールは成功したのか
1929年10月の暗黒の木曜日以来、深刻さを増すばかりの米国の大恐慌を克服するために、1933年3月に大統領に就任したルーズベルトは、ニュー・ディールと呼ばれる全体主義的経済政策を実行した。公共投資を拡大してデフレから脱却するケインズ的財政政策は、今日の知識集約経済では流行おくれとなっているが、規格大量生産を行う当時の資本集約経済では、政府が民間に代わって生産活動を担ってもあまり弊害がない。では、ルーズベルトのニュー・ディールは成功したのだろうか。

1. 挫折したニュー・ディール政策
ルーズベルト[1]の大統領主任後の9か月後、ケインズ[2]は、公開書簡の中で次のように述べて、借金してでも政府支出を増やすべきだと勧告している。
好景気のさなかでは、無制限の融資で商業投機家の興奮した熱意を支援することでインフレを惹き起こすことができます。しかし、不況のさなかでは、政府が債務を増やして支出を増やすことが、価格を上昇させながら生産量増大を早期に確実にする唯一の確実な手段です。戦争が常に激しい産業活動を引き起こしたのはそのためです。過去において、正統派の財政は、戦争を政府の支出によって雇用を創出するための唯一の合法的な口実として見なしました。大統領、あなたはそうした拘束から解き放たれているのですから、これまで戦争と破壊の目的を果たすことでしか許されてこなかった技術を平和と繁栄のために使う自由があるのです。[3]
この勧告に従うかのように、ルーズベルト大統領はまず平和的な手段で財政支出を増やした。しかし、ルーズベルトより2ヶ月先に政権の座に就いたヒトラー[4]が実行した全体主義的経済政策と比べると、結果は芳しいものではなかった。1933年に25.2%と最悪の数字を記録した米国の失業率は、ニュー・ディール政策のおかげで1937年には14.3%にまで下がったものの、翌年には19.1%にまで跳ね上がっており、14%以下になるのは、米国が太平洋戦争を行う1941年以降のことである。これに対して、ヒトラーは、45%もあった失業率を順調に減らし、第2次世界大戦前の1939年までに、失業者数を20分の1にすることに成功した。なぜ、ニュー・ディールは成功しなかったのだろうか。

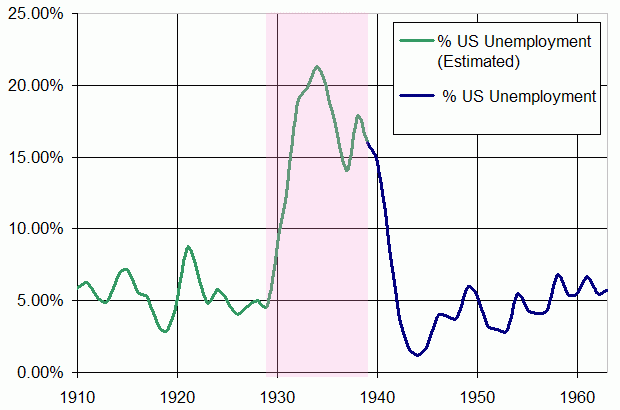
最大の原因は、ルーズベルト大統領には、ヒトラーほどの権力がなかったことに帰せられる。ルーズベルト大統領は全体主義的な経済政策を行おうとしたが、米国の政治形態は民主主義であり、全体主義ではなかった。だから、ヒトラーのように大胆な公共投資が行えなかった。国内の反対派と妥協した結果、ニュー・ディールは中途半端な形でしか実行されなかった。特に38年には、政府債務の累積を憂慮する財政均衡主義者の声に押されて、連邦支出を削減した結果、GNPは6.3%減少し、純投資も46億ドルのプラスから66億ドルのマイナスに転落した。この時、ケインズは、『ニュー・リパブリック』誌で「私の説の正しさを証明できるに十分なほどの財政支出は、戦争でもない限り不可能だ」と言ったが、この予言は的中することになる。
2. スケープゴートに選ばれた日本
1939年9月、ヒトラーは、ポーランドに侵攻し、第2次世界大戦が始まった。そして、ルーズベルト大統領は、ヒトラーと同様の方法で、大恐慌を乗り切ろうと考えるようになる。ヒトラーは、ユダヤ人をスケープゴートにすることにより、資本家と労働者との19世紀的な階級的対立を解消した。おかげで、ドイツ民族は一致団結して、国家のために奉仕労働を行い、ドイツの生産力は飛躍的に増大した。当時、党外はもちろんのこと、党内にも多くの反対派議員を抱えて、ニュー・ディール政策に行き詰まっていたルーズベルト大統領も、国外にスケープゴートを見つけ、それを叩くことで米国国民を一致団結させ、無制限な財政支出を可能にしようとした。そして、選ばれたスケープゴートが、日本人だった。
ルーズベルト大統領が日本との戦争を決断したのは、1940年の9月、日本が、北部仏印へ進駐し、日独伊三国同盟を締結した時のようだ。しかし、米国は民主主義の国であるから、大統領が戦争を決断したからといって、すぐに実行できるわけではない。第一次世界大戦の時に米国はヨーロッパの戦争に介入したが、犠牲が大きかった割には、得た利益は少なかった。その時の反省から、米国国民の圧倒的多数は、外国の戦争に介入することには反対だった。そして議員のほとんども、伝統的な孤立主義者だった。このため、ルーズベルト大統領は、国民に、米国が直接攻撃されることがない限り戦争はしないと約束せざるを得なかった。
そこで、日独伊三国同盟成立の翌月、知日派の海軍情報部極東課長であったマッカラム少佐[7]が、日本を挑発して米国への攻撃を余儀なくさせる策略を練った。以下は、1940年にマッカラムが作成し、ルーズベルト大統領の軍事顧問であったノックス大佐[8]が承認した覚書(所謂マッカラム覚書)の結論部分である。
現在の政治的見解では、米国政府はさらなる騒動なしで日本に対して宣戦布告できるとは考えられない。そして、私たちの側での活発な働きかけが日本人の態度を変えさせる可能性はほとんどない。したがって、次のような行動方針が提案される。
- A. 太平洋、特にシンガポールで英国の基地を使用するため英国と申し合わせる。
- B. オランダ東インド諸島での基本施設の使用と物資の取得についてオランダと申し合わせる。
- C. 中国政府の蔣介石にすべての可能な援助を与える。
- D. 長距離重巡洋艦の一部を極東、フィリピン、またはシンガポールに派遣する。
- E. 潜水艦の二師団を極東に派遣する。
- F. 現在太平洋に展開する米国艦隊の主力をハワイ諸島近くに配備する
- G. 日本による特に石油に対する過度の経済的譲歩の要求を認めることを拒むようにオランダに主張する。
- H. 大英帝国によって課されたのと同様の禁輸措置を日米間で行う。
これらの手段によって日本を明白な戦争行為を行うように誘導できれば、それに越したことはない。いずれにせよ、私たちは戦争の脅威を受け入れるために十分に準備しなければならない。[9]
このマッカラム覚書をルーズベルト大統領が読んだかどうかはわからないが、その後米国は、まるでマッカラム覚書に従うかのようにABCD包囲陣と呼ばれる経済制裁を強化し、戦争以外に選択肢がない窮地へと日本を追い込んだ。
真珠湾攻撃の計画は、1941年1月に山本五十六大将によって立案されたが、1941年11月5日の御前会議で「帝国国策遂行要領」をまとめた時点では、日本はまだ日米開戦を避けようと努力していた。ところが、米国側は、こうした機密文書の暗号を傍受・解読し、日本の手の内を見ながら、日本側が絶対に受け入れることができない「和平案」、ハル・ノートを提出した。これは、米国が日本に突きつけた事実上の宣戦布告だった。
スティネット[10]の『真珠湾の真実 ― ルーズベルト欺瞞の日々』(原題:Day of Deceit: The Truth About FDR and Pearl Harbor)によると、真珠湾攻撃の計画も、立案の時点で直ちに米国側に漏れたが、ルーズベルト大統領は、本当に日本が米国を攻撃してくれるかどうか心配していた。もし、日本がマライ半島やインドネシアといったイギリスやオランダの植民地だけを攻撃したなら、宣戦布告の大義名分を失うからだ。そこで、ルーズベルト大統領は、日本のスパイにハワイで調査を自由にさせ、ハワイに駐在する米国太平洋艦隊に日本軍の奇襲攻撃計画の情報を送らなかったばかりか、奇襲攻撃が事前に太平洋艦隊に悟られないように、太平洋艦隊を含めた連合国側の船舶の北太平洋地域での航行を禁止した。ルーズベルト大統領のこうした至れり尽くせりの配慮が実って、12月8日の真珠湾攻撃は大成功となった。
スティネットによるこの真珠湾攻撃事前察知陰謀説には批判もあるが、ルーズベルト大統領が事前に真珠湾攻撃をどれほど正確に予知していたかということは本質的な重要性を持たない。重要なことは、米国は平和を望んだのに、日本は一方的に卑怯な不意打ちをしたというこれまで米国が喧伝してきた真珠湾攻撃の公式見解が実際とは異なるということである。
アームストロング[11]の『「幻」の日本爆撃計画』(原題:Preemptive Strike: The Secret Plan That Would Have Prevented The Attack on Pearl Harbor)によれば、マッカラム覚書承認後に当たる1940年12月8日に、ルーズベルト大統領とモーゲンソー財務長官[12]は蒋介石[13]の代理人である宋子文[14]と面会し、長距離爆撃機の供与を提案した。そして、1941年7月23日には、ルーズベルト大統領は、中国に長距離爆撃機を供与し米国人パイロットを義勇兵として送り込み、日本を空爆する計画(Joint Board Plan 335)を承認した[15]。もっとも米国は対中支援よりも対英支援を優先したため、計画の実行は遅れ、結局、計画された「特別航空戦隊」が中国に送り込まれるよりも前に真珠湾攻撃が行われた。
スティネットは、ルーズベルト大統領が第二次世界大戦に参加したがっていたのは、世界の民主主義を守るためだったという理想主義的な解釈をしている。つまり、ナチズムから民主主義を守ることが本来の目的で、日本に米国を攻撃させたのは、「裏口からの参戦」のためだったという解釈である。しかし米国が対日宣戦布告をしたからといって自動的にドイツと戦争できるわけではない。実際、ドイツが独ソ不可侵条約を破ってソ連に侵攻した時も、日本は日ソ中立条約を守って、ソ連を攻撃しなかった。
もしもルーズベルト大統領の本来の狙いが、表向きの理念は別として、戦争という極めてインフレ効果のある公共事業を行うことで挫折したニュー・ディール政策を再開することにあるとするなら、戦う相手はドイツでなくてもよいということになる。もちろん、ドイツも相手にした方が公共事業の規模が大きくなるから、ルーズベルト大統領にとっては都合がよい。ルーズベルト大統領が枢軸国に対して無条件降伏を求め、条件付き講和を認めようとしなかったのも、できるだけ戦争を長引かせ、公共事業の規模を大きく維持したかったからではないのだろうか。
3. リメンバー・パールハーバー
ルーズベルト大統領は、真珠湾攻撃の二日前に昭和天皇宛てに戦争阻止のための親電を送っている[16]が、これは「和平の提案を拒否して、卑怯な不意打ちをした日本」を印象付けるためのアリバイ工作とみられる。ルーズベルト大統領の芝居は成功し、それまで参戦に反対していた議会はほぼ満場一致で対日参戦に賛成し、国民は「リメンバー・パールハーバー」を合い言葉に積極的に兵役に志願した。米国連邦政府の財政支出は、真珠湾攻撃があった1941年には205億ドル、42年には516億ドル、43年には851億ドル、44年には955億ドルと無制限に増えていったが、もう誰も文句を言わなくなった。そして、この挙国一致の戦争ケインズ主義のおかげで、米国は恐慌から脱出することができた。パールハーバーで、3000人近くの米国人が死亡したが、これも民主主義のコストだと思えば、安いものだとルーズベルト大統領は思ったに違いない。
戦争開始とともに、米国の日系人は、「戦時転住所センター」と呼ばれるところに強制収容された。アウシュビッツに強制収容されたユダヤ人のように虐殺されることはなかったが、米国でもドイツでも似たようなスケープゴート現象が起きたことは興味深い。米国人が考えているほど、当時の米国とドイツは異なっていなかったのである。
結論をまとめよう。狭義のニュー・ディールは失敗に終わったが、太平洋戦争をニュー・ディールの一環と考えるなら、公共事業によるデフレからの脱却という当初の目的は達成されたということができる。現在米国が行っている「テロとの戦い」は、半世紀前の「日本との戦い」によく似ている。私たちは、かつて米国人が使ったのとは違う意味で「リメンバー・パールハーバー」を合い言葉にしなければならない。
4. 参照情報
- ↑フランクリン・デラノ・ルーズベルト(Franklin Delano Roosevelt, 1882年1月30日 – 1945年4月12日):民主党出身の米国第32代大統領(1933年 – 1945年)。
- ↑ジョン・メイナード・ケインズ(John Maynard Keynes, 1883年6月5日 – 1946年4月21日):英国の経済学者。初代ケインズ男爵(1st Baron Keynes)。主著は、20世紀で最も影響力があった経済学の本と言われる『雇用・利子および貨幣の一般理論』。
- ↑“In a boom inflation can be caused by allowing unlimited credit to support the excited enthusiasm of business speculators. But in a slump governmental Loan expenditure is the only sure means of securing quickly a rising output at rising prices. That is why a war has always caused intense industrial activity. In the past orthodox finance has regarded a war as the only legitimate excuse for creating employment by governmental expenditure. You, Mr President, having cast off such fetters, are free to engage in the interests of peace and prosperity the technique which hitherto has only been allowed to serve the purposes of war and destruction.” John Maynard Keynes. “An Open Letter to President Roosevelt John Maynard Keynes.” December 16 1933.
- ↑アドルフ・ヒトラー(Adolf Hitler, 1889年4月20日 – 1945年4月30日):ドイツ国首相、および国家元首。国家社会主義ドイツ労働者党(ナチス)の指導者。著書に『わが闘争』。
- ↑Lawrencekhoo. “USA annual GDP from 1910-60, in billions of constant 2005 dollars, with the years of the Great Depression (1929-1939) highlighted. Based on data from: Louis D. Johnston and Samuel H. Williamson, “What Was the U.S. GDP Then?" MeasuringWorth, 2008.” Licensed under CC-0.
- ↑Lawrencekhoo. “U.S. Unemployment rate from 1910-1960, with the years of the Great Depression (1929-1939) highlighted.” Licensed under CC-0.
- ↑アーサー・マッカラム(Arthur H. McCollum, 1898年 – 1976年):米国海軍将校。日本(長崎)生まれで、1951年に米海軍から引退するまで、同盟海軍諜報部長、南西太平洋地域、諜報部長補佐、第七艦隊、そして第七艦隊諜報センターの指揮官を歴任した。
- ↑ダドリー・ライト・ノックス(Dudley Wright Knox, 1877年6月21日 – 1960年6月11日):米英戦争と第一次世界大戦中のアメリカ海軍の将校。
- ↑Arthur H. McCollum. “Memorandum for the Director: Estimate of the Situation in the Pacific and Recommendations for Action by the United States.” 7 October 1940. Wikisource, the free online library.
- ↑ロバート・スティネット(Robert B. Stinnett, 1924年3月31日 – 2018年11月6日):米国の写真家、作家。1942年から1946年に第二次世界大戦に海軍写真家として参加。歴史学者のゴードン・プランジュによる『明け方に眠った』と 『パールハーバーの秘話』を読んで真珠湾攻撃事前察知陰謀説に興味を持ち、独自に調査を行って、『真珠湾の真実 ― ルーズベルト欺瞞の日々』を上梓した。
- ↑アラン・アームストロング(Alan Armstrong, 1950年 – ):米国の航空弁護士、現役パイロット、国家交通安全委員会弁護士会の創設メンバー。
- ↑ヘンリー・モーゲンソー・ジュニア(Henry Morgenthau, Jr., 1891年5月11日 – 1967年2月6日):ルーズベルト政権下での財務長官の。ニュー・ディールおよび第二次世界大戦の際の資金の調達において中心的な役割を果たした。
- ↑蒋介石(蔣中正、1887年10月31日 – 1975年4月5日):中華民国の政治家、軍人。中華民国総統として、日中戦争、第二次世界大戦で日本軍と戦った。
- ↑宋子文(1894年12月4日 – 1971年4月25日)は中華民国の政治家、実業家。実の姉妹である宋慶齢・宋靄齢・宋美齢は、それぞれ孫文、孔祥煕、蒋介石と結婚した。
- ↑Alan Armstrong. Preemptive Strike: The Secret Plan That Would Have Prevented The Attack on Pearl Harbor Lyons Press. (2006/6/1). p. 118.
- ↑“ルーズベルト大統領の昭和天皇宛親電.” 1941年12月6日作成. Wikisource.


















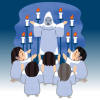



ディスカッション
コメント一覧
どうしてこのような史実は日本国民、及び世界に伝えられないのでしょうか? やはり、世界的にみて国の言動、行動はその国の知識人政治家だけの動きだと思うのですが、そのことについてどう思われますか?
太平洋戦争中、傍受された日本からの電報を閲覧できたアメリカ人はたったの36人でした。マッカラムの覚書を含め、作戦内容は、国家機密の名のもとに極秘扱になりました。現在、少しずつ情報公開が行われていますが、半世紀以上も前の出来事なのに、いまだに当時の記録の一部しか公開されていません。
なお、私は、アメリカの諜報機関が全ての重要な情報を正確に入手し、国際政治を超越的に操作しているとは考えていません。どの国家も、国際政治というパワーゲームの1プレーヤーに過ぎないというのが複雑系の考え方です。また、政治体制が民主主義的であるか否かを問わず、指導者がいつでも大衆を洗脳し、世論を操作できるわけではありません。
何時の頃からか、私の中では、表面は愛国精神はある。と装いながら
「日本は悪い国だ。」が本心となってしまっていました。
パールハーバーの奇襲をした日本人を好戦的で野蛮だ。としか考えられなかったからです。不勉強のため、このような説があると言うことを知りませんでした。
こうしたことを、知らないで、日本人である自分に劣等意識を持っている人は多いと思います。
このサイトを、広く宣伝して、そんな人の心のもやもやを払ってあげてください。お手伝いできるとよいのですがー。
ルーズベルトの推し進めたニューディールを今まで評価しておりましたが、成功の原因が日本への開戦とは・・
大変参考になりました。
全日本人に知らしめて下さい。
ニューディール幻想、永井氏のご指摘どおりです。
2008年のアメリカ金融恐慌に端を発する世界恐慌。またアメリカ金融からかというのが率直な意見。
アメリカのみならず先進国・新興工業国をまきこんだこの恐慌を乗りきる方法としてグリーンニューディールは全く効果がない。
2009年にアメリカにおける 産軍複合体解体 ・ 土地改革 ・ 労働条件の整備 を日本の判断を基準に断行してもらいたい。
なお、ワシントン裁判で平和に対する罪としてブッシュを絞首刑にしても全く効果がない。
ブッシュ政権の閣僚と産軍複合体およびあこぎな金融機関経営者を伝統的刑罰であった「流刑」として島流しとし、実質的な終身刑とする。
はじめまして。痛いテレビというブログの記事からこちらに流れてきました。
ニューディール政策については高校の世界史で習った程度の知識しかありませんでしたが、一月ほど前に関西のローカル番組で評論家の青山繁晴氏がオバマ政権の今後について触れた際に「アメリカでニューディールが成功したと思ってる人は殆ど居ない、アメリカは戦争で経済を立て直した」と発言したのを聞いてビックリした訳ですが、こちらの説明を聞いて納得しました。
最近、パールハーバーの陰謀はところどころで出ております
アメリカは、自由の国といいますが、やはり世界は、今も昔も戦勝国が支配するのだと思います
イラクのクェート進行からアメリカのイラク進行までもきな臭い話は飛んでいます
ところで、今回の世界同時不況ですが、最近、落ち着いてきとの報道が目に付きますが戦争でもないと解決しませんかね?
日本の失われた10年は、低金利による銀行の復活と海外輸出によるGNPの底上げだと思います
この世界同時不況前も内需は増えず、内需関連企業の業績は、さほど良くなかったと思います
世界同時となると輸出先、が無く(インド、中国に期待してるようですが)先が見えないような気がします
また、低金利にしても、企業は、借金をせず、内需は拡大せず、低金利を利用して躍進したのは、ある意味いかがわしとされる、MHKであったような気もします
いかがなものでしょう
ブッシュからオバマに大統領が変わることによって、米国の主戦場がイラクからアフガニスタンに変わりました。オバマを平和主義者と勘違いしていた人は、オバマ政権の誕生により、米国が対外戦争から全面撤退すると考えていたようですが、オバマが選んだ道は、国際協力を得ることが難しいイラク戦争に代わって、国際協力を得ることが容易なアフガン戦争に力を入れるということでした。だから、オバマ政権の誕生により、米国の戦争ケインズ主義が終焉を迎えたと言うことはできません。今後オバマ政権は、日本に対して、アフガンの治安回復のためという大義名分の下、資金協力を要求してくるでしょう。
はじめまして。
当サイト(伝記.com)では、
ルーズベルトについて取り上げたページを設けており、
その中で、永井氏のニューディールに関する見解を、
一部、紹介させて頂きました。
日本では「ニューディールは、偉大な改革」という
「ニューディール神話」が、どちらかといえば主流のようです。
たしかにニューディールが、
ある程度の効果があったのは事実ですが、
「ニューディールは、不十分な改革にすぎなかった」という、
もう1つの事実を知るためにも、
こうしたニューディール否定論が、必要だと思いました。
はじめまして
先生の慧眼には驚くばかりです。現在、ブログを少しずつ読み進めています。
ところで質問ですが、あの当時の日本のとるべき道としてどのようなものがあったのでしょうか?
”太平洋戦争における保守と革新”をみると、国内事情的にも国外事情的にも戦争は避けられなかったかもしれませんが・・・
盧溝橋事件の後、中華民国と早期に和解し、かつ適切なリフレーション政策を取っていたならば、第二次世界大戦に巻き込まれることを回避できたと思います。
大統領選でトランプが当選しました。彼は公共事業の増大を政策にかかげていますが、米国経済はデフレでもなければ失業率が高いわけでもありません。このような政策は今の米国で支持されうるのでしょうか?
ヒラリーが選ばれていたとしても、彼女も「大きな政府」を目指している点では同じで、好景気にもかかわらず米国民が「大きな政府」をなぜ支持するのかわかりません。巷で言われているように、やはりグローバル化による格差が問題なのでしょうか。
米国は、リーマン危機以来、量的金融緩和によるリフレにある程度成功することができましたが、2015年には、新興国経済の失速、原油価格の下落などにより、インフレ率が 0.12% とリーマン危機以来となる歴史的低水準にまで下落しました。トランプ、クリントン両候補が選挙戦で公共投資の拡大を主張したのは、そうでもしなければデフレになるかもしれないと懸念したからなのでしょう。
量的金融緩和は資産インフレをもたらし、米国の株価は史上最高値に到達しています。それに伴う資産効果があるとはいえ、恩恵は資産家に偏っており、貧しい労働者にはあまり恩恵がありません。またIT産業の進化により、テクノ失業(technological unemployment)が起きており、優秀なプログラマーが引っ張りだこになる半面、スキルのない労働者は失業もしくは低賃金労働に甘んじています。
かくして、資産もスキルもない下層労働者の間で不満が高まっています。トランプ、クリントン両候補が公共投資の拡大を主張したもう一つの理由として、こうした下層労働者に高賃金の仕事を与えることで、不満を解消しようとしたことを挙げることができます。
今回共和党の大統領が誕生し、議会も共和党が過半数を維持しました。共和党が力を入れる公共投資は国防です。実際、トランプも軍備の大幅拡張を主張しています。そのため株式市場では、選挙結果を受けて国防関連の株価が急騰しています(Wall Street Journal. “Defense Stocks Rise on Donald Trump Victory – Republican control of Congress could lead to an increase in the Pentagon’s war fund“. Nov. 9, 2016)。ただし、トランプ本人は実際に戦争することには消極的ですが。
米国の下層労働者は、絶対的貧困にはないものの、相対的貧困という点では深刻な立場に置かれており、「貧しきを憂えず、等しからざるを憂う」というのが人間のさがですから、とりわけ中間層から脱落した白人労働者が、かつての栄光を取り戻そうとして、今回“Make America Great Again”をキャッチフレーズにしたトランプを熱心に支持しました。
共和党は金持ちの味方だから、貧乏人が共和党に投票するのは非合理とリベラルは思うかもしれませんが、没落した白人労働者はそうは考えないでしょう。ピケティは、大規模な戦争は富を破壊し、資本家たちを没落させることで格差を縮小すると言っていました。だから軍備拡大を公約にする共和党を支持することは、プロレタリア型右翼の心情として、それほど不自然なことではありません。
「裏切られた自由」というフーバー元大統領による大著が、日本でも発刊されました。ルーズベルトの再評価する必要がありますね。
分かりやすく納得できる解説ですね。
伊藤貫氏によれば、米国は国内事情で世界展開するだけの軍事費を今後拠出することができず、中国の台頭も抑えられないので、オフショア戦略(東アジアから撤退)を選択する可能性が一番高いということです。
用済みの日本(中国の植民地となる日本には今後兵器を買わせることもできなくなる)を戦場にして、最後の一儲けを考えている可能性はあると思われますか?
(朝鮮半島は核武装しているので戦場にはできません)
伊藤貫氏が『自滅するアメリカ帝国―日本よ、独立せよ』や『中国の「核」が世界を制す』などで言うように、日本は今後自国を防衛するために、米国だけに依存するというわけにはいかなくなるでしょう。もっとも、それは財政問題だけが原因ではないと私は考えています(財政問題はレーガン政権の時からすでに深刻になっている)。ではなぜ米国は孤立主義になっているのかに関しては、今度私が出版する『エントロピーの理論』の中で説明することにします。
将来米国が日本との同盟関係を解消したとしても、日本が中国の属国とならないようにするには、日本と同様に中国との間に領土問題を抱えているインドと同盟を結べばよいでしょう。インドは既に核保有国であり、日本はインドと共同で核兵器を開発することで中国を牽制することができます。
確かに日本人からすると、不満の捌け口がないユダヤ人のような辛い気持ちになるのは大いにわかるんだけど、
これ客観的に見れば、ルーズベルトは自国を強くするための策として的確な行動を取ったに過ぎず、日本は手の平で踊らされていたともとれるのよね。
、、、まあ、ルーズベルト本人は後世で日本人にどれ程悪く言われようとも納得するだろうから、俺も文句は言い続けるけど。