夫婦別姓問題の解決法
日本では、結婚に際して、夫婦は同じ姓を名乗らなければならないということになっています。夫が妻の姓を名乗ってもよいのですが、ほとんどの場合、改姓するのは妻の方というのが現状です。女性が、結婚後、専業主婦として家事と育児に専念していた時代では、改姓は大きな問題となりませんでした。しかし、女性の社会進出が進むにつれて、姓のアイデンティティを維持できない現行制度の弊害が大きくなってきました。そこで、選択的夫婦別姓制度を認めるべきだという主張が出てきたのですが、反対論も根強くあります。本ページでは、この問題を解決するための私の案を提示したいと思います。

1. 夫婦同姓か夫婦別姓か
夫婦別姓(夫婦別氏)とは、夫婦が結婚後異なる氏姓を称することです。中国、朝鮮半島、ベトナムといった中国文化圏では、伝統的に夫婦別姓です。日本もかつては中国の影響を受けて、夫婦別姓でした[1]。しかし、明治維新以降、不平等条約改正のため、脱亜入欧が国策となりました。その結果、西洋風に夫婦同姓となったのです。
明治9年に出された太政官指令には、「婦女人ニ嫁スルモ仍ホ所生ノ氏ヲ用ユヘキ事」とあります。明治政府も当初、妻が実家の氏を名乗るという旧来の伝統に従っていたということです。ところが、明治31年にフランスの民法を模範に制定した民法の第243条第2項では、「戸主及ヒ家族ハ其家ノ氏ヲ称ス」とあり、家族は妻も含めて、すべて同じ氏を名乗ることになりました。昭和22年に、民法が改正されました。「家」とか「戸主」とかは、封建的で好ましくないということで、第750条は、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」となったのですが、相変わらず、家族の氏は統一しなければならないという規定が続いています。
1975年に国連の後援で第1回世界女性会議が開かれ、女性の地位向上のための世界行動計画が採択されました。それ以降、夫婦別姓や結合姓を選択する自由を認める法改正が欧米で行われるようになりました。日本が模範にしていた欧米が選択的夫婦別姓を認めるようになったのですから、日本もこれを模倣しようとする動きが出たことは自然なことです。1996年に法務省は選択的夫婦別姓を含む民法改正法案を国会に提出しようとしました。ところが、保守派の国会議員が家族の崩壊につながると言って反対し、法案提出は見送られました。それから25年が経ちましたが、選択的夫婦別姓はまだ実現していません。
日本には日本の事情があるから、欧米の動きにいちいち追従する必要はないという人もいるでしょう。しかし、実は、夫婦同姓の弊害は、欧米よりも日本の方が大きいので、制度変更の必要性はむしろ日本の方が大きいとすら言えます。欧米では、友人どうしで呼び掛ける時に使うのは、ファースト・ネーム、つまり日本語の名にあたるギブン・ネームなので、結婚してファミリー・ネームが変わっても、日常生活に大きな不便をきたしません。ところが、日本では、そうしたファースト・ネームとして機能しているのは姓の方です。実際、姓はパーソナル・ネームの最初に書かれ、通常私たちは姓だけで個人を識別しています。例えば、私のことを「俊哉」と呼ぶのは私の家族ぐらいで、それ以外の人は私をもっぱら「永井」とだけ呼んでいます。だから、姓の変更は、自己同一性の大きな喪失となってしまいます。
これまで行われた世論調査を見ると、選択的夫婦別姓の賛成派と反対派がほぼ拮抗しています。選択的夫婦別姓に賛成の人でも、多くは、家族が同じファミリー・ネームを共有する方が望ましいと思っています。賛成派と反対派の双方を説得するためには、一方で家族の氏を一つに統一することで家族の崩壊を防ぎ、他方ですべての人、とりわけ女性が一生を通じて自己同一性を失わなくてもすむ新しい制度を考案しなければなりません。新しい制度と言っても、保守派を納得させるためには、それは日本の伝統に反する制度であってはいけません。そこで次の章では、日本の氏姓の歴史を振り返りながら、解決策のヒントを探りたいと思います。
2. 氏姓と名の歴史的変遷
明治以前の日本人の呼称は、今よりも複雑でした。例えば、徳川家康の正式名称は、徳川次郎三郎源朝臣家康で、このうち、「徳川」が名字、「次郎三郎」が字(あざな)、「源」が氏、 「朝臣(あそん)」が姓(かばね)、「家康」が諱(いみな)です。なぜこのように複雑になったのか、その経緯を説明しましょう。

英語を借用して分類すると、パーソナル・ネームはギブン・ネームとファミリー・ネームに大別できます。家康は、ギブン・ネームに相当する実名ですが、諱=忌み名という表現が示す通り、死後実名を口にすることは憚れました。生前も、家康の名を呼ぶことができたのは、親や主人など目上の者に限られていました。そこで実名の代わりに通称が使われたということです。家康は、幼い時は、竹千代という幼名(ようみょう、ようめい、おさなな)で呼ばれ、元服すると、次郎三郎という字(あざな)で呼ばれました。こうした実名敬避の習俗は中国にもあり、実名とは別に字が使われていました。日本はそれを模倣したというわけです。中国における最古のファミリー・ネームは姓です。姓から氏が分かれ、日本では、さらにそこから名字が分かれました。こういう次第で、日本のパーソナル・ネームは複雑化したのです。
中国では、周以前の時代、姓(せい)は母系の出自を表していました。女が生むと書いて姓なのですから、これが母方の出自を表す漢字であることは語源的にも理解しやすいかと思います。古代の結婚は、現代の結婚ほど厳格ではなかったので、母が誰かはわかっていても、父が誰かはわからないというケースが多かったから、姓が使われたのでしょう。戦国時代になると、姓に代わって父系で継承される氏(し)が重要視されるようになりました。秦漢以降の時代、姓と氏の区別が失われ、父系で受け継がれる氏が姓と呼ばれるようになりました。秦を建国した始皇帝は、この変化の過渡期を生きた人物です。彼の諱を政と言いますが、父の姓である嬴(えい)を使って、嬴政と称したり、母の氏である趙(ちょう)を使って、趙政と称したりしていました[3]。過渡期特有の混乱を観て取ることができます。
古代の日本は、母系社会的側面を持った双系制であったと考えられています。それは、平安時代まで妻問婚(つまどいこん)の習慣が残っていたことからも理解できることです。妻問婚とは、夫が妻の家に通う婚姻の形式で、子は妻の家で育てられます。それゆえ、子が母方の出自を名乗ることは当然あったでしょう。実際、例えば、物部守屋(もののべのもりや)は、『日本書紀』では、物部弓削守屋(もののべゆげのもりや)と記されています[4]。物部は父方の出自を、弓削は母方の出自を示しています。
物部守屋を倒して権力者となった蘇我馬子も、蘇我氏という氏とは別に、姓を持っていました。馬子は、推古天皇に葛城県の割譲を要求した際、「葛城県は、もともと私の本拠地だから、その県名を自分の姓名にしている[5]」と述べています。馬子の父は、蘇我稲目(そがのいなめ)ですが、母が誰かはわかりません。しかし、この発言から推測すると、母は有力豪族の葛城氏の娘であったと言えそうです。それゆえ、蘇我氏に加えて葛城姓を称していたのでしょう。

その後、日本でも、中国と同様に、父系で継承される氏が母系の出自よりも重視されるようになりました。684年に天武天皇が八色の姓(やくさのかばね)を制定して以降、姓は、可婆根(かばね)を意味する漢字としても使われるようになりました。カバネは、母の出自ではなく、氏の格式を示す尊称です。日本語の「かばね」には骨とか尸(しかばね)[7]とかいった意味があるので、新羅の骨品と似た身分制度と考えられています[8]。このように、日本のカバネは中国における本来の姓とは異なる概念であるので、注意が必要です。
平安時代になると、朝廷から与えられる氏姓だけでは、家系の区別が十分できなくなりました。そこで、公家や武士たちは、出身地や本貫地(ほんがんち)に因んだ名字を私的に名乗るようになりました。かくして、日本では、中国や朝鮮とは異なり、非常に多くの種類のファミリー・ネームが生まれたということです。1871年(明治4年)に、姓尸不称令が出され、姓(せい)すなわち氏と尸(し)すなわちカバネが廃止となり、ファミリー・ネームは名字だけになりました。例えば、私の父方の祖先の場合、大江朝臣長井が永井になったということです。
以上の氏姓と名の歴史から二つの重要な事実を学ぶことができます。一つは、父系で継承される氏と母の出自を表す姓は、中国でも日本でも本来別であったということです。もう一つは、東アジアには実名敬避の習俗があるため、実名が欧米のファースト・ネームの様には機能していないという事実です。この二つの事実に基づいて、夫婦別姓問題を解決する新しい方式、氏姓名方式を次の章で提案したいと思います。
3. 氏姓名方式による解決
前の章で指摘した二つの事実を踏まえた上で、夫婦別姓問題を解決するために二つの提案をしたいと思います。一つ目は、氏と姓を区別し、氏をファミリー・ネーム化することです。もう一つは、姓と名を結合して、ギブン・ネーム化するということです。結果として戸籍には氏姓名という三つのネームが記載されるので、これを従来の氏名方式とは区別して、氏姓名方式と名付けることにします。
氏姓名方式だと、結婚すると夫婦が同氏別姓となります。これを具体例で説明しましょう。今、田中太郎さんと山本花子さんが結婚したとします。家族の氏は夫の氏で統一し、子供には母の姓を付けることにします。そうすると、戸籍に記載される二人のフルネームは、田中氏田中太郎と田中氏山本花子になります。次に二人に隆君と愛ちゃんという二人の子が生まれたとします。子供たちの戸籍上の名前は、田中氏山本隆と田中氏山本愛となります。

家族の氏には夫の氏を使い、子の姓には妻の姓を使うというのは、古代の伝統にしたがった由緒正しい方法ですが、常にそうしなければならないということではありません。現在多くの世帯がやっているように、すべての姓を夫の姓にしてもかまいません。その場合、子供たちの戸籍上の名前は、田中氏田中隆と田中氏田中愛となります。
また、家族の氏も夫の氏を使わなければならない必然性はありません。妻の氏を家族の氏にして、その代わり、子供の姓として夫の姓を採用するというのでもよいでしょう。家族の氏をどちらの氏にするか、生まれてくる子の姓をどちらの姓にするかは、結婚する前に決めておけば、後で揉め事にならずに済みます。
氏姓名方式は、夫婦別姓反対派と賛成派の両方を説得することができます。夫婦別姓反対派は、別姓を認めると家族の一体性が失われると主張していました。しかし、氏姓名方式では、結婚の場合でも、養子縁組の場合でも、家族の氏は常に一つに統一されるので、反対派の批判をかわすことができます。夫婦別姓だと「田中家一同」のような集合名詞的な表現ができないし、田中家の家族墓を作ることもできませんが、氏姓名方式なら可能です。賛成派は、「結婚後も姓を変えたくない」と言う女性の自己同一性を問題にしていましたが、これは姓名が維持されることで守られます。結婚しようが離婚しようが、養子縁組をしようが離縁しようが、自分を生んだ父母が変わることはないのですから、姓は名とともに一生同じであるべきです。日本では、個人のアイデンティティが姓によって最も幅広く規定されるので、姓を名とともにファースト・ネーム化する意義は大きいと言えます。
独身だから興味がないという人にも、姓名のファースト・ネーム化にはメリットがあります。それは、パーソナル・ネームのローマ字表記が日本語表記に近くなるというメリットです。現在、日本政府は、日本人の姓名のローマ字表記を“YAMAMOTO Hanako”というように、姓名の順番で書くことを推奨しています[9]が、ほとんどの日本人は、“Hanako Yamamoto”というような欧米風の順番で自分の姓名を書いています。姓を最初に書くと、たとえ大文字で書いたとしても、ギブン・ネームと誤解されてしまうからです[10]。もしも姓名全体をハイフンでつなげてファースト・ネーム化するなら、“Yamamoto-Hanako Tanaka”というように、氏は後置されるものの、姓名は転倒することなく、日本語と同じ順序となります。ファースト・ネームとしては長すぎるというのなら、略称を使うとよいでしょう。海外では、「エリザベス Elizabeth」などファースト・ネームが長い場合、「ベス Beth」といった略称を用いる習慣があるので、“Yamamoto-Hanako”の代わりに、“Yamamoto”という略称を使っても問題はないはずです。姓をファースト・ネームとして使用することは、日本国内の習慣と合致します。
最後に実務的な話になりますが、変更の影響を最低限に抑えるための移行措置について話しましょう。新しい方式は、これから結婚する夫婦あるいはまだ子が生まれていない夫婦にのみ適用されるべきです。既に子がいる家庭では、氏と姓は自動的に同じものとして戸籍に記載されます。但し、結婚や養子縁組により姓を変更した者に限り、姓を旧姓に戻す権利があるとします。こうすることで、移行に伴う混乱を最小限にすることができます。こうすることで、移行に伴う混乱を避けることができます。
4. 参照情報
本稿を基に作成したプレゼンテーション動画です。
- 八木秀次, 宮崎哲弥他『夫婦別姓大論破!』洋泉社 (1996/10/1).
- 平野喜久『夫婦別姓って何?~反対派のための反論ネタ~あなたは選択制でもダメな理由をきちんと説明できますか?』ひらきプランニング株式会社 (2013/4/3).
- 平野まつじ『選択的夫婦別姓 ―予想される大混乱―』幻冬舎 (2019/2/1).
- ヨス『「夫婦別姓」を20年間実践してみたら……』2020/10/28.
- 尾脇秀和『氏名の誕生――江戸時代の名前はなぜ消えたのか』筑摩書房 (2021/4/6).
- ↑但し、それはあくまでも建前上の話で、江戸時代の武家では、実際には妻は、儒教の伝統に反して、実家の氏ではなくて、夫の氏を称していたようだ。これに関しては、以下の論文を参照されたい:井上操「法律編纂ノ可否」in 星野通『明治民法編纂史研究』ダイヤモンド社 (1943/1/1). p. 402.
- ↑狩野探幽. “徳川家康肖像画." 大阪城天守閣. Licensed under CC-0.
- ↑「生於趙故曰趙政」司馬貞『史記索隠』巻二. 秦始皇本紀第六.
- ↑「物部弓削守屋大連・大三輪逆君・中臣磐余連、倶謀滅佛法、欲燒寺塔幷棄佛像」『日本書紀』敏達天皇十四年夏六月.
- ↑「葛城県者元臣之本居也故因其県為姓名」『日本書紀』推古天皇三十二年冬十月.
- ↑Lincun. “国土交通省 国土数値情報." 行政区域 (N03)・湖沼 (W09). Licensed under CC-BY-SA.
- ↑尸は屍とも書き、死体を意味する。姓尸不称令に見られるように、カバネには尸という漢字があてがわれることもあった。
- ↑『記紀』は、八色の姓が制定される以前から臣や連といったカバネがあったように書いているが、金石文では確認されていない。それゆえ、八色の姓は、新羅の骨品制を模したものではないかとも考えられている。新羅の骨品との関係については、以下の論文を参照されたい。孫大俊「新羅の骨品と日本のカバネについて」『法政史学』 no. 61 (March 2004): 69–79.
- ↑首相官邸「公用文等における日本人の姓名のローマ字表記について」令和元年10月25日.
- ↑ヨーロッパで、ファミリー・ネームがファースト・ネームになるのは、ハンガリーだけである。ハンガリー人は、ウラル語族のハンガリー語を話す東方起源の民族であるため、ヨーロッパとは異なる文化を持っている。



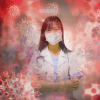



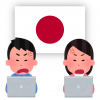











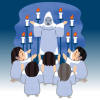


ディスカッション
コメント一覧
動画拝見しました。整合性が取れていて賛成派、反対派のどちらにとっても良い案だと思います。
ただ、夫婦別姓に関する話はTwitterなんかを見てる感じだと陳腐なイデオロギー的主張として扱われてるようで建設的な議論とはかけ離れていますから、永井さんのこの案にまともに耳を傾ける人間がどれだけいるか…。本当に問題なのはその辺じゃないですかね。
立法の権限を持っているのは、Twitter のユーザーではなくて、国会ですから、国会で与野党が現実的な解決策で合意すればよいかと思います。
ちなみに、今年の3月30日に自民党の森雅子前法相が参院法務委員会で、結婚した際に夫婦双方の姓を戸籍に書き込むミドルネーム案を出して話題となりました。
このミドルネーム案は、2019年に私が提案したものに近いのですが、リンク先のページの2021年追記にも書いたとおり、離婚した時の子供の氏姓や養子縁組での氏姓といったマージナルなケースで問題がありそうなので、今回の動画では、2008年の当初のアイデアに近い形で提案をしました。
夫婦別姓が望ましいと思うのなら事実婚を選択すればよい。というよりも、法律婚制度を廃止すべきなのだ。こう書くと「子どもの養育ガー」と反対するだろうが、今だって「認知」という制度がある。(「認知の訴え」という制度だってある。)。法律婚の存在理由は、子の養育のために離婚しづらくする、というところにあるが、不仲な両親のもとで育つ子どもは、シングルマザーの子どもよりむしろ不幸なのではないか。
子供は養育費さえあれば育つとお考えでしょうか。一人親(シングル・マザーやシングル・ファーザー)の家庭で育った子は、両親のもとで育った子よりも非行に走る割合が高いという傾向があります。一人親家庭は低所得ゆえに子供が犯罪に手を染めやすいと思われがちですが、以下の論文によると、一人親家庭の所得の低さが子供の犯罪率の高さに寄与する割合は低く、たんに金だけの問題でないとのことです。
「低所得や経済的不利益を超えたもの」が何であるかはわかりませんが、やはり両親が存在することは、子供の心の発達にとって重要な役割を果たしていると言えそうです。
江戸時代以前は公家や将軍家・大名家などの上流階級において夫婦別姓でも社会的な問題・混乱が生じなかった理由は何でしょうか?考えるに昔は女性が実名の署名がついた書類を書くことがあまりなかったためでしょうか?例えば源頼朝の正室の名前は一般的には北条政子であり、「源政子」ではありません。「源」は氏で「北条」は苗字と言う違いがあります。
夫婦別姓ではないことで起こる問題として、ある女性の苗字が珍しい苗字でかつ1人娘であり、どうしても苗字を残すために婿養子が必要になる。そんな中結婚を考えている交際中の男性に事情を説明して、「婿に入ること」が結婚の条件として相手の男性の親族にも説明されたが、男性は1人っ子であるから婿入りができないと親族が拒否。どうしても婿入りするなら男性の親類の中から別の人物を男性の家へ養子に入れないといけないが、養子になってくれる候補者がいない。養子の候補は渦中の男性の血縁の男性に限るとの事情。これにより結婚が厳しいと言うこともあり得ます。このような事情で結婚が遅れている女性が少なからずいると思います。あるいは結婚ができないまま数十年後に養子をとるにしてもすぐに見つかるとは限りません。
本文に書いたとおり、東アジアには実名敬避の習俗があるため、親や夫以外が女性の実名を口にすることはほとんどありませんでした。北条政子は、平という氏や北条という名字を冠して呼ばれることすら少なく、周囲からは御台所と呼ばれていました。一般的に言って、日本人は人を呼ぶ時、その人が居住する場所に因んだ替名を使うことがあります。御台所もそうですし、天皇を「御門」、大名を「御屋形様」、貴人の妻を「奥方」と呼ぶこともそうです。日常的に替名を使っているなら、家の一体感を出すために氏を統一する必要性はあまり感じられないことでしょう。
夫婦別姓の前に、戸籍制度を廃止すべきでしょう。マイナンバー(カード)があれば、血縁関係を管理できるでしょう。政策実行の順序を間違えてはいけません。
市町村ごとに紙媒体で管理している戸籍は廃止するべきでしょうが、多くの政策が世帯単位で行われている以上、マイナンバーのデータベースから抽出される世帯単位の電子戸籍は今後もクラウド上で活用されるべきでしょう。
中国や韓国では夫婦別姓と聞きます。そうなると中国や韓国では「婿養子」という制度・概念が存在しないのはでは?と思いますが、韓国の場合は「娘1人しかいない夫妻」が、家族・親族構成上の理由で夫の姓を継ぐ立場の男性(韓国では子供が男性であっても女性であっても父親の姓を生涯名乗る)が必要であっても、単純に親類以外の男性を養子にしても結婚を伴う婿養子にはできないのでしょうか?
韓国にも、1990年に禁止されるまで、婿養子による戸主承継があったようです。これに関しては、床谷文雄著「韓国家族法の改正動向 : 養子法を中心にして」『国際公共政策研究』第6巻第2号を参照してください。
事実婚の唯一のデメリットとは、相続権の不存在である。しかし、これは有効な遺言をすることにより回避することができる。ニッポンで事実婚が流行しないのは、戸籍が存在するからである。事実婚だと世間体が悪いからね。なお、韓国ではすでに戸籍が廃止されたそうな。
経団連が夫婦別姓を要求する理由とはなんだろうか。それは旧姓使用の女性従業員が海外出張をする際に、入国審査でハネられたり、ホテルで宿泊を拒否されることがあり、企業の利潤追求に支障が出ているからである。これからはオンナの時代なのだから、自民党は経団連の主張を丸呑みすべきである。