無限性のコペルニクス的転回
微積分学が創設された当時、極限は無限小や無限大といった無限概念を用いて求められていた。しかし、初期の頃の手法には矛盾が含まれており、この矛盾を解消するために ε-δ(イプシロン-デルタ)論法や超準解析などの方法が考案された。数学者たちは自覚していないが、これらの方法は、カントの超越論的観念論によって成し遂げられた哲学的なパラダイム転換によって基礎付けられる。すなわち、現代の方法は、「無限自体」の認識を断念し、《無限の認識》を《認識の無限》へと転換するコペルニクス的転回によって、無限のパラドックスを解消しているのである。

1. 極限における無限の問題
無限とは何かという問題は、古代ギリシャのゼノンが提起して以来、重要な哲学的問題であったが、アイザック・ニュートンやゴットフリート・ライプニッツが17世紀に微積分学を創設したことで、改めて考えられることになった。もっとも当時は、関数の極限を求める際の無限小(infinitesimal)や無限大(infinity)の扱い方は粗雑であった。
当時の方法にどのような問題があったかを、f(x)=x2 の導関数を求めるという簡単なケースで確認しよう。一般に導関数は、x が h だけ増えた時の f(x) の増加率を微分商(difference quotient)として表し、h が限りなくある値に近づくときの微分商の極限を求めることで得られる。2次関数の導関数は、以下のようになる。
hで約分すると、
となる。ここで、h が 0 に近づくと、2x に近づくので、
という結論になる。
こうした極限の求め方は、今でも初心者向けの解説に使われることが多いが、最初 h はゼロでないという前提で約分を行いながら、後で h をゼロとみなしているのだから、矛盾していると言わざるをえない。|h| が無限大になる場合も、その逆数 1/h が無限にゼロに近づくのだから、同じような問題が生じる。
ニュートンが『プリンキピア』を出版したのは1687年であるが、1734年には、ジョージ・バークリーが、この点を指摘して、ニュートンを批判した[1]。この批判を回避するために考案されたのが、ε-δ 論法である。
2. ε-δ 論法による問題の解決
ε-δ 論法は、オーギュスタン=ルイ・コーシー[2]、ベルナルト・ボルツァーノ[3]の試みを経て、1861年にカール・ワイエルシュトラス[4]によって完成された。ε-δ 論法では、無限小の概念を用いずに極限を求めることができるというのが一般的な認識である。
先ほどの例を、ε-δ 論法を用いて、証明しよう。どのような正の実数 ε に対しても、
となるような正の実数 δ が存在する。この時、この関係を満たすどのような h に対しても、
であるから、
という ε-δ 論法により、
と言うことができる。
このように、ε-δ 論法においては、「限りなく小さくなる」という表現が直接出てこないのだから、ε-δ 論法は、無限概念の追放に表面的には成功している。しかし、ε 自体が無限小ではないにしても、その代わりに、ε は全称記号(∀)で全称量化されている。したがって、無限は極限から消滅したのではなくて、ε 自体が無限に小さくなるという際限の無さから、ε により小さな数値を代入し続ける作業の際限の無さへと変化しただけと評することができる。
ε-δ 論法の開発者自身が自覚していたことではないが、ε-δ 論法の意義は、極限における有限と無限を分割し、後者を認識対象の属性から認識作用の属性へと振り替えたところにある。そして、それは、カントが『純粋理性批判』で行ったコペルニクス的転回とよく似ている。コペルニクス的転回とは、本来、「観察された運動を天空の諸対象の中ではなくて、その観察者の中に求めること[5]」であり、形而上学においては、無制約者を認識対象ではなくて、認識作用に求める思考の転回である。
もし私たちの経験認識が物自体としての諸対象に従うものと想定されるなら、無制約者は矛盾なしには全く考えられないこと、これに対して、私たちに与えられるままの事物についての私たちの表象が、物自体としての事物に従わず、これらの対象がむしろ現象として、私たちの表象の仕方に従うと想定すれば、矛盾はなくなること、またしたがって、無制約者とは、私たちが知る限りの事物については見出されないが、おそらく私たちの知らない範囲の、すなわち物自体としての事物について見出されるのでなければならないことが知られるとすれば、明らかに私たちが最初たんに試みとして想定したこと[コペルニクス的転回]が基礎付けられことになる。[6]
この引用の後半部分からわかるように、カントは、物自体は無限(無制約的)と推測していた。しかし、カントがそう主張したように、私たちが物自体について何も知りえない以上、物自体が無限かどうかも分からないと言わなければならない。むしろ、この引用の前半部分に書かれているように、無限という無制約者は、表象される対象ではなくて、表象する仕方に求められなければならない。
無限分割が可能かどうかという問題は、カントの『純粋理性批判』では、宇宙論的理念の第二番目の二律背反を帰結する。カントによれば、空間の無限分割の原理は、認識対象を構成する原理ではなくて、認識作用を統制する原理である。そして、無限分割は可能であり、かつ可能でないという二律背反は、統制的原理を構成的原理と誤解することで生じる仮象である[7]というのがカントの結論である。
ε-δ 論法の開発者の一人、ボルツァーノは、もしもこのようにカント的に解釈されるのを聞いたなら、きっと異議を唱えたことだろう。物自体の認識を断念し、認識の根拠を主観の側に求めたカントとは異なり、ボルツァーノは、命題自体(Satz an sich)を彼の知識学(Wissenschaftslehre)の対象にした客観主義的な哲学の提唱者だったからだ。彼が『無限のパラドックス』という著書を書き、半直線が無限なら、その半直線に有限な長さの線分を足したものは、最初の無限よりも長いのかとか、直線は無限の長さを持つ半直線よりも無限の長さの分だけ長いのかといった問題を提起し[8]、無限がパラドックスを帰結することを指摘したのも、彼が無限をコペルニクス的に転回しなかったことが原因である。
無限大とは任意の数よりも大きな数であるが、この客観的な定義をコペルニクス的に転回するならば、無限大とは大きすぎて認識主観にとって計測不可能な大きさという主観的な定義になる。この定義で解釈すると、半直線も半直線プラス線分も直線も長すぎて長さを計測できず、したがって長短の順番もわからないという結論になり、ボルツァーノの逆説も逆説的ではなくなる。
ε-δ 論法の開発者あるいは解説者が、ε-δ 論法によって極限から無限概念を排除することに成功したと信じていたのも、真理とは認識主体とは独立に認識対象に帰属するという素朴な客観主義を前提にしていたからだということができる。無限を認識対象から認識作用へと排除することで、無限を目立たなくさせることはできるが、無限はなくなったわけではない。ε-δ 論法は有限と無限を区別した点で正しかったが、無限が排除されたのではない以上、有限と無限の区別を維持しつつ、無限を再び可視化する必要が出てくる。1960年代から登場した超準解析の意義はそこにある。
3. 超準解析による問題の解決
超準解析(Non-standard analysis)は、1966年にアブラハム・ロビンソン(Abraham Robinson)がその考えを公表して[9]以来、無限小や無限大を数学的に厳密に扱うアプローチとして注目されている。ジェロム・キースラー(Howard Jerome Keisler)が超準解析に基づく分かりやすい教科書、『初等微積分学(Elementary Calculus)』をオンライン上で無料公開しているので、それをもとに簡単に紹介しよう。
超準解析においては、無限小や無限大を扱うために実数概念が拡張され、実数の集合に無限小や無限大の集合を含めた数の集合は超実数体と呼ばれる。超実数のうち、正の無限大と負の無限大は無限の超実数(infinite hyperreal number)と呼ばれ、それ以外の、二つの実数間に存在する超実数は有限の超実数(finite hyperreal number)と呼ばれる。無限小は有限の超実数ではあるが、0 以外は実数ではない。0 ではない有限の超実数 hは、限りなく 0 に近く、h ≈ 0 と表記される。
実数と超実数の関係は、実数と複素数の関係に類似しており、複素数を実部と虚部に分けることができるように、超実数は実数である標準部分(standard part)と実数ではない超実数である非標準部分(nonstandard part)に分けることができる。無限の超実数には標準部分がないが、有限の超実数には標準部分があり、「実数+無限小」の標準部分は、そこから無限小を取り除いた実数に等しい。極限は、変化が無限小の時の変化率の標準部分と定義する。
以上の知識を踏まえて、超準解析によって、f(x)=x2 の導関数を求めてみよう。
h は、限りなくゼロに近いが、ゼロではないとする。
その時、
であるから、導関数は、その標準部分を取って、
となる。
超準解析による方法は、ε-δ 論法と比べると、ニュートンやライプニッツの方法に近いように見えるが、実数と無限小/無限大を峻別している点で同じではない。とはいえ、実数と無限小/無限大がどのような関係なのかは超準解析において明らかではない。0 と最小の正の実数との間に隙間があって、そこに無限小という超実数が位置しているのでもなければ、最大の正の実数の隣に無限大という超実数が固定的に存在するのでもない。実数数直線には、その連続性(continuity)からして、いかなる隙間もない。実数ではない超実数は、認識対象である実数数直線のどこかに客観的に存在する数ではなくて、認識作用の際限のなさという主観的な都合で作り出された数なのである。超実数の「超」は、認識対象を超えて、認識作用にまで及ぶという意味に解釈しなければならない。
4. アキレスと亀のパラドックス
無限のパラドックスは、微積分学が考案される前から指摘されていた。最も有名なのは、古代ギリシャの哲学者、パルメニデスあるいはその弟子のゼノンが考案したとされるアキレスと亀のパラドックスである。無限性のコペルニクス的転回がその難点をいかに解決するかを確認しよう。

アキレスと亀のパラドックスとは、アキレスが、彼の一歩前を歩いている亀を追い抜こうとしても、アキレスが亀のいる地点に辿り着く間に、亀がアキレスの一歩前を進むということが無限に繰り返されるために、駿足のアキレスがいつまでたってものろまな亀を追い抜くことができないという逆説である。
この問題を数学的に考えてみよう。今、スタート時点におけるアキレスと亀との間の距離を d m、アキレスの速度を va m/s、亀の速度を vt m/s とする。すると、アキレスが亀に追いつくまでに走らなければならない距離 D m は、
ここで、仮定より、0 < vt< vt であるから、
この無限等比級数は収束する。よって、求める距離は、
という有限な値になる。距離が有限であるから、追いつくまでの時間も
と有限になる。では、ゼノンはどこで間違っているのか。アリストテレスは、次のように述べている。
ゼノンの議論は、有限な時間ではいかなる無限の物にも追いついたり追い越したりすることは不可能だと主張している点で間違っている。というのも、長さであれ、時間であれ、何であれ、一般に連続的なものが「無限」と呼ばれる意味には、無限分割と無限延長の二つあり、有限な時間で量的に無限なものに追いつくことは不可能であるが、無限分割の方は、時間自体も無限に分割できる以上、可能であるからだ。[11]
もしもゼノンがこの説明を聞いたなら、納得しただろうか。彼ならば、あるいは、アキレスが亀を追い抜くまでの時間が無限に分割可能なら、その時は永遠に来ないというような詭弁を弄したかもしれない。そうした混乱を避けるためには、分割される時間と分割する時間を区別しなければいけない。もしも各分割に一定の時間がかかるとするならば、無限分割には無限に長い時間がかかるだろう。しかしそれは分割する主観の時間であって、分割される対象の時間は、そしてそれに対応する距離は、有限な長さしか持たない。このように、アキレスと亀のパラドックスも、客観的な無限を主観的行為の無限に帰属させるコペルニクス的転回によって解決される。
5. 無限に対応する対象はあるのか
古代ギリシャの哲学者たちにとって、無限小や無限大が存在するかどうかは自然学の問題であったが、物質を、原子、素粒子等々と無限に分割できるのかとか、宇宙は無限の大きさを持つのかといった物理学的な問題は実証的に検証されるべきであって、そうした物理学的問題と純粋に理論的に解決される数学的な問題は区別しなければならない[12]。
幾何学的に定義された完全な円が現実の世界に存在しないことからもわかるように、数学が扱うイデアールな対象と実証科学が扱うレアールな対象は異なる。そして、無限小や無限大は、レアールな対象の属性でもなければ、イデアールな対象の属性ですらなく、イデアールな対象に対する認識行為の属性であるというのが本稿の結論である。
私たちには有限な認識能力しかないので、イデアールな対象、あるいはレアールな対象に、私たちが無限小あるいは無限大と呼んでいる概念に対応する対象があるかどうかは、わからない。しかし、わからないからこそ、無限小や無限大という概念があるということもできる。すなわち、私たちが無限を認識することができるのは、私たちの認識能力が無限ではないからである。言い換えるならば、無限の認識能力を持つ無限な存在者と私たちが想像する神には、いかなる無限も存在しないであろうということである。
6. 参照情報
- ↑George Berkeley. The Analyst: a Discourse addressed to an Infidel Mathematician. §. 15.
- ↑Augustin-Louis Cauchy. “Résumé des leçons données à l’École royale polytechnique sur le calcul infinitésimal." in Oeuvres complètes d’Augustin Cauchy, Série 2, tome 4. Reprinted: Forgotten Books (February 19, 2018). p. 47.
- ↑Bernard Bolzano. Rein analytischer Beweis des Lehrsatzes, daß zwischen je zwei Werten, die ein entgegengesetztes Resultat gewähren, wenigstens eine reelle Wurzel der Gleichung liege. Reprinted: University of California Libraries (January 1, 1905).
- ↑Karl Weierstraß. “Differentialrechnung – Ausarbeitung der Vorlesung an dem Königlichen Gewerbeinstitut zu Berlin im Sommersemester 1861 von H. A. Schwarz."
- ↑“die beobachteten Bewegungen nicht in den Gegenständen des Himmels, sondern in ihrem Zuschauer zu suchen" Immanuel Kant. Kritik der reinen Vernunft. Felix Meiner Verlag (July 1, 1998). p. 14-15.
- ↑“Findet sich nun, wenn man annimmt, unsere Erfahrungserkenntniß richte sich nach den Gegenständen als Dingen an sich selbst, daß das Unbedingte ohne Widerspruch gar nicht gedacht werden könne; dagegen, wenn man annimmt, unsere Vorstellung der Dinge, wie sie uns gegeben werden, richte sich nicht nach diesen als Dingen an sich selbst, sondern diese Gegenstände vielmehr als Erscheinungen richten sich nach unserer Vorstellungsart, der Widerspruch wegfalle; und daß folglich das Unbedingte nicht an Dingen, so fern wir sie kennen (sie uns gegeben werden), wohl aber an ihnen, so fern wir sie nicht kennen, als Sachen an sich selbst angetroffen werden müsse: so zeigt sich, daß, was wir anfangs nur zum Versuche annahmen, gegründet sei." Immanuel Kant. Kritik der reinen Vernunft. Felix Meiner Verlag (July 1, 1998). p. 14.
- ↑Immanuel Kant. Kritik der reinen Vernunft. Felix Meiner Verlag (July 1, 1998). p. 460.
- ↑Bernard Bolzano. Paradoxien Des Unendlichen. Reprinted: Felix Meiner Verlag; 1., edition (February 1, 2012). §. 19.
- ↑Abraham Robinson. Non-standard Analysis. Reprinted: Princeton University Press; Revised, Subsequent edition (January 8, 1996).
- ↑Martin Grandjean. “Zeno’s paradoxes are a set of philosophical problems generally thought to have been devised by Greek philosopher Zeno of Elea (ca. 490–430 BC) to support Parmenides’s doctrine that contrary to the evidence of one’s senses, the belief in plurality and change is mistaken, and in particular that motion is nothing but an illusion..” Licensed under CC-BY-SA.
- ↑“διὸ καὶ ὁ Ζήνωνος λόγος ψεῦδος λαμβάνει τὸ μὴ ἐνδέχεσθαι τὰ ἄπειρα διελθεῖν ἢ ἅψασθαι τῶν ἀπείρων καθ’ ἕκαστον ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ. διχῶς γὰρ λέγεται καὶ τὸ μῆκος καὶ ὁ χρόνος ἄπειρον, καὶ ὅλως πᾶν τὸ συνεχές, ἤτοι κατὰ διαίρεσιν ἢ τοῖς ἐσχάτοις. τῶν μὲν οὖν κατὰ τὸ ποσὸν ἀπείρων οὐκ ἐνδέχεται ἅψασθαι ἐν πεπερασμένῳ χρόνῳ, τῶν δὲ κατὰ διαίρεσιν ἐνδέχεται. καὶ γὰρ αὐτὸς ὁ χρόνος οὕτως ἄπειρος." Aristotle. Physics (ΑΡΙΣΤΟΤΗΛΟΥΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΚΡΟΑΣΕΩΣ). Book 6.
- ↑物理学者によると、時空を小さく分割するほど量子のゆらぎが激しくなり、プランク長(1.616×10−35メートル)とプランク長に等しい距離を真空中における光速度で通過するのに必要な時間であるプランク時間(5.391×10−44秒)よりも小さな時空の単位は意味をなさない。しかし、これに異論を唱える物理学者もいる。宇宙が有限か無限かに関しても、コンセンサスは得られていない。








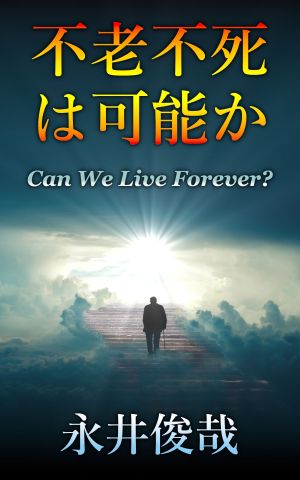

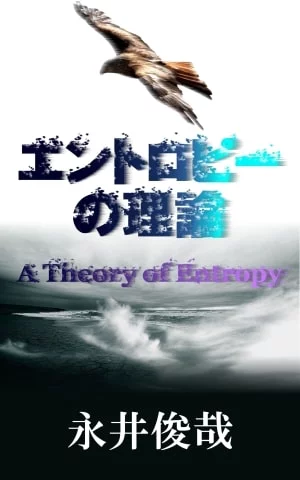

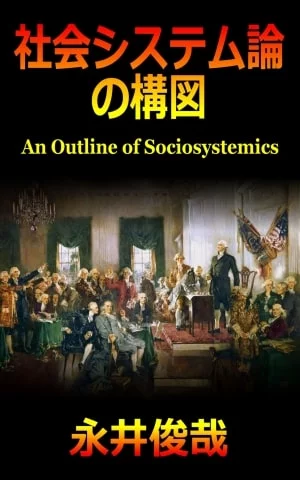

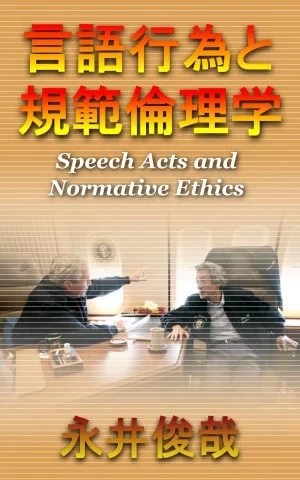
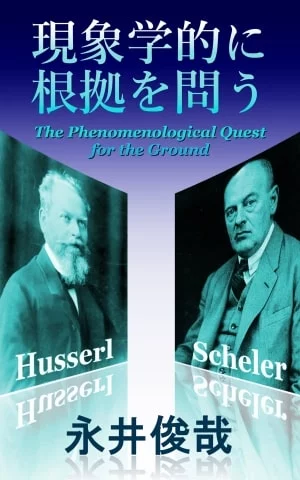

ディスカッション
コメント一覧
まず,プリンキピアでは微積分は図形的に説明されているため,
式的な反論は不可能だと思います.
冒頭の微分の計算はどちらかというとライプニッツが行ったものに近いです.
また,超準解析は無限小と無限大という数を実数の上に拡大した体系の元で
議論されるものと思います.
また,超準解析の意義ですがε-δ論法の矛盾というよりかは
これによってオイラーのような無限小解析が展開できること
であると思います.(そもそも,ε-δ論法は極限の定義(公理)であり
間違っている判断はできない元と思いますが....)
ジョージ・バークリーが、矛盾していると批判していたのは、『プリンキピア』の lib. 2. lem. 2. Momentum Genita aquatur momentis Terminorum singulorum generantium in eorundem laterum indices dignitatum & coefficientia continue ductis で、そこでの説明には図形は用いられていません。
また、微積分を図形的に考えていたという点ではライプニッツもニュートンと同じなのですが、図形的に説明したからといって、無限小をゼロかつゼロでないと扱う矛盾を免れることができるというわけではありません。
わかりやすさを優先してライプニッツの表記法を採用しましたが、表記法がライプニッツ的であるかニュートン的であるかということは本質的なことではありません。
「実数の上に拡大した体系」ということがどういうことなのかを哲学的に考察しようというのが本稿の趣旨です。
私は、ε-δ論法が矛盾しているとも間違っているとも言っていません。ε-δ論法は、ニュートン・ライプニッツの矛盾を回避することに成功しているが、それは無限小を排除することに成功したからではないというのが私の主張です。