『社会システム論の構図』を出版しました
私の著作『社会システム論の構図』の解説動画、書誌情報、販売場所、概要、読者との質疑応答などを掲載します。本書に関してコメントがありましたら、このページの下にあるコメント・フォームに投稿してください。誤字脱字の指摘から内容に関する学問的質問に至るまで幅広く受け入れます。

1. 解説動画
2. 販売場所
販売価格は小売店によって異なることもあります。リンク先で確認してください。
- Amazon.co.jp :: 社会システム論の構図
- Amazon.com :: Shakai System Ron no Kozu
- Rakuten Kobo :: 社会システム論の構図
- Google Play Books :: 社会システム論の構図
- Smashwords :: 社会システム論の構図
3. 表紙画像
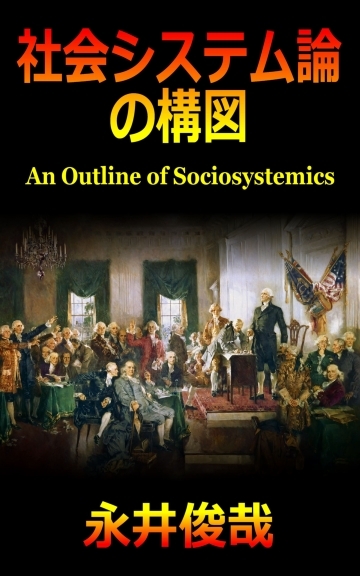
4. 書誌情報
- Title :: 社会システム論の構図
- Furigana :: シャカイシステムロンノコウズ
- Romaji :: Shakai System Ron no Kozu
- Author :: 永井俊哉
- Furigana :: ナガイトシヤ
- Romaji :: Nagai, Toshiya
- Author bio :: 著作家。インターネットを主な舞台に、新たな知の統合を目指す在野の研究者。専門はシステム論。1965年8月、京都生まれ。1988年3月、大阪大学文学部哲学科卒業。1990年3月、東京大学大学院倫理学専攻修士課程修了。1994年3月、一橋大学大学院社会学専攻博士後期課程単位修得満期退学。1997年9月、初めてウェブサイトを開設。1999年1月、日本マルチメディア大賞受賞。電子書籍以外に、紙の本として『縦横無尽の知的冒険』(2003年7月, プレスプラン)、『ファリック・マザー幻想』(2008年12月, リーダーズノート)を出版。
- Language :: ja
- Page :: 293ページ
- Publisher :: Nagai, Toshiya
- ISBN :: 9781310767760 (Smashwords, Inc.)
- BISAC :: Book Industry Standards and Communications
- Science / System Theory
- Social Science / Sociology / General
- Philosophy / Social
- 社会科学 > 社会学 > 一般
- 哲学 > 社会哲学
- Tags :: キーワード
- Japanese :: フロイト、ラカン、レヴィ=ストロース、フーコー、バタイユ、ブルデュー、クーン
- English :: anthropology, capital, communicaion, exchange, paradigm, psychoanalysis, social philosophy, structuralism, system theory, theory of sociology
5. 短い概要
社会秩序は、いかにして、万人の万人に対する戦いである無秩序から人々を救い出し、社会秩序を可能にするのか。この問題は、社会学の永遠の課題である。本書は、ニーチェ、マルクス、フロイト、ラカン、レヴィ=ストロース、フーコー、バタイユ、ブルデュー、クーンなど、ヘーゲル以降の現代思想の流れを踏まえつつ、社会秩序の問題を、社会システム論の立場から考察する。
6. 長い概要
社会システムとは、ダブル・コンティンジェンシー、すなわち、自己の選択と他者の選択が相互に相手の選択に依存している二重の不確定性を縮減する機能である。パーソンズも、ルーマンも、ダブル・コンティンジェンシーがいかにして縮減されるのかを根源的に説明しておらず、彼らの説明は、畢竟「社会システムが存在するから、社会システムは存在する」という循環論法を越え出るものではなかった。ルーマンの社会システム理論は、オートポイエーシス論と称して、その循環論法に居直ったが、それでは社会システム論の発生論にはならない。
ダブル・コンティンジェンシーがもたらす囚人のディレンマから抜け出すには、高資本の媒介的第三者が必要である。媒介的第三者は、言語、貨幣、刑罰などのコミュニケーション・メディアを通じて、社会的エントロピーを縮減するのだが、従来の社会システム理論では、こうした媒介的第三者の役割が正しく評価されていなかった。本書は、市場や資本の概念を、経済システムにおいて適用される狭義の概念から、家族システム、文化システム、政治システムにおいても適用される広義の概念へと拡張し、結婚市場、言語市場、政治市場での交換による評価のメカニズム、身体資本、文化資本、社交資本の非対称な蓄積のプロセス、支配のロジックと物象化の問題点を社会システム論の立場から幅広く考察する。
本書は、この問題意識に基づき、第一章で、交換としての認識、交換としての結婚、交換としての復讐を取り上げ、これらの交換が、貨幣というコミュニケーション・メディアを通じた経済的交換と同一の構造を持つことを示し、文化システム、家族システム、政治システムにおけるコミュニケーション・メディアの役割と資本蓄積の格差について説明する。第二章では、家族システムにおける父、政治システムにおける権力者、文化システムにおける神といった抑圧的な存在として君臨する媒介的第三者を描き、第三章では、反逆を鎮圧する暴君としてではなく、人々を自発的に服従させ、訓育し、支配する現代の権力のあり方を論じる。
7. 関連著作
ルーマンについては、前著ですでに文献の紹介を行ったので、ここでは、日本語で読める現代フランス思想関係の文献を紹介する。
内田樹:寝ながら学べる構造主義
橋爪大三郎:はじめての構造主義
浅田彰:構造と力―記号論を超えて
酒井健:バタイユ入門
小田亮:レヴィ=ストロース入門
新宮一成:ラカンの精神分析
中山元:フーコー入門
加藤晴久:ブルデュー 闘う知識人

















ディスカッション
コメント一覧
アマゾンでレビューが書かれました。
もともと大学院生時代に様々な雑誌に掲載した論文をまとめ上げた本ですから、「じゃがいもを切って、肉を切ってカレーは作らない」という印象を受けたというのはもっともなことです。システム論は、私のライフワークで、完成と呼べる到達点にはまだ達していませんが、2019年の『エントロピーの理論』の方がよりカレーに近いと思うので、「他の本も買ってみようと」言ってくださるのなら、新しい方を読んでいただくことをお勧めします。引用が多いというアカデミズムの弊害も『エントロピーの理論』の方が少ないです。
「パーソンズ、およびルーマンの社会システム論を循環論法への居直りと批判しているが、本書で循環論法を超えた社会システム論を構築出来ているかは僕には分からなかった」とありますが、これに関しては、『エントロピーの理論』あるいは『システム論序説』において、対称性の自発的破れによって説明しているので、これらを参照してください。
コミュニケーションメディアの議論は、政治システム、経済システム、文化システムといったさまざまな社会システムが、異なるように見えるけれども、実は同じ構造であるということを示すために行っていることに留意してください。真理/愛/貨幣/権力が各システムにおいて果たす役割は同じではなく、これでは異なるシステムの同一構造が示せないということを問題にしているのです。コミュニケーションメディアに関しても、『エントロピーの理論』で詳しく取り上げているので、この点でも、この本を読むことをお勧めします。