“It must be true”の否定文は何か
“It must be true.”の否定文は何か。これは、英文法の問題というよりも、様相論理学の問題である。答えは、“must”という法助動詞(modal auxiliary)を使う以上、二値論理学的にではなくて、多値論理学的に求められなければならない。
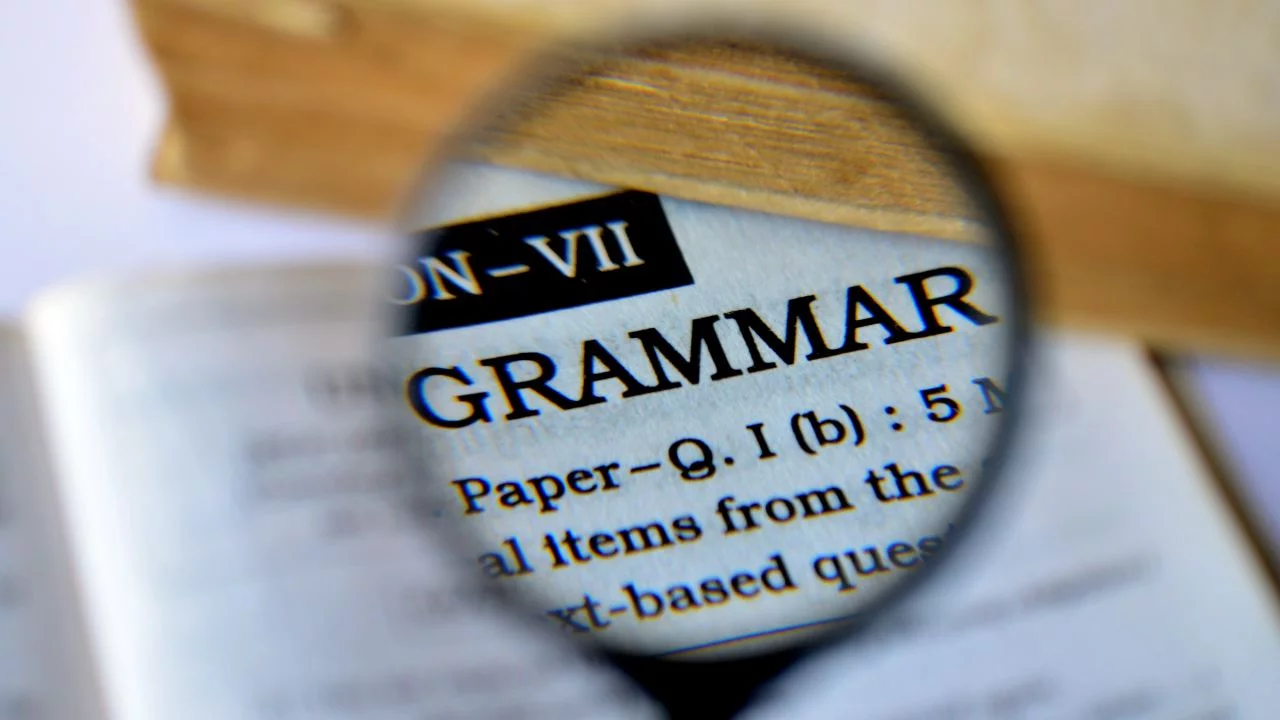
1. 認識的様相と義務的様相
日本の中学校の定期考査などでは、
You must do it. (それをするべきだ)
の否定文を作りなさいという問題がよく出される。一般に、否定文を作るには、助動詞に“not”をつければよいので、
You must not do it. (それをしてはいけない)
としたいところだが、正解は
You don’t have to do it. (それをする必要はない)
であるということは、よく知られている。
もう少し学習が進むと、助動詞“must”の用法として、義務的様相以外に認識的様相があることを学ぶ。そこで、一つ問題を出そう。次の文の否定文は何か。
It must be true.(それは本当に違いない)
多くの英文法書は、この文の否定は、
It can’t be true.(それが本当であるはずがない)
だと書いている[1]。しかし、これは間違いである。少なくとも、“You must do it.”の否定が“You don’t have to do it.”であるのなら、“It must be true.”の否定は“It can’t be true.”ではなくて、
It may not be true. (それは本当でないかもしれない)
である。あるいは、もしも“It must be true.”の否定が“It can’t be true.”なら、“You must do it.”の否定も“You must not do it.”でよいことになる。
2. 様相論理学的説明
このことを説明するには、様相論理学(modal logic)の話をしなければならない。様相論理学とは、命題の必然性・可能性・不可能性を取り扱う論理学である。古典的な二値論理学が真(100% 正しい)と偽(0% 正しい)の二つしか扱わないのに対して、様相論理学は両者の中間をも扱う多値論理学である。
“must”は法助動詞(modal auxiliary)の一種であるが、「…しなければならない」という義務的様相(deontic modality)を表すこともあれば、「…であるにちがいない」という認識的様相(epistemic modality)を表すこともある。
この様相の記号化の方法はいろいろあるが、ここでは、P(…)が「…である確率」を表すことにして、例えば、
You must do it.
では、
P(その行為が正しい)=1
と表記することにしよう。この場合では「その行為は正しい」と判断して、真である確率が1であるということである。これに対して、
You must not do it.
では、「義務の否定」ではなく、「否定の義務」が表現されているので、
P(その行為が正しい)=0
となる。もし、二値論理学の立場をとるのなら、1の否定は0であり、0の否定は1であるから、“You must do it”の否定は“You must not do it”であり、後者の否定は前者となる。しかし、もし「やってもやらなくてもどっちでもよい」という1と0の間の領域を認めるのなら、P=1の否定文としては、
You don’t have to do it.
という、確率が
0<P(その行為が正しい)<1
の範囲にある様相を表現した文が相当する[2]。
P=0の否定文としては、
You may do it.(それをしてもよい)
という、確率が
0<P(その行為が正しい)<1
の範囲にある様相を表現した文が相当する[3]。
以上の義務論的様相についての分析を、今度は認識論的様相について行ってみよう。
It must be true.
では、
P(それが正しい)=1
となる。つまり、「それは正しい」と判断して、真である確率が1である。これに対して、
It can’t be true.
では、
P(それが正しい)=0
となる。もし、二値論理学の立場をとるのなら、1の否定は0であり、0の否定は1であるから、“It must be true”の否定は“It can’t be true”であり、後者の否定は前者となる。しかし、もし「本当かもしれないし本当でないかもしれない」という1と0の間の領域を認めるのなら、P=1の否定文としては、
It may not be true.
という、確率が
0<P(それが正しい)<1
の範囲にある様相を表現した文が相当する。
P=0の否定文としては、
It may be true.(それは本当かもしれない)
という、確率が
0<P(それが正しい)<1
の範囲にある様相を表現した文が相当する。
以上をまとめると、必然性の否定は偶然性で、不可能性の否定は可能性であると言うことになる。
必然性 : It must be true.
偶然性 : It may not be true.
可能性 : It may be true.
不可能性 : It can’t be true.
偶然性と可能性は、0<P<1という不確定的な中間領域として、様相論理学的に等値である。他方、必然性と不可能性は、肯定か否定かは別として、確定性の領域に属する。多値論理学においては、確定性の否定は、反対の確定性ではなく、不確定性である。
3. 他の文法問題への応用
この否定関係を、「全体否定と部分否定」と呼ばれている事項にも適用してみよう。
全体肯定: All of the passengers were alive.
(乗客は全員生きていた)
部分否定: Not all of the passengers were alive.
(乗客は全員生きていたわけではなかった)
部分肯定: Some of the passengers were alive.
(生きていた乗客もいた)
全体否定: None of the passengers were alive.
(乗客は全員生きていなかった)
全部肯定の否定は部分否定で、部分肯定の否定が全体否定である。
様相との対応関係を示すと、全体肯定は必然性に、部分否定は偶然性に、部分肯定は可能性に、全体否定は不可能性に相当する。もっとも、これは、アナロジーではない。全体/部分の肯定/否定関係は、次のように考えれば、集合論ではなくて、確率論で説明できる。すなわち、乗客のうち任意の一人を選んだ時、「乗客は生きている」という命題が真である確率は、全体肯定のときは1で、全体否定の時は0で、部分否定と部分肯定のときは、0と1の間である。
集合の要素が二つしかない場合でも、同じ否定関係を指摘することができる。
全体肯定: She has read both articles.
(彼女は記事を両方とも読んだ)
部分否定: She has not read both articles.
(彼女は両方の記事を読んだわけではなかった)
部分肯定: She has read either article.
(彼女はどちらかの記事を読んだ)
全体否定: She has not read either article.
(彼女はどちらの記事も読まなかった)
頻度を表す副詞にも使える。
全体肯定: I always get up early.
(私はいつも早起きする)
部分否定: I don’t always get up early.
(私はいつも早起きするわけではない)
部分肯定: I sometimes get up early.
(私は時々早起きする)
全体否定: I never get up early.
(私は決して早起きしない)
一般に、英文法を教えている先生は、数学や論理学に疎いことが多く、文法の授業で、こうした否定関係の論理をちゃんと教えないことが少なくない。しかし、様相とその否定の論理は、だれでもわかる簡単なことなのだから、教育現場では、お茶を濁さずに、しっかり教えるべきである。
4. 参照情報
- ↑例えば、『ロイヤル英文法―徹底例解』(初版1988年)には、「must の否定は can’t で表す」と書いてある(p.397)
- ↑厳密に言えば、P=1の否定は0≦P<1であり、P=0の否定は0<P≦1である。しかし、Pが1か否かを問題にしている時には、0は論外であり、Pが0か否かを問題にしている時には、1は論外であるから、こうした反対側の端は、定義域、論理学的に言えば、論議領界(universe of discourse)からあらかじめ排除してかまわない。
- ↑“modality”は、論理学では「様相」と訳され、言語学では「法性」と訳されているが、以下、二つの言葉が同じ英語の翻訳であることに留意されたい。








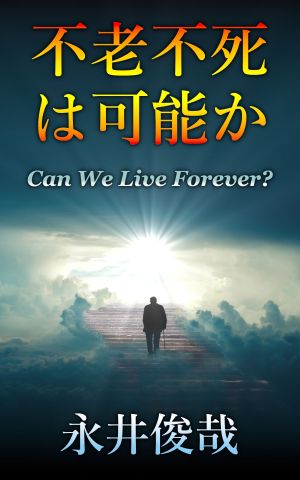

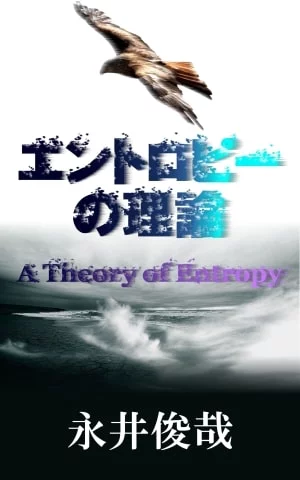

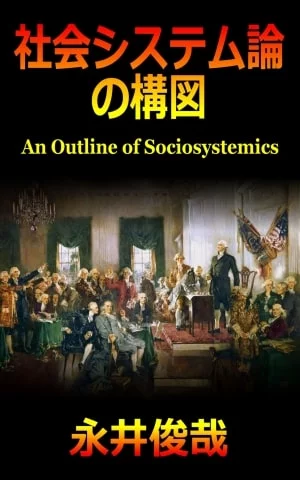

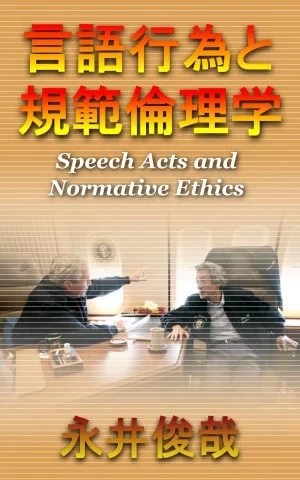
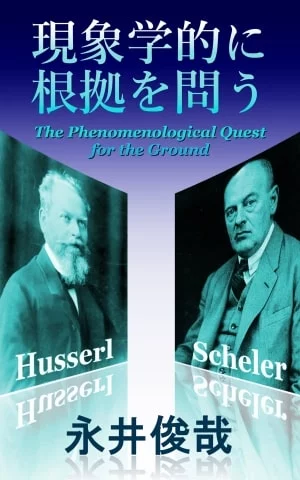

ディスカッション
コメント一覧
はじめまして。福岡勇と申します。
“It must be true” の否定文についての考察、大変興味深く読ませて頂きました。そこで内容自体には全く同意なのですが、もしかすると一言付け加えておく必要があるのかなと思い、ご参考になればと筆を取らせて頂きました。
永井氏の結論によれば、must be の否定は may not be であるとのことですね。論理的に言って確かにその通りだと思います。但し、『現代英文法講義』安藤貞雄(著) p.279 にある can の認識的可能性に関する解説によると、以下のように述べられています。
上記の理由から、認識的必然性の must の否定形では can が用いられている(同書p.289)ようです。つまり、論理的には may not が正しいのですが、can と may における慣用的相補分布の関係性から cannot が選択されるというのが実態のようです。
また、アメリカ英語における認識的必然性の must の否定形は must not となり、禁止を表わす must の否定形を mustn’t とすることで意味を使い分けているのだそうです(同書p.290)。
結論として、認識的様相に関する must の否定形は論理的には may not が正しいが、実態としては cannot が適当である(文法的に正しい)ということが言えそうです。故に、『ロイヤル英文法』に代表される参考書で述べられている「must の否定は can’t で表す」という認識が正しいものであることが分かります。
長文、駄文失礼いたしました。ご参考になれば幸いです。
もしもこの命題が、
1. <認識的可能性>の can は, <認識的可能性>の may が普通, 平叙文で用いられているのと相補分布をなしている.
2. <認識的可能性>の can は, 通例, 疑問文・否定文で用いられて, 話し手の発話時における命題内容の真実性に対する疑いを表わす.
ということだけを主張しているのであれば、私も異存はありません。しかし、この二つの命題からは、
may not = can not
という関係は導けません。
「否定」と「否定形」を区別するのであれば、「must の否定形」は、must not ないし mustn’t です。否定形は文法の問題ですが、否定は論理の問題です。
もしも二値論理でいくなら、認識論的様相の「must の否定は can’t で表す」でよいと思います。ただし、その場合、義務論的様相の must の否定は mustn’t で表さなければいけません。
これはよくある日本人の間違いが関係している。mayという言葉は「?かもしれない」という弱い意味を持ってます。しかし、may notは非常に強い否定を表します。ですから、may notでいいと思いますし、意味的にはcannotでもいいと思います。
“may not”が「非常に強い否定を表す」のは、義務的様相の場合であって、認識的様相においてではありません。“It cannot be true.”と“It may not be true.”では、否定の強さが違います。