幸福とは何か
たんに幸福と感じていれば、それが幸福なのか。それとも、本当の幸福には、それ以上の条件があるのか。SF的な思考実験を通して考えてみよう。

1. 感覚は騙される
幻肢と呼ばれる現象がある。手足を失ったにもかかわらず、なくなったはずの手もしくは足が未だ存在するかのように感じる幻覚のことである。実際には切断面に生じた刺激であるのに、「親指にかゆみを感じる」とか「小指に圧迫感がある」というように、神経のかつての末端に生じた刺激であるかのように感覚してしまう。これは手足にかぎった現象ではない、人間の五感を司る神経はすべて同様にだますことができるのである。
この現象に注目したあるベンチャー企業家が、脳管理会社を作ったとしよう。人体から、脳を取り出して電線につなぎ、その脳に快楽刺激を送りつづければ、その人は一生幸福な人生を送ることができる。脳は、実際には身体を失ったのにもかかわらず、いまだに身体を持っているかのように錯覚する。あなたは、脳管理会社があらかじめ用意したプログラムにしたがって、すばらしい恋人ととろけるような恋愛をしてめでたく結婚し、順風満帆に出世して名声と巨万の富をものにし、かつ自分の子孫が同様の幸福な人生を送っていることを見届けつつ、円満な人生を終えることができる。
やじ馬根性でこの会社を見学しに行くことにしよう。その会社では、たくさんの電線でつながれた脳が各々水槽の中に保存されている。その異様な光景をながめていると、経営者が近づいてきて、あなたに、全財産を提供してこうした脳管理サービスの契約をするように強く勧める。さあ、あなたならどうする?
戸惑う顧客に対して、経営者は、「もし不安を感じているのでしたら、一度、契約した人たちの声をお聞きください」と言って、音声入力装置に向かって、「みなさーん、最高ですかー?」と問う。するとノーミソたちは、音声出力装置を通して、一様に「最高でーす」と答える。
そう、この話は、全財産をなげうってカルト教団に出家するかどうかという話とよく似ている。あなたは、洗脳された信者が、どんなに熱心に教団のすばらしさを語っても、たぶんその話を信用しないであろう。同様にあなたは、契約を結んだ幸福そうなノーミソたちに対しても、軽蔑的な視線を投げかけつつ、「そんなのは本当の幸福ではない」とつぶやきながら、脳管理会社を後にすることであろう。
2. 本当の幸福とは何か
しかし私たちが「ホントーの幸福」と呼んでいるものは、電線につながれたノーミソたちの「最高でーす」とどう違うのか。私たちは、周囲の評判が良いと幸福を感じるが、その評判は社交的なお世辞かもしれない。私たちは、苦労の末に何かに成功すると、幸福を感じるが、その成功は、自分の努力や才能のおかげではなくて、たまたま偶然が重なってもたらされたものかもしれない。こうして疑っていくときりがない。菊地寛の忠直卿行状記に登場する殿様のように、懐疑地獄に陥っていくことになる。
結論として言えば、真の幸福と電線につながれたノーミソの幸福との間に本質的な違いはない。このことを確認するために、電線につながれたノーミソが、「ホントーに幸福」と感じるための条件を探っていこう。
まず、自分が体験していることが、幻想ではなくて、現実だと思っていなければならない。もし幻想だということがわかっているならば、ハッピーエンドのドラマを見ているようなもので、少しも楽しくない。だから契約者の脳を初期化して、脳管理の契約を忘れさせ、人生を誕生から再スタートさせなければいけない。
さらに産まれたときから楽しいことばかりだと、ちょうど甘いものばかり食べていると味覚が麻痺してきて、むしろ気持ち悪くなってくるように、幸福を感じなくなるので、適当につらいことや悲しいことを体験させなければいけない。法の華三法行でも、信者は「足裏診断」とやらを受けて、「あなたは3ヶ月以内に癌で死亡する」と宣告され、いったん地獄に落とされてから「救済」されて初めて「最高でーす」の境地に至ることができる。最高の幸福を体験するためには、最低の不幸を体験しなければならない。良い意味でも悪い意味でも、電線につながれたノーミソは、今の私たちと同じ種類の人生を送らなければならないのである。
真の幸福も偽の幸福も、幸福を感じる感覚のレベルでは違いがない。しかし幸福の根拠となる認識が、真理に近いか遠いかという違いはある。アンケートを行うと、先進国よりも発展途上国のほうが、「自分が幸福だ」と感じている人の割合が多い。しかし私たちの多くは、「地上の楽園」に住むと信じている北朝鮮の人々が、自分たちよりも幸福だとは考えていない。
「真理とは何か」で述べたように、真理は、それに基づいて行為することが、長期的な生存に貢献する可能性があるかどうかを判定基準とする。
3. 幸福はシステムを維持するための感情である
北朝鮮の独裁体制は、長期的な維持が難しい。法の華三法行の寿命も短かった。脳管理会社が倒産した時、契約者のノーミソはどうなるのだろうか。その運命は、教団の解散で路頭に迷う出家信者の運命と同じである。本当の幸福と偽りの幸福の違いは、持続可能か否かというところにあるのだ。
ところで、もしみなさんがある朝目を覚ますと、見たこともない水槽の中にいて、見たこともない人から、「あなたが生まれてから今にいたるまで送ってきた人生は、実は脳管理会社が提供してきた幻想でした。しかし残念ながら、その会社は本日倒産したので、これ以上サービスを続けることはできません」と言われ、ふと鏡を見ると、自分が身体を持たない電線につながれたノーミソであることに気が付いた時 … さあどうする?
4. 追記:マトリックスについて
読者から、『マトリックス』のパクリだと指摘された時、マトリックスが誰かわからなかった。その後、映画のタイトルだと知り、遅まきながら、2003年6月6日、日本テレビで放送された映画を見た。なるほど、みんな似たようなことを考えるものである。これまで現実だと思っていた世界が実はバーチャルな世界だったと気付くストーリーが、これまた映画というバーチャルな世界の出来事だったという二重の否定で、現実が肯定されている。マトリックスの製作者が何からヒントを得たのかわからないが、「これまで現実だと思っていた世界が実はバーチャルな世界だったと気付くストーリー」の一番古い例は、プラトンの洞窟の比喩と荘子が見た蝶の夢(蝶が見た荘子の夢?)だ。重要なことは、何が本当の世界なのかという問いに答えることではなくて、なぜ私たちは、何が本当の世界なのかを問わなければならないかという問いに答えることだ。ヘーゲルが洞察したように、絶対に覚めない夢は、夢ではなくて現実なのだ。夢から覚めるか、あるいは少なくとも覚める可能性が現れ、夢に安住していると、夢の中での自分の存在が危うくなる可能性が生じて初めて、夢に現実としての価値がなくなる。逆の場合は、マトリックスに登場する裏切り者のように、夢から覚めないほうが良かったと思うことになる。




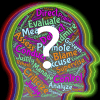












ディスカッション
コメント一覧
映画「マトリックス」とカルト集団を掛け併せた駄作と拝察しました。真理は、もっと深いところに根ざしています。我々の五感で察知できるものは真理のごく一片に過ぎず、いまだ真理そのものを明確にした科学者、哲学者は存在しません。だからこそ非科学的な宗教に身を委ねる人間が後を立たない訳です。言葉や感覚で表せない真理の偉大さが、人類が畏怖して来た「神」の存在なのかも知れません。貴殿がパンドラの箱を開いた以上、生を与えられる限りこの追求を止めてはなりません。そう、この「哲学」することが貴殿の貴殿たる存在の証であるからです。
私たちは、有限な存在であるがゆえに、真理を完全に認識することができません。このことを「だから私たちの努力はすべて空しい」と悲観するか、「だから私たちの認識には無限の進歩の余地がある」と前向きに捉えるかという違いが、宗教と科学の違いになります。宗教と言っても、いろいろあるわけですが、その多くは主体性の放棄を前提にしています。私は、「言葉や感覚で表せない真理の偉大さに畏怖する」ことは、真理の放棄だと考えています。
宗教に関する認識が不足しています。4大宗教のうち「人は有限の存在であるから、努力しても空しいと悲観」しているものはありません。もしそのような新興宗教があるとすれば、それこそオカルト、いやカルト教団です。では参考まで簡単にエッセンスだけ述べます。
まず「仏教」は、空と因果応報がその真髄です。空とは何も無いと言う意味ではなく、唯物論的に厳然として存在する空です。空を述べた学者、哲学者は多いですが、空そのものを完全に規定した人は未だいません。では、因果応報とは。これは人にも努力を求めています。出家した専門化集団すなわち僧侶は、悟りを開くために極めて厳しい戒律を守り修行するのがその具体例です。魂は、悟りを開くまで輪廻転生を繰り返し現世で修行を積むことを義務付けられているのです。
しかし、日本で中世に広まった大乗仏教(最澄、親鸞、日蓮等)は、いずれも無知な大衆(農民)への布教を優先するあまり仏教の戒律そのものを捨て去りました。この時点で、日本の仏教は、真の仏教であることを放棄して、新興宗教として広まった訳です。現代の日本の多くの僧侶が、SEXし、酒肉を食し、さらには脱税し、綺麗な衣装を纏い、高級車に乗り、贅沢三昧をしているのは、戒律を捨てたがゆえの当然の成り行きなのです。因果応報とは字のごとく結果には、必ずそれに至る原因がある、努力(善)をすればするなりに、しなければしないなりにと言うことです。お気付きでしょうが、人間に対し主体性の放棄を求めてはいません。
次に経典宗教(仏教には絶対的な経典は無いことに対して言う)である「キリスト教(主イエス・キリスト)」や「イスラム教(主アッラー)」ですが、これらは仏教と反して完全なる運命論を展開しています。簡単に言うと、人の人生は幸福になるか否かも含めてすべて神によって定められていると言うものです。このことをすべて「人は非力なるがゆえに努力することは空しい」と結び付けるのは極めて軽率、短絡思考です。では、この場合、人は何に努力するのか?ですが、これは極めて明白です。そう、その通り、それぞれの経典の戒律、教えが絶対であり、これを守るべく主体的に努力するのが人間(信者)としての最大の義務なのです。決して客体的に身を任せてしまうことでは有りません。極めて簡単に述べましたが、紙面と時間の制約で次に進みます。
最後に「儒教」ですが(ここでも日本の儒教とは異質のもの)、これは一言で言うと鉄人宗教です。国家の安泰を主眼に置いており、そのためには大衆を治める政治家が倫理・道徳において完全であることを求めます。社会、組織、家族においては、その秩序の維持と厳守を最優先とするものです。これは日本に伝播すると早々に官僚主義と結付き、現代に至るまでその弊害を露呈している次第です。結論を言うと、鉄人になるために、また、倫理道徳を守り秩序を維持するために君主は客体的であって良い訳がありません。
以上が宗教に関する極めて短いエッセンスです。揚げ足を取りますが、「科学とは技術における無限の可能性の論理的、系統的探求」であって認識の無限の進歩ではありません。対外的物質の世界と内面的精神の世界の識別が未だ出来るに至っていないことが表れていると思われます。
畏怖することと放棄とは、論理的に全く繋がりません。真理の偉大さに畏怖しないということは、その偉大さどころか真理そのものを全く認知できていない証明であり、放棄するまでも無く放棄するものさえ全く無い状態を指します。真理の絶大さ偉大さを一瞬でも垣間見れば、それに畏怖せざるを得ません。それは、逃げたいという怯えの恐れでは無く、尊敬の念を超越したむしろ驚嘆の恐れであるはずです。絶対真理とは、それそのものの偉大さゆえに、宇宙や時空からすればゴミにすぎない小さな人間が、人類創生以来、内面的な精神上に、千差万別の「神」として存在を認め恐れ崇めてきたものなのかも知れません。
「それぞれの経典の戒律、教えが絶対であり、これを守るべく主体的に努力するのが人間(信者)としての最大の義務なのです」。
与えられた経典の戒律や教えを絶対視して、それを守るべく努力することが主体的なのですか。科学者には既存の学説を疑う自由があり、新しい学説を提示することがむしろ推奨されています。しかし宗教は、信者に戒律や教えを疑ったり、これを改作したりすることを推奨していません。私が、宗教の信者が主体性を放棄していると言ったのはこの意味においてです。
物質/精神を対外的/内面的と捉える古い二元論はいただけません。かつて自然科学は、物質とエネルギーしか扱いませんでしたが、現在では情報/エントロピーをも射程内に入れています。
もしこの世に、宇宙のすべての情報を知る存在者がいるとするならば、私はその存在者を尊敬するどころか軽蔑します。あなたは、電話帳一冊を丸暗記した人を尊敬する気になれますか。私は、自分にとって必要かつ重要な情報しか知りたいとは思いません。そもそも生物は、自分たちのサバイバルのために情報を得ようとします。滅びることがない存在者がいるとしたならば、その存在者には、情報は無用の長物でしょう。
「幸福とは何か」を読んでいて頭がこんがらがってきてしまったので、御教授ください。質問は以下の2点です。
1.「幸福」という概念の定義(基準)は?
「幸福」は、人それぞれ判断基準が違うものなので定義できないのでしょうか?どういう状態を「幸福」と考え、どういう状態を「不幸」と考えるのか、ということについての一般的な判断基準みたいものはないのですか?
2.人間は幸福を求めているのか?
そもそも人間は幸福になりたいと常に思っているものなのでしょうか?そうだとしたら、なぜ幸福になりたいと思うのでしょうか?
二つの質問には、同時に答えることができます。幸福とは、選択される状態です。人間は幸福を求めているというよりも、求めているものが幸福だと考えるべきでしょう。では、人々は何を求めているかといえば、それはネゲントロピー、平たく言えば自己保存であると答えることができます。自己保存を求めない人は、自己保存を求めないがゆえに、存在しなくなります。私の幸福の定義は行動主義的で、もっと内観的な定義が必要だと考える人もいるでしょう。幸福を快の意識で定義するのは、その典型です。そして「幸福とは何か」は、そうした hedonistic な幸福の定義を批判するために書いたものでした。
御回答ありがとうございました。「幸福」についてはよく分かりました。御回答の中に、「人々は何を求めているかといえば、それはネゲントロピー」という箇所があり、これについてもう少し質問させていただきたいのですが、この「求める」というのは、「人は、必ずエントロピーを減らすように行動(選択)する」ということなのですか?それとも単にエントロピーを減らしたいと「望む」だけで、行動しない場合や、行動が結果としてエントロピーを増すことになる場合があるのですか?
どのような行動/選択でも、それが行われれば、何らかの可能性が排除され、エントロピーが減ります。たんなる願望も、それが何が望ましいかに関する情報エントロピーを減らす以上、一つの選択です。ただ、私たちは、物質的・社会的存在でもあるわけですから、物質的エントロピーや社会的エントロピーを縮減しないたんなる願望や予想に反して増加させてしまう間違った情報には、価値を見出さないわけです。
本文及び、[投稿者メルトモチャン氏]との議論に関連してご意見及びご質問をさせて頂きます。
引用文「本当の幸福と偽りの幸福の違いは、持続可能か否かというところにあるのだ」と論じていらっしゃいます。
それに関連して、北朝鮮や法の華三法行を例に挙げていらっしゃいます。最近では、オウムも15年程で衰退しました。確かに、最近の新しい宗教は持続していません。
ただし、一般に3大宗教と呼ばれる「仏教・キリスト教・イスラム教」は(形は変えてきているとはいえ)、約2000年にわたって継続しているということは、少なくてもそれらの宗教は人々を幸福にしてきたという結果なのでしょう。
周知の通り、現在の日本はどちらかというと多神教で、また、宗教色が薄いですが(多神教だから宗教色が薄いのかもしれませんが)、世界レベルで考えると、宗教を取り入れている国の方が圧倒的に多い。
つまり、継続性があれば、宗教は人間を幸福にする要素があるということでしょうか。
ただし、継続性は結果だから、その時点で判断するのは難しそうですね。
ウェーバーは、プロテスタンティズムの倫理が、資本主義の成立に貢献したことを指摘しました。しかし、プロテスタンティズムの倫理自体が、近代になって生まれた、新しい宗教の形態でした。このように、宗教を含め、私たちの思想は、そのつど環境に適応できるように変化するものだと思います。
その時代、(宗教心・信仰心を持った)プロテスタントが時代を変えました。
現在において、宗教心の有無は、立場や学歴や肩書きは関係していません。政治家の中にも宗教心を持った人はいる。警察官にも、弁護士にも、キャリア官僚にも、極道の世界の人にも、大卒の人にも、中卒の人にも、金持ちにも、低所得者の人にも・・・。ブッシュ大統領も。
その時代の事を考えてもそうですが、宗教心を持った人達の力(影響力)は、時代を変える力を持っているということを物語っています。
これは私の想像ですが、政教分離というしくみを作ったのも、影響力が強い反面、客観性に乏しい傾向にあるからではないかと思うのです。
多種多様に存在するとはいえ、「宗教」それ自体が人類史当初から現在に至るまで存在している/継続している、ということは、宗教は人間に幸福をもたらしているということは事実と言わざるを得ないと解釈しています。
ぜひとも勉強させて頂きたいのですが、宗教心を持つ人というのは、哲学的な立場からすると(というより、永井さんのお考えとして)、どういう傾向の人が持つに至るのでしょうか。宜しくお願い致します。
長々と失礼足しました。
宗教が人を動かす媒介になっているからといって、宗教が社会を変えているとはいえません。私は、たんなる中間項に過ぎないと思っています。
また、宗教自体が様々ですから、一概にどういう人が宗教を信じやすいかとは言えないでしょう。
荘子が見た蝶の夢(蝶が見た荘子の夢?)→”荘子の「胡蝶の夢」”のようです。
私も中国の古典で”荘子の「胡蝶の夢」”に近い夢物語を読んだことがあります。題名は思い出せません。30年前の日本の漫画にも時々、似たようなものが出てきました。
今が現実かどうかは、多くの人が一度は疑うことで、「マトリックス」は、その疑問を現実のコンピューター社会に具体的に面白く映画化されたことが素晴らしかったのでは?
「脳管理会社」という具体的な発想が、素晴らしい。
ただし、脳管理会社に全財産を提供するのは、現実味に欠ける気がします。
委託した脳管理会社が、倒産することも十分有り得るため、年間何円または、一生で金何円と契約するのが現実的ではないでしょうか?保険を掛けていたかもしれないが。
「脳管理会社」が登場すると例えば、電極からの情報スピードを上げれば、一生を不死鳥のごとく1万年以上生きる経験をすることが可能になる気がします。
また、脳の中で研究開発すれば、1日の内(脳の中では、例えば1000年)で、研究開発費が1000兆円するかもしれない核融合発電が完成することも可能で、その研究データを電極から引き出せば、短時間で、極めて安い費用で、研究開発ができることになるのでしょう。
となると、現実世界より「脳管理会社」の脳の中の方が、永続性(時間が長い)が高いため、より現実的と考えられます。
科学技術により、多様な現実(多次元)を作る世の中が将来やってくる可能性があると言えます。
幸福とかよく分からないものにつて考えるのはよく考えたほうが何か分かるからでしょうか?自分自身が存在しているかどうかもよく分からないのにどうしてその先の不確定な物を考えるのか?我々は何故考えるのでしょうか?未知なる物の仕業でしょうか?教えてください。
自分自身が存在しているかどうかわからないのですか。考えている以上は、考えている私は存在するというのがデカルト以来の認識なのですが、それには納得していないということですか。
自己保存を求めない人は、自己保存を求めないがゆえに、存在しなくなりますとありますが自己保存を求め過ぎて結果として自滅する事が有るのですが
「自己保存を求めない人は存在しなくなる」と「自己保存を求める人は存在し続ける」は論理的に等値ではないので、後者の否定は前者の否定を帰結しません。
幸福とは「無限」と「無」だと思います。
1、幸せとは、その人が死ぬ時、私の人生は幸せだった皆さん、ありがとう、感謝です。
2、その反対は死ぬ時、死にたくない、こんハズではなかった、もう一度やり直したい。
「もし幻想だということがわかっているならば、ハッピーエンドのドラマを見ているようなもので、少しも楽しくない。」
終わりのないオンラインのバーチャルゲームに、起きている人生の時間ほとんどを捧げ、人生を幸福と感じた人間がいた場合この文章はあてはまらないのでは?
ゲーム中毒者は、他の依存症患者と同様に、これではいけないと思いつつ、そこから抜け出せないという人がほとんどだと思います。
屁理屈で申し訳ありません。「ゲーム中毒者」とはどのような人を指すのでしょうか?
実際ゲームのプロもいることですし、プロ野球選手や「金持ちの野球バカ」は野球中毒で依存症患者ということができるのでしょうか?生活そのものが成り立っていて個人の信念があり他人に迷惑をかけていない、さらには他の人に夢を与えている場合、依存症患者、ゲーム中毒者ということは言えないのでは?
「終わりのないオンラインのバーチャルゲームに、起きている人生の時間ほとんどを捧げ、人生を幸福と感じた人間」はまさに「ネット中毒者」と呼ばれるべき人ではないでしょうか。
お返事ありがとうございます。実は屁理屈の疑問はただ永井さんのような知識人がどのような凄い観点からいってくるのか楽しみなだけで質問させて頂きました。
こんなにたくさんの鋭い論文を書く方に返答を頂けるということがここ最近の私の幸福でした。まぁ偽の幸福なのかもしれませんが。とりあえず、自分も哲学者で知識があるようなバーチャル感にひたれたということは私の感覚の事実なのかとかんじました。
私が考える幸福とは、生活が送れること、公正に扱われること(宗教迫害や、あらゆる差別、公正な裁判、公正な分配)、そして、自由があることにあるように思います。そして、これらのことが達成できなかった場合に、民心を他に向けさせてしまうものが、宗教であるように思います。しかし、宗教とはとても危ういもののように思います。たとえば(これは、キリスト教徒の皆さんには大変失礼ですが。)いま私の目の前に本物のイエス・キリストが表れて、「私は神の使いである」などといった場合間違いなく私は変質者が現れたとか、新手の新興宗教(カルト)だろうかと考えるでしょう。彼が、いくらいいことを言ったとしても、そのようなことをいう新興宗教の方々を知っている私は、彼を決して信じないでしょうし、神の存在も認めないでしょう。(というより私の場合運命などと言った時点でその人を疑います。)それにもかかわらず、現在でも多くの宗教が存在し、数多くの人が、神(もしくはそれに類するもの)を信じ、宗教に幸福を求める人は多くいます。彼らがはたして幸福であるか、私にはわかりません。しかし、彼らが少なからず、宗教によって救われていることは確かであり、否定のしようもありません。このことについてどのようにお考えでしょうか。
この世の森羅万象は必ず「過去」の影響を受けています。「生まれる前の世界」や「死んだあとの世界」を考慮しないという前提で話を進めさせていただくとすれば、一人の人間の「究極の過去」は、この世に「生」を受けた瞬間ということになります。それぞれ異なる両親、異なる遺伝子や才能や健康状態、異なる国や環境、異なる経済状態、等々、それぞれ2つと同じものではない固有の条件を背負って、この世に生まれてくるのです。
しかも、本人が望んでその条件の元に生まれてきたのではありません。もっと究極的にいえば「生まれてきたこと自体」が本人の意思や希望ではなかったとさえいえます。
でも、我々人間は、この世に「生」を受けてしまった以上、その瞬間から、たとえそれがどんなに望まない条件下であったにせよ「生きなければならない」存在となってしまっているのです。だから「生きよう」という「本能(欲求・欲望)」を備えて生まれてくるのです。これを、ほとんどの人は「生きたい」と自らの「意思」が望んでいるのだ、と思い込もうとしています。
一方、一人の人間の究極の未来とは「死」の瞬間ということになります。当たり前過ぎるほど当たり前ですが人間は「死ぬ瞬間」まで休まず生き続けるのです。これは、自らの意思で「生きよう」と思い続けているから生き続けてきたのではなく、生きなければならないから、今も生き続けているのです。「先週の土曜日と日曜日は、生きるのが面倒だったので2日間ほど死んでいました」という人は今生きている人の中には絶対いないはずです。どんな3日坊主でも、これまで「生きる」ことだけは中断しなかったから、今なお生きているのです。それは「意思」ではなく「本能(欲求・欲望)=プログラム」の力だと私は思ています。自分の「意思」の力だけでは、こんなに大変な「生きる」ということを死ぬまで続けていくことは非常に困難であると私は思います。
人間の「命=時間」は、この世に「オギャー」と生まれた瞬間」から「死ぬ瞬間」に向けてカウントダウンが始まっています。「死ぬ瞬間」が、何年何月何日の何時何分何秒であるかを事前に知らないだけで、確実に今この瞬間も自分の「命=時間」は減り続けています。
さて、なぜこのようなことを長々と述べたかと申しますと、人の人生(命=時間)は、客観的には所詮自分の意思では決められない「生まれてから死ぬまで」の時間的な量にすぎないということを前提にして「幸福」と言う概念を私なりに考えてみたかったからです。
「幸福」という概念だけに限らず、「生きがい」だとか「やりがい」だとか「充実感」だとか「喜び」、反対に「苦悩」だとか「苦痛」だとか「恐怖」だとか「罪悪感」だとか「嫌悪感」だとか「悲しみ」、また「欲望」だとか「願望」など全ての人生に「意味付け」をする概念は、人間が生まれてから死ぬまでのただ「生きなければいけない無味な時間」に対し、「本能」や「感覚」や「感情」や「理性」や「知性」などといった人間が持っている全てを総動員した「味つけ(スパイス)」にすぎないのだと私は思います。したがって「幸福」とは、この世に生まれ、生きていかなければならなという宿命を前提とした、後付けの概念にすぎないと思ています。それなのに「幸福になること」を人生(生きること)の目的であると考えてしまうから話がややこしくなるのです。だから「私は幸福でないから死にたい」とか、私にとっての「生きている目的がわからないから死にたい」などという、生まれた時から逃れる事の出来ない宿命を放棄するがごとき発想が生まれてくるのです。
人間には「生まれた以上死ぬまで生きなければならない」という宿命があるだけなのです。「生きること」は「権利」というよりはむしろ「義務」なのです。それは考えただけで「うんざり」するような宿命なのです。にあまり詳しくありませんが、仏教でも四苦は「生・病・老・死」と言っていますよね。「生」はもともと「苦しみ」なのです。
どうせその時間を生きなければならないのなら、その瞬間瞬間を「味けない」なものではなく、少しでもましに「味つけ=意味づけ」をしたい、というのが「幸福になりたい」ということなのではないかと思うのです。だから、人間は「感覚」や「感情」を持って生まれてきたのです。だから芸術や音楽やグルメ、恋愛、結婚、子供などすべてを「幸福」のための象徴としてとらえようとしているのです。
どんな「味つけ」を望むかは、生まれた時の条件や過去の経験によって千差万別なのは言うまでもありません。さらに、同一人物の「味つけ」の好みも時間と共に変わることを忘れてはなりません。したがって、未来永劫変わらない究極の幸福などというものは存在しないと私は思っております。
冒頭で、この世の森羅万象(人間もその一部)は「過去」の影響を受けると述べましたが、人間は過去の「自分」の影響を必ず受けると言い変えることができます。過去の自分は、厳密に言えば現在の自分とは別人です。その「他人」である過去の自分が、今の自分にことごとく影響してくるのです。過去の自分が望み、幸福と感じていたことが未来の自分にとってもそうであるという保証はどこにもありません。また、過去の自分が正解と思ったことが未来の自分にとっても正解である保証もありません。
過去に望んで購入した住宅ローンの支払いで現在悩む人。過去好きで結婚した相手と今は一緒にいることすら耐えられない人。食べたいものを食べたいだけ食べ、太ってしまった現在の自分をみて後悔している人、等々。「過去」の自分の幸せだと思ってやったことが「現在」の自分の幸せの邪魔をするようなことは多々あります。
過去の自分が望んで「幸福感」いっぱいにやったことですら、現在の自分の不幸の原因になることがあるくらいですから、そこに自分の意思によらない他の不幸の原因が重なったら、もう理想の幸福な人生とは程遠いものとなってしまうのは言うまでもありません。
このように人生の瞬間瞬間をみると「自分は不幸だ」と感じる瞬間が多々あるのですが、とにかく生きなければならないので、全力でそれを「リセット」して未来に希望をつなぐため「幸福になりたい」と思い続けることが必要になるのです。それで、やっと人は死ぬまで生きて行くことができるのだと思います。
今「幸せだ」と感じている人はそれで「今」を生きられます。今「不幸」だと感じている人は将来「幸せになる」という「希望」によって「今」を生きられる。そうやって「生きる」ことをつないでいけるのです。
「幸福」という概念をもつことは、「生きる目的」ではなく「生きる続けるための手段」であるのだと思います。
さて、人生全体で「幸福であったかどうか」は、他のどなたかがおっしゃっていたようですが、やはり「死ぬ瞬間」の自分の人生が幸せだ(または幸せだった)と感じるかどうかで決まると思います。
「オギャー」と生まれてから、「幸せ」と「不幸」の両方を繰り返してきて、最後の最期に
自分は「不幸」であると思ったとすれば、今までの人生全ての蓄積に「0」をかける掛算をするようなもので、自分の人生は「無意味だった」と決定付けてしまうようなものだと思います。逆に「幸せ」だったと思えば、「1」をかけ「有意義な人生だった」と思うことになります。
従って、いつぃまでも「電極に繋がれた脳みそ」のまま意識と感覚が生きていたとすると、永遠に自分の人生が「幸福」であったか「不幸」であったかの最終ジャッジができないまま、無間地獄のように生き続けなけばならなくなると思います。
まとまりがない文章を長々と失礼致しました。
pathfinderの考える芸術ってなんですか?
永井さん
幸せには多くの人がなれますが、「心からの幸せ」になれる人は少ないと考えます。
なるには複数の条件があります。
幸福も不幸も人の考えです。
また、バーチャルの世界と現実世界という話をしている時点で宇宙の仕組みを知り得ない者だと思います。
何故なら、宇宙の力と繋がった者が現実を作るからです。
ですから、想像されないと実現化しないのです。
井上恵美子
不幸な人間の類型は無数にある。
一方、幸福な人間の類型は ひとつしかない。それは、貧乏ではなく、健康であり、配偶者と子どもがあり、老人になったときには孫がおり、裏切らない友人もいる、という状態だ。
「貧乏ではなく、健康であり、配偶者と子どもがあり、老人になったときには孫がおり、裏切らない友人もいる」にもかかわらず、自分が幸福だとは思わない人もいます。またこれらの条件が満たされていなくても、幸福と思っている人もいます。
ああいえば上祐
幸福な者はより幸福に、そうでない者はお先真っ暗、というのが社会の掟だ。