貨幣とは何か
貨幣は、かつては金や銀など、価値のある財であったが、今では、それ自体では、取るに足りない金属や紙のかけらあるいは電子情報に過ぎない。それにもかかわらず、なぜ貨幣には価値があるのか。共同幻想に基づく惰性によるのか、それとも根拠があって貨幣は流通するのかを考えてみよう。[1]

1. 貨幣の機能は何か
貨幣は、交換の相手が、自分が望む商品を所有しているかどうかという不確定性と自分が所有している商品を望んでいるかどうかという不確定性からなるダブルコンティンジェンシーを縮減するがゆえに、交換媒体(コミュニケーション・メディア)である。
今、n人が、それぞれ自分で消費するつもりのない異なった等価の商品を一つづつ持っていて、かつ他者が所有する商品を一つだけ求めているとしよう。任意の二人の間で交換が成立する確率は、1/(n-1)2 でしかない。逆に言えば、物々交換の不便を解消するシステムは、エントロピーを 2log(n-1) 減らすことができるということである。
実際には、すべての商品が等価というわけではないから、自他の欲望が一致することはさらにまれである。もし相互に、相手が望む商品を所有していないのならば、その商品を自らの労働によって生産しなければならない。ところがこのとき、囚人のジレンマが発生する。
今、魚を手に入れることを望む山の住人と猪の肉を手に入れることを望む海辺の住人が、一定の日にまでに、それぞれ一定量の猪と魚を捕獲して、交換する約束をしたとする。
このとき、山の住人は、次のように推論する。
相手が約束の期日に、約束しただけの魚を捕るかどうかわからない。もし相手が約束を破るなら、私は自分で消費するつもりのない余計な猪を獲る必要はない。もし相手が約束通り魚を捕ったとしても、相手は自分ですべての魚を消費できないのだから、食べ残った魚を盗めばよい。
もちろん、海辺の住人も同じ戦略を考える。その結果、どちらも約束を破って自分が消費できる分しか生産しないから、ナッシュ均衡は自給自足ということになる。しかしこれは最も望ましい状態ではない。比較優位の理論が教えるように、たとえ一方が他方に対して絶対優位の競争力があったとしても、分業と交易は、全員の利益を増加させるからだ。では、分業と交易はいかにして可能か。
分業と交易に躊躇している二人の前に、価値があるならどんな商品をも受け入れ、それを誰にとっても価値がある等価商品と交換し、そして別の商品が欲しくなった時には、それと等価な任意の商品と交換してくれる信用できる豊かな第三者が現れれば、問題は解決する。貨幣という普遍的媒介を通して、山の住人は海辺の住人と魚と猪の交換をすることができる。
2. 貨幣はなぜ流通するのか
なぜ貨幣は誰にとっても価値あるものとして流通することができるのか。いったん流通すれば、貨幣が交換媒体、価値測定尺度、価値貯蔵手段として有用であることは自明である。しかし特定の財が貨幣となることに何か根拠があるのだろうか。かつて、金や銀などの貴金属が貨幣素材として使われていたが、今では卑金属や紙や電磁波がそれに取って代わっているので、貨幣を構成する素材に貨幣の価値の根拠を求めることはできない。
では、貨幣は法律で貨幣と定められているから貨幣なのだろうか。そうではない。法律で特定の財を貨幣として定めても、人々がそれを使うとは限らない[2]。また、民間企業でも、独自のマネーを発行できる。例えば、消費者がアンケートに答えてポイントを貯めると、それをプレゼントと交換することができるというルールを作れば、企業は貨幣を発行していることになる。
ならば、貨幣の価値には何の根拠もなく、ただこれまで貨幣として流通してきたから今も貨幣として流通しているだけなのだろうか。そうではない。もし貨幣が自己完結的な価値を持つならば、なぜ政府の財政赤字や政情の不安定化が通貨価値の下落をもたらすのかが説明できない。
3. 貨幣の価値を担保するものは何か
私は、貨幣とは発行者の資産と期待収益を担保とした証券であると考える。現在の貨幣は不換銀行券だから、政府や中央銀行に持って行っても何か価値ある商品と換えてもらえるわけではない。しかしそれは国民が税金を貨幣で納めているからである。政府は、その気になれば、江戸時代の幕府のように、税を物納させることもできる。その場合、中央銀行が発行する貨幣は、国有財産と歳入を担保にした証券であることがはっきりする。
もちろん、実際に発行されている貨幣価値の総計は、国有財産と歳入の規模をはるかに超えている。これは、政府の担保価値だけでは説明できない。むしろこのことは、交換媒体としての有用性により、価値がそれ以上に膨らまされていることを意味している[3]。しかし、それにも限度がある。政府の財政赤字が担保価値という観点から通貨価値を下げるのに対して、政情の不安定化は信用という点で通貨価値を下げる。
貨幣の額面価値と貨幣製造費用との差額はシニョリッジと呼ばれる[4]。現在最もシニョリッジの恩恵に浴しているのは、アメリカである。FRBは、ドル紙幣を世界の基軸通貨として国内で使える以上に発行できる。シニョリッジはしばしば不当な利益として非難されるが、実は信用という商品を作る政治的・軍事的労働への正当な報酬なのである。実際信用は不確実性(エントロピー)を減少させるがゆえに価値を生むのである。
日本が経済大国であるにもかかわらず、円がドルのように国際的に通用しないのは、国際社会における日本の政治的軍事的役割が小さいからである。貨幣が普遍的な価値を持つためには、発行者自身が普遍的存在でなければならない。
4. 参照情報
「貨幣とは何か」に関するより新しい私の見解です。
- 岩井克人『貨幣論』筑摩書房 (1998/3/10).
- フェリックス・マーティン『21世紀の貨幣論』東洋経済新報社 (2014/9/26).
- ランダル・レイ『MMT 現代貨幣理論入門』東洋経済新報社 (2019/8/30).
- ↑本稿は、2001年2月25日のメルマガ記事「貨幣とは何か」に加筆修正を施して再掲したものである。
- ↑律令制下の日本は、和同開珎をはじめとする皇朝十二銭を鋳造したが、通貨としてあまり普及せず、10世紀末には鋳造が中止となり、以後、600年間、公的な貨幣が鋳造されなかった。国家が何かを貨幣にすると法律で決めるだけでは、通貨として普及しないことを示す事例である。
- ↑法定通貨は、信用貨幣であるだけでなく、商品貨幣でもあり、商品貨幣としての需要を満たす限りで、財政赤字は許容される。詳しくは、このページに埋め込んだ、2021年の関連動画を参照されたい。
- ↑これは、マネタリー・シニョリッジだが、これ以外にも、インフレによって目減りする債務の実質価値であるインフレ税シニョリッジや発行した通貨で購入した資産から得られる収益である機会費用シニョリッジがある。





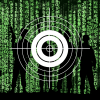











ディスカッション
コメント一覧
はじめまして、経済の初歩的かつ、根源的な質問をさせてください。
それは、
「通貨総量-借金は一定?」
というものです。
貿易などもない、閉じた市場を考えます。
また簡単のため、不良債権など、借金の棒引きなどが起きない
世界を考えます。このような世界では、
「信用創造」によって、銀行の預金総額を増大させることは可能ですが、
その分、借金をしている人が増えているので、
預金-借金は一定のような気がします。
借り手が商売で成功し、銀行に利子と一緒に払えば、
預金-借金は増えるかもしれませんが、借り手が収益を上げたということは、
誰かが富を失って(替わりに物品が手に入るが)るわけで、
「借金を引いた後の通貨の総額」は不変のような気がします。
仮に銀行が日銀からお金を借りたりして、通貨量を増やしたとしても、
その分、銀行が抱える借金が増えるわけです。
今の日本の法律では日銀が勝手にお金を印刷して、
市場にばら撒くわけにはいかず、常に市中銀行との取引によって、
市場に通貨を供給しているようです。
一方、資産は勝手に増える可能性があります。
庭の林檎が実をつけたり、
自分の家の床下から金鉱脈が発見されるかもしれません。
この場合、市場の中の資産は増えますが、
通貨の量が市場に不足している場合、
林檎や金を買いたい人は、借金をするしかないのでしょうか。
もし上記が正しければ、市場に出回る通貨が増大しているということは、
借金の総額も増えているということを意味していますか?
正当に通貨量を増やすためには、日銀に林檎や金を納入するしかないように
思えます。この林檎や金の役割を間接的に果たしているのが、
国債なのでしょうか?しかし、国債を発行しても、国の借金が増えているので、
やはり通貨総量-借金は一定のような気がして、
頭がこんがらかり、よくわからなくなります。
上記についてお教えいただければ、幸いです。
よろしくお願いします。
もしも林檎のなる庭さんが国家以外は信用しないというのであるならばそういう考えでもよいのですが、実際には、民間も国家と似たような信用創造ができます。国家は、徴税能力や国有財産を担保に通貨を発行します。これは国家による信用創造です。銀行は、預金を担保に貸し出しをします。これは民間による信用創造です。企業は、自らの資産価値を担保に社債を発行します。これも一種の民間による信用創造ですが、社債は、流動性が低いので、普通は通貨とはみなされません。結局のところ、国家が発行する貨幣と民間が発行する有価証券との間には流動性が高いか低いかという違いしかありません。両者に質的な違いがない以上、通貨の定義を林檎のなる庭さんの定義よりも拡大して、民間による信用創造でマネーサプライが増減すると考えることは、経済学的に見て、有意味なのです。
迅速な回答ありがとうございます。
私がお尋ねしたかったのは、狭い意味での通貨、貨幣の総量についてです。
社債を発行しても、その売買には狭い意味での通貨が用いられますよね。
社債を発行し、その会社はその代わりに流動性の高い通貨を手に入れ、
買った側は通貨を払うことで、将来それが増えて戻ってくることを
期待しているわけです。このやり取りで、社債の満期に達したとき、
利子がゼロであれば、通貨の総量は不変です。替わりに社債という
紙切れが一時的に交換されるのみです。
しかし、ここで会社は利子をつけて、「通貨」を出資者に払わなければ
なりません。しかし、普通の経済活動では、通貨の湧き出しは
ないように思えます。
(物理がお得意な永井さんなら、湧き出しの意味はわかりますよね。
湧き出しがなければ物理量は保存されます)
通貨を湧き出させるためには、
前回書いたように、信用創造という行為を伴い、これはその陰で
誰かが借金をしていることに相当しています。
利子を林檎などで物納すれば、出資者に払うことは可能ですが、
そうでなければ、
この会社が最後に利子を払えているということは、
1、市場内メンバーの誰かが通貨を失い、会社に利益をもたらしている。
2、市場内メンバーの誰かが借金をして、会社に利益をもたらしている。
3、会社自らが借金をして、出資者に利子を払っている(自転車操業)。
の3つしか解がないように思えます。
(もちろん貿易などにより市場外から通貨を調達するという方法は除きます)
以上の場合、通貨総量-借金は保存されます。
もしも現金通貨を増やさないなら、現金通貨は一定です。これはトートロジーです。利払いは、通貨が増えるインフレ局面においては容易ですが、その逆であるデフレ局面においては困難となり、最終的には、借り手が債務不履行となることで調整が行われます。
ありがとうございます。
ということで、日銀が通貨を勝手に印刷してばらまかない限り
(現在の日銀はそうなってると思いますが)、
通貨総量-借金は一定ということですね。
経済成長とは大雑把に言うと、マネーサプライの増加
とほぼ同義だと思いますが、経済成長して、
さらに通常マイルドなインフレ局面となっているということは、
国民の借金総額も徐々に増えていっているということですね。
(通貨の増加は信用創造のみによって行われると考えているので)
通常GDPなどの値も国民の総資産ではなく、現金や預金の出し入れによって
測られていると記憶しております。
輸出に頼らなければ、
GDPの増加は借金の増大と同義ということになってしまい、
必ずしも良いこととは感じられないというパラドックスへと帰着していしまいました。
たとえば、今から100年前に国民の現金・預金総量が100億円、
借金総額が10億円だったと仮定します。
通貨総量-借金=90億円ですね。これが保存されたまま、
現在に至り、経済成長により、国民の現金・預金総量が100兆円に
なったとします。すると上の式から、国民の借金総額は、
99兆9910億円ということになり、国民一人当たりの借金は、
ほぼその総現金・預金量と等しい、超借金社会となってしまいます。
そう思えば、政府の借金が国民一人当たり、これこれで、
毎日XX円だけ増えていっている、という話を聞いても、
ある意味当然だという気もします。
現実には上記のような借金社会というのは成り立たないでしょうから、
時々大口の破産者が出て、借金が放棄され、
通貨総量-借金も増えていくのだと思います。
というわけで、私のいたった結論は
「管理通貨制度下にある経済成長とは、ある一定の破産者、
借金の踏み倒しを前提としている」
となりました。何か自分でも納得がいかない部分もあるのですが、
間違ったところがあったら、是非ご教授よろしくお願いします。
デフレのときは、中央銀行が現金通貨を増やせばよいのです。バブルが崩壊したとき、日銀がこれをしなかったために、不況が長引きました。
貨幣論を読みました。政府がもつ資産や徴税力が貨幣の価値を担保しているとのことですが、政府の資産は徴税やシニョリッジによって築かれたものなので、結局のところ貨幣の価値は徴税によるものではないでしょうか。また、シニョリッジもそもそも徴税(国家権力)によって貨幣価値が産み出された後の話なので、政府の運営コストというよりは、国家権力そのものではないかとおもいます。シニョリッジを批判するなら、そもそも国家はなぜ国民から搾取する権利があるのか?と疑問をもつべきかと思います。
これは誰に向かって言っているのでしょうか。私は、シニョリッジを批判してはいません。
こんばんは。
深く調べものをすると大体こちらのサイトにたどり着きます。笑
さて、「貨幣の価値を担保するもの」についての今回の記事ですが、一つ疑問が残ります。
とのこと。
現代のような債務性と表裏をなすタイプの貨幣においては、まさに的を得たお考えだと感じます。
では残る疑問とはなにか。
それは、発行者不在のままで、尺度、保蔵、媒介をなすタイプの貨幣についてです。
貝殻やゴールドなど自然物、そして最近ではブロックチェーンを用いたタイプの仮想通貨もそうです。
このような、発行者と債務性が不在のタイプの貨幣において、その価値を担保するものは、なんなのか。
この疑問が残りました。
なぜ、人々はこのようなタイプの貨幣も信認するのでしょうか。
もしお考えがあればお聞かせいただければ幸いです。
私がそう定義した時の貨幣とは、純粋な信用貨幣のことで、商品貨幣を考慮に入れていません。貝殻やゴールドなど自然物は、典型的な商品貨幣で、歴史的に信用貨幣は、そうした商品貨幣から商品としての性質を捨象することで成立したという点で両者は不可分の関係にあるものの、貨幣の本質を見定める上では、商品貨幣の商品性(有用性)を排除する必要があります。
仮想通貨は、外見上ゲームのポイントとよく似ていますが、その価値を担保しているのは娯楽サービスではありません。代表的な仮想通貨であるビットコインでは、マイナーというソフトで流通量と発行時期に関する数理的問題を解決することでビットコインを「採掘」します。つまり、仮想通貨システムの維持に貢献した者が、そのサービスの対価として、仮想通貨を受け取るのです。
ビットコインを用いた取引は、法定通貨による取引と比べて、手数料が安くて、消費税(付加価値税)がかからないので、商品の交換に用いる人がいます。ということは、仮想通貨の価値は、法定通貨による取引コストとの差額によって担保されているということです。取引サービスという商品が貨幣化しているという意味で、仮想通貨もまた商品貨幣の一種と言うことができます。