供犠のエクスタシー
2003年7月2日、長崎市万才町の築町パーキングビル敷地内で、前日から行方不明になっていた4歳の男児、種元駿ちゃんが、頭から血を流し、全裸で倒れて死亡している状態で発見された。犯人が同市内に住む12歳の中学生であったことで、この事件は社会に大きな衝撃を与えた。この12歳の少年は、なぜ何の罪もない駿ちゃんを7階の立体駐車場から落として殺害したのか。

1. 少年の殺害の動機
少年は、補導後の県警の事情聴取で、「いたずらしようとしたら騒がれたので突き落としてしまった」あるいは「自分のやっていることが分からなくなった」と語ったと伝えられた。読売新聞の連載「12歳と向きあう」(7月16日)に掲載された、千葉明徳短大特別講師(臨床心理学)の富田富士也氏の見解によると、現在の少年は、他者とコミュニケーションする能力が乏しく、自分の思い通りにならない相手と分かると、すぐにカッとして、別人格のように豹変することがあるので、今回の事件でも、男児を裸にして嫌がられたため、極端な行動に走ったのではないかとのことである。実際、この少年には、思い通りにならないと、パニックになるという証言がある。
このように、少年は、駿ちゃんを裸にしようとしたところ、騒がれたので、気が動転して、発作的に突き落としてしまったと当初は考えられていた。しかしこのストーリーは、その後の捜査によって否定されることになる。少年は、事前にハサミを購入して用意し、駿ちゃんを裸にした後、性器にハサミでむごい切り傷をつけた。これでは、駿ちゃんが騒ぐのも当然である。頭脳明晰な少年にこのことが予見できなかったとは考えにくい。
もしも駿ちゃんの悲鳴が周囲に聞こえることを恐れて殺したというのであれば、首を絞めて殺すというのが目的合理的な方法である。外へと突き落とすのは、逆効果ではないだろうか。また発作的に突き落としたにしては、駿ちゃんの落下地点が真下過ぎる。突き落とされたと思われる場所の手すりには、駿ちゃんの小さな足跡がついていたので、少年は、駿ちゃんを抱き上げ、いったん手すりに立たせ、それからストーンと下に落としたようだ。
この事件が起きる前、この少年が屋上から犬を突き落とすところが同級生の母親に目撃されている。だとするならば、少年は、初めから犬にしたのと同じことを駿ちゃんにするつもりではなかったのか。いずれにせよ、この少年は、自分の目的が達成できなかったから気が動転して駿ちゃんを殺害したというよりも、気が動転するような殺害(傷害?)の快楽を味わうことを当初からの目的としていたと見た方が真実に近い。
2. エロティシズムの快楽
多くの人は、6年前に神戸で起きた酒鬼薔薇聖斗事件との類似性を指摘しているが、確かに、二つの事件はよく似ている。私は、「酒鬼薔薇聖斗の深層心理」で、バタイユのエロティシズム論を援用して、酒鬼薔薇聖斗事件の解釈を試みたが、その解釈は間違っていないと今でも思っている。後に酒鬼薔薇聖斗が語ったところによると、彼は、小学五年生の時、ナメクジやカエルを解剖して、体のうずきを感じ、小学六年生の時、猫を解剖して、初めて射精を体験したとのことである。今回の長崎での事件にも、同じエロティシィズム論が使えそうである。
エロティシズムとは、日常性を破って非日常性をあらわにし、エクスタシーの快感に酔うことである。例えば、強姦は、典型的なエロティシズムである。男が法を「破って」処女を犯すとき、彼は彼女の服を「破って」非日常的な裸体をあらわにし、処女膜を「破って」秘密の内奥と一体になって、興奮する。このように、禁断の木の実を手にすることがエロティシズムの本質であり、エロティシィズムにおいては、性の欲動と死の欲動、快感原則と涅槃原則が根源的に一体となっている。
酒鬼薔薇聖斗も、長崎の少年も、小動物の虐待という、男の子なら誰でもやる比較的日常的な段階からエロティシズムを始めた。ちょうど、性器の写真も、見慣れて希少価値がなくなってくると、もはやエロティシズムを惹き起こさなくなるように、動物虐待も、繰り返しているうちに、新鮮味がなくなって、エロティシズムを惹き起こさなくなる。だから、エロティシズムの追求者は、比較的日常的な段階から出発して、より非日常的な体験を求めるうちに、犯罪をエスカレートさせてしまうことが多い。
長崎の少年も、7月の事件に至る前に、中間的な段階の犯罪を行っていた。少年は、同じ年の4月に、3歳の男の子を誘拐し、衣服を脱がして逃げた。この時は、これだけで、少年にとって十分なエロティシズムだったのである。7月の時には、男の子を裸にするだけでは不十分で、ハサミで性器を傷つけなければ、エクスタシーを体験できない段階にまで来ていたと考えることができる。
少年は、事件を振り返って、「自分のやっていることが分からなくなった」と言っているが、こうした、自分が自分でなくなる状態は、エクスタシーの心的状態を表していると考えることができる。エクスタシーという言葉は、「外に置く」という意味のギリシャ語に起源を持つ。エクスタシーとは、魂が、エロティシズムによって自己の身体から外に置かれて、我を忘れて(beside oneself 自分の外で)昇天する恍惚状態である。
セックスしている時、「イク!」と叫ぶ人は、エクスタシーを体験している。それは天空に「行く」ような昇天体験である。「行く」は、同時に「逝く」でもある。私たちは、死ぬと魂が体を抜け出して、天に向かうと想像している。死んだ経験がないのに、多くの人が、こうしたセックスの体験からの類推を受け入れるのは、性の欲動と死の欲動が根源的に同一であるからだ。
ダットンとアロンは、深い谷に架かっている長い吊り橋を渡る男性に、魅力的な女性が声をかけ、電話番号を書いた紙を渡すという心理学の実験を行った。その結果、吊り橋を渡っている最中に紙を渡された男の方が、安全な場所にいる時に紙を渡された男よりも高い割合で女性に電話をかけてきた。この有名な実験は、死の危機に接している時の方が、そうでない時よりも性的に興奮しやすいという事実を実証している[1]。
エロティシズムにおけるエクスタシーをこう解釈すると、なぜ少年が駿ちゃん(あるいは犬)を、高所から落として殺したのかという謎を解くことができる。駿ちゃんの落下が、少年の目にどのように映ったのかを想像してみよう。落下するにつれて、駿ちゃんの体はどんどん小さくなる。それを肉体の落下と見ないならば、魂としての自分が天高く上昇しているように見える。肉体の落下は、同時にヴァーチャルな魂の昇天である。少年は、駿ちゃんを、7階の立体駐車場から落とすことで、魂の昇天というエクスタシーを体験した[2]。
こうしたエロティシズム追求型の犯罪が起きる家庭的背景は何であろうか。酒鬼薔薇聖斗と長崎の少年とのもう一つの共通点は、家庭が母権的で、父は母の言いなりになっていて、存在が希薄であることだ。長崎の少年の母は、一度離婚して、子供をつれて実家に戻っており、その後復縁したものの、この家庭では、一時的に父親が文字通り不在だったことになる。幼稚園と小学校を三度も転園・転校させたことも、少年の超自我の形成を阻害させることになった。
3. 人類史の母権的段階
個体発生的にも系統発生的にも、エロティシズムの追求は母権的段階で見られる特徴であり、父権的段階ではそれが抑圧される。個体発生に関して言うと、男根期や学童期に、子供は母への依存を捨て、父や教師を自我理想として超自我を形成し、エスの奔放な動きを制御するようになる。系統発生に関して言うと、男性宗教が成立した時期に、人類は、エロティシィズムのエクスタシーで神と一体になるプリミティヴな女性宗教を捨て、父なる神を自我理想として超自我を形成し、性に対して禁欲的になる。
キリスト教や仏教やイスラム教といった男性崇拝の宗教は、一部の怪しげな異端を除けば、エロティシズムを惹き起こすオルギアを宗教的儀式としては認めない。しかし、それ以前の女性崇拝の宗教では、生贄を屠ることで聖なるエクスタシーを体験するというタイプの宗教的儀式が盛んに行われていた。マヤでの人身御供はその一例である。エクスタシーは、生贄が、聖なるトーテムやかわいい我が子など、貴重であればあるほど大きくなった。
今でも未開社会の人々は、動物の供犠を盛んに行っていることが多い。人身御供は、文明社会の影響を受けて、さすがに近年見られなくなったが、大航海時代には、世界の辺境のいたるところで行われていた。未開社会での人身御供の儀式がヨーロッパから来たキリスト教徒たちに与えたカルチャーショックは、長崎の少年や酒鬼薔薇聖斗による人身御供の儀式が世の大人たちに与えた衝撃と似たものだった。
もちろん、近現代の未開社会と原始社会とを安易に同一視してはいけない。個体発生が系統発生を繰り返すと主張するならば、文明成立以前の太古の時代に、人々が供犠によって聖なるエクスタシーを体験した証拠を示さなければならない。生贄として屠られたと考えられる動物や人間の骨なら多数出土しているが、それだけでは供犠を執行した人々の心の内までを窺い知ることはできない。その点、16500年ほど前に描かれたラスコー洞窟の壁画は、これから説明するように、氷河時代の人々が、長崎の少年と同様に、エロティシズムのエクスタシーを体験していたことを示す証拠として特筆に値する。
ラスコー洞窟は、ヨーロッパに多数存在する氷河時代の壁画遺跡の一つである。多くの壁画は、人間の居住に適さない洞窟に描かれた。人間が居住する洞窟に描く場合でも、人が住めない、洞窟の奥に描かれた。だから、洞窟壁画は、住居の装飾として描かれたわけではない。そうした世俗的な絵は岩陰などに描かれたのであって、洞窟内部に描かれた絵は、宗教的な性格を帯びている。
宗教的な絵が洞窟の中に描かれるのは、この時代の宗教が地母神崇拝であることと関係がある。すなわち、洞窟の中は、母なる大地の子宮の中として表象されていた。フランスとスペインの国境付近にあるニオー洞窟は、床が粘土で、その上には小さな足型がたくさん残っている。ここで成人式が行われたのかもしれない。胎児が子宮の中から出てきて産まれるように、子供たちは、地母神の「子宮」の中から、狭い通路を通って出てくることで、成人式という第二の出産の通過儀礼を行ったと考えることができる。
洞窟に描かれているのは、牛、馬、鹿、ヤギなどの動物で、これは当時の自然崇拝を反映している。日常的な食料となったトナカイはあまり描かれていない。描かれている動物は、トーテム的な性格を持つと考えられる。人間が描かれることは少ないが、ラスコー洞窟には、まるでそれが秘事であるかのように、一箇所、見つけにくい深い堅坑に、鳥の顔をした奇妙な人間の絵が描かれている。近くには、鳥が杖に止まったような物と腹から腸が出ている瀕死の野牛が描かれている。少し離れた左の方にはサイの絵がある。

ラスコー洞窟を世界に紹介したブルイユ神父によると、野牛を傷つけたのはサイで、怒り狂った野牛は狩人を角にかけて殺し、そして鳥の杖は狩人の死体が埋葬されている場所を示しているとのことである。しかしこの説明では、なぜ狩人の顔が鳥の形をしているのかが分からない。さらに、もしこの鳥人が狩りで死んだとするならば、なぜ彼のペニスが勃起しているのかも説明できない。牛の内臓が露出している所には、槍が突き刺さっているのだから、牛を殺したのは、サイではなくて、人間ではないのか。
ドイツの考古学者、キルヒナーは、狩猟中の事故という常識的解釈を斥け、シベリアのヤクート族に、牛を生贄として屠る、氷河時代から続く儀式があることを手掛かりに、鳥人をシャーマンとして解釈しようとする。ヤクート族は、鳥の杖を、犠牲となった牛の魂を天国に導くための補助の精霊として使っている。そして、ヤクート族のシャーマンも、その性質を分け持つために、鳥の衣装を身につけている。ラスコー洞窟の鳥人も、同様の理由で鳥の仮面をかぶっている。鳥人が倒れているのは、死んだからではなくて、トランス状態になっているからだと理解しなければならない[4]。
私も、このキルヒナーの解釈に賛成である。ラスコー洞窟の鳥人が、長崎の少年と同様に、生贄を屠ることで、エロティシズムのエクスタシーを体験していることは、彼の勃起したペニスを見れば明らかである。鳥人の肉体は、地に倒れるが、彼の魂は、それこそ鳥のように昇天する。実際、彼の両手は、鳥が羽ばたくように、大きく広げられている。
4. ジル・ド・レの快楽殺人
エロティシズムへの欲望は、個体発生的にも系統発生的にも、父権的段階で抑制されるが、決して消滅するわけではない。象徴的な意味での父の権力が揺らぐ時、文明社会の大人であっても、快楽殺人に走ることがある。快楽殺人の過去の実例は枚挙に暇がないが、ギネスブック掲載ものの快楽殺人の世界記録を樹立したのは、15世紀のフランスの大貴族、ジル・ド・レである。バタイユも『ジル・ド・レ論―悪の論理』でこの事件を主題的に取り上げている。
ジル・ド・レは、部下に命じて領内の男児を誘拐し、城内の自室に引き入れ、ひもや縄を用いて男児の頸を棒や鍵などに吊るした。男児が苦しんであえぐと、ジル・ド・レは性的に興奮した。男児の頸の血管を切って、血がほとばしると、エロティシズムは頂点に達し、ジル・ド・レのペニスからは精液がほとばしった。殺害方法の残忍さは、次第にエスカレートしていったのだが、こうして生贄として殺された無垢の男の子は、死体の数から少なくとも150人はいたことが確かめられている。犠牲者は1000人を超えるという説すらある。長崎の少年や酒鬼薔薇聖斗など、ジル・ド・レの足元にも及ばない。
ジル・ド・レは、いつからこのような野蛮な儀式を楽しむようになったのか。ジル・ド・レは、22歳の時から、キリスト教が禁止する降魔術にのめりこんだが、これは男児殺しを始める6年前のことで、直接的なきっかけではない。直接的なきっかけは祖父の死である。ジル・ド・レが11歳の時、父が戦死したので、祖父がジル・ド・レの後見人になった。男児殺しが始まるのは、祖父が死んだ年からである。祖父は、ジル・ド・レにとっての唯一の重石であり、祖父の監視から解放されたジル・ド・レは、手綱から解放された荒馬のごとく、存分にエロティシズムを楽しみ始めた。当時のフランス国王は、国王としては有名無実の存在で、ジル・ド・レの領地は、事実上彼の独立国だった。
このように、ジル・ド・レの狂った犯罪の背景には、イエス・キリストや祖父や国王といった、象徴的な意味での父の権力の不在があったと考えることができる。父の権力が強すぎると、別のタイプの犯罪を惹き起こすことになるが、弱すぎると、快楽殺人が横行するようになる。
5. 追記:坂東眞砂子の子猫殺し
日経新聞(2006年8月18日夕刊)の「プロムナード」というコラムに、仏領タヒチ島在住の直木賞作家、坂東眞砂子が子猫殺しを告白して、日経新聞社に抗議の声が殺到している。
こんなことを書いたら、どんなに糾弾されるかわかっている。
世の動物愛護家には、鬼畜のように罵倒されるだろう。
動物愛護管理法に反するといわれるかもしれない。
そんなこと承知で打ち明けるが、私は子猫を殺している。
家の隣の崖の下がちょうど空地になっているので、生れ落ちるや、そこに放り投げるのである。
タヒチ島の私の住んでいるあたりは、人家はまばらだ。
草ぼうぼうの空地や山林が広がり、そこでは野良猫、野良犬、野鼠などの死骸がころころしている。
子猫の死骸が増えたとて、人間の生活環境に被害は及ぼさない。
自然に還るだけだ。[5]
子猫を高所から落として殺す方法に注目して欲しい。これは、長崎の少年と同じではないのか。非難を浴びた後、坂東は子猫殺害に関して次のように弁明している。
タヒチ島に住みはじめて8年経ちます。この間、人も動物も含めた意味で『生』ということ、ひいては『死』を深く考えるようになりました。7月から開始した日本経済新聞社紙面『プロムナード』上での週1回の連載でも、その観点からの主題が自然と出てきました。『子猫殺し』のエッセイは、その線上にあるものです。ことに、ここにおいては、動物にとって生きるとはなにか、という姿勢から、私の考えを表明しました。それは人間の生、豊穣(ほうじょう)性にも通じることであり、生きる意味が不明になりつつある現代社会にとって、大きな問題だと考えているからです。[6]
これは、エロティシズムを「死にまで至る生の称揚」と捉えていたバタイユの考えと同じではないだろうか。
6. 参照情報
- ↑Dutton, D.G., & Aron, A.P. “Some Evidence for Heightened Sexual Attraction Under Conditions of High Anxiety” , Journal of Personality and Social Psychology 30, 1974. p.510-517.
- ↑麻薬などを吸ってトランス状態になることを「ハイになる」と言うことがあるが、これは文字通り訳せば、「高くなる」ということである。薬物を吸うことも、一種の死の体験である。
- ↑Le Ministère de la culture et de la communication. “Homme et oiseau/Le Puits, vue d’ensemble” Accessed on 2019/08/29.
- ↑ミュンヘン大学のラッペングリュックによると、ラスコー洞窟の壁画に描かれている牛の目、鳥人、棒の上の鳥は、それぞれ、夏の大三角を構成するべガ、デネブ、アルタイルに相当するとのことである。だから、この三つは、独立した絵ではなくて、相互に密接な関係がある。反面、これらの三点セットとサイトの関係は不明確だ。バタイユは、『ラスコーの壁画』の中で、キルヒナーの解釈ではサイが説明できないと言って、シャーマン説に難色を示しているが、だからといって、キルヒナーの解釈を受け入れるわけにはいかない。そもそも氷河時代のヨーロッパにサイがいたはずがない。氷河時代のヨーロッパ人にとって、サイは直接見たことがない伝説の動物であり、あの世でしか出会えない獣神ではなかったのか。こう考えれば、トランス状態のシャーマンと関係付けることができる。
- ↑坂東眞砂子「子猫殺し」in『日経新聞』プロムナード(2006年8月18日夕刊).
- ↑『日経新聞』2006年8月24日.





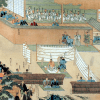
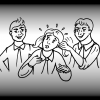










ディスカッション
コメント一覧
何と単純なエロティシズム論争でしょうか。。。。。どの様なお方か存じませんが、強姦をエロティシズムとは驚きました。暴力がエロティシズムならどの様な行為もエロティシズムに属する事になります。戦争も貴方様にとってはエロティシズムになりますね。先ずこのようなことをお書きになるお方は多分男性でしょうね。先ず貴方が強姦されてからそのご意見をお聞きしたい事です。長崎の少年もエロティシズムのために殺害をしたのでないと確信致します。この犯罪を犯した少年はすでにこの殺害以前にも問題があり、精神的に異常者、正常に精神が育たなかった子供でエロティシズムとは関係ないと断定致します。そうでなかったら人を殺す事、即ち自分が凶器を持ち他者より優位に立った時点で、または動物を虐待、殺害して征服することに喜びを感じている異常者の何者でもありえない。精神異常者にエロなどという感覚は存在しないと思っておりします。それをエロティシズムなどと勘違いなさる意見は受け入れる事は出来ません。先ず人が生死をかけている時点でエロなどという興奮が起こるでしょうか?多分犯人も被害者もパニックみたいな状況で、頭の中には真暗な闇、思考が消えうせたただの暴力を振るう人間であると思います。貴方様が戦争の最前線に立って敵に打たれる状態において、エロティシズムを感じたのなら貴方の説を納得するでしょう。
バタイユが言っているエロティシズムとは、たんなる暴力ではありません。エロティシズムには、「…のために」という目的意識が欠けています。だから、例えば、戦争は、領土拡大のため、あるいはデフレ対策のためなどの目的に対する手段として行われる限り、エロティシズムではありません。逆に、セックスも、それが子供を産むための労働と意識される限り、エロティシズムではありません。こうした初歩的な説明は、「蕩尽と至高性」で既に行っているので、今回は、省きました。まずは「蕩尽と至高性」を読んで、バタイユが言うエロティシズムと常識的な意味でのエロとの違いを理解してください。
長崎の少年はアスペルガー症候群ではないか?精神科医の作田氏も言っていた。アスペルガー症候群(自閉症スペクトラムに属す)←脳の機能的疾患(遺伝が要因)
●変化を嫌う
●接し方のルールがわからず無邪気に周囲の人に対して迷惑なことをしてしまうことがある。人を傷つけるということには鈍感(相手の立場に立って考えられない)。
●パターン的行動、生真面目すぎて融通が利かない。毎朝の通学電車では同じホームの同じ場所から、同じ時間の同じ号車に乗ることに決めていたりする。パターンを好むということは反復を厭わないことでもある。
●アスペルガー症候群の子どもは(大人も)感覚刺激に対して敏感。敏感さは聴覚、視覚、味覚、嗅覚、温痛覚のいずれの感覚の敏感さもありえる(特に視覚が敏感らしい)。
●アスペルガー症候群の子ども(大人も)は予測できないことや変化に対して苦痛を感じることが多い。
●独り言を言うことが多い(考えていることを口に出す)
●物事をいつまでも同じにしておこうとする欲求が強く、そうでないと非常に不安。いわゆる「こだわり」。
●自発的に行動することが少なく、興味の幅が狭い
●物まねをしているような不自然な言語表現
●自閉症スペクトラム全体としては一万人に91人(およそ100人に1人)。
確かに、長崎家裁に提出された精神鑑定書は、少年を高機能広汎性発達障害(アスペルガー症候群/高機能自閉症)と診断しています。しかし、この障害が非行など反社会的行動につながる直接的な因果関係はありません。碇浩一、碇精神医学研究所(福岡市)所長曰く、
前々からの疑問がここでも頭をもたげて来ましたので質問させて戴きます。もし犯人が成人で通常裁判が行なわれ、弁護士が永井俊哉氏の「意識に関する説」=「意識とは選択である」を引用して、「犯人は性的興奮に基づく激情の故に、他の行動を選択できる意識状況にはなかったと言えます。つまり、犯人にはそれをする意識がなかったのです。よって、夢遊病者の行動と同等を言え、殺人罪は成立しません。」と、このような弁論を展開した場合、永井先生はどのように反論なさるでしょうか。興味が有ります。
これは刑法38条3項の問題です。「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない」という条文です。判例は「違法性の意識不要説」ですが、普通は、制限故意説としての「違法性を意識する可能性の有る事が可罰的責任の根拠」という「違法性の意識の可能性」説を採る人が多いで
しょう。
私の推察では、「意識する可能性有るところには、意識有り」と構成するしかないように思うのです。これは「記憶はその時思い出さなくても、思い出す可能性がある限り、記憶として存在する」という論理構成と同じだと思います。とはいえ、「意識」と「意識の可能性」とはやはり、同一とは言えず、違うものでしょう。冷静な状況では意識する可能性が有ったとしても、実際の切羽詰まった状況では「他の多数の選択肢を意識できない」ことは多々あります。この場合、「狭い選択肢の中での選択意識」となりますが、これをもっと極端化して行くと、二者択一の中の選択意識、更には「一者のみの選択不能の状態」という問題になります。この選択不能の一本道を行く場合、この場合はすべて「意識なし」と評価すると、今回のような事件も違法性を問えなくなる可能性があるのではないでしょうか。
悪魔礼拝の生贄殺人のエクスタシーに酔いしれている時、「酔いしれる」の「しる」は「占る」ですから(拙著参照。大野晋博士の説でもあります)、この場合、悪霊に憑依され悪霊の道具と化しているとも分析できます。また、悪霊を認めない唯物的な立場の場合、「違法の快楽に酔う状態」と見て、酩酊状態は心身喪失又は心身耗弱状態と評価され、意識が無いか、希薄な状態と評価できるでしょう。
この場合でも「意識はあった」という場合、「現実的な選択能力はこの時点で既に喪失しているものの、それを行なっていない状態や、他の選択肢を実行している状態について意識することはできた」と構成する必要があるでしょう。となると、「選択」と「意識」にはズレがあると分かって来るように思うのです。つまり、「意識=選択」という永井説は崩れませんか?
刑法では、「原因において自由な行為」理論で、選択不能の一本道の場合に違法性を問えなくても、その一本道に「入る前の段階」では選択の余地が有ったのだから、その選択不能の道に「入る選択」をしたという、そこに非難の余地が有る、と構成する場合があります。この事件の場合も「意識が無い」説ならこれで行くことになるでしょうが、酩酊状態との同一視はやはり無理として、「意識は有った」説で行く説を永井先生はとりますか。それとも当該犯罪行為者に意識はなかったと構成しますか?
法学的には、最後に挙げた解釈でよいと思います。薬物の服用等により、精神錯乱状態になって、知らないうちに犯罪に手を染めるような場合、薬物の服用が犯罪につながるかもしれないということを予見するだけの能力があるならば、有罪になります。自由を否定するだけの自由があるならば、その自由に見合った責任が問われるということです。
「意識されない選択は、選択ではない」というようなことを私は主張していません。選択とは、複雑性の縮減であり、たとえ意識されなくても、可能性の数が減れば、選択が行われたことになります。私は、「意識とは何か」で、次のような例を挙げました。
このロボットが、たまたま「犯罪行為」を選択したとしても、そのロボットには罪がありません。このロボットを作った人には責任があるかもしれませんが。
種元駿ちゃん事件についての私の質問に対して先生は「法学的には、最後に挙げた解釈(★原因において自由な行為の法理★)でよいと思います。」と回答なさいました(★内は大空挿入)。しかし、この回答には大きな問題が有るように思われます。というのも、判例・学説ともに、「サディスト的な性的異常興奮に基づく殺人行為」にまで「原因において自由な行為」の法理を適用する見解は無いからです。
性的異常興奮のさなかに殺人行為を実行しても、法学的には、行為者に「意識なし」とは認めません。欲望と快楽追求の一本道であったとしても、なお「事理弁別能力は有った」と見ますし、自己規制も不可能とは言えないと見ますし、犯罪回避の期待可能性も皆無ではないと見て、翻意可能性の余地を認め、殺人の故意責任を認めます。また、バタイユのエロティシズム論から言っても、意識的・主体的に「禁止領域」への侵犯行為を実行するからこそ、そこに「領域打破・限界超越」体験や自己存在の拡大体験などの歓喜を味わう、という「バタイユ的弁証法」が成立するのでしょう。ですから、この種の性的異常興奮には、「悪いことをしている、いけない事をしている」という明確な意識があるからこそ、その侵犯行為に興奮する、という部分があると思われます。つまり、反規範性を認識した上で「敢えて」それを踏みにじる処にこそ、至高の快楽を感じてしまう、という「恐ろしい悪性」が潜んでいる、という見方も可能ではないでしょうか(勿論、実際には低年齢ゆえの「超自我の未熟」という点も大きいでしょうが)。
恐らく、低年齢ゆえに、「犯罪回避の期待可能性」「翻意可能性」は、その分、低い数字になるでしょうから、その分、非難の度合いも低くならざるをえないでしょう。しかし、だからといって、永井先生のような「翻意可能性ゼロゆえに意識なし」ゆえに「原因において自由な行為の法理でその可罰性を論じる」というお立場(前半は私の推測ですので、そんなことは言っていないと言われてしまうかも知れませんが)は、ドライに過ぎるように思います。
この問題は「意識をどう考えるか」に関わる問題でしょう。意識の本質を「主体的選択作用」だと見る場合、この選択肢を「単一の選択肢」に絞る作用のみを念頭に置くと、この種の事件での翻意可能性をゼロに見る見方になる傾向があるでしょう。しかし、意識は同時に複数の選択肢を選ぶことも可能だとの、「複数同時選択作用」を考慮に入れるなら、翻意可能性を充分に認めることができます。
ここで私の言う「複数同時選択作用」とは、風景の一点をフォーカスして凝視する作用のほかに、少林寺拳法の「八方目」のように、四方八方を同時に見て敵の攻撃に備えるような意識の働かせ方です。あるいは、嫌いな男に現実には身をまかせて抱かれていても、思いは他所にいる別の好きな男のことを思っている、というような働かせ方です。
他に、意識には「能動意識」と「受動意識」の2種類があるようにも思います。感受作用による意識は受動意識と言えるでしょう。「きく」行為にも、能動的に「聴く」意識と、嫌でも聞こえてしまう「聞こえる」意識があるでしょう。こうした考察をして行くと、意識の本質は「理解」にあるように思います。「理解のないところに意識なし」ではないでしょうか。
昆虫は触覚を激しく動かして環境状況を理解・把握しようとしています。ゴキブリを新聞紙をまるめたもので叩いて殺そうとしてそれが失敗すると、この突然の攻撃にゴキブリは「驚いて」逃げようとして、動作を最高速度に上げて、動き回ります。このゴキブリは「危険」を彼なりに察知、即ち「理解=意識」しているのではないでしょうか。
前回の投稿で、私は、“このロボットが、たまたま「犯罪行為」を選択したとしても、そのロボットには罪がありません。このロボットを作った人には責任があるかもしれませんが”と書きましたが、この文章の「ロボット」を「少年」、「ロボットを作った人」を「少年の両親」で置き換えてみてください。
現行の刑法は、14歳に満たない少年には責任能力を認めていませんから、少年は処罰されませんが、少年を育て、かつ親権を持つ両親には、もし子供を甘やかすと、将来問題行動を起こすかもしれないと予見するだけの能力があると認められるので、その能力に見合った責任を問われることになるでしょう。
鴻池祥肇防災相が、「親は市中引き回しのうえ打ち首にすればいい」と発言したのは周知のとおりですが、両親にこうした刑事罰を与えることはできません。子供を甘やかすこと自体は違法行為ではないからです。たぶん、民事裁判を通して、加害者の両親が、被害者の両親に対して、賠償金を支払うことになるのだと思います。
最初の投稿で、私は
と書きましたが、その回答として、永井先生から“法学的には、最後に挙げた解釈(★原因において自由な行為の法理★)でよいと思います”との回答を戴いたので(★内は大空挿入)、「やややっ」と思った次第です。
もし、最初の前提を見落としておられたのなら、再度質問させて下さい。仮に21歳の青年が強いエクスタシーを感じながら無我夢中で快楽殺人を犯した場合、法学的には殺人の実行行為の時に犯人には事理弁別能力も翻意可能性も故意責任も有り、と見ますが、永井哲学からしても「意識有り」「他の選択をすることは可能だった」と評価しますか? 性の抗し難い強烈な欲動と恍惚意識のさなかにあっても、「他の選択をする自由は有る」と評価なさいますか?
エクスタシーの快感の故に、脳内麻薬が分泌して、脳髄が麻痺して「他の選択を想起することすらできない状態」になっていたとしても…?
大空さんが、成人の犯罪について質問しているということには、気が付きませんでした。うっかり読み飛ばしたために、議論がかみ合わなかったのかもしれません。
そこで、もう一度、これまでの投稿を読み返してみたのですが、どうやら、私たちの議論は、
1.意識=主体的に選択する能力
2.理性=善悪を分別する能力
という二つの異なる能力をはっきり区別していないために、わかりにくいものになっているようです。意識的選択と無意識的選択を区別するだけでなく、理性的選択と非理性的選択をも区別するべきです。フロイトの言葉を使うならば、1と2の区別は、自我と超自我の区別に対応します。自我は、超自我ともエスとも異なるのですから、“超自我の不在→無意識”という判断は成り立ちません。
1と2の区別に基づき、触法行為を三つのケースに分けて、どのような刑が求められるのかを考えてみましょう。どの場合にも、触法行為の因果関係を遡って、“意識があり、さらに理性的な分別がある存在者”に責任を負わせるというのが、基本原理です。
【ケースA】1と2の両方が存在しない場合
甲が乙を笑わせた結果、乙が口の中に含んでいた飲み物を吐き出してしまい、その結果、乙は丙の衣服を汚してしまった場合。この場合、乙の行為は反射的で無意識的行為なので、乙には全く何の責任もありません。もし甲が、このような事態を予測するだけの能力があり、かつ理性的な分別がある場合には、甲がその責任を負わなければなりません。
【ケースB】1は存在するが、2は存在しない場合
14歳未満の子供が、法に触れる行為をした場合、少年に意識があり、選択能力があっても、現行法は、少年には善悪を分別する能力がないとみなすために(例の12歳の少年には、殺人を悪と判断する能力ぐらいはあると、私は個人的には考えているのだけれども)、少年は罰せられません。しかし、少年の保護者は、責任を取らなければならないでしょう。
触法行為の因果関係を遡ってみると、“意識があり、さらに理性的な分別がある存在者”(今の例だと、少年の保護者)が、同一人物である場合もあります。薬物の服用等により、精神錯乱状態になって、犯罪に手を染めるような場合、意識はあるが、理性が失われているために、その時点では責任能力があると言えないが、服用前に理性的な分別がある場合は、その時に遡って責任を問うことができます。
【ケースC】1と2の両方が存在する場合
成人が、エロティシズムの快楽を求めて、法を破る時、その人物は、自分の行為が悪いとわかっているにもかかわらず、否、悪いと感じるからこそ犯行に及んでいるわけだから、通常の犯罪と同様に処罰されます。