芸能人とはいかなる存在か
2004年から、日本のマスメディアに韓流ブームがおきた。国粋的な日本人の中には、眉を顰める人もいるが、もともと日本の芸能界には在日コリアンが多いし、外国人が芸能界でもてはやされるというのは自然な現象である。そもそも芸能人とはいかなる存在なのか、カタルシス理論の観点から分析しよう。

1. 境界をまたぐ芸能人
芸能界には、美川憲一、カルーセル真紀、ピーコ、おすぎ、山咲トオルなど、男か女かよくわからない人がたくさんいる。こうした性の境界をまたぐ人[1]は、通常の就職では差別されることが多いのにもかかわらず、なぜ少年少女が憧れる職業に就いて、テレビで活躍することができるのだろうか。
民族の境界をまたぐ芸能人も枚挙に暇がない。セイン・カミュ、デーブ・スペクター、ダニエル・カールなど、一見してわかる外人タレント以外にも、名前と外観は日本人風だが、実は在日コリアン(出身)という芸能人も多数いる。松坂慶子、和田アキ子、都はるみ、にしきのあきら等がそうだ(と言われている)。ハーフであることは、ニューの方を含めて、芸能人になる上で、メリットになることはあっても、デメリットにはならない。
日本とアジアの文化的境界上に位置する沖縄も、日本における経済的ステータスが低いにもかかわらず、安室奈美恵、喜納昌吉、MAX、SPEED、DA PUMPなど、多くの芸能人を輩出している。フィンガー5などの過去の例を見ればわかるように、これは、沖縄アクターズスクールだけのおかげというわけではない。この他にも、例を挙げることは控えさせてもらうが、人間とは思えないような体格や頭脳の持ち主、人間と動物の境界上の両義的存在も、芸能人として活躍している。
境界上の両義的存在は、スケープゴートの特性である。スケープゴートは、システムと環境との境界を不明確にし、システムのエントロピーを増大させるがゆえに、穢れた存在と表象され、排除されるが、その排除がカタルシス効果をもたらすために、排除された後は一転して、秩序の体現者へと祭り上げられる。イエス・キリストや天皇は、そうしたスケープゴートの段階を経て、社会システムの複雑性を縮減する媒介者となった。では、境界上の両義的存在である芸能人も、同様に、スケープゴートとして、カタルシスをもたらすのだろうか。
2. 俳優の原点
古代の日本では、芸能人は、俳優(わざをぎ)と呼ばれた。「俳優」という漢字の「俳」は「戯れ」を、「優」は「憂い」を意味する。だから、「俳優」という漢字の語源は、観客を笑わせたり、泣かせたりする、今の俳優(はいゆう)の演技と遠く隔たってはいない。ならば、古代の日本人が、「俳優」を「わざをぎ」と訓じたのはなぜか。
白川静『字訓』によると、「わざをき」とは、隠されている神意である「わざ」を「招(を)き」求めることである。『日本書紀』では、「猿女君(さるめのきみ)の遠祖(とほつおや)天鈿女命(あめのうずめのみこと)、則ち手に茅纒(ちまき)の鉾(ほこ)を持ち、天石窟戸(あまのいはやと)の前に立たして、巧みに俳優を作す。[2]」という文で使われている。
この時の俳優行為は、滑稽なものだったようだ。『古事記』によると、アメノウズメは、「胸乳(むなぢ)掛き出し、裳の緒を番登(ほと)に忍し垂れ」、つまりストリップ・ダンスをし、「爾くして、高天原(たかまがはら)動(とよ)みて、八百萬(やほよろず)の神、共に咲(わら)いき」とのことである。岩隠れしていたアマテラスは、神々の笑いを不審に思って、天の岩屋戸を少し開けて、様子を見ようとした。その機会をとらえて、アメノタヂカラヲノカミがアマテラスを引き出し、高天原と葦原中国(あしはらのなかつくに)は、再び明るくなった。神意というよりも、神そのものを招き求めたことになる。

「是に八百萬の神、共に議りて速須佐之男の命に千位(ちくら)の置戸(おきど)を負わせ、また鬚と手足の爪を切り祓(はら)えしめて、かむやらひやらひき」とあるように、アマテラスが岩隠れする原因を作ったスサノヲには、厳しい刑が科せられた。スサノヲもまたスケープゴートであった。後にスサノヲがヤマタノオロチの尾から獲た神剣は、現在熱田神宮に還座され、それを記念して、熱田神宮は、暗闇の中で神職がいっせいに高笑いをするという奇妙な神事を執り行っている。天の岩屋戸の神話に描かれている出来事が、この酔笑人神事(えようどしんじ)の起源となっていると推測できる。
天の岩屋戸の神話が、卑弥呼の殺害と二代目卑弥呼(万幡豊秋津師比売命)の即位に対応していると解釈しよう。すると、ここには、三つのカタルシス(ケガレがハレること)が重ねられていることに気が付く。一つは、笑いである。これまで「人はなぜ笑うのか 」と「人はなぜ泣くのか」で述べたように、笑うことは、泣くことと同様に、カタルシスである。もう一つは、アメノウズメのストリップ・ダンスに見られるエロティシズムである。エロティシィズムは、魂を昇天させ、肉体の穢れから浄化する。そして、エロティシズムは、死の体験と結びついている。あと一つは、卑弥呼の死(太陽神の岩隠れ)に見られるスケープゴートの排除である。卑弥呼の後継者を擁立し、太陽が復活することで、カタルシスが成し遂げられる。
3. スケープゴートとしての芸能人
古代の天皇は日数み(ヒヨミ→カヨミ→コヨミ)、すなわち暦の支配を職能としていた。だから、卑弥呼の治世の末期のように、天候不順となった場合は、責任を取らされて「王殺し」となることは、未開社会の慣例として、決して珍しいことではなかった。天皇は、そのスケープゴート的起源のためなのか、歌舞伎では、怨霊と結びられることが多い。山口昌男は、天皇、歌舞伎俳優、芸者、遊女、「穢多」は、スケープゴートの候補となるアウトカーストだったと言う[3]。
歌舞伎は、「乱暴する」という意味の「かぶく」という動詞が名詞になったものである。折口信夫の「ごろつきの話」によると、
日本の芝居には、濡れ場・殺し場など言ふ、残虐な或は性欲的な場面が少なくない。[…]しかし、歌舞伎芝居にあつては、既に、其起こりが。乱暴・異風 ― そして、それが性欲的であつた ― を取り入れた芸術なのであるから、そうしたこと ― 残虐的、或は、性欲的な場面 ― が、多分にあつたとしても、其は、必ずしも、不思議とするには当たらないのである。[4]
今でこそ高尚な伝統芸能と位置付けられている歌舞伎も、成立当初はヤクザ映画やポルノ映画と同じ機能を果たしていた、つまり、大衆のエロティシズムへの欲望を満たす見世物を提供していたのである。
4. 晒し者としての芸能人
ここで、芸能人とは何かについて、私なりに定義をしてみたい。芸能人とは、その芸能によって、不特定多数の大衆から注目を集めることでその存在が可能となる有徴な存在者である。一般の堅気の職業に就いている無徴の人たち(昔の農民や今のサラリーマン)は、職務遂行上、自分自身を大衆の好奇心の対象にする必要がない。しかし、芸能人、少なくともプロの芸能人は、自分自身を大衆の好奇心の対象にすることが仕事そのものなのである。かつて見世物小屋では、奇形児が晒しものになった。今日、さまざまな境界上の両義的存在者がテレビの画面に映し出されるのも、その異様さが、視聴者の注意を引くからである。
しばしば、芸能人にプライバシーはないと言われる。実際、有名芸能人は、公人(政治家など、公職に就いている者)でなくても公人扱いで、プライバシーがある程度犠牲になっても仕方がないと考えられている。これは、たとえプライベートなことであっても、世間を騒がせて注目を浴びることは、芸能人の仕事の一部であるからだ。このことを最も自覚して成功したのが、アメリカのセレブ、パリス・ヒルトンである。彼女は、セックスビデオの流出や刑務所入りといったスキャンダルを、世間に自分を注目させる手段として利用し、女優としてのステータスを上げることに成功した。
私の「芸能人」の定義を用いるならば、プロスポーツ選手も芸能人ということになる。芸能人として振舞うベッカムとは異なり、マスコミで騒がれることを好まない、サッカー選手の中田英寿は、サッカーとは関係のない、プライベートなことを聞く記者に嫌悪感を示し、取材を拒絶する。彼は、自分の仕事を堅気の仕事と勘違いしているようだ。
スポーツ(sports)という言葉は、もともと「遊び」「ふざけ」という意味であるが、観客が金を払うプロスポーツは、たいてい狩猟や決闘を起源としている。西洋では、見世物としての格闘技のルーツは、古代ギリシャのオリンピックで行われたレスリングやローマ帝国のコロッセオで行われたグラディエーターの闘いだが、どちらの試合でも、死者続出だった。日本の伝統的スポーツである相撲も、四世紀に成立した当初、相手が死ぬまで闘う決闘だった。スポーツとしての狩猟で獲物(game)を殺したり、決闘で敗者が死ぬの観客が見るのは、エロティシズムの快楽が目的である。サッカー選手がシュートを打ってゴールを決めたり、野球の選手がホームランを打って、ボールを観客席に入れ、観客が興奮するのは、それが射精的行為でもあるからだ。
スポーツ選手を含めて、芸能人が大衆にエロティシズムの快楽を与えるのは、本業によってのみではない。ゴシップ誌やスポーツ新聞やワイドショー番組は、「〇〇が××と結婚!」、「〇〇の愛人発覚!」、「〇〇が××と離婚!」といった、無徴の個人がしたとしても決して報道されることがない、マイナーでプライベートなネタを「電撃的スクープ」と称して、連日大々的に報道して、大衆の覗き願望を満たしている。供犠執行人が刃物で生贄を切り裂き、その内奥を暴き出すように、あるいは、興行主がストリップ・ダンサーに服を脱がせ、その裸体を観客に見せるように、イエロー・ジャーナリズムは、芸能人の私生活を公衆の面前に赤裸々に露出させ、エロティシズムの快楽を求める大衆を喜ばせる。
5. 統合の象徴としての芸能人
大衆は、エロティシズムにおいて犠牲者と一体となり、そしてこの集団的な内的体験を通して、大衆どうしが一体となる。実際、大衆たちは、共通の関心事である芸能人を話題とすることでコミュニケーションしている。だから、スケープゴートは、社会統合の原理(コミュニケーション・メディア)となるのであり、その結果、天皇のような社会統合の象徴的存在と近似した存在様態を持つのだ。そして、ここから、なぜ芸能人が容易に政治家になることができるのかをも説明することができる。
1995年に、東京都と大阪府で、タレント出身の知事が同時に誕生した。2003年には、俳優のアーノルド・シュワルツェネッガーが、カリフォルニア州知事に就任して話題となった。知識人たちは、経済や法についてほとんど何も知らない俳優やスポーツ選手などの芸能人が、選挙で当選する現象を衆愚政治として非難するが、経済や法に詳しいスペシャリストなら、ブレーンとして雇えばよいのであって、それよりもむしろ、大衆がトップの資質として問題にすることは、自分たちの統合を代表象するようなカリスマ性を持っているか否かということである[5]。指導者が、凶弾に倒れたことで、神格化され、その妻が、政治の素人であるにもかかわらず、次の指導者に担ぎ上げられることが発展途上国でよくあるが、それも同じ理由による。
6. 追記:韓流ブームと嫌韓流ブームを考える
この本文は、2004年1月1日に書いたもので、当時は、まだ韓流ブームはなかったのが、もともと日本の芸能界では、在日韓国人/朝鮮人が活躍していたのだから、日本でこういうブームが起きてもおかしくはない。韓国人/朝鮮人は、日本国内に最も多く住む外国人であり、日本人にとっては、《内なる外》とでも言うべき、両義性を帯びた存在である。
韓流ブームと同時に、嫌韓流もブームになっている。2005年7月に出版された『マンガ嫌韓流』は、2006年2月現在で、45万部も売れた。嫌韓流ブームは、一般には、韓流ブームの逆のように思われているが、はたしてそうだろうか。2ちゃんねるなどで活動している所謂ネット右翼を観察してわかることは、彼らは、韓国人を嫌っているというよりは、むしろ韓国人の愚かさを嘲笑して楽しんだり、彼らを蔑むことで優越感に浸ったりしているということである。だから「嫌韓」よりも「嘲韓」と表現するほうが、適切である。
現在、右翼掲示板等に書き散らかされているネット右翼の韓国に対する侮辱と悪罵の言語群は、まさに眩暈と嘔吐を催すほどの常軌を逸したものであり、偏狭で蒙昧で醜悪なファナティシズムの常態化であり、日本人であることを羞恥してしまうような程度と内容のものである。「嫌韓」という言葉は状況を正しく表現していない。嫌韓ではなく、蔑韓であり、嘲韓である。[6]
2ちゃんねるで「嫌韓厨」と呼ばれている人たちは、韓国人のことが気になって仕方がない人たちであり、韓国をエンタテインメントの対象として、嫌っているのではなくて、逆に愛好している人たちなのである。
社会の底辺にいて、日ごろ劣等感に悩んでいる人ほど、自分たちよりも劣っている(と彼らが考えているところの)境界上の両義的存在を放逐し、カタルシスの快感を得たがるものだ。してみると、韓流ドラマを見て涙を流す日本のおばさんたちも、韓国人の言動を笑い飛ばす2ちゃんねらーたちも、韓国人を芸能人として愛好しているという点では同じということになる。実際、例えば、盧武鉉大統領は、「嫌韓厨」の間で「お笑い芸人」として認知されている。
7. 参照情報
- ↑「KABA.ちゃん」(本名、椛島永次)のように、男と女の境界だけでなく、子供と大人の境界をまたぐタレントもいる。
- ↑「又猿女君遠祖天鈿女命 則手持茅纏之鉾 立於天石窟戸之前 巧作俳優」『日本書紀』巻第一の神代上第七段
- ↑山口昌男.『天皇制の文化人類学』や「皇制の神話=演劇論的構造」in『山口昌男著作集〈5〉周縁』を参照されたい。山口昌男は、王と道化、秩序の中心とトリックスターを対比的に考えているが、私は両者は後者が転じて前者になると考えている。
- ↑折口信夫「ごろつきの話」in『古代研究〈2〉祝詞の発生』
- ↑もちろん、私は、芸能人が政治家として望ましいといっているわけではない。大衆心理学的に、芸能人が政治家として好まれるという事実を指摘しているだけである。フロイトは、大衆心理学に関する本の中で、大衆は、一人の指導者の中に自我理想を見出し、それを通して、お互いの自己同一を成し遂げると言っている。Sigmund Freud, “Massenpsychologie und Ich-Analyse" in Gesammelte Werke in 18 Bänden mit einem Nachtragsband. Bd.8. S.128.
- ↑世に倦む日日.「盧武鉉談話の正論 ― 韓国は日本の右翼に妥協してはならない」2006/05/12.



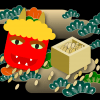


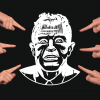
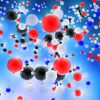










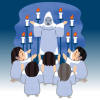



ディスカッション
コメント一覧
プライバシーの説明の中で。スポーツ選手のことが書かれているが、スポーツ選手を単なる芸能人と同一の分野で括るのには、無理があると思う。プロレスなどの分野ではそうかもしれないが。。。
これをプライバシーのない分野に入れるのであれば、大学教授などはその典型的な職業になってくると思われる。なぜならば論文の際に、学生の評価と批判にさらされて一人芝居を打っているのであるから、そのように歪曲した取り方をされても仕方が無い。
一つのことを極めていく中において、トップの選抜過程では確かに公正を記す意味で、多くの観客の中でプレーすることとなることについての見識がない。この理屈で進めるとオリンピックの各種目の選手も、プライバシーが無くなることになる。
ナガイさんにもプライバシーが無くなることになり、ストーカーのようなパパラッチに追いかけられることになっても良いのなら、この主張で進められると良い。おつりが沢山返ってくる事でしょう。
まず、「エロティシィズム」とは、バタイユが言うように、それ自体何の役にも立たない純然たる蕩尽の快楽であることを再確認しましょう。「何の役にも立たないがゆえに役に立つ」というパラドキシカルな表現も可能ですが、ここでは、「役に立つ」という言葉を通常の意味で使いましょう。
大学教授などが行っている教育や研究という仕事は、人類が生存していく上で役に立つ活動であり、教育職あるいは研究職という職業は堅気の仕事です。だから、大学教授が、学生や同僚や行政から、その仕事ぶりが監視されたとしても、それはステージの上で注目を集める芸能人とは存在の性格が異なります。また、教育/研究活動の生産者や消費者が知的満足を感じたとしても、それはエロティシィズムの快楽とは言えません。
ただ、大学教授の中にも、メディアで活躍する「タレント教授」と呼ばれている芸能人的な人もいます。彼らのタレント活動は、アカデミズムから見れば、学術活動には何の役にも立たない売名行為ですが、それにもかかわらず、否それゆえに、タレント教授は、堅気の研究者よりも大衆に人気があります。
スポーツに関しても、自分の健康増進のため、あるいは個人的な楽しみのためにしているのなら、それは他者にエロティシィズムの快楽を与えることはありませんし、そのスポーツのプレーヤーは芸能人的ではありません。では、オリンピックに出場する選手は、このような純粋なアマチュアなのでしょうか。
古代ギリシャのオリンピックで優勝しても、月桂冠を与えられるだけですが、優勝者が郷里に帰ると神として崇められ、一生かかっても使い切れないほどの財宝を与えられたとのことです。古代においても、オリンピックに参加することは、名声目当て、金目当てだったわけです。
近代オリンピックは、当初は、有閑階級の人が、名声を求めて優勝を争う試合だったようですが、現在では、商業化が進み、たんなるアマチュアのゲームではなくなり、タレントの登竜門のようになっています。もちろん、中には、金や名誉のために参加しているのではない選手もいるかもしれませんが、本人が望むと否とにかかわらず、メダリストは芸能人的な扱いを受けます。
スポーツ選手が、狭義の芸能人と同様に、大衆のスターになることができるのは、スポーツが何の役にも立たない非生産的な活動であることと深い関係があります。政治の世界でも、実務的な行政に携わっているのは、官僚や黒子役の政治家で、目立つ政治家ほど非実務的な仕事をしています。ワイドショー番組で芸能人扱いされている田中真紀子などは、特にそうです。
媒介者として機能するスケープゴートのもう一つの例として、貨幣を挙げることができます。家畜、米、貴金属など、かつて使用価値を持っていた貨幣商品は、その使用価値を捨て、世俗的な実用性から自らを解放しました。貨幣は、それ自体では何の役にも立たないにもかかわらず、否それゆえに、貨幣として機能して、すべての人の欲望の対象になることができるのです。
議論の焦点が少しずれているように思います。言いたいことはサッカー選手にプライバシーが無いとの言い切りに対して、それは無いやろというところなのです。
持ち出されている教授の件に対しても、マスコミだけではなく内部の学生からの拒否反応が強い人がいますよ。大学改革が言われていますが、それはなぜでしょうか? 何十年も変わらぬことを言い続けている学者もいますし、もっとマスコミに迎合してあえて世間の反発を買うようなことをもっともらしく述べる学者もいますね。慶応の植草氏なども、アンチ竹中、アンチ小泉のみでしか議論できない、レベルの低い人物のように思います。本人が望むと望まないに関わらず、芸能人の扱いを受けると言うのは、あなた方のようなそれなりに、論が達人が言うからであって、逆にそのような扱いをしてはいけないのだよと言うべきものだと思います。
スポーツが、人の生きていくうえで役に立たず、学者の研究が人の生きていくうえで役に立つなどというのは、思い上がりもいいところだと思います。役に立たなくても、生かせてもらっていると言う謙虚な考えを持つべきでしょうね。
私は「サッカー選手にプライバシーが無い」と言い切ってはいません。私は、本文の中で、
と書きました。このように、公人や準公人は、その職業を選択することにより、私生活、経歴などプライバシーの権利の一部を自ら放棄したとみなす理論を公人理論と言いますが、放棄しているのは、あくまでも「一部」であって、「全部」でないことに気をつけましょう。すなわち、「ある程度犠牲になっても仕方がない」ということは、「ある程度までは尊重されなければならない」ということでもあります。
「役に立つ」については、最初の投稿の冒頭で断ったように、「普通の意味」で使っています。つまり、それは「物質的利益に貢献する」という意味です。「何の役にも立たないがゆえに役に立つ」という広い意味の用法は、排除されています。
「スポーツは何の役にも立たない」という私の発言は、スポーツを貶めた発言ではありません。おもしろいことに、役に立つものの中で、「崇高な」とか「感動的」と形容できるものは、何もありません。道具には、道具以上の価値がないのです。私たちが、偶像(アイドル)として崇拝するものは、すべて実用性から切り離された祝祭空間の中にあります。
不思議なのですが、排除されて神にまでいく場合もありますが、学校などのいじめを思い浮かべるとただ排除されて終わりという場合も多いと思います。この神に祭り上げられる場合とまったく上げられない場合の差はどこからでてくるのでしょうか? 最近だとフセイン大統領や金正日(キムジョンイル)もスケープゴートのようですが別に神格化されていません。
神格化されるかどうかは、排除者たちが、スケープゴートの排除に後ろめたさを感じるかどうかにかかっています。神に捧げ物をするとき、殺すことに後ろめたさを感じる生贄ほど、効果が期待できるのはこのためです。
いじめなどで自殺者が出た場合、自殺者の名前が、いじめに加担した者の間でタブーになることがあります。これは神聖視の第一歩です。加担者たちが、後ろめたさに耐え切れなくなり、自殺者の遺影の前に泣き伏す時、自殺者は神格化されることになります。
フセインや金正日は、殺されたわけではないので、スケープゴートとしての性格はあまりありません。もしもアメリカ軍が、フセインを殺害していたならば、フセインを支持するスンニ派の人々は、元大統領を殉教者として神格化したかもしれません。
アメリカ側は、そうした事態となることを避け、代わりに、口をあけて健康チェックを受けるぶざまなフセインの映像を流しました。あれを見て、フセインを神と崇める人はいないでしょう。
スケープゴートの神格化は感動とか罪悪感とかを民衆が感じるかどうかにかかってるわけですね。(フロイトの「トーテムとタブー」でも殺害者(子供たち)の罪悪感が父(被害者)を神格化していたと思います)スケープゴートされた人の中でも、良心的な民衆、民衆に訴えるような劇的な死、カリスマ性、正当性などのいくつかの条件がそろった者がその分だけ神格化されていくのでしょう。神の背後にはスケープゴートで終わる人も多いということですね。私も機会があればもう少しその条件について考えてみたいと思います。ありがとうございました。
前回の衆院選挙で、老いたかっての総理大臣が二人、引退を余儀なくされました。典型的なスケープゴート現象だと思います。今、王殺しというスケープゴート現象が定年制という制度として政治的に定着しようとしている時期なのだと思います。わが国の政治風土では、制度化を阻止しようとする力もいまだ健在だと思えます。スケープゴート現象が制度化されるともはや大衆のエロチシズムとは無縁の現象へと転生してしまうようにも思います。このようなスケープゴート現象の制度化により何が失われ何が得られると考えればいいのでしょうか?
定年制とエロティシィズムとの共通点は、実用性からの解放です。
kodamaさんとの応答で、
また本文でも
といわれています。このあたりのことが、半分わかって半分分からないのです。つまり、使用価値を捨てるとか、排除までは分かるのですが、それが全ての人の欲望の対象になるとか、秩序の体現者に祭り上げられるというのがどうしてなのかわからないのです。ゴミを捨てた後に、ゴミが宝物になったりする場合がある。あるいは、一旦ゴミになった物だけが宝物になりうるということですか?
捨てたものがごみになるのか否かに関しては、「匿名希望者」さんへの返信を読んでください。貨幣は、政府の信用に裏付けられているため、貨幣の形態は政府の形態の象徴でもあります。政府が、国内の特定の集団の利益にのみ奉仕する存在ならば、国民から広く支持されることはありません。同様に、貨幣は、それが広く使われるためには、特定の目的にのみ奉仕する使用価値を持っていてはいけません。だから、貨幣=政府は、媒介される存在から等しく距離を隔てた(等しく排除された)存在でなければならないのです。
匿名希望者さんとの応答で永井さんは、
と答えておられます。 後ろめたさを感じるかどうかが決め手なわけですね。水子地蔵のようなものを連想しました。
貨幣や定年制の成立についても、これとパラレルな議論が可能なのですか?貨幣は、単に便利な発明だし、定年制は組織維持にとっての合理的な仕組みで、永井さんのいう後ろめたさやタブーとは全く無縁な現象のような気もするのですが?
前回言ったように、貨幣は発行者の象徴です。貨幣だけ見ていても、貨幣になぜ価値があるのかわからないように、貨幣がなぜスケープゴート的存在なのかはわかりません。
定年制度一般はスケープゴート現象とは言えません。ただ、中曽根康弘氏の場合、彼が反小泉の牙城である亀井派のドンであったことから、定年を口実に比例名簿から排除されたことは、スケープゴート的色彩を帯びていると考えることができます。
問題となっていた「プロスポーツ選手は芸能人」の部分ですが、私も以前から主張しておりました。しかし同意してくれる方は少なく残念に思っておりました。
また中田の態度に対しても同様の違和感を感じておりました。
それも含め今回の文は私的には非常に同意できるものでした。
これからも面白い論文を楽しみにしています。
何かめちゃくちゃな論文ですね。これでは議論に値しませんよ
興味深く読ませていただきました
サッカーの中田氏が慈善団体を立ち上げたとのニュースに
強い違和感を覚えておりましたが、腹におちた思いがします
彼がやろうとしていることは、単にサッカービジネスであり
野球で言えばマスターズリーグに似た、一種のドサ廻りであるのに
それをことさらに慈善団体といいつのる姿勢に問題を感じたのです
幸いにも異能をもっているのに、そのことを屈辱的にしか捉えられない
その点で彼には見世物の自覚があるといえるのでしょうか?
であれば施しを与えるというのはちょっと場違いな気がしてしまいます
芸能人が、その知名度とアイドル性を利用して、慈善団体の募金に協力することはよくあることです。
「芸能人は世襲の人物が優遇される」と言う定説が存在する様です。ある俳優さん(この人は世襲ではない)が先ごろTV番組の中でこの説を指摘していました。
日本の芸能界は伝統芸能の関係者(歌舞伎、狂言、能。戦後では落語家の一部)が世襲となるケースが多く、その以外のジャンルでは昭和50年前後まで「世襲」の人は、数える程度でした。ただ芸能人の「ジャンル」も「世襲」も範囲が広く、「祖父がごく短期間にエキストラ俳優だった」という人でさえも世襲とみなされます。中には親がすでに芸能界を引退して、子供の方が大物になった人もいますが。
世襲芸能人は近年かなり数が増えて、今ではアイドル歌手も「世襲化」しつつあります。現在の芸能界は「親の七光りだけで勝負できる世界」なのでしょうか?
「地盤・看板・カバン」が保障される議員とは違い、「TV出演頻度」と言う結果を出さなければ、短期間で引退に追い込まれる(追い込まれた)2世タレントがかなりいます(ただし、親が「芸能界に顔が利く」大物芸能人の人はあまり関係がない)。
昔の芸能界の方がこういう世襲芸能人に、厳しい世界(いい意味で言えば「業界に鍛えられた」)ではなかったのかと思います。先生のご意見をお願いします。
テレビをはじめとする既存のメディアが衰退期に入り、既存のメディアで活躍していた芸能人たちも保守化しつつあるのでしょう。これからは、インターネットなど、新しいメディアで、新しいタイプの芸能人が出てくることでしょう。
昭和時代に素人参加型番組が流行したり、おニャン子クラブやAKB48といった素人のようなアイドルが絶大な人気を得たのは、そういった人が一般人と芸能人の境界をまたぐ両義的存在だからだったんですね。
ところで、永井先生は「スケープゴートは何色か」でアジア人は黄色人種と呼ばれてスケープゴートになりやすいと述べていますが、欧米の芸能界では白人と黒人ばかりでアジア人が全くといっていいほど注目されません。どうしてでしょうか?
欧米の芸能界でアジア系が全く注目されていないということはありません。エキゾチックなアジア系芸能人は、彼らにとって好奇の対象となります。ヨーロッパでは、古くから、ジプシー(ロマ)が旅芸人として活動を行っていました。ジプシーという呼称は、エジプト出身という誤解に基づくもので、実際には、出身はインドのラージャスターン地方だったようです。アジアというヨーロッパの外部からヨーロッパに来た、人種的にもコーカソイドとモンゴロイドの両方の特徴を持つこの流浪の民は、一方では差別され、迫害されていたものの、芸能人としては珍重されていたので、その意味で、ジプシーはスケープゴート的芸能人の好例です。
実はフセインに憧れる人もいる
フセインが凄く冷酷であることを知っていて冷酷な成功者が好きな人は憧れる
最近では日本人の場合は同世代の著名人(芸能人も含む)には特別関心を持たない傾向のようですが、これはどういった理由があるのでしょうか?
「同世代に無関心」ということは特に日本人に強い傾向と思います。相手がどういう人かに関係なく同世代に無関心と言う事は外国でもあるんでしょうか?
「最近では日本人の場合は同世代の著名人(芸能人も含む)には特別関心を持たない傾向」があるという事実はどこにあるのでしょうか。
>経済や法に詳しいスペシャリストなら、ブレーンとして雇えばよいのであって
家族経営みたいのが囁かれるけどトランプ大統領についてはどう思いますか。
大統領に就任してから解任・辞任に追い込んだ人数は物凄く多いです。
また安倍首相が「政治主導」という言葉を数年前から掲げていますが
これが例え表向きだとしてもこれが意味するところは
「政治を官僚から政治家(国民の代表)に取り戻す!」という意味ですよね。
トランプは伝えられるところによると書類に殆ど目を通さないらしいです。
それでもアメリカは維持されておりトランプ支持率もそれほど
落ちる傾向にないので「問題ない」「問題なのは騒ぎ立てる方だ」とも
言えるけども政府高官からは非常に煙たがられています。
>知識人たちは、経済や法についてほとんど何も知らない俳優やスポーツ選手などの芸能人が、
>選挙で当選する現象を衆愚政治として非難するが、
>もちろん、私は、芸能人が政治家として望ましいといっているわけではない。
全肯定でなくとも多々好意的に書いているように思うのは気のせいだろうか。
>加担者たちが、後ろめたさに耐え切れなくなり、自殺者の遺影の前に
>泣き伏す時、自殺者は神格化されることになります。
現在のネット社会ですと現状だと加害者が罪の意識を
感じていなくても被害者は神格化される傾向にあると思います。
と言いますか加害者が罪の意識を感じなければ感じないほど
生存(加害者)-不在(被害者)というギャップが
明らかになり事件の悲惨さをより強調させますので
神格化するのならば加害者が猛省するのは逆効果です。
>もしもアメリカ軍が、フセインを殺害していたならば、
>フセインを支持するスンニ派の人々は、元大統領を殉教者として
>神格化したかもしれません。アメリカ側は、そうした事態となることを避け、
>代わりに、口をあけて健康チェックを受けるぶざまなフセインの映像を流しました。
神格化を事態を避けた過去があるアメリカが何故に後に
ビンラディンやザルカウィを殺害したのだろうか。
特に後者はアメリカがイラク戦争を始める時に悪名高い人物として
紹介したことで本人の実力以上に世界中に名前が知れ渡った経緯があります。
そのような者は絶対に殺してはならずに生け捕りにすべきですが
アメリカは殺害しました。そしてザルカウィの意思を
継ぐ形で悪名高いISISが出来ました。
>加担者たちが、後ろめたさに耐え切れなくなり、自殺者の遺影の前に
>泣き伏す時、自殺者は神格化されることになります。
あまり関係ないと思います。全てはプロパガンダ(情報戦)次第でしょう。
全て関係ないとは言ってないです。自分は飽く迄も
一理あるというふうに留めて置きます。
>加担者たちが、後ろめたさに耐え切れなくなり、自殺者の遺影の前に
>泣き伏す時、自殺者は神格化されることになります。
それは加担者限定の神格化であり民衆による神格化とは
別ではないですか。情報過多な現代に於いて
加担者達がそのようなことをすれば
ネット民は白けるだけだと思います。
それでは神格化以前に「事件の終わり」を意味します。
現代は過去よりも賞味期限が短くなっており
また娯楽が多様化したことで細分化されている印象があります。
>大衆は、エロティシズムにおいて犠牲者と一体となり、そして
>この集団的な内的体験を通して、大衆どうしが一体となる。実際、
>大衆たちは、共通の関心事である芸能人を話題とすることで
>コミュニケーションしている。だから、スケープゴートは、
>社会統合の原理(コミュニケーション・メディア)となるのであり、
>その結果、天皇のような社会統合の象徴的存在と近似した存在様態を持つのだ。
この文章を読みふと思ったのですが事件というのは社会に有益ですか有害ですか。
事件があれば民衆は必ず危機意識を持ちます。そしてその度に民衆は
日常生活で忘れ掛けていた国家を思い出して国家と一体となるように
行動しようとします。シャルリーエブド事件に於けるものなり
クライストチャーチのモスク銃撃事件に於けるものが該当します。9.11等も。
社会統合もとより共同体の一員としての意識を強く持つことになります。
この論文では善し悪しは語られていないのですが国家という意識が
所々薄まる現代に於いては実は事件というものが国家にとり
非常に有益なのではないかと感じたので書かせてもらいました。
国家(国民)とは血を求める側面もあるのですね。
9.11後に「愛国者法」が制定されたと記憶しています。
昨今のトランプ政権によるネット企業への攻撃ですが
9.11(社会統合=共同体帰属意識)が
現在までも波及している証拠でもあります。
「事件=社会統合」は国家を持ち出すには
非常に便利なものになっており9.11が無ければ
今現在行われている中国への対応が遅れた可能性があります。
陰謀論を主張する気はさらさらないです。有益にするか
無益にものするのかは生存者の選択で決まるのですが事件が
国家にとり奏功したと考えると何とも皮肉なものです。
トランプは実業家ですが、アプレンティスというリアリティ番組のホストを長年務めていたので、芸能人としての性格をも色濃く持っています。
排除された者が排除する者にとって神となるという特殊ケースについて質問されたので、そう答えたまでで、第三者(傍観者)にとって神となるというケースももちろんあります(むしろ、こちらのほうが多い)。
フセインを捕獲した時、米軍は地上軍を大規模に送ってイラクを制圧していたから、生け捕りも可能だったけれども、ウサーマ・ビン・ラーディンの場合、パキスタンは主権国家ですから、同じようにはいかなかったということが考えられます。アブー・ムスアブ・アッ=ザルカーウィーは、おそらく殺害当時それほど大物とは米国からみなされていなかったのでしょう。
一口に事件といっても色々なものがあるので一概には何とも言えません。社会統合に資するかどうかは、スケープゴーティングとして機能するかどうか、カタルシス効果があるかどうかにかかっています。
小室圭&眞子の結婚騒動も芸能ネタとして消化してる感じですかね。私は正直興味ないんですがテレビでもネットでも未だに取り上げています。
永井さんは、この通称”コムマコ“をどのようにご覧になっていますか?
小室圭&眞子さんだけでなく、秋篠宮家までがバッシングの対象になっていて、皇室の将来を危ぶむ人もいますが、皇族は、そもそもその起源からして、尊敬の対象でもあると同時に怨嗟の対象にもなりうるという両義性を帯びています。詳しくは、拙稿の「天皇のスケープゴート的起源」をご覧ください。