『市場原理は至上原理か』を出版しました
私の著作『市場原理は至上原理か』の解説動画、書誌情報、販売場所、概要、読者との質疑応答などを掲載します。本書に関してコメントがありましたら、このページの下にあるコメント・フォームに投稿してください。誤字脱字の指摘から内容に関する学問的質問に至るまで幅広く受け入れます。

1. 解説動画
2. 販売場所
販売価格は小売店によって異なることもあります。リンク先で確認してください。
- Amazon.co.jp :: 市場原理は至上原理か
- Amazon.com :: Shijogenri ha Shijogenri ka
- Rakuten Kobo :: 市場原理は至上原理か
- Google Play Books :: 市場原理は至上原理か
- Smashwords :: 市場原理は至上原理か
3. 表紙画像
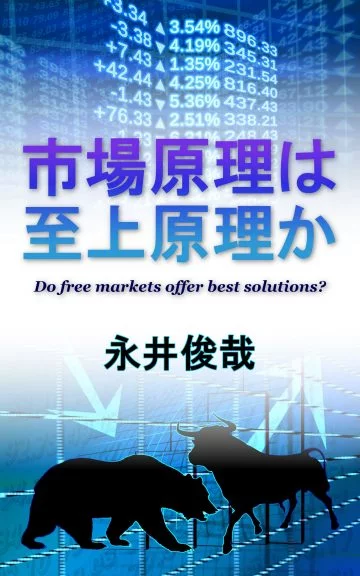
4. 書誌情報
- Title :: 市場原理は至上原理か
- Furigana :: シジョウゲンリハシジョウゲンリカ
- Romaji :: Shijogenri ha Shijogenri ka
- Author :: 永井俊哉
- Furigana :: ナガイトシヤ
- Romaji :: Nagai, Toshiya
- Author bio :: 著作家。インターネットを主な舞台に、新たな知の統合を目指す在野の研究者。専門はシステム論。1965年8月、京都生まれ。1988年3月、大阪大学文学部哲学科卒業。1990年3月、東京大学大学院倫理学専攻修士課程修了。1994年3月、一橋大学大学院社会学専攻博士後期課程単位修得満期退学。1997年9月、初めてウェブサイトを開設。1999年1月、日本マルチメディア大賞受賞。電子書籍以外に、紙の本として『縦横無尽の知的冒険』(2003年7月, プレスプラン)、『ファリック・マザー幻想』(2008年12月, リーダーズノート)を出版。
- Language :: ja
- Page :: 291ページ
- Publisher :: Nagai, Toshiya
- ISBN :: 9781310457012 (Smashwords, Inc.)
- BISAC :: Book Industry Standards and Communications
- Nonfiction » Politics and Current Affairs » Economic policy
- Nonfiction » Social Science » Political science » Political economy
- 政治学 > 公共政策 > 経済政策
- ビジネス・経済 > 商業政策
- Tags :: キーワード
- Japanese :: 市場経済、民営化、構造改革、規制緩和、小さな政府、リバタリアン、政策科学
- English :: market, libertarianism, socialism, nationalism, collectivism, individualism, capitalism, decentralization, politics, economics
5. 短い概要
日本の国際競争力を低くしていると言われている、建設、金融、流通、農業、医療、教育といった保護産業の分野に市場原理を導入することは、社会にとって望ましいことなのか否かをめぐって、国家主義者、社会主義者、自由主義者の三人の論者が激論を戦わせる、バーチャル・ディベート・ショー。あなたは市場原理の導入に賛成か反対か。日本の将来を考えよう。
6. 長い概要
公共の利益は、公共心があるということになっている一人あるいは少数のエリートが中央集権的なシステムで意図的にそれを実現しようとすることで実現できるのか、それとも中央による統制を行わずに、諸個人を自由に利己的に振る舞わせた方が、「見えざる手」によってより良く実現できるのか。この問題はアダム・スミスの時代以来論じられてきた。
1929年に始まった世界大恐慌で、レッセ・フェールが世界的に疑われ、右の国家主義と左の社会主義が台頭したものの、冷戦終結後は市場経済が再評価され、自由主義が国家主義や社会主義よりも優れているとみなされるようになった。それでも、グローバル経済が危機に陥るたびに「市場原理主義は死んだ」と言われる。はたして市場原理は至上原理なのか。それとももっと優れた原理があるのか。
本書は、日本の国際競争力を低くしていると言われている、建設、金融、流通、農業、医療、教育といった保護産業の分野に市場原理を導入することは、社会にとって望ましいことなのか否かをめぐって、国家主義者、社会主義者、自由主義者の三人の論者が激論を戦わせる、バーチャル・ディベート・ショーである。自由主義者は著者の立場を代弁しているが、あなたはその主張に納得できるだろうか。
(*)本書は1999年にネット上で公開した『激論!市場原理は至上原理か?』の第二版です。本文の修正は最小限にとどめ、2016年時点での見解を注釈を加えるという形でアップデートが行っています。なお、本書は、DRMフリーです。
7. 関連著作
反市場原理・反小さな政府の立場の人は、今でもたくさんいる。いくつか例を挙げると、
内橋 克人+グループ2001:規制緩和という悪夢
根井雅弘:市場主義のたそがれ 新自由主義の光と影
服部/茂幸:新自由主義の帰結-なぜ世界経済は停滞するのか
トマ・ピケティ:21世紀の資本
などがある。市場原理の不在がどのような弊害をもたらすかを理解するには、特殊法人の問題を最初に提起した
猪瀬直樹:日本国の研究
猪瀬直樹:続・日本国の研究
を読むべきである。市場原理至上主義は、海外ではリバタリアニズムと呼ばれている。リバタリアニズムの入門書としては
がある。海外の古典としては、社会主義経済をファシズムと同様の反自由主義・反市場経済と位置づけて批判した
フリードリヒ・ハイエク:隷従への道―全体主義と自由(The Road to Serfdom)の翻訳)
が、必読文献である。



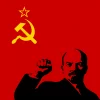






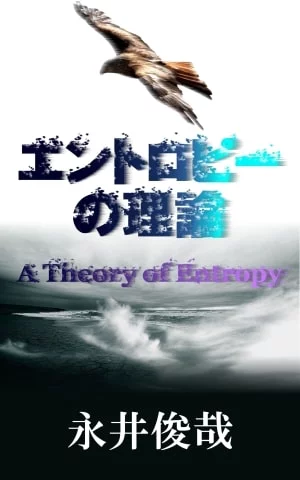

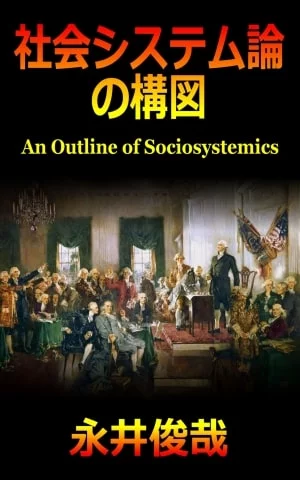

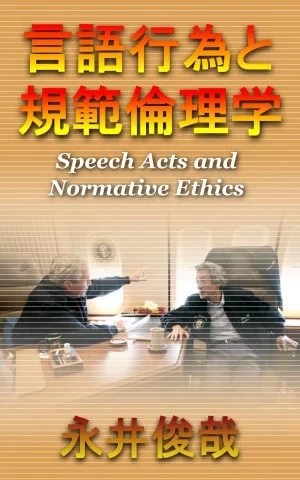
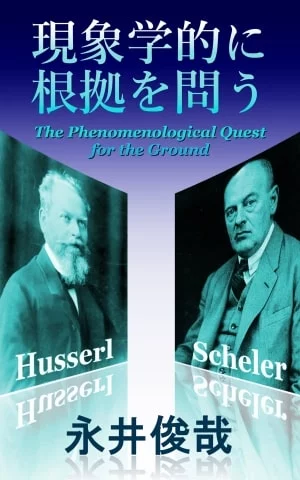

ディスカッション
コメント一覧
永井さんは市場原理至上主義の立場でいらっしゃいますが、わたしも経済がうまく機能するためにはできるだけ小さな政府が望ましいと考えております。しかしそれは全ての国家を対象にはできないのではないかと思います。開発経済について以前、青木昌彦氏が述べられていた中にでてきた market enhancing view(市場補完論)で「経済の発展段階によって政府の役割は変化する」と書かれていたのをちょっと読んだことがあります。「至上原理としての市場原理」で情報産業時代は知識集約型であり、この場合は小さな政府が望ましいと書かれていましたが、開発途上にある国でも、開発するうえで知識集約的産業は成立するのでしょうか?ある発展途上国の土台作りまでの段階では、小さな政府はむしろ妨げになるのではないでしょうか?
私は、市場原理が超歴史的に望ましいシステムであるとは思っていません。もし私が50年前の日本に生まれていたとするならば、資本集約的な重化学工業を育成するために、大きな政府(福祉国家)の理念に賛成していたことでしょう。1973年以降時代が変わりました。今は小さな政府の時代です。それでも、市場原理は超国境的に望ましいシステムではないと言う人もいます。
「現在の発展途上国は、かつての日本と同じ発展段階にある。かつての日本で開発独裁的な大きな政府が成功したのだから、今の発展途上国には開発独裁的な大きな政府がベストである。」こうした考え方をする人がしばしば見落としている点は、発展段階の格差は、閉鎖系としての各国の経済システムに偶然的に現れるのではなく、中心/周縁という権力的な差異を伴ったグローバルな分業の結果として現れるということです。日米欧などの先進諸国=中心において、技術革新の結果、付加価値が低くなった製造業の空洞化が、発展途上国という周縁における工業化を引き起こしているわけです。発展途上国の工業化は、一見、南北格差を縮小させる働きがあるように見えますが、実際には雁行形態における分業的な格差の固定にしかならないのです。
もちろん中には、「農業国がいきなり情報社会になるのは不可能だ。まず工業化からはじめるのが順番というものだ」と言う人もいるでしょう。しかしこうした議論こそ、各国経済を閉鎖系と誤認している証拠です。アイルランドは、農業社会からいきなり情報社会に「飛び級」しました。アメリカのIT産業が、英語のできる安い人材が多数いるという理由で、ヨーロッパ進出の拠点としてアイルランドに投資した結果です。今ではアイルランドはヨーロッパ有数の経済優等生です。発展途上国の人々を先進国の惨めな下請けから解放するために必要なことは、OECD予算を橋やダムの建設にではなくて、教育、特に初等中等教育に使い、かつグローバルな労働市場を流動化することです。そうしなければ、発展途上国に生まれた人々は、いつまでたっても高収益な仕事につくことができません。以上の理由から、発展途上国には、その「発展段階」にふさわしい開発独裁体制が適切であるという主張には賛成できません。
お忙しい中、ご丁寧なお返事をいただきましてありがとうございました。前回、社会主義についてわたしがメールをしたときもとても丁寧にわかりやすく説明していただいてどうもありがとうございました。今回のお返事を読みまして、各国経済が連鎖して国が発展していくのだということに改めて気づかされました。確かに、冷静になって考えてみると、そうですね。もうちょっと理論と現実の経済の動きがつながるような勉強の仕方をしなくては、と思います。
今、国立大学の1年生なのですが、大学の独立行政法人化が学内でも問題となっており、「3~5年で成果のでない基礎研究や文化系の研究が採算や効率を理由に切り落とされる」といった、声があがっています。僕も、学問、研究という、単純に金額に換算できないものを、そのように市場原理にゆだねる、というのには疑問を感じているのですが、それについてはどのようにお考えですか。僕自身、多分に「学生側の主張」に影響されている点があると思うので、この”大学の独立法人化”という問題そのものについても、そもそもどのような経緯で、どこから発生したのか、というような、解説をお願いします。
私は市場原理という言葉と市場経済という言葉を使い分けています。市場原理は、必ずしも金額による評価に基づかなくてもよい。例えば選挙では、候補者への評価は票数によって決定されます。学者の世界では、金銭よりも名声が富です。票田も名声も換金可能な富ですが、独立した種類の資本とみなすことができます。市場原理/非市場原理との区別は、拝金主義/非拝金主義という区別ではなく、多数の評価者が意思決定に加わる複雑系/一人の権力者が評価する単純系という区別なのです。
なお私は、国立大学を私立大学にするといった中途半端な民営化には反対です。私の主張はあくまでも公教育全体の廃止です。詳しくは、「教育改革はどうあるべきか」をご覧下さい。独立法人化反対が「学生側の主張」ということですが、学生は消費者なのですから、教師を選ぶ権利・評価する権利を主張するべきでしょう。それが大学に市場原理を導入する第一歩となるはずです。
大学の独立法人化は、70年代から始まった大きな政府に対する批判の帰結である行政改革の一つと位置付けられていますが、実際には、大学を天下り先にしようとする意図に基づいていると考えられます。つまり、小さな政府というよりも大きな政府の政策ということです。
市場原理に関し、永井様のお話を、共感を覚えながら読ませて頂いておりますが、「農地には転用ができない第一種農地と転用が可能な第三種農地、および両者の中間である第二種農地がある。この規制がある限り、…」との表現がありました。私は法律に関する知識は殆どなく、まとを外れた質問かもしれませんが、この文章は、永井さんらしくなく、土地に関する規制を容認している発想に取れました。多分、これらの土地の区分によって税金が違うのでしょうが、これこそ憎むべき規制の一つではないでしょうか?もちろん、都市計画上の必要からくる規制はある程度必要と考えますが、土地の利用方法も市場原理に任せるべきと思います。
私は無政府主義者ではないので、「すべての規制は不要である」とは考えていません。例えば、環境保護のための規制は必要な規制の一つです。しかし実際には、「環境保護」という大義名分のもと、一部の利益団体が既得権益の保護を画す場合があるので、要注意です。「環境保護のために農業に補助金/減税措置を」といった主張はその典型です。農地法にある農地転用規制は、農業振興地域の整備が目的で、環境保護規制としての性格が薄いので、農地を含めた植物生育地面積の減少を防止する規制に変えるべきだと思います。なお農地法は最近改正されました。
私は現在普通(集配)郵便局に勤めるものですが、郵便事業が民営化された場合、内容証明の公証性はどうなってしまうのかと考えております。(通信の秘密は、民営化された方が競争原理により一層守られるでしょう)近年金融機関の内容証明引受数はもとより、一般市民の、特にクーリングオフなどその重要性と需要が高まってきております。利潤追求ならば、特定の企業にのみ有利な扱いをして、ペイしない(しかも書式を知らず、挙げ句の果てには文句を言い出す)一般市民を切ることは働く側にとっても利便性があるでしょう。
郵便サービスを民営化しても、内容証明サービスだけを切り離して郵政省の仕事とすることができます。まず郵政省がインターネット上に内容証明専門のサイトを開設します。客が内容証明したい手紙を持ってきたら、窓口でその内容をスキャナで読み取り、そのデータを郵政省のサイトにオンライン登録しておきます。出した日付は自動的に記録されます。内容証明を要する手紙を受け取り手に手渡す時、配達人がモバイルコンピュータを用いて、受取人に受け取る日付と時間の確認をさせた上で、それを指紋など本人確認の機能をもつデータといっしょに郵政省のサイトに送ります。こうすれば、郵政省の方で、内容証明、日付証明、配達証明をすることができます。
郵政省は98年2月から1ヶ月、インターネットを使って内容証明郵便の申し込みを処理する実験を、札幌中央郵便局で実施したそうですね。現在の内容証明郵便は、差出人があらかじめ同内容の文面を3通用意して窓口で内容の確認を得る必要があるなど手続きが煩雑です。デジタル化すれば、利用者にとっての利便性も増えるし、コストが削減されるので、郵便サービス提供会社にとっても相応の利潤が期待できます(少なくとも1通420円もとれるなら)。
カントの「判断力批判」についてサーチする中で永井さんのホームページに出会い、その該博な知識とデータに裏付けられた論証の精緻さに感嘆いたしました。これからも愛読させていただきたいと思います。
ところで、市場原理についての論争を、興味を持って拝見するうち、ひとつご意見を伺いたくなりました。それは南北問題に関する事柄です。掲示板の中に「飛び級」を行った「経済優等生」としてアイルランドについての指摘がありましたね。しかし問題はある特定の地域が「経済優等生」になりうるとしても、同時にそれが他の「経済劣等生」との関わりにおいてしか存立しえないと言うことです。というのは資本の増殖のためには、経済的発展の地域的不均衡が必要であり、「優等生」は必然的に安価な原料・安価な「下請け」労働力等を供給する「劣等生」を求め、固定化するだろうからです。
永井さんは教育への投資と労働市場のグローバル化によって世界的な機会均等を達成すべきだと考えておられるようですが、そうした施策も資本の要請に従って成されるである以上、経済効率のいい限定された地域に集中されるだろうし、「優等生」リストの入れ替えといった枠を超えて真にグローバルな機会均等を実現するかどうか疑問です。結局南北問題の解決のためには、世界資本主義の中心-周縁構造自体の是正を考えなければならないのではないでしょうか。
市場が、現在人類が知っているもっとも効率的に資源の分配を行うシステムであったとしても、現在その平等性は主に国家の枠内にとどまっており、国家間の格差を維持しつづけるという側面も無視することはできません。こうした観点は当然マルクス主義者の側から出されるべきだったのでしょうが、論争において「社会」氏は社会主義者と言うよりは社民主義者であり統制経済主義者であったために、そのような発言はなかったようです。
私自身経済には素人であり、明確な考えを持っているわけではありませんが、少なくとも統制経済よりは市場原理の方が望ましいと考えています。しかし一方、市場原理(というよりは資本主義)によっては内在的に解決できない問題のひとつが南北格差ではないかとも思います。永井さんはいかが思われますか。