イニシエーションとは何か
イニシエーションとは、入社式または加入礼とも呼ばれる、通過儀礼の一つである。外部の人間が新たに共同体に加入する時、しばしば苦痛を伴う儀式の洗礼を受けなければならない。こうしたイニシエーションがなぜ必要なのかをシステム論的に考えてみよう。

1. イニシエーションとしての成人式
代表的なイニシエーションは、男の子(場合によっては女の子)が、母親との甘えた関係を断ち切り、成人の仲間入りをするときに受ける割礼である。割礼とは性器の一部を「断ち切る」儀式で、男の子の割礼の場合には陰茎包皮を切除し、女の子の割礼の場合には陰核の全体あるいは一部を切除する。割礼は、イスラム教圏、ユダヤ教圏、アフリカ、アジア、オーストラリア等で行われ、全世界の割礼人口は10億人と推定されている。
日本の成人式では、割礼は行われないが、縄文時代では、上顎の両犬歯と、下顎の前歯2本を左右対称に抜き取る抜歯が、成人となるためのイニシエーションとして行われていた。今でもオーストラリアでは、抜歯をしている民族がいる。この他、小指や耳たぶの切断、鼻の隔膜や処女膜の穿孔、頭蓋変形、唇や首の伸長、瘢痕文身など、痛々しい身体毀損と暴力がイニシエーションとして世界各地で行われている。
2. イニシエーションとしての入学式
暴力を伴うイニシエーションは、遠い過去のあるいは未開の社会で行われている野蛮な習慣というわけではない。現代の日本でも、イニシエーションを目にすることができる。個人的な体験談で恐縮だが、応援団の先輩が一年生全員をしごく歌唱指導という行事は、私が高校に入学した時に経験したイニシエーションだった。一週間にわたって、新入生は二種類の校歌に寮歌を加えた三種類の歌と応援を練習する。歌や振り付けを間違えたり、たるんでいると受け取られたりすると、応援団員に「ふらふらしてんな!」と怒鳴られ、ど突かれる。こうしたバンカラなセレモニーは、創立が古い田舎の高校によく見られる。
そうした練習が、その後何かの行事で本番を迎えたことはなかったし、大体、寮など廃止されてなくなっていたから、寮歌を覚えることなど無意味である。歌唱指導は、それがイニシエーションであることを除けば、正当化する理由は何もない。すなわち、歌唱指導の本当のねらいは、応援団員という最も愛校心の強い先輩たちが、校歌という集団との自己同一の象徴を新入生に叩き込むことによって、彼らに集団の一員としての自覚を持たせるところにある。
一般的に言って、日本の大学や高校は、海外の学校とは異なって、卒業よりも入学の方が難しい。このことは、日本の学校が、機能的・手段的性格よりも、共同体的性格を強く帯びていることを示している。入学試験に合格するために、受験勉強という苦難を経ることも、一種のイニシエーションである。
3. イニシエーションとしての入社研修
学校だけでなく、会社に入る時にも、似たような、苦痛を伴うイニシエーションを受けなければならない場合がある。最近では、企業も、定年までの人生をそこで過ごす共同体ではなくなりつつあり、機能的・手段的になっているから、しごき型の研修は減ってきているが、かつては、次のような研修がよく行われていた。
「仕事は男の戦場だ」「気力は体力に先行する」
1969年(昭和44年)、都内の電機メーカーの社員だった男性は、箱根山中の研修所で、大きな声を張り上げた。天井からは、黒墨で書かれたげき文がつるされていた。2泊3日のスケジュールで、テーマごとの討論会は、相手を論破するまで延々続く。討論というよりは、ば声の飛ばし合いに近い。中には、精神的に追い詰められ、泣きだす社員もいた。睡眠をほとんど取れないのに、早朝からは2キロのマラソンも強制され、講師がムチのようなものを持って追いかけてきたという。
現在、50代になるこの男性は研修を振り返り、「参加しつつどこか冷ややかに見ていた。今も酒の席で話題になったりするが、あの研修が仕事で役に立ったとは思わない」と語った。[2]
この男性は、研修の意味をあまり理解していないようだ。しごき型の研修が実用的でないのは、私が受けた歌唱指導が実用的でないのと同じことである。何十年も経った後でも、酒の席で話題になるのなら、この研修は、本来の目的を達成しているということができる。もしも、入社の時、社長の退屈な話を聞くだけだったならば、それも一種のイニシエーションではあるが、決して、これほど記憶に残ることはなかっただろう。
4. イニシエーションとスケープゴートとの関係

通過儀礼の原型は、出産である。子宮から、狭い隘路を経て、この世に生まれ出る過程は、死ぬときと同様に、大変に苦痛に満ちたものなのだそうだ。成人になるなど、新たな生まれ変わりをするとき、擬似的に出産のプロセスが反復される。しかし、イニシエーションとしての通過儀礼には、システム論的観点からすると、別の機能もある。
入所式としてのイニシエーションとスケープゴートは、方向は反対だが、機能は同じである。すなわち、自分たちと異質であるにもかかわらず、自分たちと同じ共同体に属する中間的存在を完全に排除することにより、共同体の境界(システムと環境の差異)を明確にすることがスケープゴートであるのに対して、外部から自分たちと同質のメンバーとなる中間的存在者に、境界を意識させることにより、共同体の境界(システムと環境の差異)を明確にすることがイニシエーションなのである。どちらのケースでも、中間的存在者が境界を通過する時、暴力がふるわれるという現象が起きることが多い。
通過儀礼一般には、暴力は必ずしも必要ではない。例えば、結婚式は、イニシエーションとしての性格がない通過儀礼であるから、既存のメンバーから暴力を振るわれるということは、まずない。しかし、既存のメンバーがいる集団に入る時には、境界を通過する新参者に何らかの苦痛を味合わせることによって、境界をはっきりさせ、システムと環境との差異である、システムの秩序を維持しなければならないわけである。
5. 参照情報
- ↑Leo Moko (@leomoko) . “Human, person, tribe and festival.” Licensed under CC-0.
- ↑人と情報の研究所「会社人間養成 研修ブーム」Original:『読売新聞』朝刊平成12年3月17日.
- ↑Wikimedia. “Initiation of an apprentice Freemason around 1800. This engraving is based on that of Gabanon on the same subject dated 1745. The costumes of the participants are changed to the English fashion at the start of the 19th C and the engraving is coloured, but otherwise is that of 1745.” Licensed under CC-0.






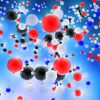










ディスカッション
コメント一覧
「苦痛」を与える事により境界を明確にするでは受け手に対する抵抗が強すぎるように思えます。即効性のある影響力は抵抗力が少ない物ですから、その影響を拡大するには如何に抵抗を抑えるかが肝要に思います。「リスクを背負わせその結果養われた経験の同一性によって人々は連帯し固い絆で結ばれていき、結果、共同体としてのシステムをここの裁量によって培う事ができるのである」というのは如何でしょうか。
一般的に言って、私たちの感覚と認識は抵抗です。他のようでもありうる自由の否定が意識です。だから抵抗が強ければ強いほど、境界は強く意識され、境界を通過した後、新参者は既存のメンバーと「連帯し固い絆で結ばれ」るようになります。
かつての日本では男子が成人すると改名しました。この「元服改名制度」を現代に生かして、「性別・国籍・理由など関係なく20歳になれば任意で改名できる」という様に法改正を行うのはどうでしょうか?先生のお考えはどうですか?ただ「別人が自分に成りすます」詐欺目的の改名を、未然に防ぐ手段を同時に設けます。「元服改名により大人としての自覚を促す」と言う目的もあります。
現在では「親族に同姓同名(「結婚・養子縁組により、そうなる可能性のケース」も入れる)の人がいる」、「著名人と同姓同名で恐れ多い、または精神的苦痛を感じる」と言った理由ではないと、改名できません。また裁判所に手続きしなければなりません。
余談ですが、出生届に字を書き間違えた、または役所の入力ミスで違う名前になる「過失」であっても、訂正改名には法的な手続きが要る様です。
最近は20代以下(特に平成生まれ)の世代の名前で、保守的な人の言い分では「暴走族風の当て字」、「場末のスナックの店名」みたいな名前が時折目立ち、また、「ハーフやクォーターでもないのに、なぜ外国人風の当て字の名前にするのだ?」と言う指摘もあります。小学校や中学校では先生が名前を呼ぶに苦労していると聞きます。近い将来、「名前が変だから改名したい」と言う、若者の改名希望者が役所に殺到する可能性もあります。
最後に個人的なテーマのリクエストです。「天才少年・天才少女はなぜ大人になると能力が平均以下に落ちるのか」です。ぜひ取り上げてください。
改名問題は、「夫婦別姓問題を考える」で取り上げたので、そちらをご覧ください。
その事実を実証する証拠はありますか。
先ほど上げた「天才少年・天才少女は大人になると能力が平均以下になる」は数字では確かにわかりません。俗説で言われる事で今まで論文として証明した人はいません。
音楽やスポーツ分野では大人になると、違う分野(一般人と同じ職種)に転向する人が多い傾向があり、転向分野で大成する人がいると聞きます。
ただ芸能人の場合は原則定年がないため、俳優の場合は「子役の時代だけで引退する」タイミング(特に女の子、この「引退タイミング」は大人の都合で決まる事が割と多い)の判断が難しく、演技力が十分に向上しないまま時間だけが過ぎて、「大人になって演技力が落ちた」とマスコミに言われると思われます。
スポーツ選手の場合も、似たように練習を重ねて経験を日々積んでいるにもかかわらず、自分の能力レベルの推移が「他人の目」にはっきりした上昇と受け取れずに、反対にマスコミに「20歳を過ぎて衰えた」と、言われると私は思うのです。最近の「10代天国」の様なスポーツ界の風潮に私はいささか疑問に感じます。
さて「本題のイニシエーションの事」に移りますが、昔の元服の年齢が時代によって意外とまちまちだったと言うのは、「時代ごとの平均寿命」が影響しているのでしょうか?最近よく議論になる「18歳成人案」にはどう思われますか?
江戸時代の場合は武士階級の男子が15歳ごろで、現代と比較するとは5年早い年齢です。ただ「家督を急遽継承する」場合などでは、もっと早い1ケタの年齢で元服する時代もあり、元服した日に結婚すると言う事もありました。成人した男子は遊郭での「女遊び」を、年長者から教わったとも聞いた事があります。
元服すると「1人前」とみなされます。一説では「未成年」と言う言葉は明治時代前半までなかったとも言われます。現代社会の男女の15歳は体格的には成人と言えますが、精神で見ると「子供=未成年」であるとよく言われます。
余談ですが、庶民の場合は男子の場合はふんどしを作り、女子の場合は腰巻を作って元服式の日に「お祝い品」として送った地域があったと聞きます。これは現代でも名残りが残る地域があります。
江戸時代は、20歳の女性を「年増」と言っていた時代ですから、現代の参考にはなりません。修学年限が伸びている以上、自立や結婚の時期が遅くなるのは仕方がありません。
共同体の境界を意識させる理由は何ですか?
共同体内の秩序を維持することで、その共同体を長期的に存続させるためでしょうか?そうだとすると、電機メーカーの50代の男性は、会社が潰れても良いと思っているということですか?
この男性は、技術的な意味で、役に立たなかったといっているだけです。だから、私は、「この男性は、研修の意味をあまり理解していないようだ」と書いたわけです。
いくつか質問させてください。
共同体内の人間が、自らが所属する共同体の秩序を維持するためにイニシエーションを必要とする事は分かりました。
しかし、ある共同体に新たに入る際、通過儀礼を受けなければならない理由はあるのでしょうか?
私は今年で20歳になりましたが、高校の卒業式・大学の入学式・成人式のいづれにも参加しませんでした。他にも高校時代の部活は先輩との付き合いが嫌で辞めてしまいましたし、大学受験も英国数理社をただただ勉強するのが嫌で小論文と数学だけ勉強して大学に入学しました。
去年8月末の選挙も、立派な成人として投票しろと親に言われていましたが、思うところがあった事とわざわざ外出しなければならないのが嫌で投票しませんでした。
私としては、重くて息苦しい上に退屈な話を長時間聞かされる式典は嫌いです。部活・受験・選挙も同様に、要は自分の利益にならない上に苦痛・労力をともなうような事をしたくないというのが私の言い分でしょうか。(勿論、苦痛・労力以上に利益がある場合は問題ありません。)
むしろこういった通過儀礼をしなければならないような共同体は信用ならないとさえ思っていました。
しかし、このようなイベントを拒否するたびに親から叱られ、自分が間違っていたんじゃないかと思ってきました。
やはり共同体に所属する以上、通過儀礼を黙って受け入れ、その共同体の秩序を維持することに貢献しなければならないのでしょうか。
通過儀礼(特に苦痛を伴う)を廃止した方が、もっと幅広く人材を取り入れる事が出来ると思うんですが、どうなんでしょうか。
よろしくお願いします。
通過儀礼は、プレモダンな共同体において顕著に見られる現象であって、プレモダンからモダンへ、そしてモダンからポストモダンへと社会が変化するにつれて、減っていくと予想されるし、現に減りつつあります。通過儀礼が嫌いだというあなたのような人の方が、ポストモダンな時代では普通だと思います。