超越論的認識とは何か
哲学の専門家たちは、「超越論的認識」とか「超越論的間主観性」などと、「超越論的」という形容詞を頻繁に使う。今回はこの一見難解そうなジャーゴンをできるだけ平易に説明してみたい。
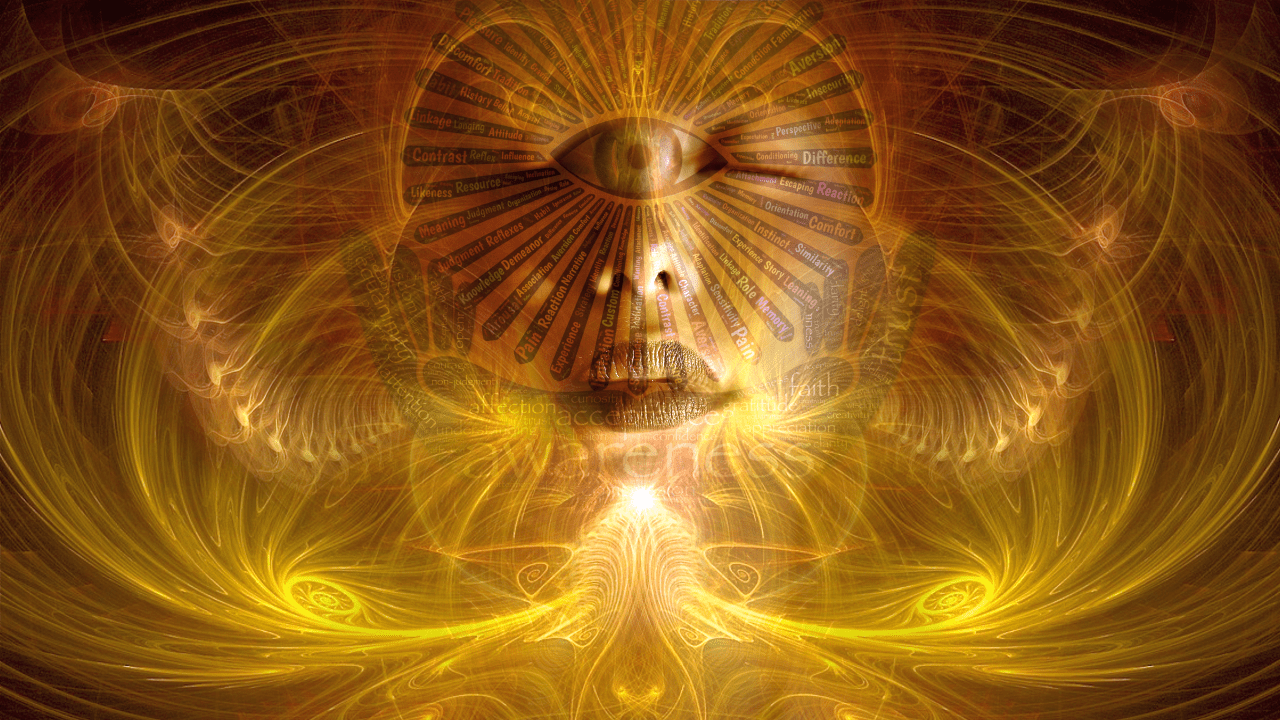
1. 超越論的認識とは有限性の自覚である
ある人が、「自分は愚かな人間だ」と自覚しているとしよう。この人は、本当に愚かな人だろうか。そうではない。本当に愚かな人は、自分が愚かだということすらわかっていない人である。「生兵法は大怪我の基」という諺があるが、自分の能力の限界を知らない人ほど、大失敗をするものだ。自分の限界を心得ている人は、無理をしないし、その限りでは利口なのである。
自分の認識に限界があると認識できる人は、実は自分の認識の限界を超越している。限界の内部にいる人には、限界が見えない。限界を超越して初めて、限界を認識することができる。認識の限界を認識することは、超越を論じることであり、超越論的である。
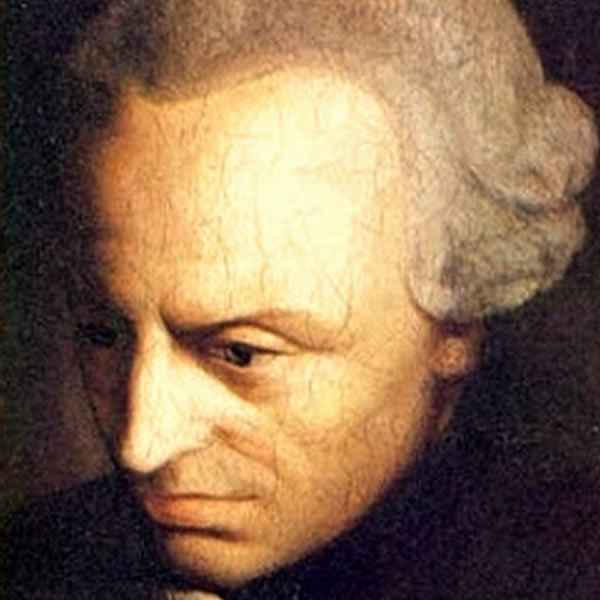
超越論的哲学の源泉となったカントの哲学では《超越論的 transzendental》は《超越的 transzendent》から区別される。両者は、英語で言えば、"transcendent" と “transcendental" に相当する。ドイツ語や英語の接尾辞“-al”には、「…に関する」という意味があり、したがって、超越論的認識とは超越に関する認識ということになる。全知全能の存在者が限界を持たず、したがって限界を認識することもないので、端的に超越的であるのに対して、有限な存在者は自己の限界を意識せざるをえず、その認識の様態は超越論的になる。
2. 限界認識のパラドックス
それにしても、私たちの認識に限界があるということの認識自体が、限界を超えているということはパラドキシカルだ。そこには、もし私たちの認識が有限であるとしたならば、私たちの認識が有限であるという認識自体も有限であり、したがって、私たちの認識は有限とは限らないという自己矛盾は存在しないだろうか。
答えは否である。私たちの認識は常に正しいわけではないが、常に間違っているわけでもない。「私の発言はすべて間違っている」という発言は自己矛盾であるが、「私の発言はすべて間違っているかもしれない」という発言は自己矛盾ではない。対象レベルでもメタレベルでも偽と断定しているわけではないからだ。
3. 不確定性の自己反省は可能か
しかし、はたして私たちは、自分の認識がすべて不確定であると言うことができるのだろうか。私たちが何かを疑う時、何かの信念を前提にしている。いや、もっと正確に言うと、何かを信じているからこそ、それと矛盾することがらを疑うのだ。
確かに、すべてを一度に疑うことはできない。しかしすべてを個別的に疑うことならできる。例えば、今世界にA,B,Cという三つの命題しかないと仮定しよう。私は、A,B,Cすべてを同時に疑うことはできない。しかし、Aを前提にBを疑い、Bを前提にCを疑い、Cを前提にAを疑うことならできる。結果として、すべては疑いうるということになる。超越論的認識とは、不確定的存在者による不確定性の自己反省である。不確定性とは、「他のようでもありうること」であり、この《認識の他者性》が《他者性の認識》の基礎になっていることは、「他者は存在するのか」で既に述べた。
ここから、超越論的意識とは、本質的に超越論的間主観性であると言うことが、そして「自分の認識に限界があると認識できる人は、実は自分の認識の限界を超越している」という命題を「自分の有限性を自覚している人は、他者の立場に立った多元的な思考が可能である」と新たに解釈し直すことができる。私は他者ではないが、しかし他者を理解できるという微妙な立場が、限界があるにもかかわらず、その限界を超越しうるということの意味である。これに対して、自己の有限性に気が付かずに、自己を絶対視する人は、かえって社会のネットワークにおいて存続することが困難である。




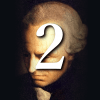


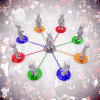











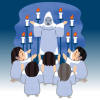


ディスカッション
コメント一覧
《もし私たちの認識が有限であるとしたならば、私たちの認識が有限であるという認識自体も有限であり、したがって、私たちの認識は有限とは限らないという自己矛盾は存在しないだろうか。答えは否である。》について。
私は、答えはイエスである。自己の限界を意識することは、自己の限界の外に立つ(を超える)ことであり、有限な限界の外に立つことは、有限な存在が無限な存在になることである。認識が有限であるということは、認識が有限の外に、有限を超えるということがあることによってはじめて可能になる。つまり、認識が有限であることを知るためには人間が有限を超える、無限になることによってはじめて可能になるということを意味する。有限が有限であるためには、有限が無限になることによってである。無限なしには有限はない。
ひとつ、質問。メタレベルとはどういう意味か。私は最近の用語がよくわからない。また「間主観性」とはどういう意味か。また、誰がこのジャーゴンを使いはじめたのか。「他のようでもありうること」という不確定性という概念は、アリストテレスならなんと定義するであろうか。
《超越論的意識とは、本質的に超越論的間主観性であると言うことが、そして「自分の認識に限界があると認識できる人は、実は自分の認識の限界を超越している」という命題を「自分の有限性を自覚している人は、他者の立場に立った多元的な思考が可能である」と新たに解釈し直すことができる。私は他者ではないが、しかし他者を理解できるという微妙な立場が、限界があるにもかかわらず、その限界を超越しうるということの意味である。これに対して、自己の有限性に気が付かずに、自己を絶対視する人は、かえって社会のネットワークにおいて存続することが困難である》について。
自己の認識の限界を自己の絶対性にもとめるのではなく、他者に移すことによって、つまり自分には認識できないが、他者の立場に立つならば認識できる、とする論理に移行する。「私は他者ではないが、しかし他者を理解できるという微妙な立場」が「超越論的意識」である。こういうことであろうか。だが、認識はそれでよいとして、道徳の場合はどうであろうか。道徳では自分が絶対(=自由)にならないかぎり、自分の行為を決定できないのではなかろうか。自分の行為を他者に決定してもらうのであろうか、あるいは、他者の立場に立って決定するのであろうか。どうも腑に落ちない。(道徳においては、自分が絶対、神、無限者、全知全能の存在者となって、言い換えれば、「自由」おいて、行為を決定する。そうでないと、無責任とか、主体性がないと言われる)
まず言葉の問題から答えていきます。
メタレベルというのは、英語圏の哲学でよく使われる用語で、対象レベルを語る一段上のレベルのことです。物理学とメタ物理学(meta-physics 形而上学)は、対象とメタの関係にあります。間主観性とは、個別主観性を超えた社会的主観性のことで、フッサールが哲学的問題として取り上げて以来有名になりました。一般に間主観的認識は、普遍的で必然的だと考えられていますが、私はむしろ間主観性は不確定的だと考えています。不確定性の定義ですが、アリストテレスは必然的(アナンケー)を「そうあるより他ではありえないこと」と定義しました。不確定性(偶然性)は必然性の否定ですから、「他のようでもありうること」と定義できます。
次にもっと本質的な問題について。
「自己の限界を意識することは、自己の限界の外に立つ(を超える)ことであり、有限な限界の外に立つことは、有限な存在が無限な存在になることである」という弁証法には異論があります。限界を自覚することが、内在的有限を超えることだとしても、それは直ちに超越的無限を意味せず、せいぜい超越論的有限でしかありません。カントは、物自体は認識不可能(unerkennbar)だが、思惟可能(denkbar)だと言っていましたが、「物自体」を「限界の外」と言い換えても同じことです。もし限界の外を認識することができるならば、その存在者は超越的無限でしょうが、私たちはそのような存在者ではありません。
また私は決して「自己の認識の限界を自己の絶対性にもとめるのではなく、他者に移すことによって、つまり自分には認識できないが、他者の立場に立つならば認識できる、とする論理に移行する」というようなことを主張していません。これではまるで奴隷(Knechtschaft)の意識です。自己が絶対的でないように、他者も絶対的ではなく、《他のようでもあるが、他のようでもないかもしれない》という相対性が不確定性なのです。道徳においても同じことが言えます。私は、カントのように、理論理性には限界があるが、実践理性には限界がないとは考えません。私たちは神が死んだ時代を生きているのです。
丁寧に質問に答えていただきありがとうございました。間主観的という用語はカントの理性との関係でいろいろな人が扱っているのを知って驚きました。
カント自身は、間主観的という言葉を使っていないし、またそうした問題意識もなかったようですが、超越論的哲学の開祖的存在ですので、超越論的主観性を論じるときには、よく引き合いに出されます。
永井様の論考『超越論的認識とは何か』の末尾における、「認識という複雑性の縮減を通じて、私たちが存在するこの世界を選び取っている」という句について、お聞きしたいことがあります。『超越論的認識とは何か』の中心的な主張からははずれてしまうと思いますが、この一句には、「私たちが認識においてどのような複雑性の縮減のしかたをするかによって、私たちが存在するところの世界は異なってくる」という含意があると思います。そのことに関して私はまったく賛成です。ところで、現代哲学では、実在論と反実在論の論争が活発になされています。私の質問というのは、システム論的な視座が、この実在論と反実在論の論争に一石を投じることができないだろうか、というものです。何かが実在するという認識のあり方は、複雑性の縮減の結果として到達する、私たちが選び取ったところの、私たちが存在する世界のあり方なのではないでしょうか?そして、反実在論と実在論の関係は、複雑性とその縮減の関係にパラレルなものではないでしょうか?(あるいはまったく逆に、複雑性こそ実在するものだ、という考えもありうるかと思います。)永井様はどのようにお考えになりますか?また、私は読書量が少なくて、システム論的な視座から実在論反実在論について論じている著作を知らないのですが、(そのようなものがあるとしたら)永井様はご存知でしょうか?
実在論か非実在論かを論じる前に、榊原さんが「実在論」でもってどのような立場を考えているのかを確かめるために、次のことを質問しましょう。
まず、「実在する」と「存在する」の区別ですが、私は両者を区別しません。(つまり、「桃太郎は実在しないが存在する」といった言い方は許容しないということです。)
次に、3が存在する(実在する)かという問題ですが、かつて、数が存在するかどうか、喧々諤々の議論がかつて行われたのは事実です。たしかに、私は「2と5の間に素数が存在する」という文を理解できます。しかし、「3が存在する」という文は、それによって「2と5の間に素数が存在する」という以上の何かが主張されているとは思えません。そして、「2と5の間に素数が存在する」という文を主張することは、3の存在(あるいは実在)についての特定の哲学的な立場にコミットする主張ではないと思います。つまり、数の存在非存在についての議論は、何をめぐっての議論だったのかが私には理解できません。
理念的存在者こそ真の実在であるか、ということですが、私の考えではそれは真の実在ではないでしょう。存在するものとして想定しているのは、例えば、犬のイデアではなく、個々の犬、ポチやタロなどです。したがって、イデアに実在を、感覚の対象を存在を割り振って区別するというのは、私が想定していたものとはだいぶ離れてしまいます。
量子力学の解釈論に関しては、余り詳しくはないのですが、永井様の説明を読む限り、「波動関数」や「多世界」の存在を想定する以上、コペンハーゲン解釈も、多世界解釈も、実在論に与する考え方だと思います。
私が当初想定していたのは、主に科学的実在論、つまり電子は存在する、クウォークは存在するという主張を認めるか、それとも道具主義や操作主義の立場から、電子やクウォークは現象を説明するために導入された概念であって、存在しないと考えるか、という対立に、システム論の考え方が一石を投じることができるかというものだったのですが、私の方も混乱していて、(特に物象化論とシステム論を混同していて)私の論点を明確に打ち出すことができませんでした。
私の質問は、システム論に精通した永井様に、システム論の視座が、実在論・反実在論と絡んでくると考えているかどうかをお尋ねするものでした。したがって、永井様が、私の質問を見てピンとこなかったのであれば、私の質問はネガティブに答えられたものと私は考えます。そこで、貴重なお時間を裂いて私の問いを検討していただいた永井様には大変申し訳ありませんが、この議論については、私の方からはこれでおしまいにしたいと思います。私はシステム論に大変興味を持っているので、今後も質問を提起することがあるかと思います。このたびはどうもありがとうございました。
いつもお世話になっています。次の諸点についてご教示頂けないでしょうか。
1.『超越論的認識とは何か』でいう「複雑性の縮減が、常に他のようにも縮減できるという可能性を持つこと(後略)」と『システムの基本概念』でいう「システムとは要素の選択性であり、その結合様式がシステムの構造となる。」の両文は同じ文脈と見て宜しいでしょうか。選択(可能性)から外れた領域が物自体や間主観性と捉えるのは妥当でしょうか。両文における認識と構造は対応関係にあるようですが。
2.『人間原理』にある「生命を育む宇宙を初期の特異点が作る確率は10の1230乗分の1と試算されている」において特異点とはビッグバンを指すとして、この数字の根拠は何でしょうか。これは次にある量子力学の多世界解釈に基づく値でしょうか。
3.『物自体の量子力学的解釈』において「認識の限界を超えた多世界の総体こそ物自体である。」とありますが、認識の内容や程度は人により異なりますので人間の数だけ世界があるとする方が現実的と思われます。それとも物自体とはダークマターやダークエネルギーを指すのでしょうか。
まず、私の議論とカントの議論を区別して考えましょう。カントが言う「物自体」は、形而上学的(メタ物理学的)な概念で、経験科学としての物理学が想定する多世界をさらに超越した世界です。100年後、科学者たちは、多世界という概念を否定しているかもしれませんが、それでも科学者たちは、世界について何らかの概念で語っていることでしょう。カントが想定する「物自体」は、経験科学の理論がどうなろうが、科学者たちがそれについて語り続ける、前述定的な対象のことを言っているのであって、「物自体とはダークマターである」というように、何らかの述定を行ったとたん、それは物自体ではなくなって、現象になってしまいます。私は、カントが行った物自体/現象界の区別を現象界の内部で繰り返していますが、メタ物理学的な議論と物理学的な議論は、区別して考える必要があると思います。なお、10の1230乗分の1という数字は、どこかの本に書いてあった数字を参照したのですが、出典は失念しました。判明したら、追記します。
私は日常生活において、知覚できない物が存在することを了解しています。私が外出している間も私の部屋は存在すると思っています。その時(その時にとっての今現在)知覚できないものが存在するという了解も超越論的認識、もしくは超越論的了解と呼んで良いのでしょうか。今私にとって知覚されないものが知覚から「超越している」とすると「今私にとって知覚されない物が存在する」という認識・了解は超越に関する認識・了解であるように思えます。
超越論的認識は、認識についての認識というメタレベルの認識です。つまり、それは、「知覚できないものが存在する」といった一階の認識ではなくて、「「知覚できないものが存在する」という認識は可能である」という二階の認識です。
認識は不確定で「別のようでもあり得る」から、「「知覚できない物が存在する」という認識が可能である」と言えるということでしょうか。
もう一つ質問させてください。私が「私の認識は別のようであり得る」と言う時、私はその理由について「その時、私はSはPであると認識していたけれど、現在私は、SはPではないと認識しているから」と説明したとします。私はここで、過去の経験的意識を反省し、現在の超越論的意識と区別しています。しかし、私はここで過去の経験的意識を反省しているとして、現在保持している過去の経験的意識の「記憶」を反省しているだけのように思えます。私が「私は現在の地平から、その時、私はSはPであると認識していたという「記憶」を認識することが可能であるけれど、現在私は、SはPではないと認識している」と言ったところで、私の認識が他のようであり得るとはならないのではないでしょうか。
カントの『純粋理性批判』は、理論認識の有限性を示した書です。感性的に直接与えられていない対象に対する悟性の判断は、正しいことも可能ですが、正しくない可能性もあるという意味で有限であり、判断は他のようでありうるということです。
もしも「SはPである」という過去の認識が経験的であるなら、その否定である「SはPでない」という現在の認識も経験的であって、超越論的ではありません。
たしかに、私が認識を改める経験をしたからといって、将来も同じことをするという必然性はありません。では、現在の認識が将来にわたって決して変わることはないのかといえば、そう断言できるほどの必然性も過去の経験則からしてありません。要するに「私の認識が他のようであり得る」ということは「他のようでもありえる」けれども「同じままもありえる」ということなのです。
「その時、私はSはPであると思っていたけど、今ではSはPではないと思っているんだから、私の認識なんて不確定なものだね」と言う時の「私の認識なんて不確定なものだね」という認識が超越論的認識ということでしょうか。
後半の質問は私の意図が伝わってないようです。つまり、私が言いたいのは過去の経験的意識を取り出して、現在の経験的意識と比較して「私は、その時と今では、異なった認識をしているんだ」と言うことはできないのではないか、ということです。「過去の経験的意識を反省している」と言う時、私は経験的意識の「記憶」を反省しているはずです。この「記憶」を持っているからといって、「その時、私はSはPであると認識していた」という過去の経験的意識を指示することはできないはずです。私が過去の経験的意識を反省するということが、「私は現在の地平から、その時、私はSはPであると認識していたと「思う」ことができるけど、現在私は、SはPではないと認識している」ということにすぎなかったら、「私の認識が改められた」とは言えない気がします。極端に言うと、「その時、私はSはPであると認識していたと「妄想」しているが、現在私は、SはPではないと認識している。」と言ったところで「私の認識なんて不確定なものだね」とは言えないと思います。しかし、過去の経験的意識の反省とは「妄想」としてしかできないのではないでしょうか。
カントの場合、形而上学的(超越的)な問題に関する二律背反で悟性的判断の限界が示されるのであって、経験的な判断が時間とともに変わることは根拠にはなっていませんが、有限性に対する一般的な認識としてはそれでよいと思います。
私が記憶違いをするということはありうることですが、そうではない時もあるし、過去に書いたものや録音あるいは録画したものを参照して、今の認識との違いを確認することもできます。あるいは、新田さんが言っていることは、そういうことではなくて、永井均の独今論(過去や未来は存在せず、今しか存在しないという哲学的な主張)のような立場を主張しているということなのでしょうか。
私が、録画された映像の中で「私は神だ」と言っていたとして、その映像を見た私が「今私は私のことを神ではないと思っているから、私の認識なんて不確定なものだね」と言えるとは思いません(現在の私は、過去の私が「私は神だ」と言っている時点の記憶が無いとして)。映像に映る私は、現在の私にとって、私に似た姿をした他人以外の何物でも無いはずです。
私は「記憶」を頼りに、過去の時点で私がかくかくのように認識していたと言うのは、「記憶」が無いのに映像を見て画面の中の彼が、かくかくのように認識しているのだ(そして、彼がかつての私なのだ)と言うのと同じように頼りなく感じます。
独今論についてはよく知らないのですが、過去が実在するかどうかもわかりませんが、もし私が考えたように、過去の経験的意識を指示することが出来なければ、過去の認識が現在に至って変化したとは言えないと思います。
記憶も映像も過去の写しであって、過去の経験的意識を指示できないのではないか。過去の経験的意識が指示できなければ、認識が変化したとは言えないのではないか。というのが私の疑問です。
それなら、やはり永井均の独今論に近いですね。過去とは、今における私の記憶でしかなく、未来とは、今における私の予測でしかない。だから、今しか存在しないというような議論です。永井均よりも前に、バートランド・ラッセルが似たような議論を世界五分前仮説という形でしています。独今論に関しては、「他者認識と認識の不確定性」での投稿の時と同じような議論になってしまいます。
実在論を否定し、観念しか存在しないという立場を観念論と言い、独今論と同じようなロジックで正当化されています。私が実在だと思っているものは、常に実在に対する私の観念であり、したがって、私の観念以外は何も存在しないというわけです。ところが、すべては妄想に過ぎないという主張は、すべては妄想ではなくて、実在するという主張と言っていることは同じです。後者は、その外部が存在しない実在界にすべてがあると言っているのですから、たんに使っている言葉が観念界から実在界に変わっただけで、観念論と同じ世界観ということになります。
「妄想」が妄想であるためには、妄想ではない正しい認識が存在する必要があります。もしも正しい認識の正しさの根拠である実在が存在しないなら、正しい認識と妄想の区別がなくなり、正しい認識が正しくなくなると同時に、妄想が妄想ではなくなります。過去に対する記憶も同じで、私たちは記憶違いにより、過去に対して妄想を抱くことはあり得ますが、それは、そうではない正しい記憶が存在するからこそ、妄想なのです。過去が存在しなければ、過去に対する正しい記憶がなくなり、同時に妄想すらなくなります。
永井さんは、過去の経験的意識を現在の地平から認識する際に、その認識はあいまいなものでいいと思っていますか?
ところで、私は、今現在の私がいないなら、今も現実もないかもしれないという世界認識よりも、今現在の私がいなくても、今や現実はありうる方が面白いと思っています。私は、哲学的な問題についてあまり真面目に考えていないので、さっさと「今現在の私がいなくても、今や現実はありうるよ」と言いたいのですが、哲学は難解な用語がどんどん出てくるので耐えられず、心の哲学の周辺をウロウロしている格好になっています。いまいちべったりくっつける哲学者が見つかりません。私は誰から始めればよいのでしょう。いきなり悩み相談になりますが、アドバイスしてください。
不確定性をはっきり認識するということとあいまいなまま放置することは同じではありません。
独今論と観念論は、正当化のロジックが似ているということで引き合いに出したまでで、独今論が観念論と同じということはありません。実際、実在論的な世界観に基づいて独我論や独今論を主張している人はたくさんいます。
とりあえず、永井均の本から始めてはいかがでしょうか。